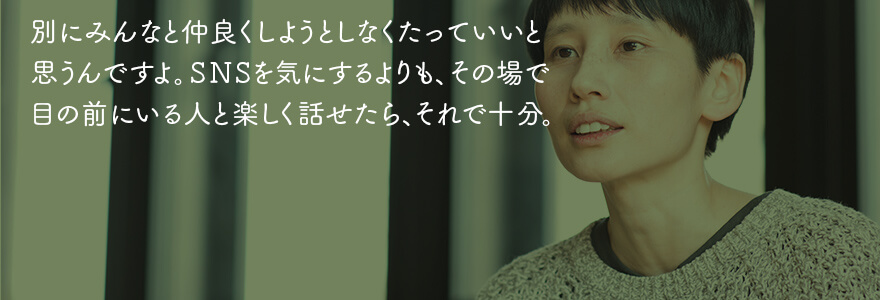
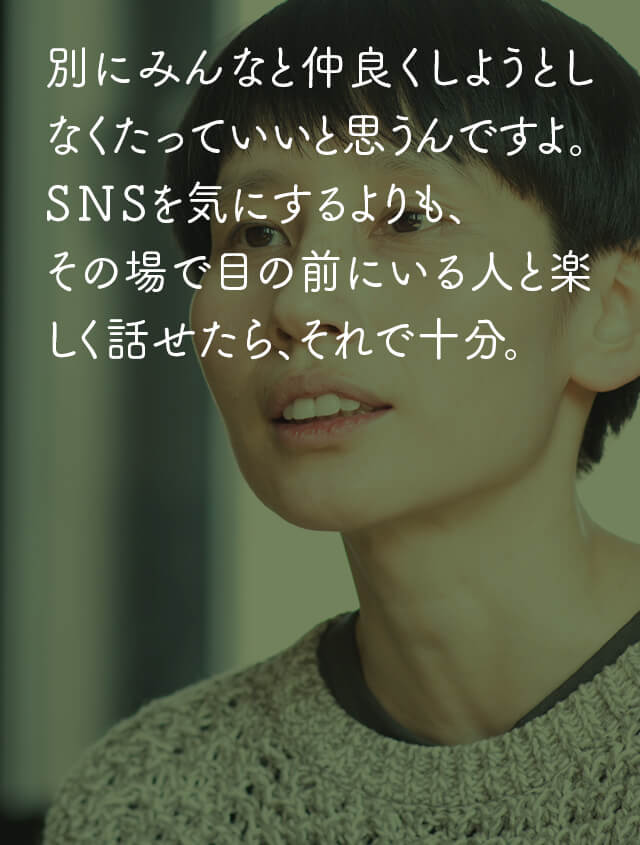
「リア充VSぼっち」を乗り越えて 寺嶋由芙×箕輪はるか(ハリセンボン)対談<後編>
-
●「友だちづくり」という、もっとも新入生が悩むであろう話題を、それに苦しんだ二人に取材していたのはよかったと思う。多くの大学生が希望を抱いて本学に入学してくると思うが、みんながみんなそれに成功するとは限らない。でも、それでも大学を離れて努力すれば、一線で活躍することができる。新入生にとっては、慣れない大学生活へ向けて、一歩背中をおしてくれるような、そして在校生で何者にも成れないとくすぶっている人たちにも温かいエールをくれるような記事だった。(文化構想学部/2年/女)
-
●もともとお笑い芸人のハリセンボンさんが好きだったので、タイトルから興味を持ちました。無理して友達を作らなくてもいいんだとこの記事を読んで感じ、肩の力が抜けました。(スポーツ科学部/2年/女)
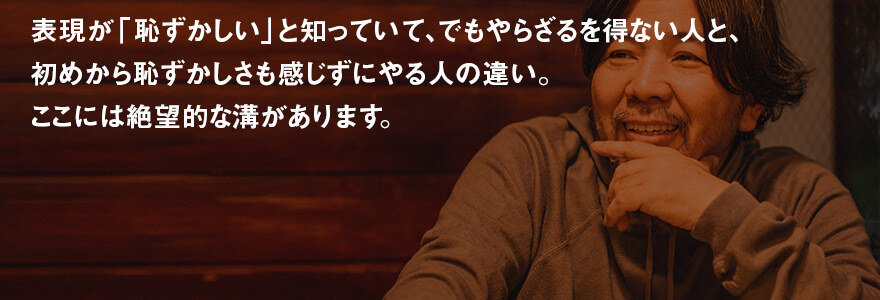
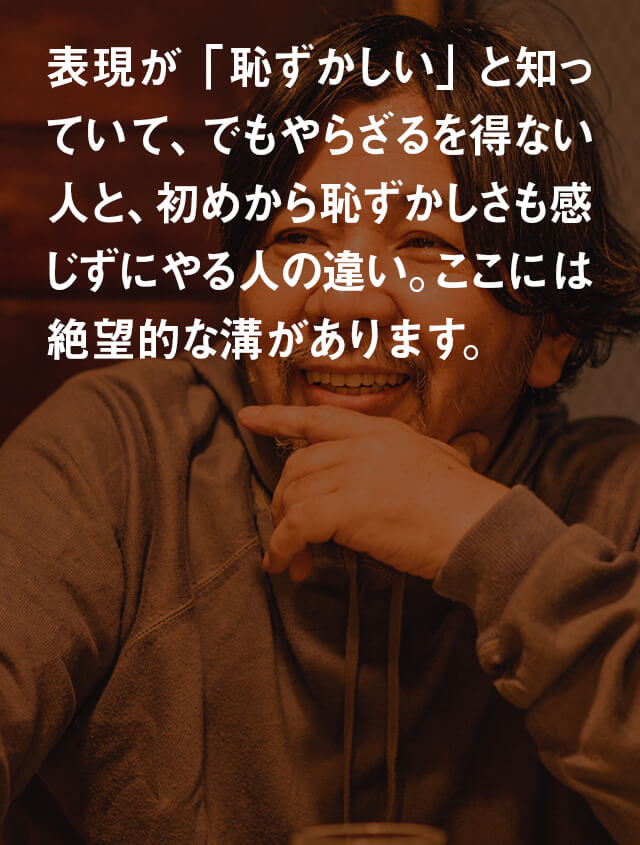
「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談
-
●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)
-
●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)
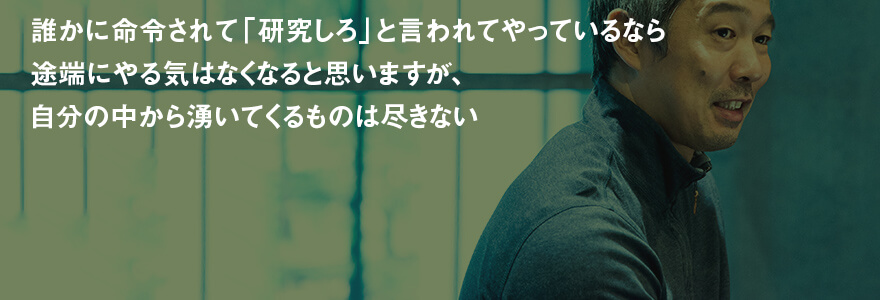
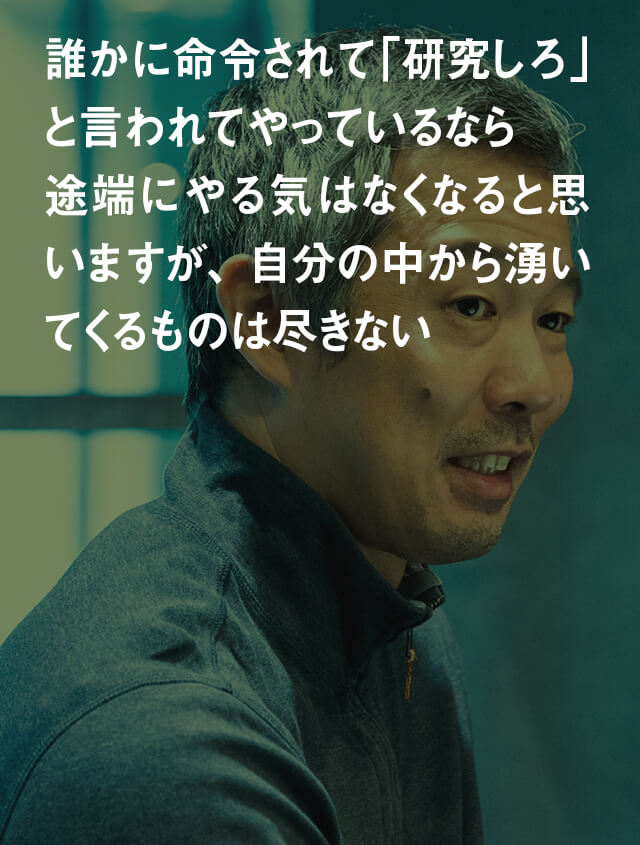
「人はまだ進化できる」世界を拡張するVR 玉城絵美×笠原俊一×渡邊克巳
-
●私達は社会の節目節目で「個性を出しなさい」とか「〇〇のために」と言われるが、つまるところ「自分の喜びのために」やりたいことをすることが、就職であれ研究であれ最も効率よくモチベーションを維持し、結果的に高い生産性と社会貢献度を生み出すことなのだと感じた。またVRによって、自分たちの感覚のスタンダードがやがて変化し、現実に対する定義も変わってくるだろうという予感を感じ、少し怖いのが正直なところ。(先進理工学部/3年/女)
-
●社会自体が予測不可能性を持っているので、そこに研究をはきだした結果、また新たな展開の可能性がうまれ、さらに研究が進んで行く。世に受けるかどうかだけ気にしていては疲弊してしまうので探究心を持って何事にも当たる。またインプットとアウトプットの循環の中で幸せを感じるようにできてる、ということなど、心の支えになるような言葉がたくさんあった。論理的に知識があるからこそ落ち着いて議論できる話題とそれを扱いこなす3人の議論が面白かった。(創造理工学部/3年/女)
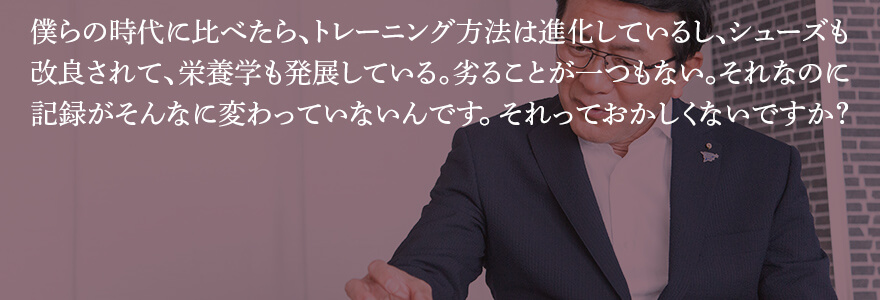
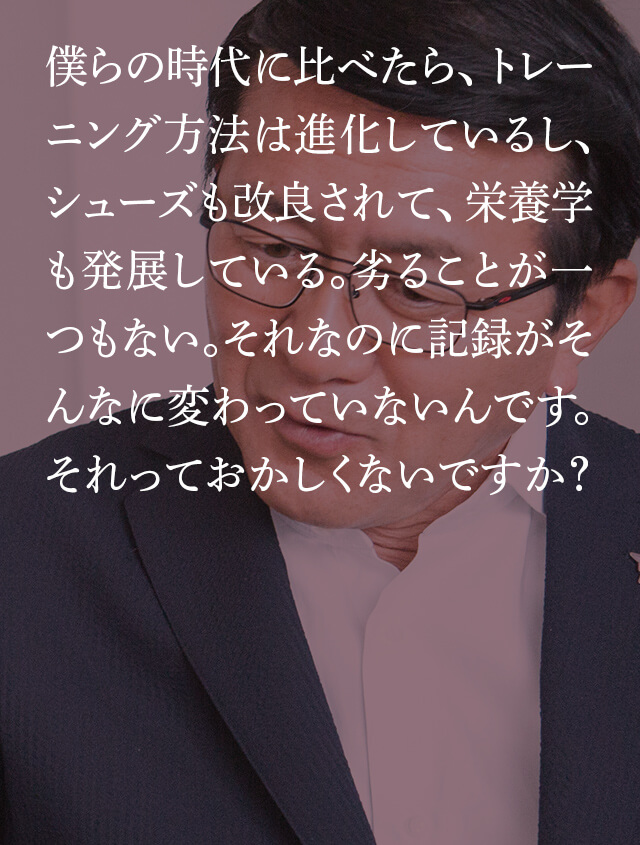
箱根から五輪へ 瀬古から大迫へ 「Wの系譜」が見せた日本マラソン界の光
-
●「瀬古さんについて、いつも箱根駅伝や マラソンの解説をしている人という印象しかなかったが、インタビューを読んでほんとにすごい人だなと思った。日常がすべて繋がっているし、なりふりやらなければ身につかないこともあるということ、それができるということもひとつの才能であるということに勇気が湧いた。効率がいいことが求められる世の中であるが、それだけではないのだ。決めたからにはやるしかないと、無理があるかもしれないけど私は好き。覚悟を決めるということにはそれだけ力があると思う。 (創造理工学部/3年/女)
-
●先日の箱根駅伝、解説に瀬古さん、渡辺さん、大迫さんと早稲田のOBの偉大さを改めて感じました。瀬古さんの言葉だからこそ重みがあり、説得力があります。現在のマラソン選手に対する鋭い指摘も載っていて読んでいて楽しかったです。(政治経済学部/1年/女)
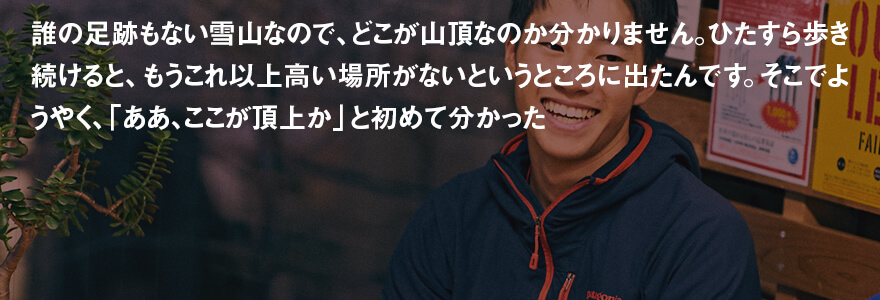
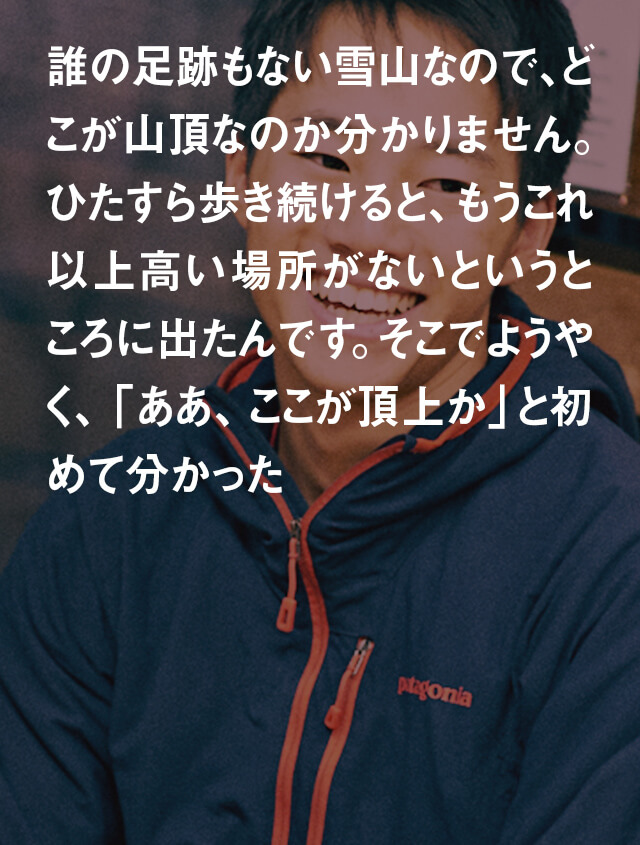
「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹
-
● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)
-
●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)
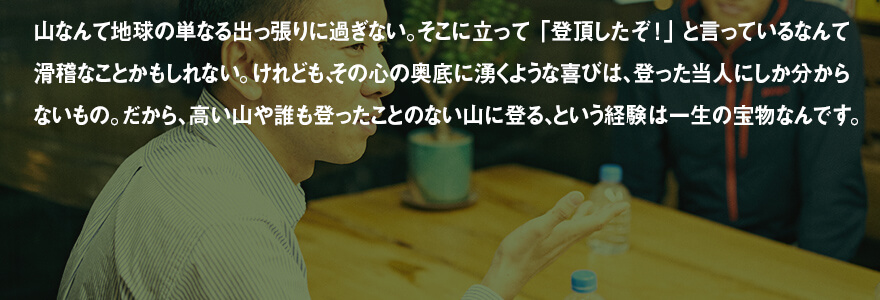
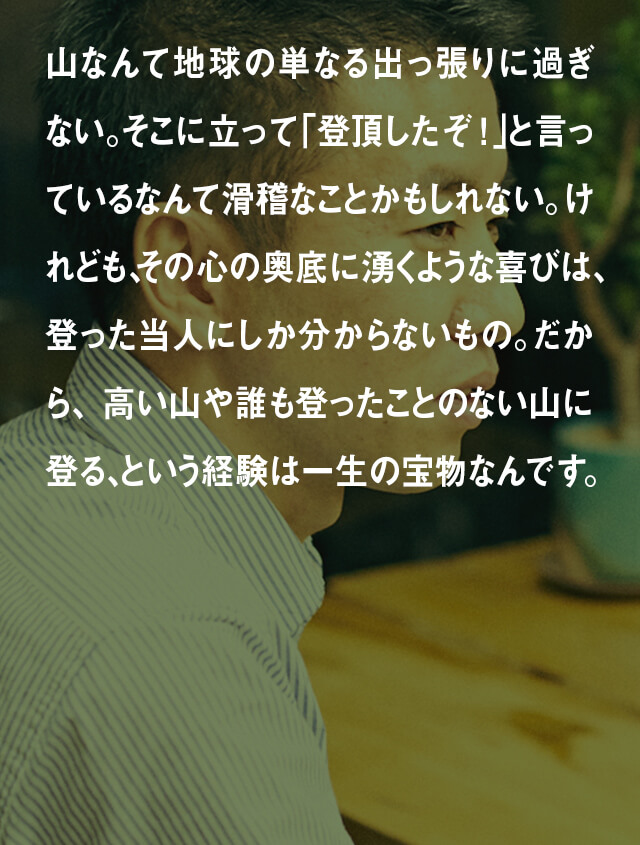
未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹
-
●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)
-
●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)
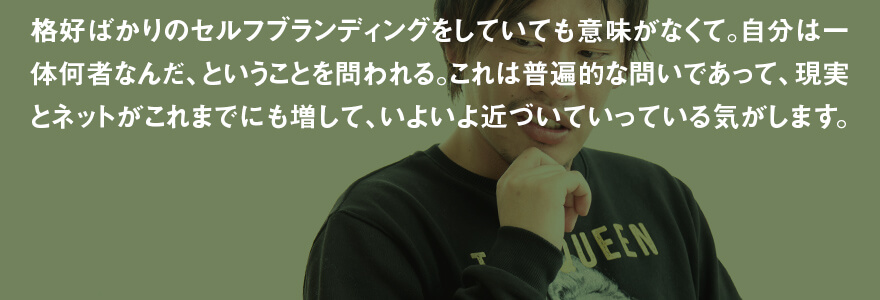
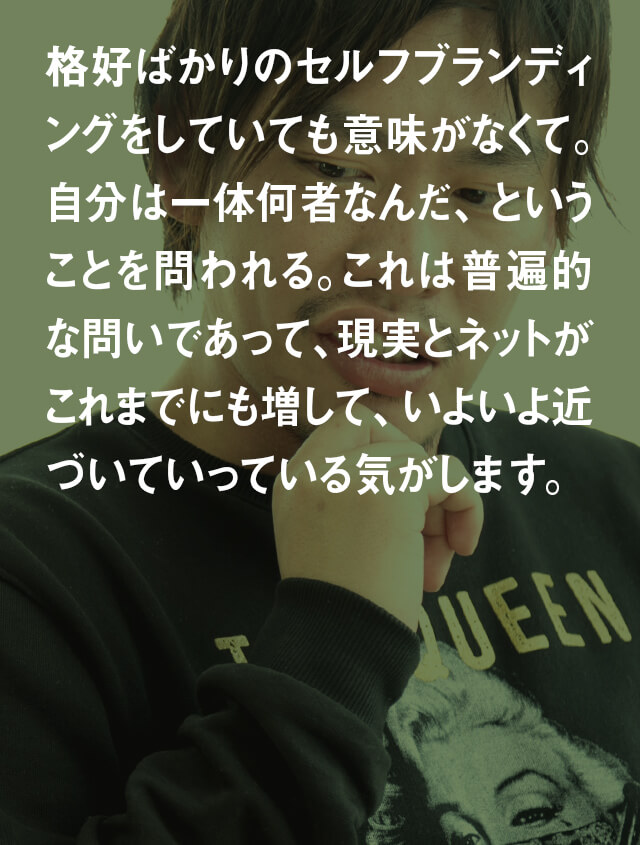
箕輪厚介×津田大介“凡人”対談 SNS生存戦略「信じてもらえる人であれ」
-
●自分の「山」を作っていくうえで、自分の中のルールが崩れることもあると思いますが、社会にも既存のルールが存在します。そのルールに異議を唱えられるのは「すごい人」と思いがちですが、凡人にも凡人なりの戦い方や社会貢献の仕方があるのだということは、私たち学生にとって、これからのために貴重なメッセージだと感じました。(政治経済学部/2年/女)
-
●事実の持つ価値や価値観が"信仰"として相対化している風潮に対し、興味を共有する人々が「箕輪研究室」のようにネット上でも閉じたコミュニティを形成し始めている事を始めて知った。 この中で、事実を単に示すに留まらず、「情報を届ける相手とどのような関係を築くことができるのか」を考えてきた二人の対談は価値があるだろう。 (人間科学部/2年/男)
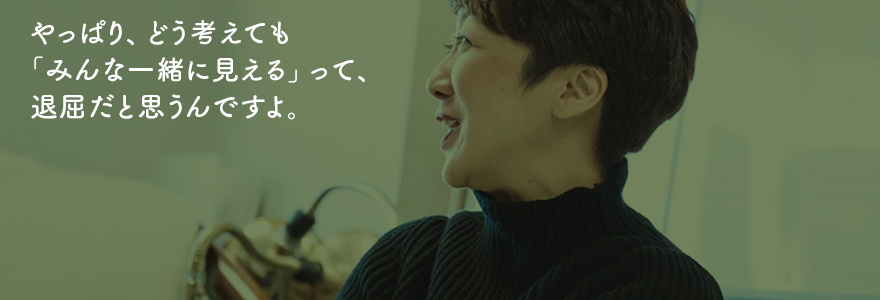
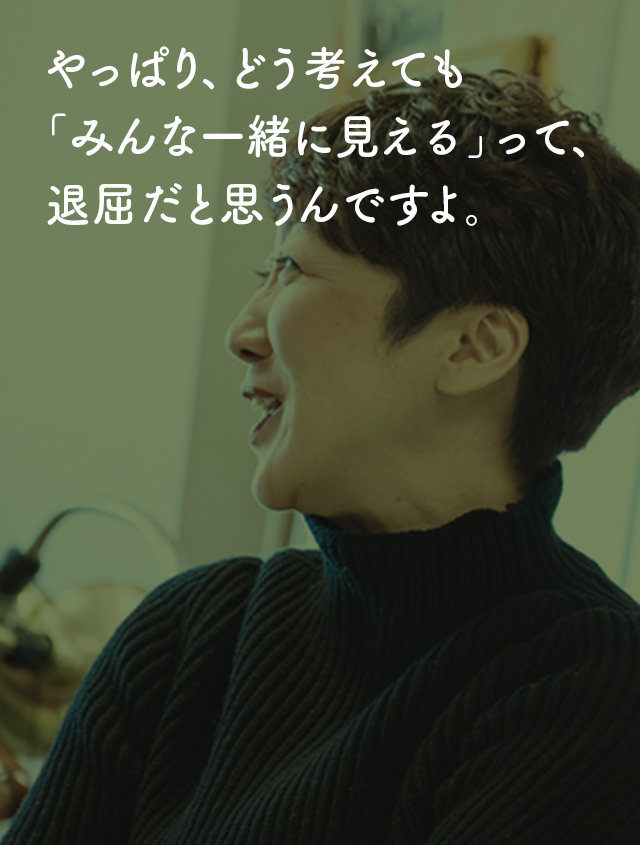
#STYLE #from #WASEDA 森永邦彦×シトウレイ×木津由美子 鼎談<後編> 「ファッションは世界を拡張する」
-
●けっこう異色(?)な特集だと思いました。日頃ファッションに興味のない私ですが、3者の話題が文化論などに及び、すごく勉強になりました。個人的には「ちゃんと足で探す事を大事にしてもらえたら」という言葉にビビッときました。やはりプロフェッショナルな人必ず「足を使う」というのを大切にしているなと思いました。(大学院文学研究科/2年/男)
-
●服については、以前に、ルワンダでファッションブランドを立ち上げた根津さんのお話を読んだこともあって、今回の話も踏まえると、早稲田は世間からみてダサいというよりも、自分の望むことを追求していった結果多少は世間とは異なる姿になったのかもしれないと思いました。現在でも早稲田はマスコミに強いとされていると思われますが、そんな中でも、木津さんのように進んで異なる業界に進む方がいるおかげで、今の早稲田大学の多様性が保たれているのではないかと思われました。2016年の春夏コレクションの写真を見ると、陰を活かすという発想は非常に独特なものだと感じました。すなわち、デザインが映えるのは光に照らされてそれが認識できるからだと思われますが、上記コレクションのデザインのような陰翳礼賛に現れる日本の陰の考えを反映した点が独特だなと思われました。(法学部/2年/男)
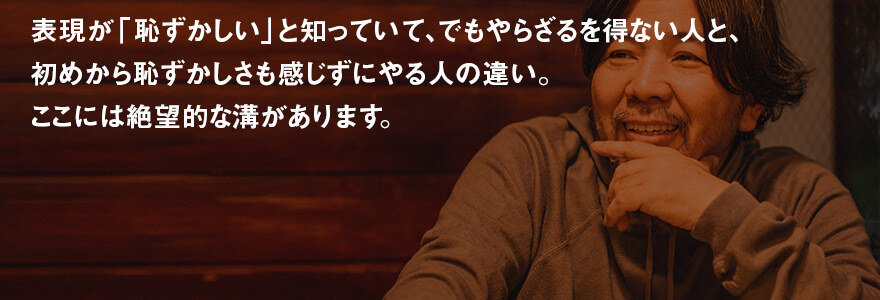
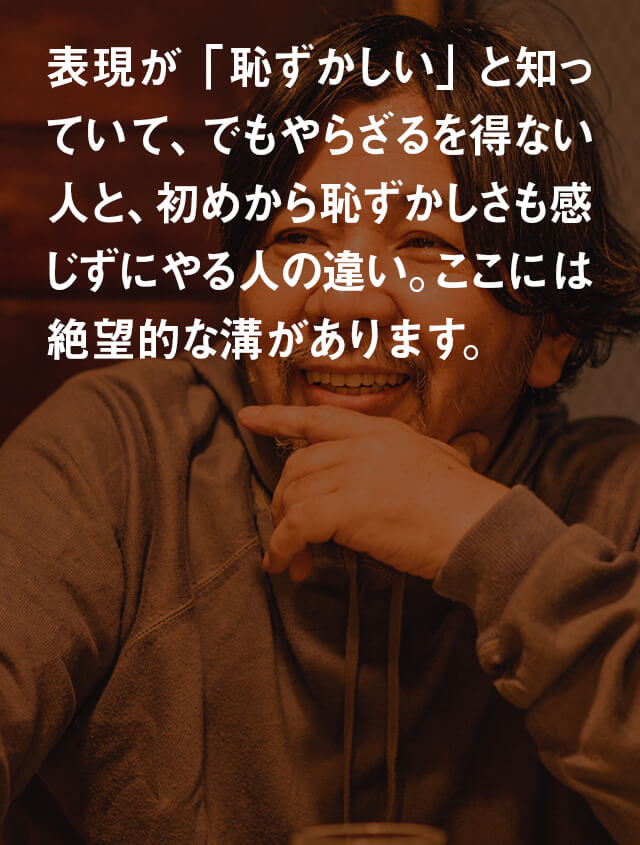
「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談
-
●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)
-
●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)
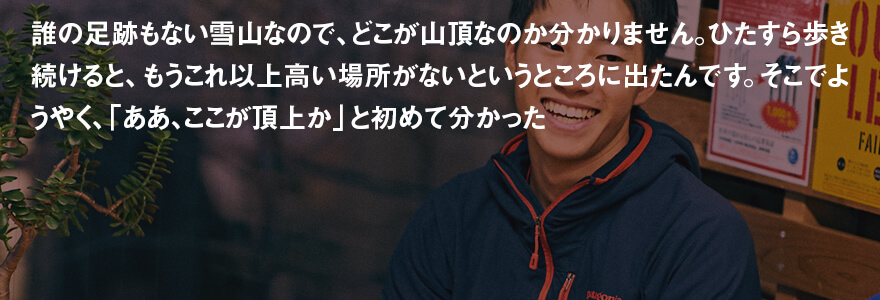
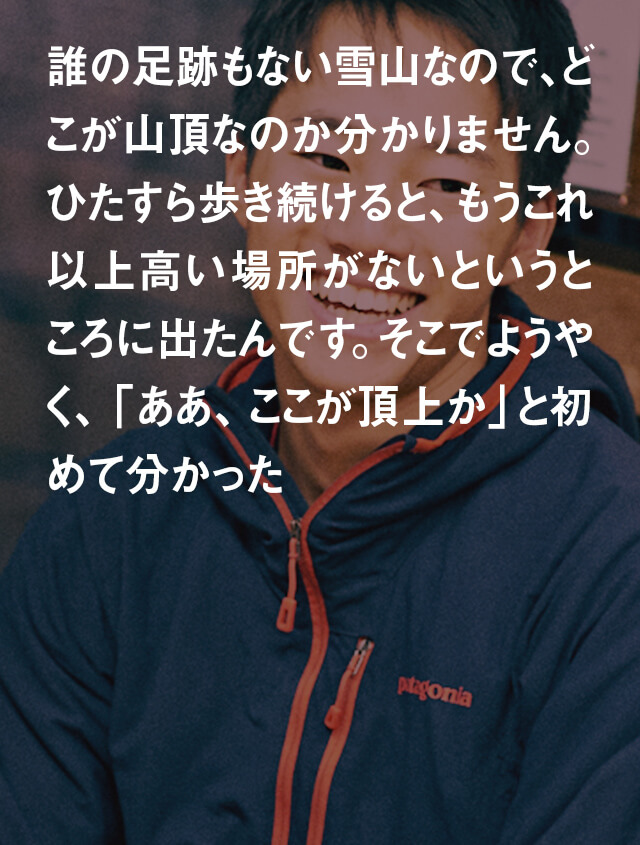
「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹
-
● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)
-
●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)
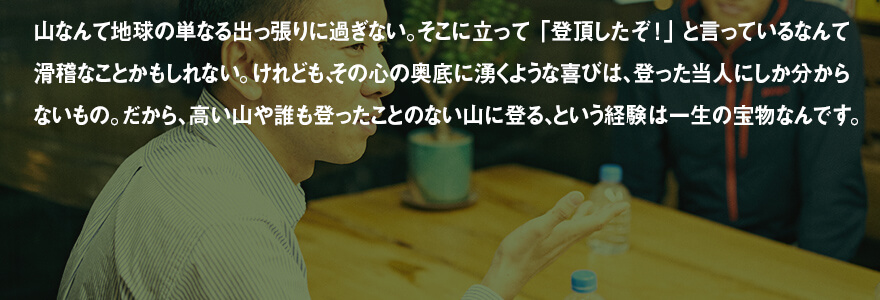
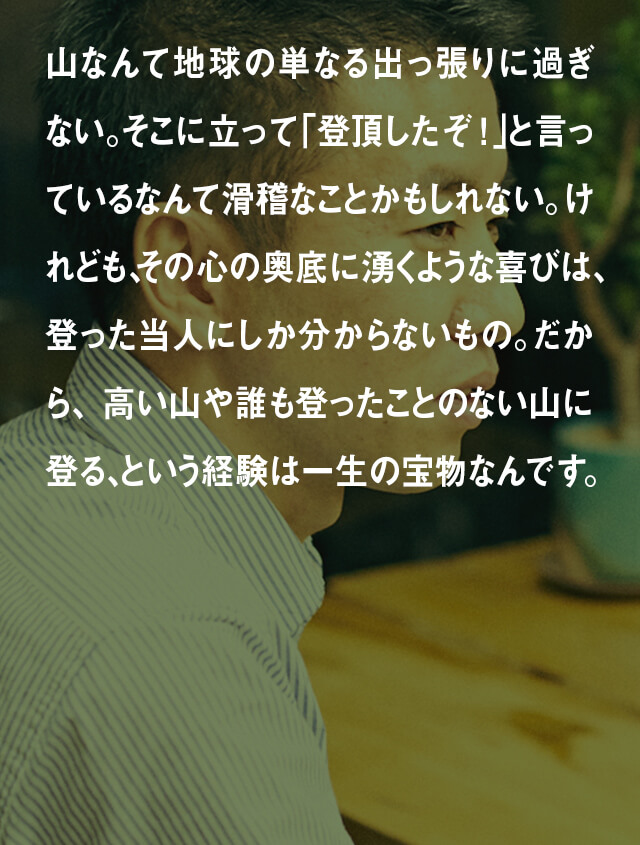
未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹
-
●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)
-
●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)
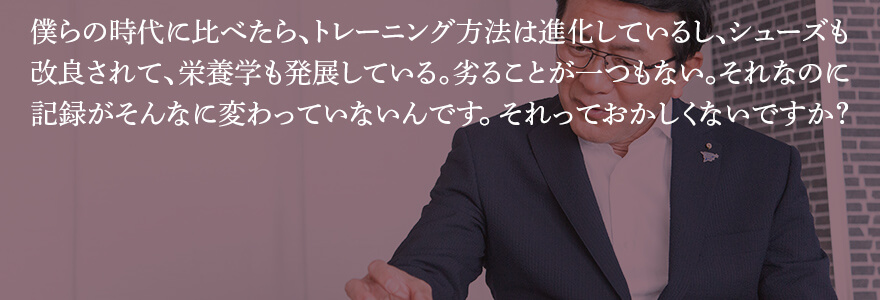
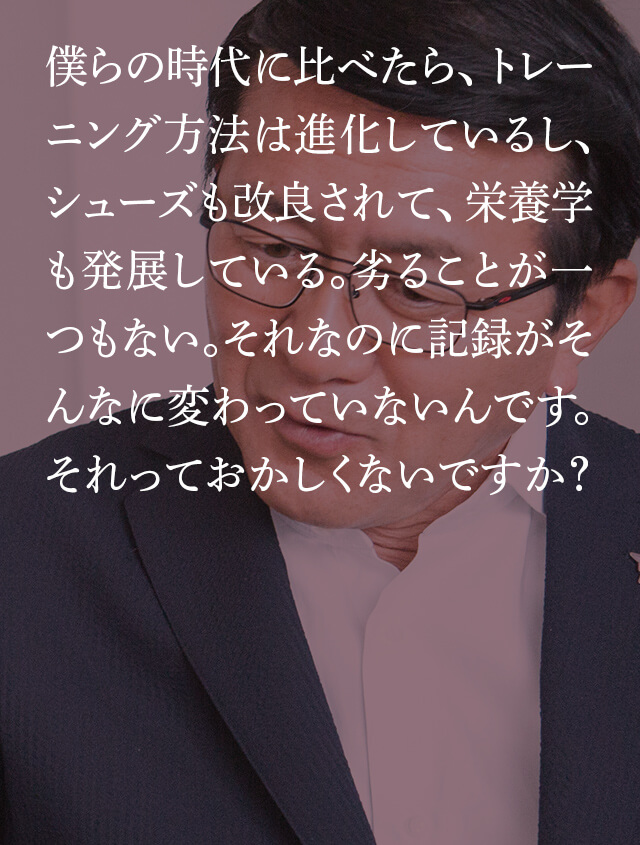
箱根から五輪へ 瀬古から大迫へ 「Wの系譜」が見せた日本マラソン界の光
-
●「瀬古さんについて、いつも箱根駅伝や マラソンの解説をしている人という印象しかなかったが、インタビューを読んでほんとにすごい人だなと思った。日常がすべて繋がっているし、なりふりやらなければ身につかないこともあるということ、それができるということもひとつの才能であるということに勇気が湧いた。効率がいいことが求められる世の中であるが、それだけではないのだ。決めたからにはやるしかないと、無理があるかもしれないけど私は好き。覚悟を決めるということにはそれだけ力があると思う。 (創造理工学部/3年/女)
-
●先日の箱根駅伝、解説に瀬古さん、渡辺さん、大迫さんと早稲田のOBの偉大さを改めて感じました。瀬古さんの言葉だからこそ重みがあり、説得力があります。現在のマラソン選手に対する鋭い指摘も載っていて読んでいて楽しかったです。(政治経済学部/1年/女)
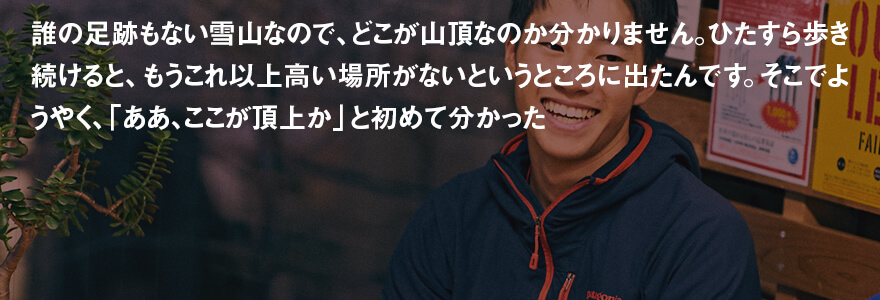
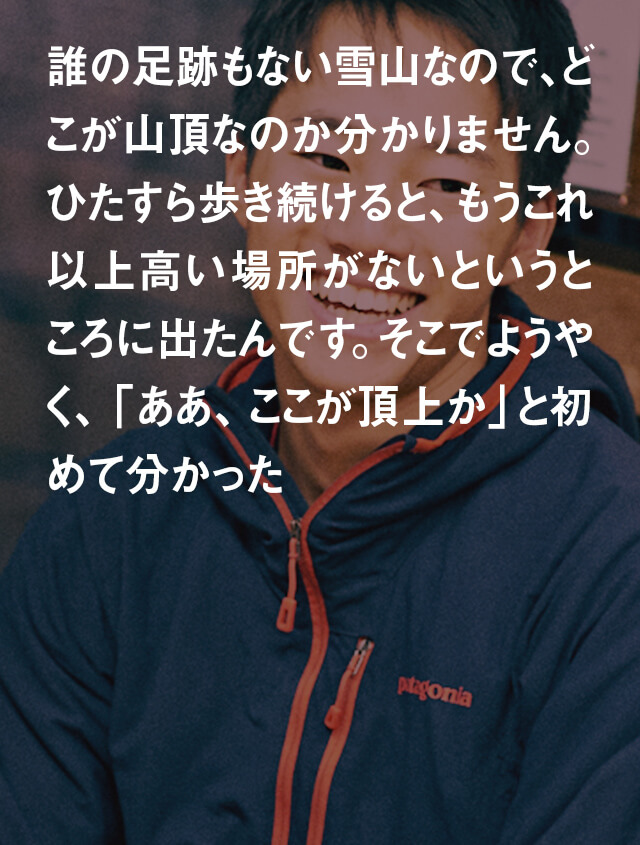
「山頂での3分間」ヒマラヤ未踏峰で見た景色の価値 早大山岳部×石川直樹
-
● 誰もやったことのないことに挑戦し、成功させるのはかっこいい。高山病になったとか雪崩に巻き込まれたとか、想像できないような事態を乗り越えて未踏峰登頂に成功したのを知って感動した。また早稲田の山岳部をあまり知らなかったので知る良い機会となった。(政治経済学部/1年/女)
-
●熱のこもったドキュメントに仕上がっていると思いました。「頂上」の後にはすぐ、降りることを考えるとのことには驚きました。また「下山して山頂を見上げたときにじわじわと感動が湧いてくる」、「仮眠をとって起きたときに、遠くにラジョダダの頂上が見えました。そこで『あそこに行ってきたんだ』と、胸が熱くなりました」など、この言葉は頂上に到達した人たちだからこそ味わうことのできる感覚で、言葉以上の想いがあるのだなと感じた。(大学院文学研究科/2年/男)
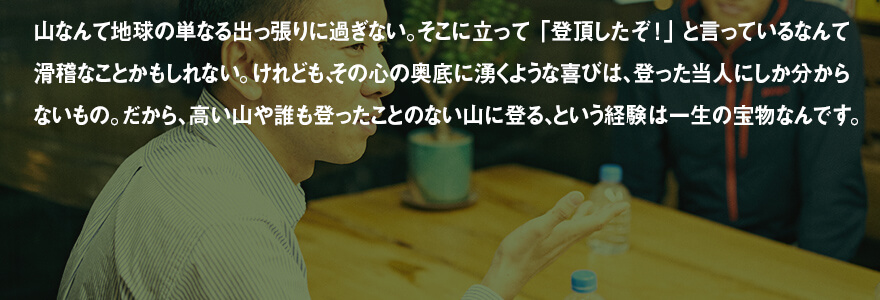
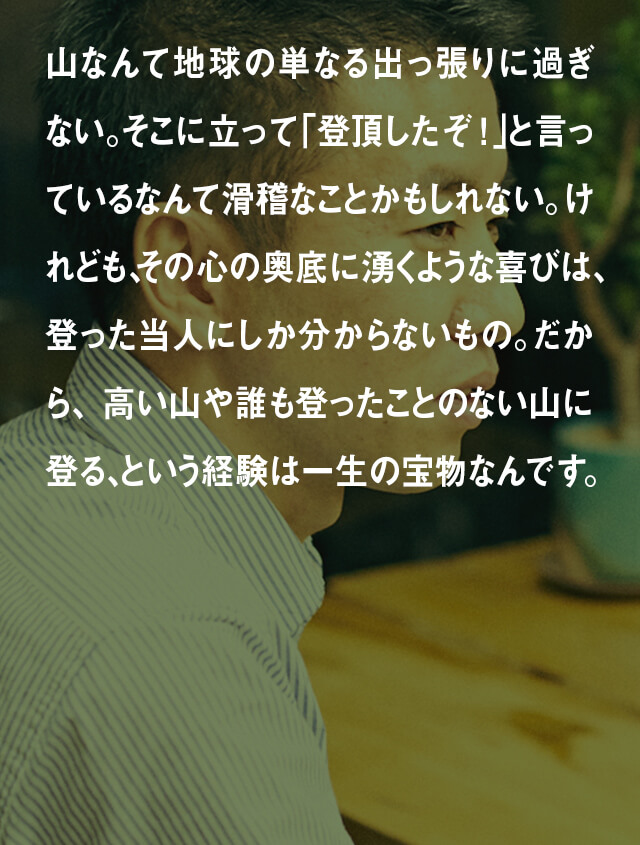
未踏峰か? 最高峰か? 冒険の価値はどこへ行く 早大山岳部✕石川直樹
-
●未踏峰という山がまだあることに感動したし、ロマンがまだあるのだなと感じた。萩原さんが会社をやめた選択もすごいと思う。ばかげた行動だなんて思わない。OGOBを説得するのが一番難関だったということだが、そのような安全管理に細心の注意を払う姿勢はさすが伝統がある部活だと思う。雪崩に巻き込まれたことや26時間歩き続けたこと、仲間との連携などどれをとっても簡単に経験できないことであり、自分の自信につながると思う。(創造理工学部/3年/女)
-
●未登頂の山登りがいかに大変かを知ったうえで挑戦した、OBや山岳部のメンバーは本当にかっこよくて尊敬します。いつか自分も、このような大きな決断をして誰もやったことのないことを達成してみたいなと思いました。(創造理工学部/3年/男)
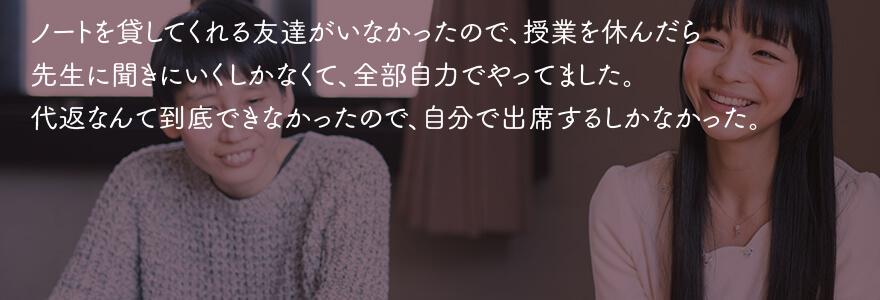
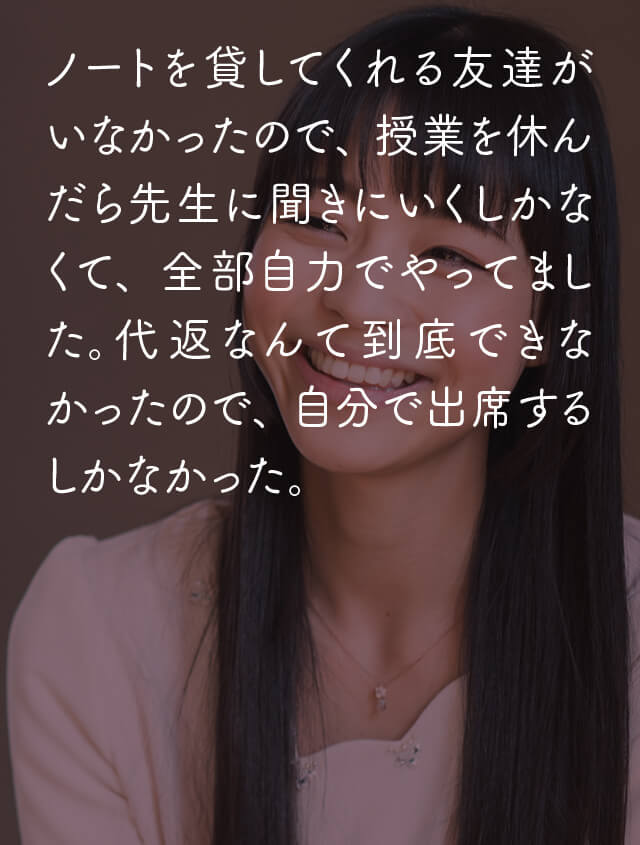
「ノート貸して」が言えなかった私たち 寺嶋由芙 × 箕輪はるか(ハリセンボン)対談
-
●私自身も構内を一人で動いているので、良い意味で関心を持った。一人の方が自由に気楽に行動できて良いが、やはり講義を休んでしまった時に「ノート貸して」と言える友だちがいないというのはなかなか辛いこと、また図書館やコンピュータルームがいわゆる「ぼっち」には最高の場所だということなど、お二人の対談内容には共感できるところがいくつもあった。教室の空き状況を公開し、一部を「ぼっち」の学生専用の自習教室のようにしてもらいたい。多様性を認める早稲田大学だからこそ、「ぼっち」にもそういった配慮があっても悪くはないのではないか。 (教育学部/2年/男)
-
●ハリセンボンのはるかさんが早稲田卒とは知らなかった! いわゆる「大学生らしい」陽の当たる道を歩いてきた人だけではなく、ネガティヴなぼっちを検証しようという試みは果たして本当にぼっちの学生に届くのか? 1人でいることは素敵なことでもあるが、孤独は寂しさも伴う。情報があるのとないのでは、単位をとるにも困難の程度が大きくかわるし、人間は人間と関わることで成長させられるし、元気ももらえる。ぼっちを肯定して終わらせないでほしいとは思う。 (創造理工学部/3年/女)
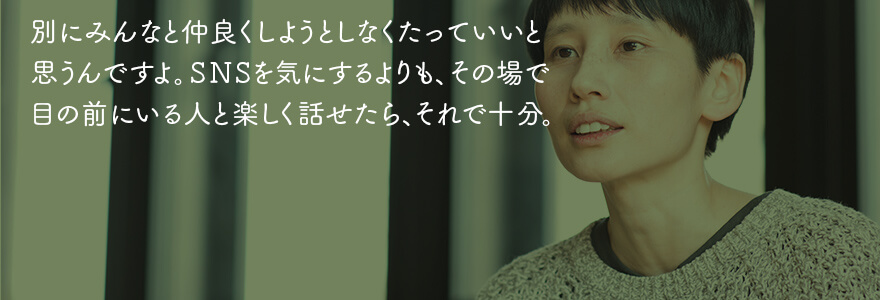
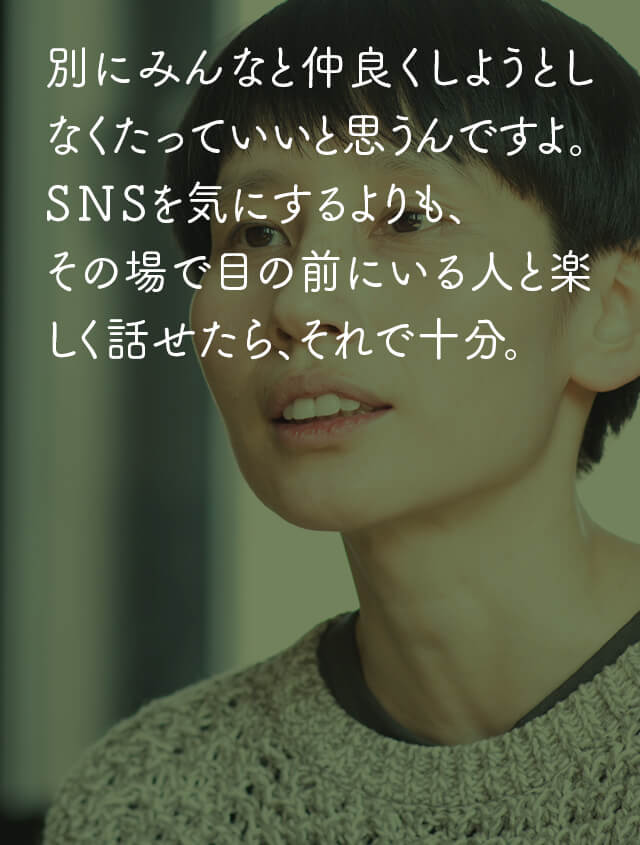
「リア充VSぼっち」を乗り越えて 寺嶋由芙×箕輪はるか(ハリセンボン)対談<後編>
-
●「友だちづくり」という、もっとも新入生が悩むであろう話題を、それに苦しんだ二人に取材していたのはよかったと思う。多くの大学生が希望を抱いて本学に入学してくると思うが、みんながみんなそれに成功するとは限らない。でも、それでも大学を離れて努力すれば、一線で活躍することができる。新入生にとっては、慣れない大学生活へ向けて、一歩背中をおしてくれるような、そして在校生で何者にも成れないとくすぶっている人たちにも温かいエールをくれるような記事だった。(文化構想学部/2年/女)
-
●もともとお笑い芸人のハリセンボンさんが好きだったので、タイトルから興味を持ちました。無理して友達を作らなくてもいいんだとこの記事を読んで感じ、肩の力が抜けました。(スポーツ科学部/2年/女)
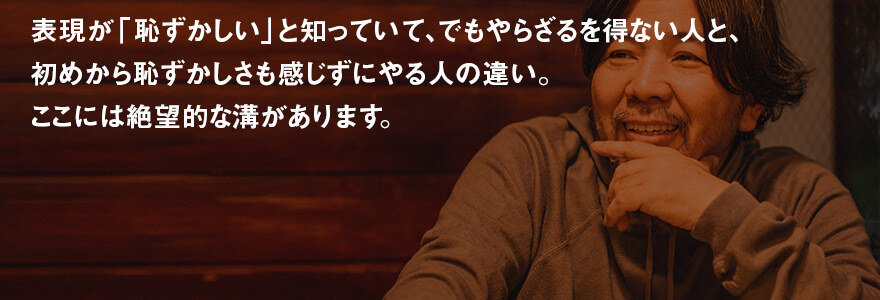
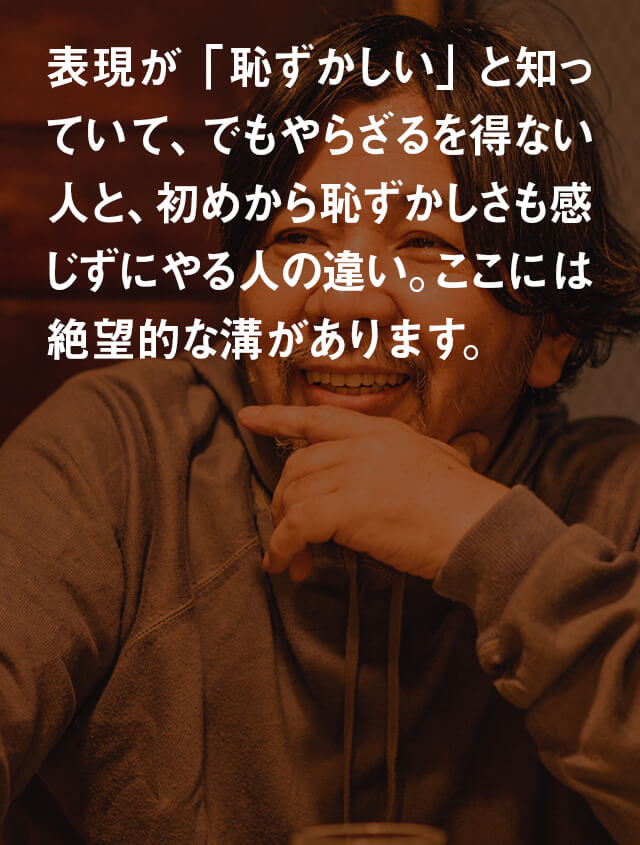
「時代をつくる、言葉とサブカル」“知れ恥”−−表現は恥に向き合い生まれる 宮沢章夫×吉田靖直(トリプルファイヤー)対談
-
●表現は恥ずかしいとわかっているかどうか。という話に鳥肌がたった。確かに、普通に生きているだけでは皆同じことをしているのだから恥ずかしいということはない。しかし、生きる上で余計である表現をすることをわざわざするということはスマートではないし、表現しない人が側から見たら何しているのという気持ちを持つだろう。つまり表現は恥ずかしいことなのだ。それでもなお、表現せずにはいられないというひとが表現者だ、恥ずかしいということを知っていなきゃならない、という言葉がとても痺れた。以前宮沢さんのなにかに寄せた文を読んで感動してスクラップして持っている。『インスタントな奇跡はない』心の支えになっている。(創造理工学部/3年/女)
-
●二人の言葉に対する意識がとても面白いと感じています。本当に「ふつう」の人でありながら、どこか深掘することでどこからかその普通がおかしさに変ってゆくのは、お二人の世界観に通じるように思います。 (大学院文学研究科/2年/男)
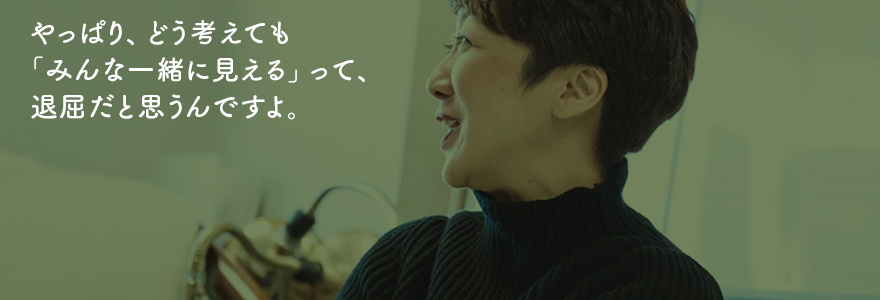
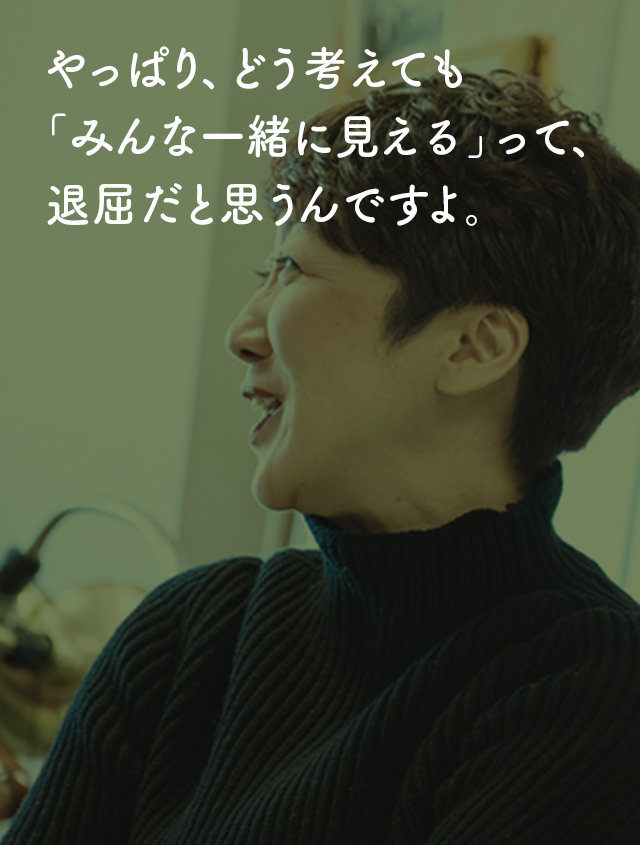
#STYLE #from #WASEDA 森永邦彦×シトウレイ×木津由美子 鼎談<後編> 「ファッションは世界を拡張する」
-
●けっこう異色(?)な特集だと思いました。日頃ファッションに興味のない私ですが、3者の話題が文化論などに及び、すごく勉強になりました。個人的には「ちゃんと足で探す事を大事にしてもらえたら」という言葉にビビッときました。やはりプロフェッショナルな人必ず「足を使う」というのを大切にしているなと思いました。(大学院文学研究科/2年/男)
-
●服については、以前に、ルワンダでファッションブランドを立ち上げた根津さんのお話を読んだこともあって、今回の話も踏まえると、早稲田は世間からみてダサいというよりも、自分の望むことを追求していった結果多少は世間とは異なる姿になったのかもしれないと思いました。現在でも早稲田はマスコミに強いとされていると思われますが、そんな中でも、木津さんのように進んで異なる業界に進む方がいるおかげで、今の早稲田大学の多様性が保たれているのではないかと思われました。2016年の春夏コレクションの写真を見ると、陰を活かすという発想は非常に独特なものだと感じました。すなわち、デザインが映えるのは光に照らされてそれが認識できるからだと思われますが、上記コレクションのデザインのような陰翳礼賛に現れる日本の陰の考えを反映した点が独特だなと思われました。(法学部/2年/男)
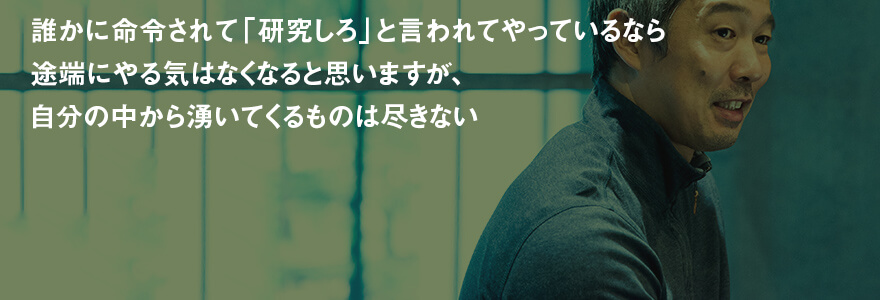
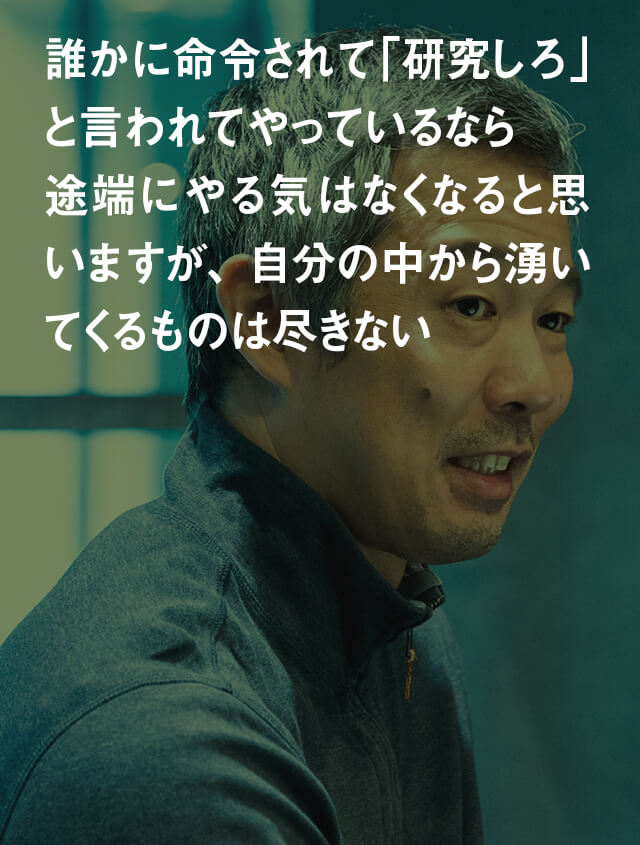
「人はまだ進化できる」世界を拡張するVR 玉城絵美×笠原俊一×渡邊克巳
-
●私達は社会の節目節目で「個性を出しなさい」とか「〇〇のために」と言われるが、つまるところ「自分の喜びのために」やりたいことをすることが、就職であれ研究であれ最も効率よくモチベーションを維持し、結果的に高い生産性と社会貢献度を生み出すことなのだと感じた。またVRによって、自分たちの感覚のスタンダードがやがて変化し、現実に対する定義も変わってくるだろうという予感を感じ、少し怖いのが正直なところ。(先進理工学部/3年/女)
-
●社会自体が予測不可能性を持っているので、そこに研究をはきだした結果、また新たな展開の可能性がうまれ、さらに研究が進んで行く。世に受けるかどうかだけ気にしていては疲弊してしまうので探究心を持って何事にも当たる。またインプットとアウトプットの循環の中で幸せを感じるようにできてる、ということなど、心の支えになるような言葉がたくさんあった。論理的に知識があるからこそ落ち着いて議論できる話題とそれを扱いこなす3人の議論が面白かった。(創造理工学部/3年/女)

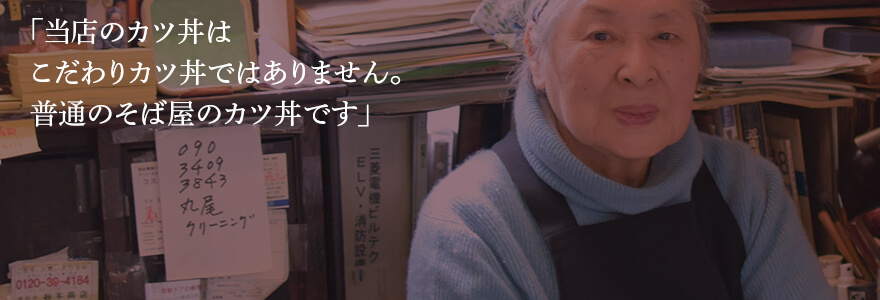
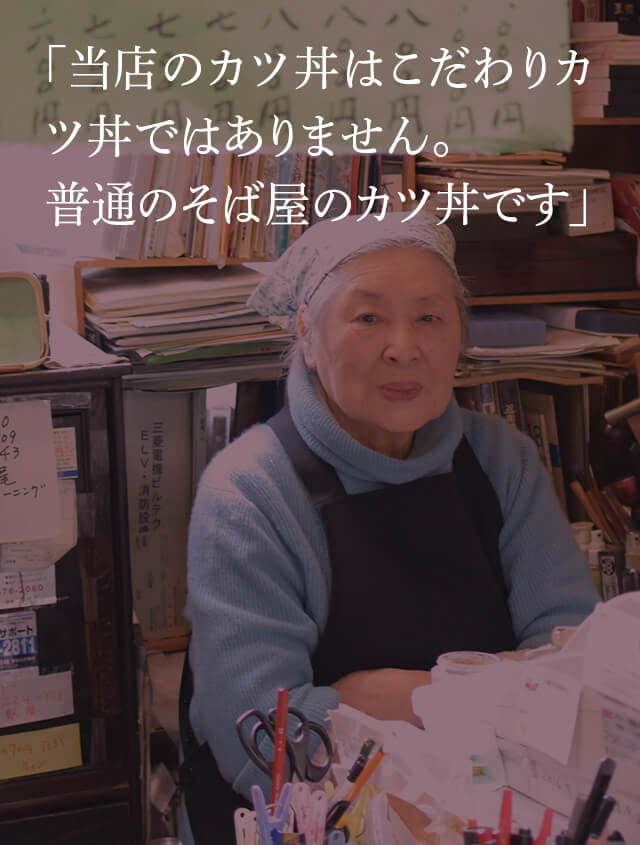


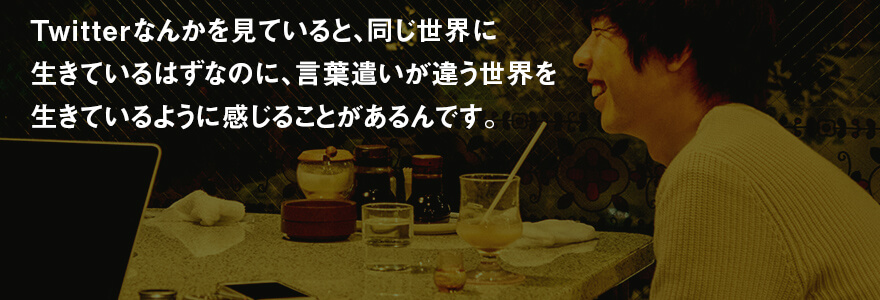
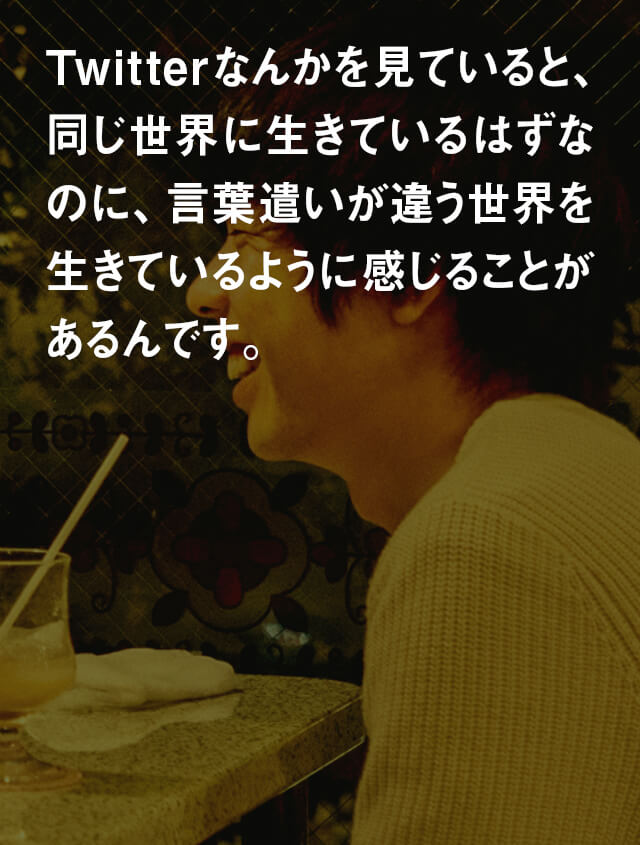
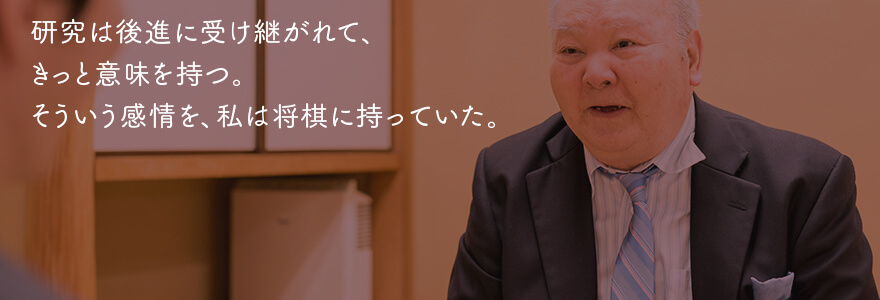
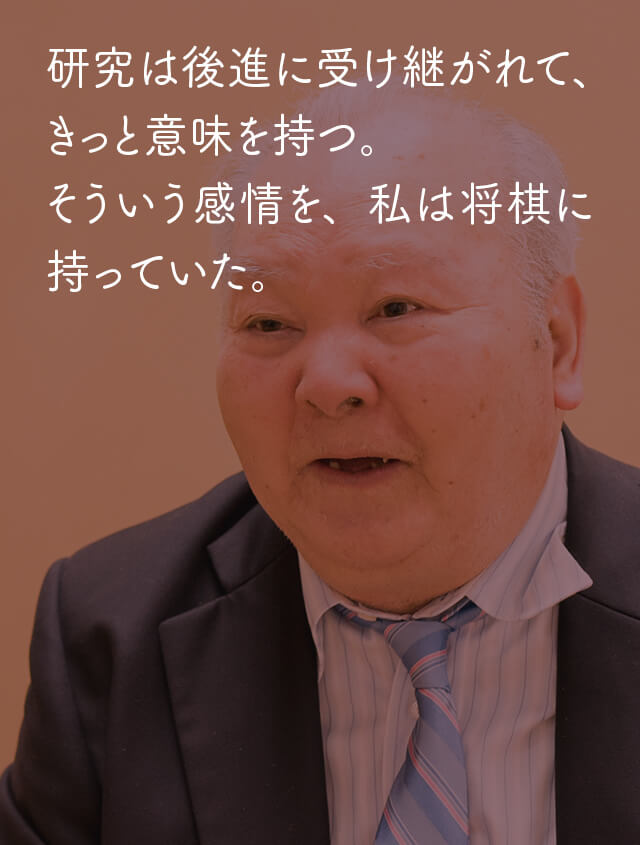
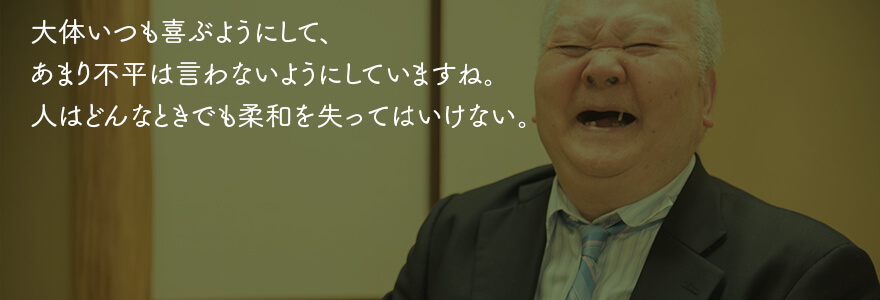
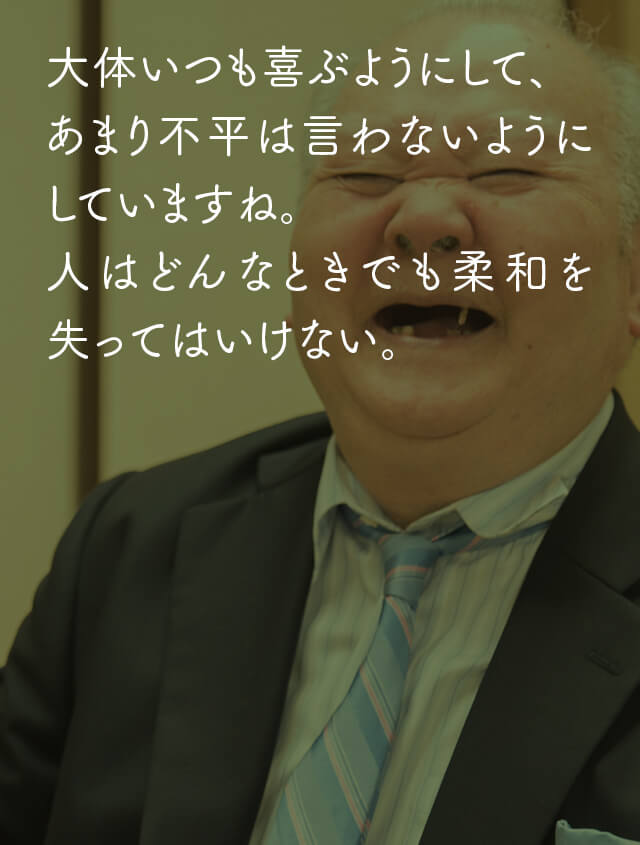

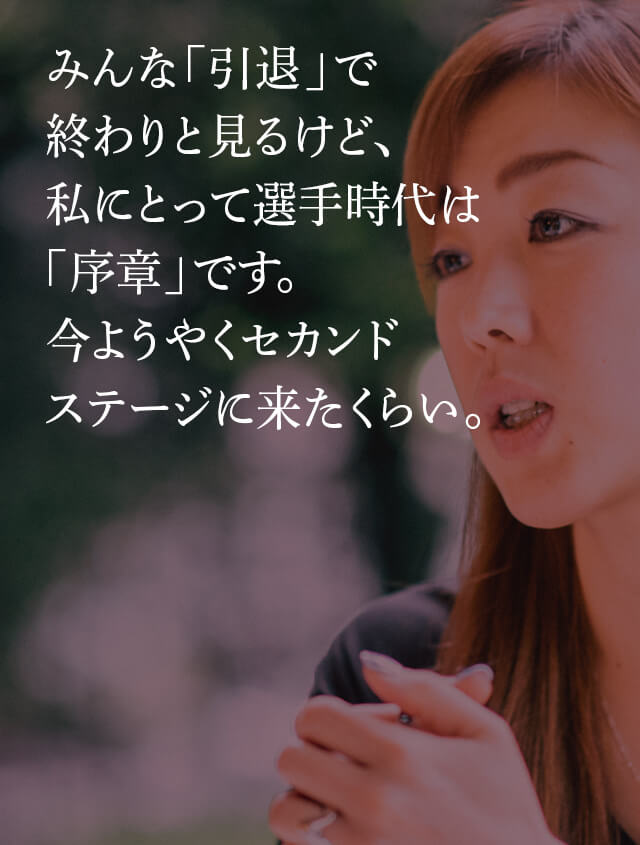
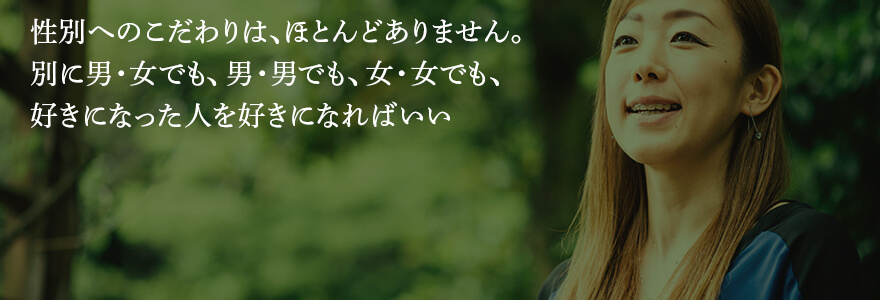
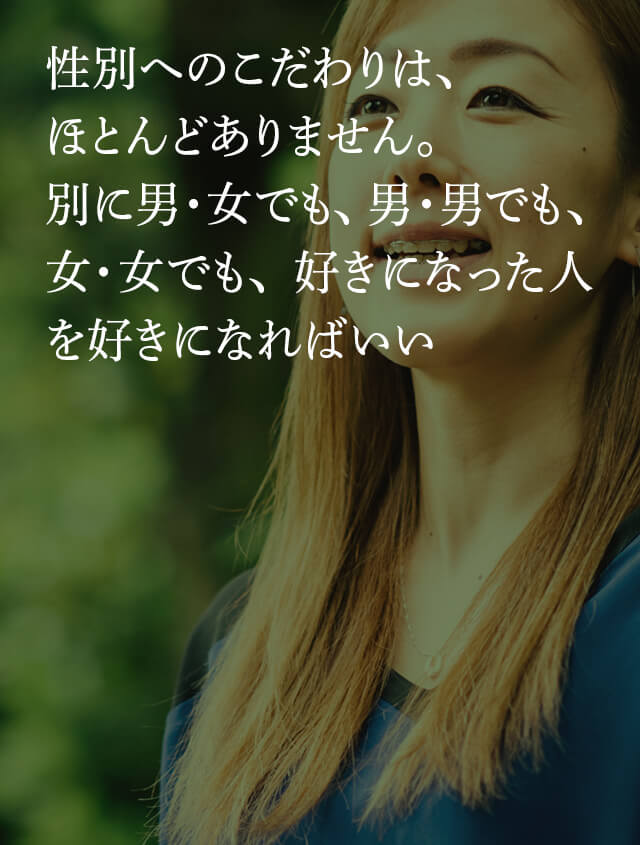
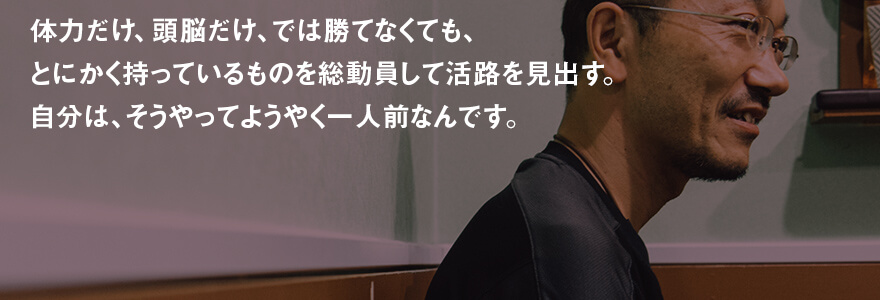
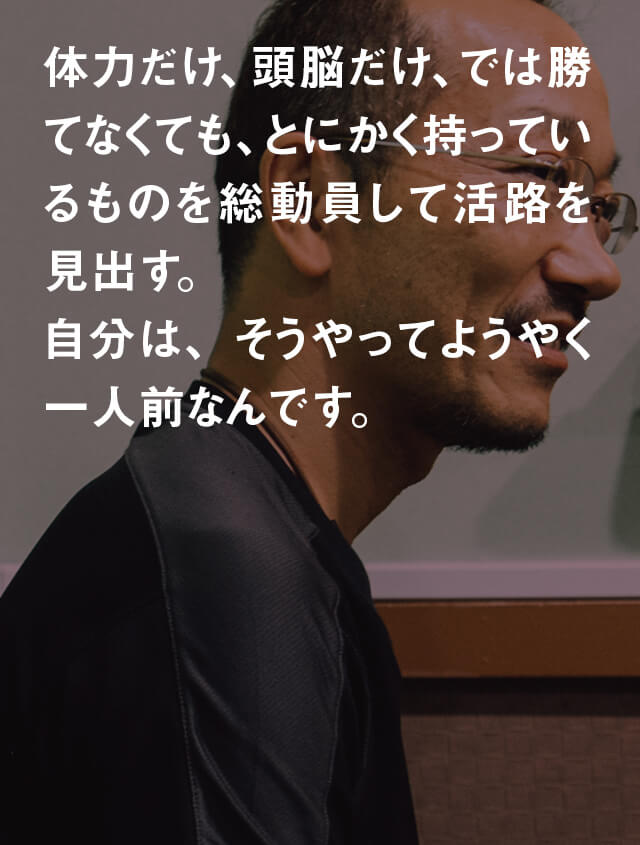
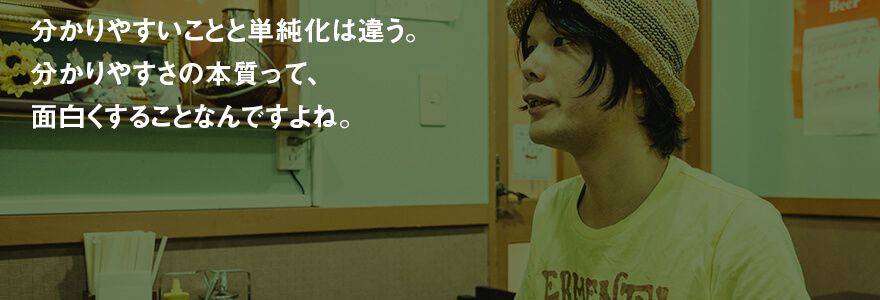
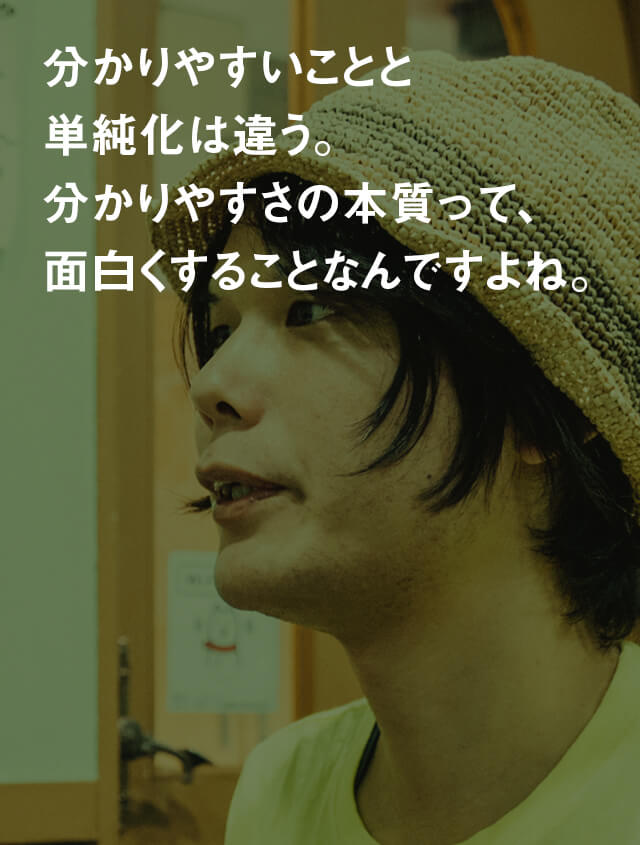
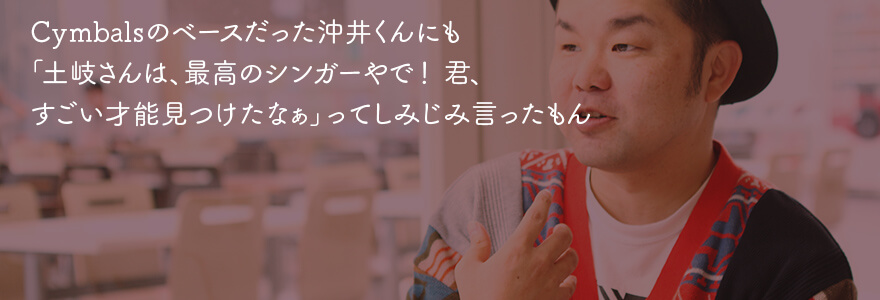
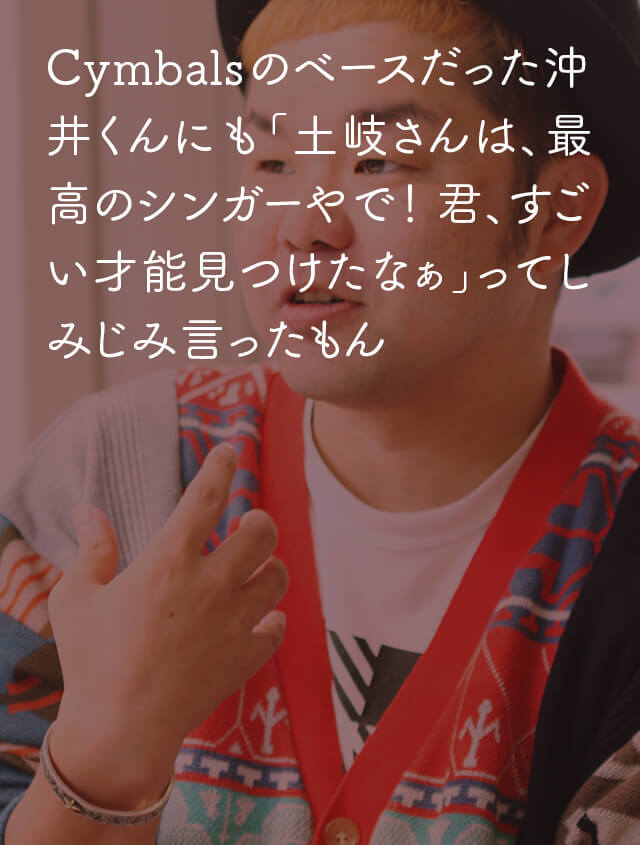
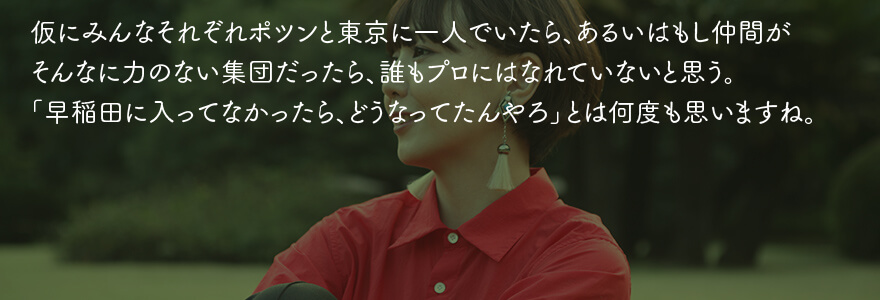
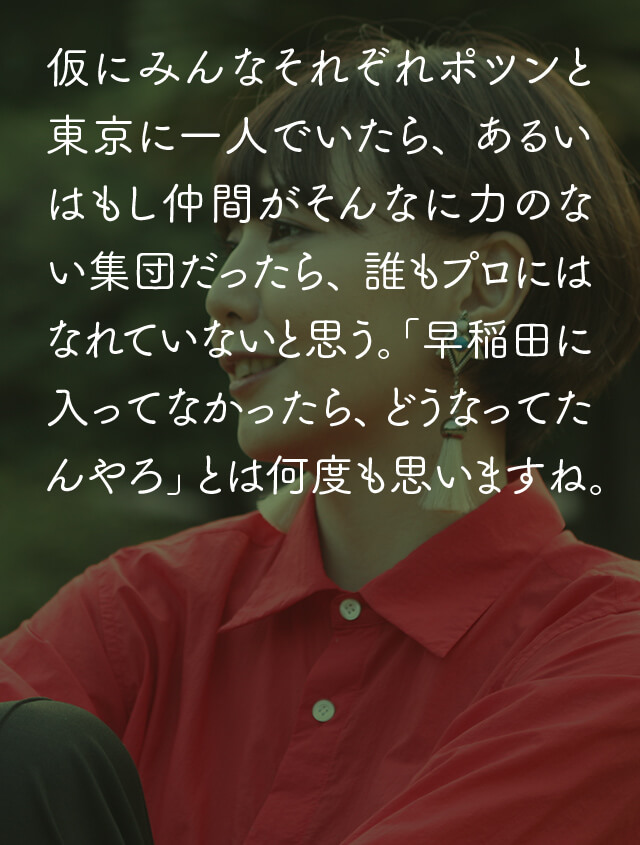
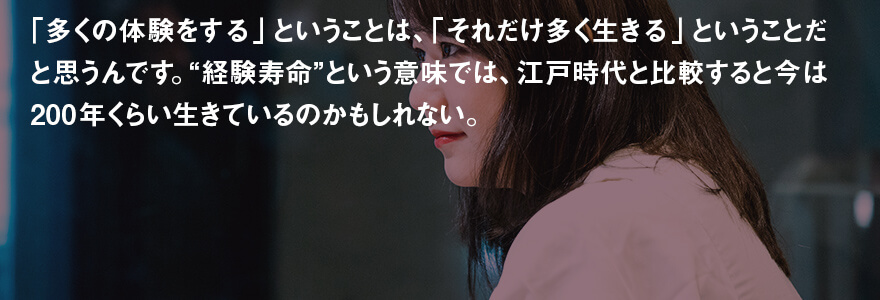
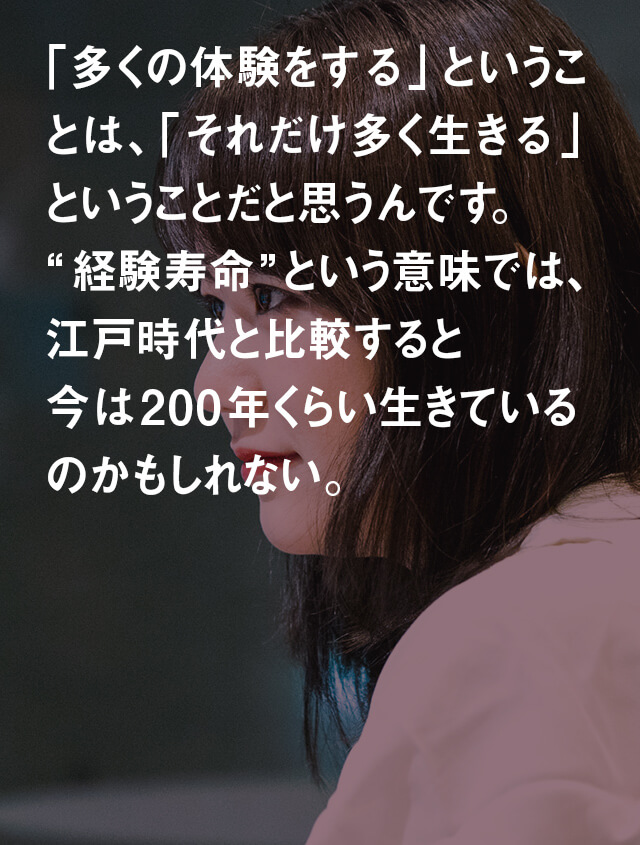
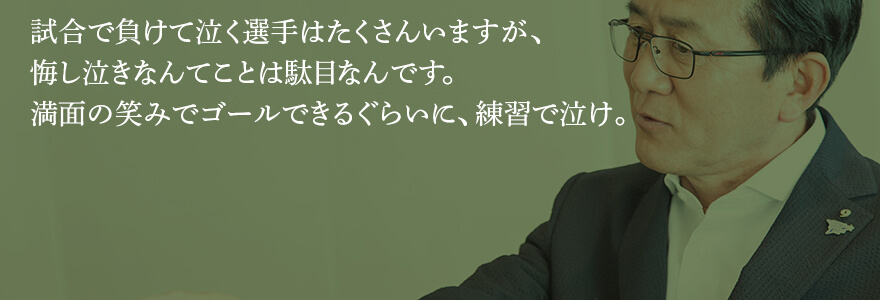
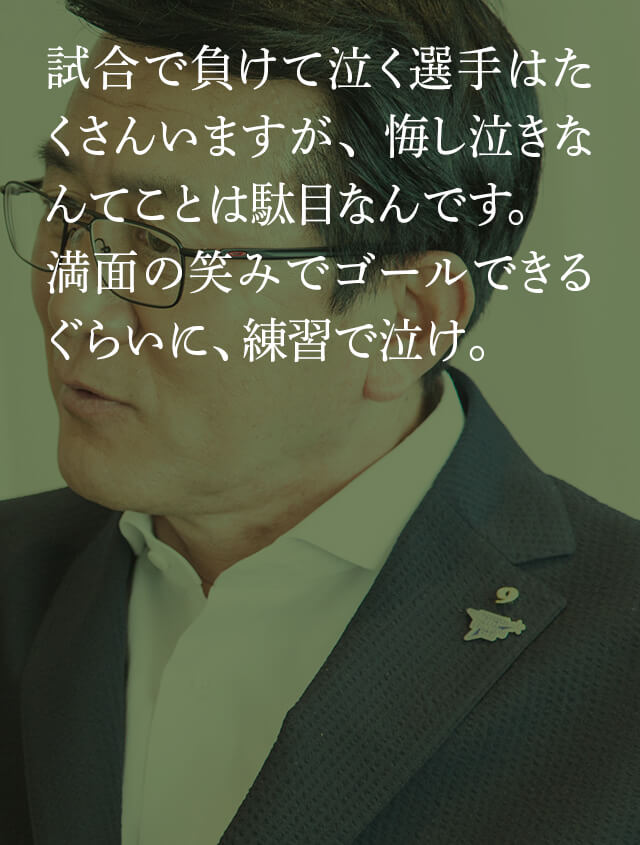
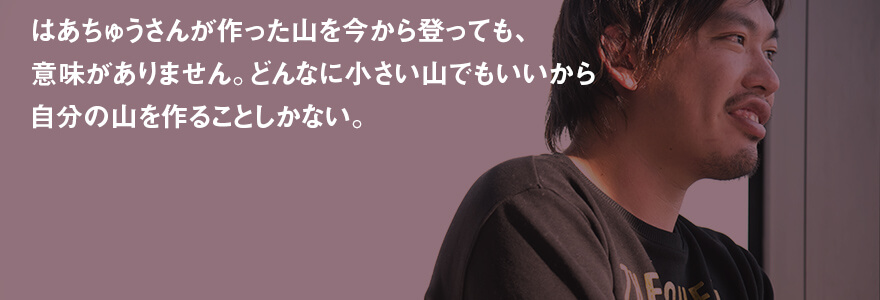
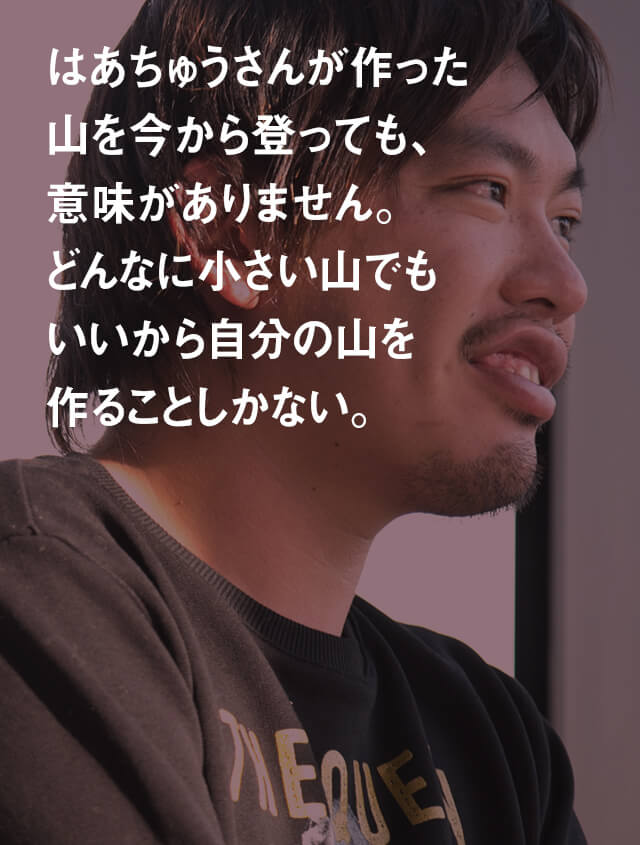
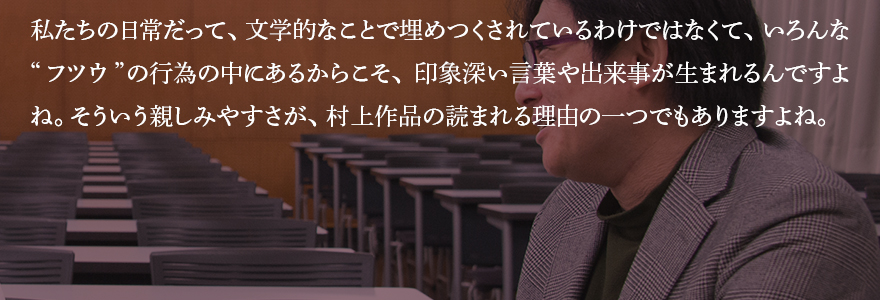
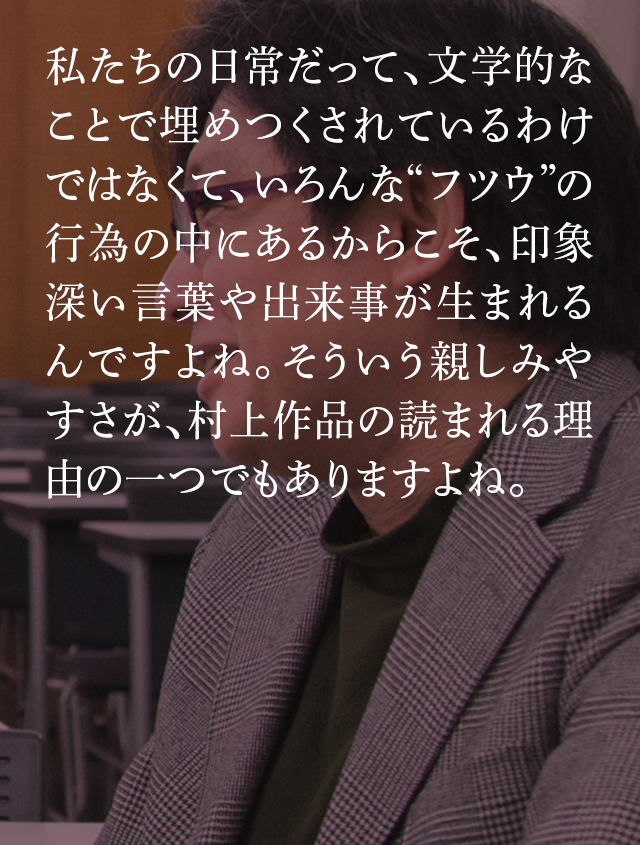
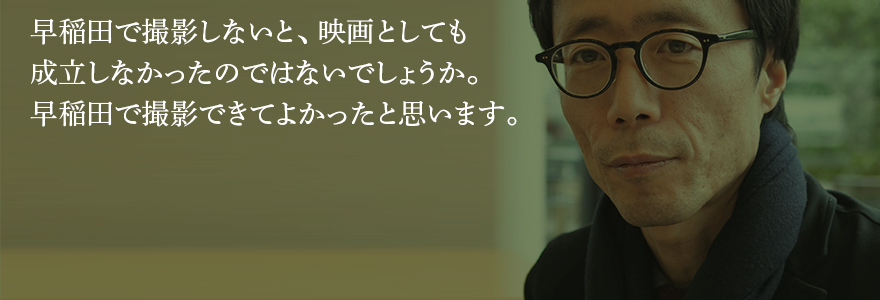
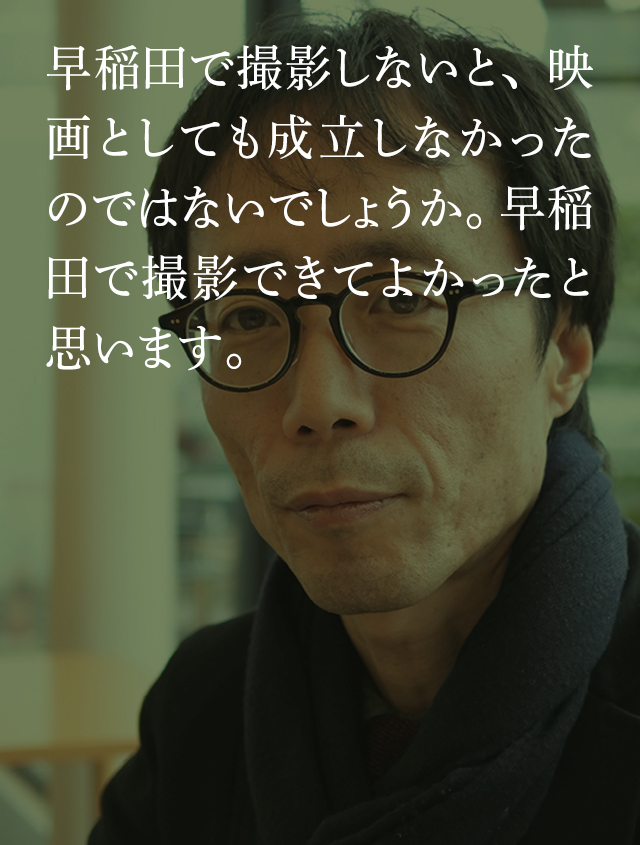
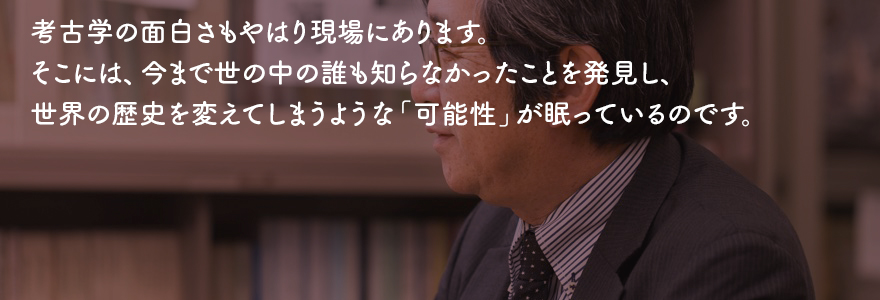
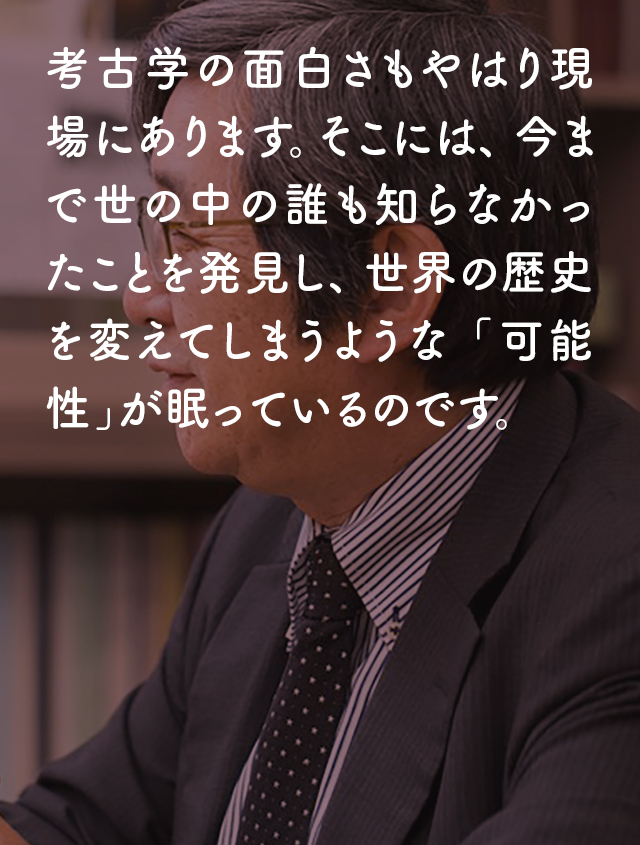
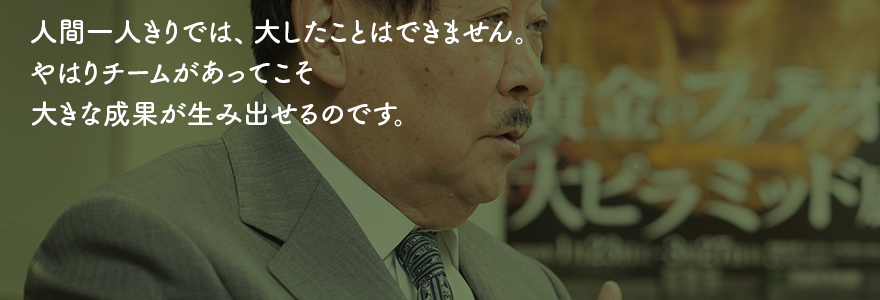
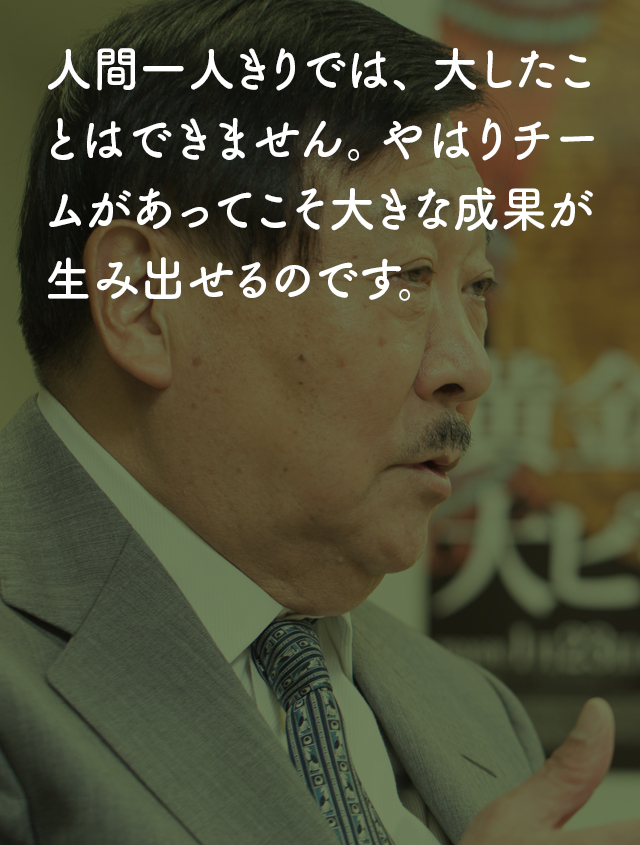
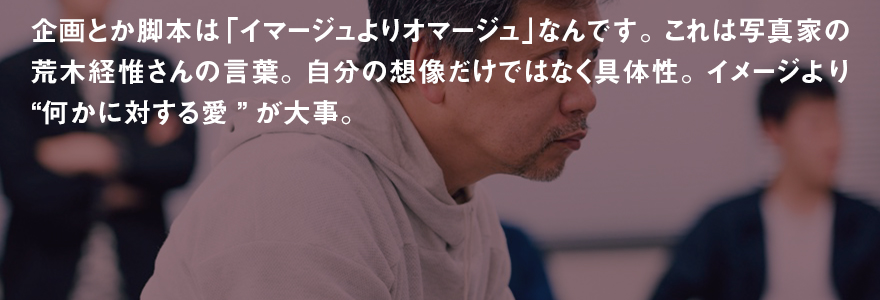
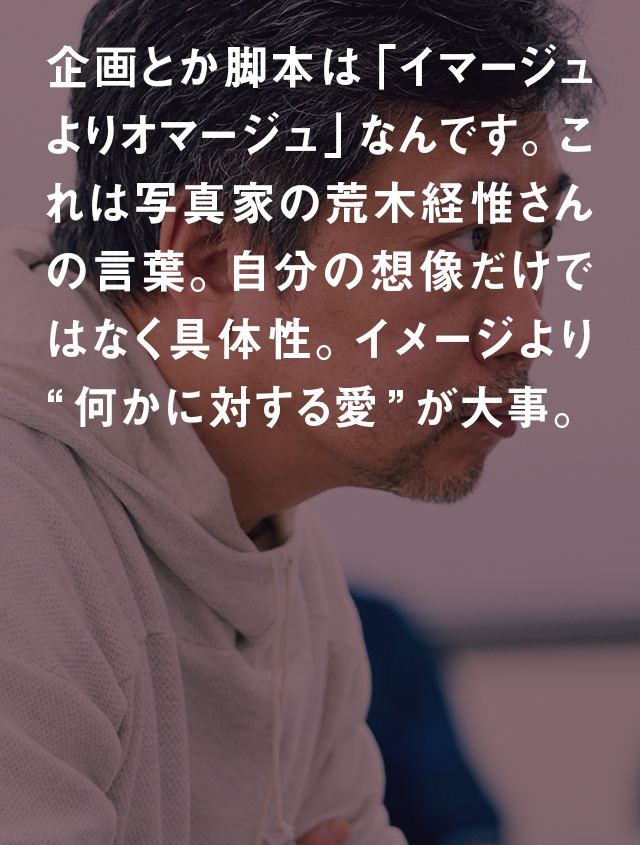
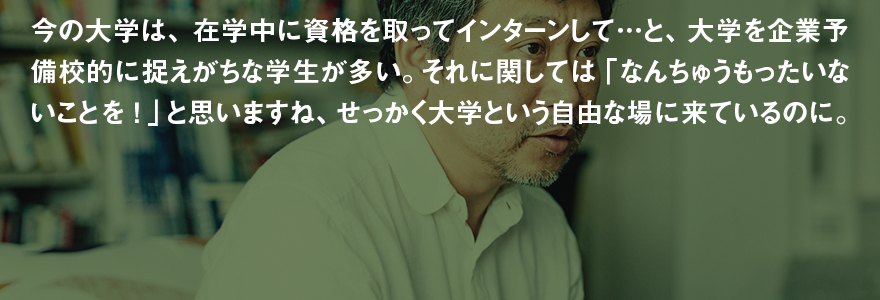
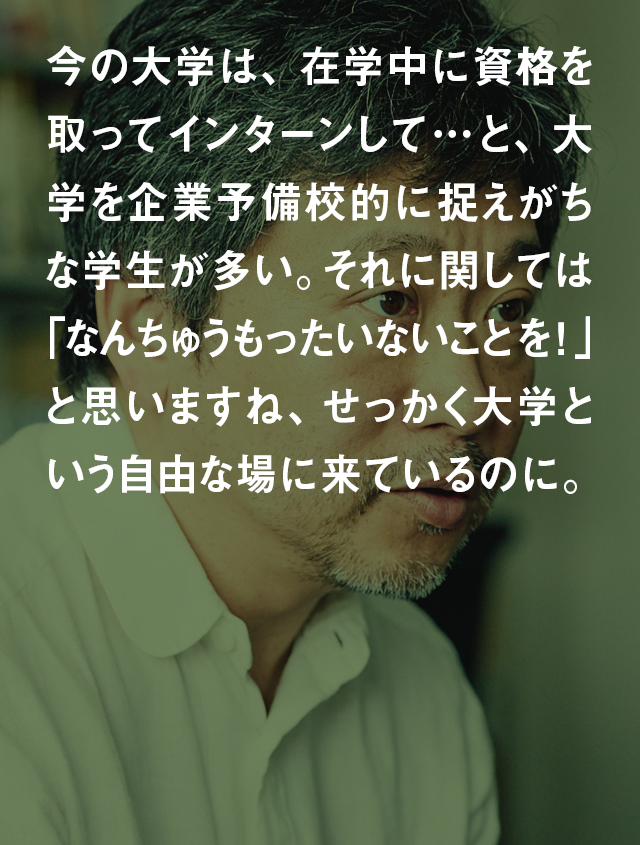
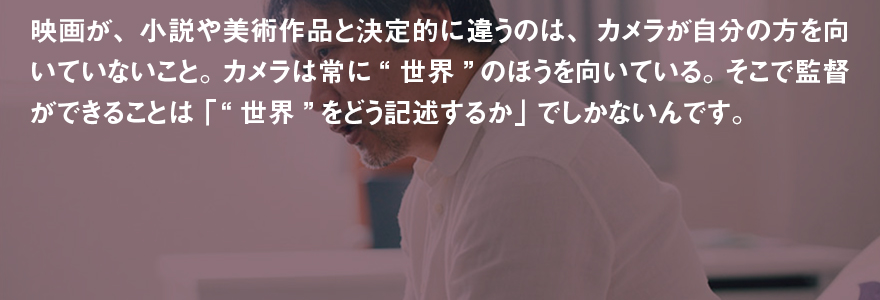
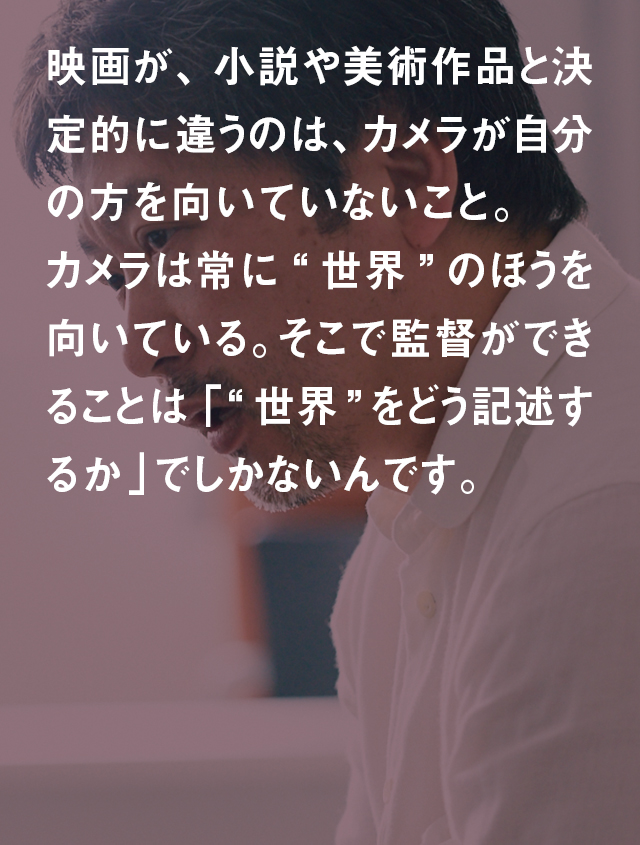
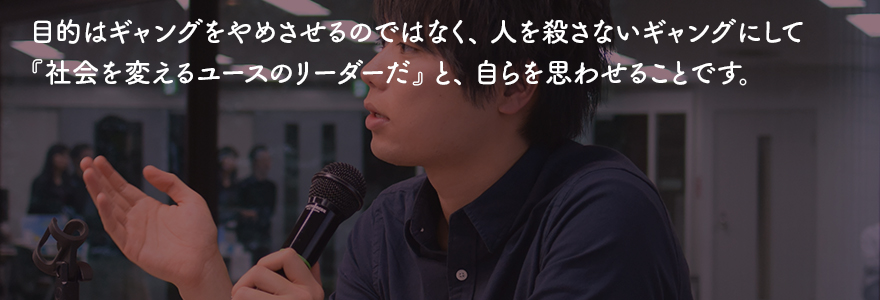
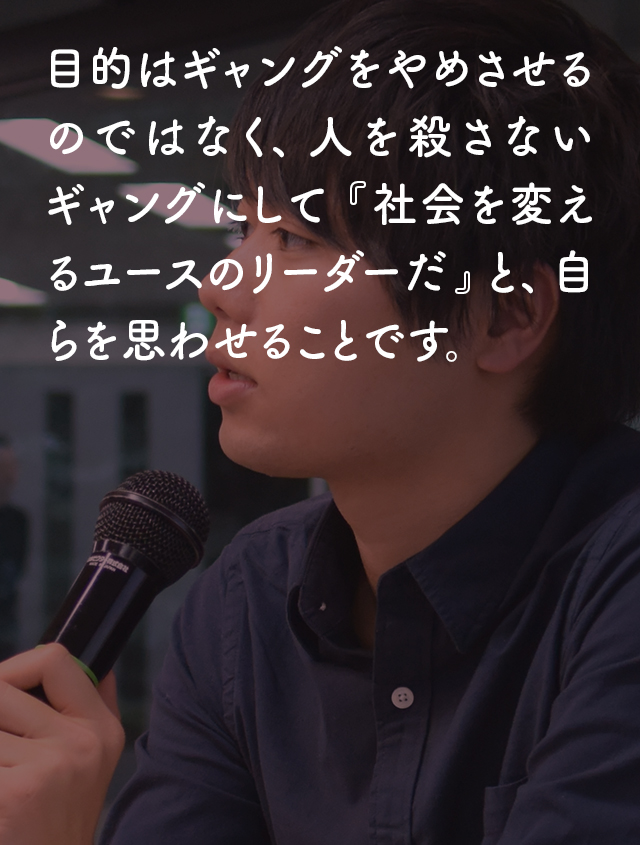
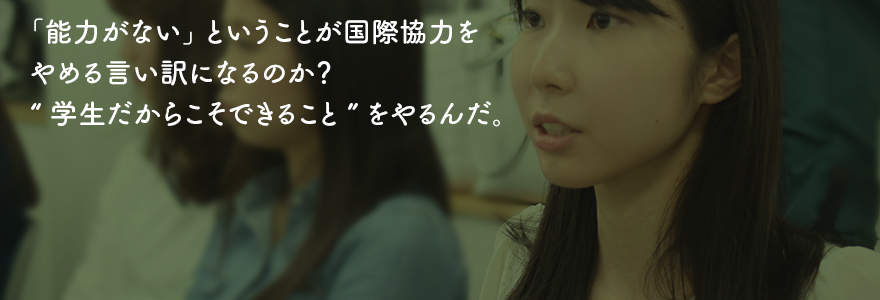
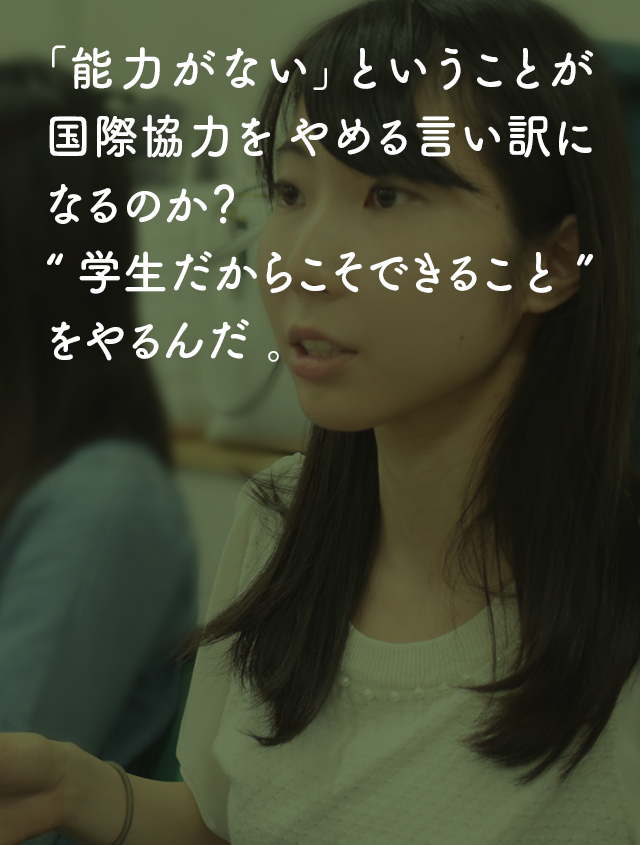
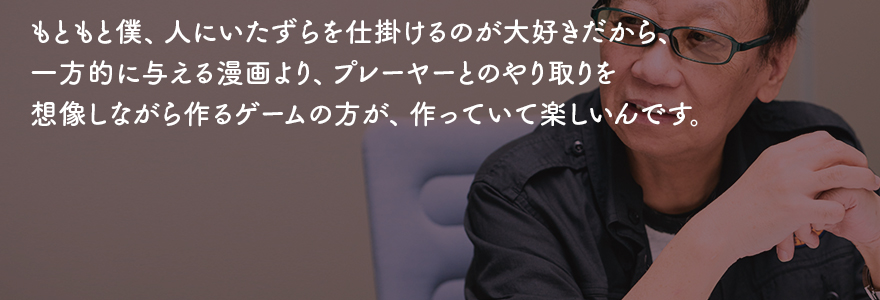
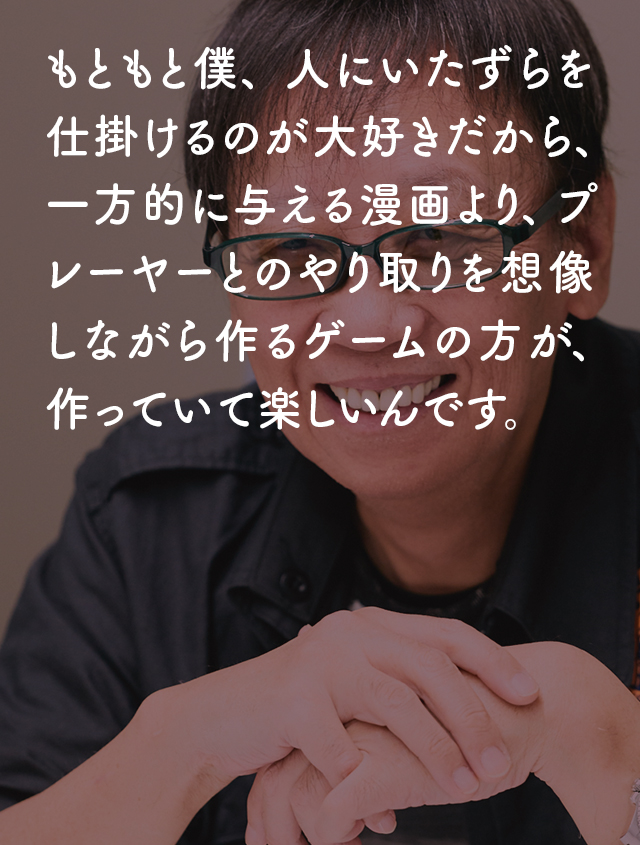
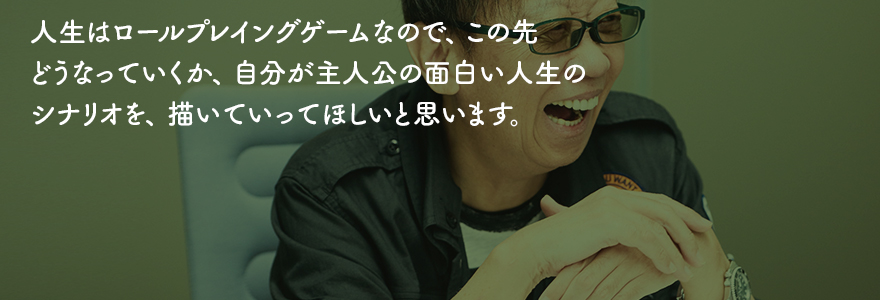
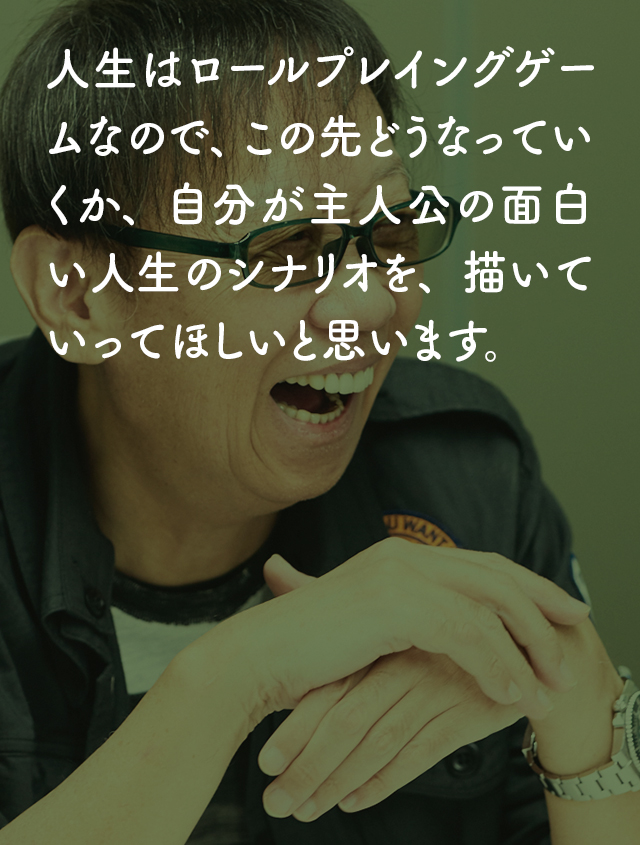
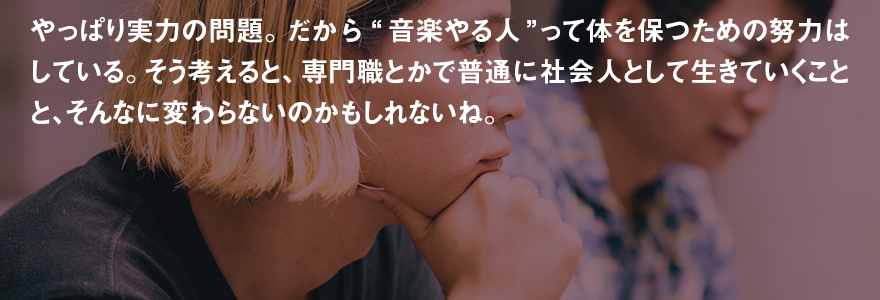

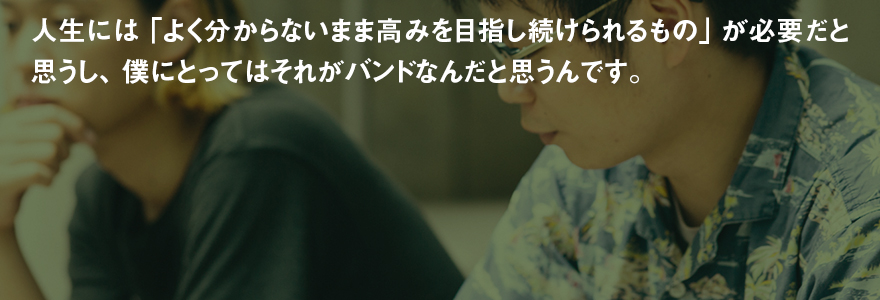
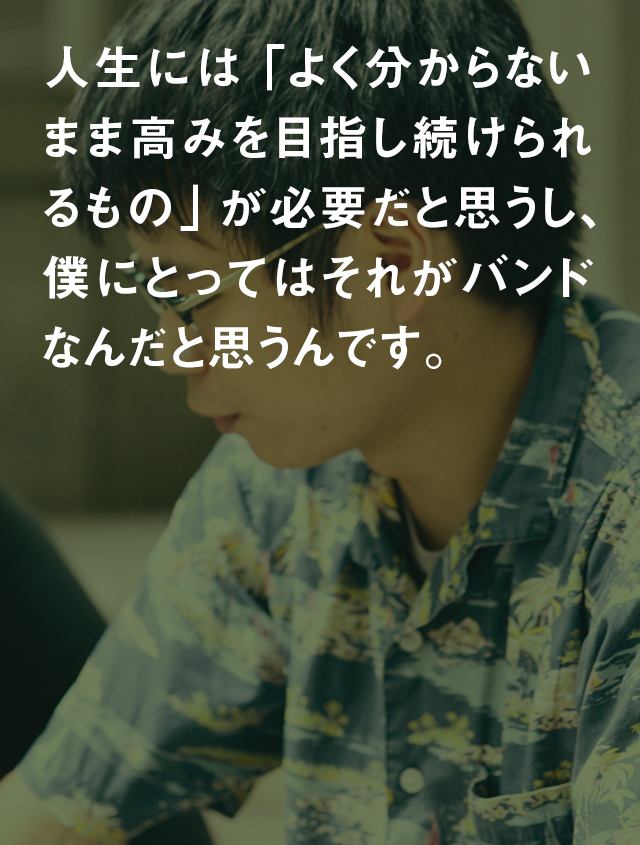
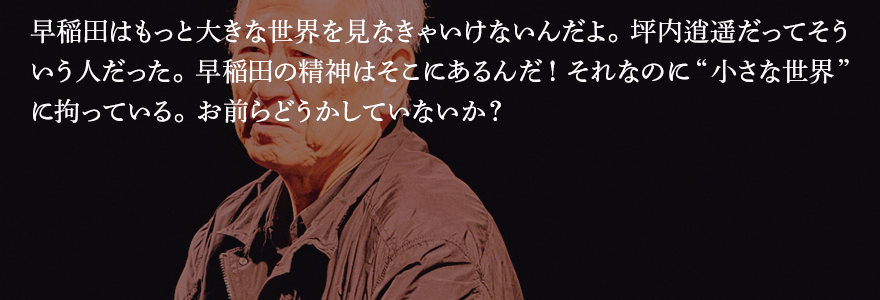
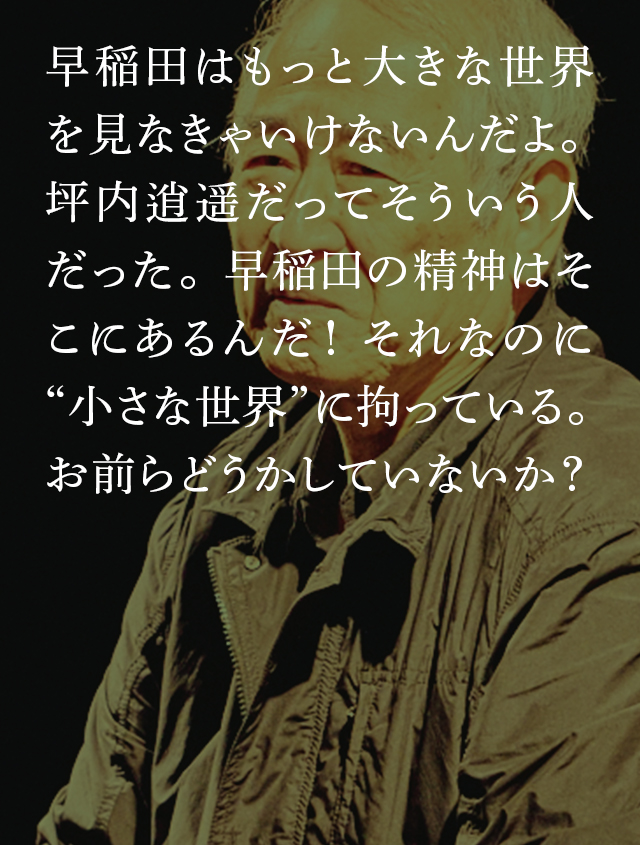
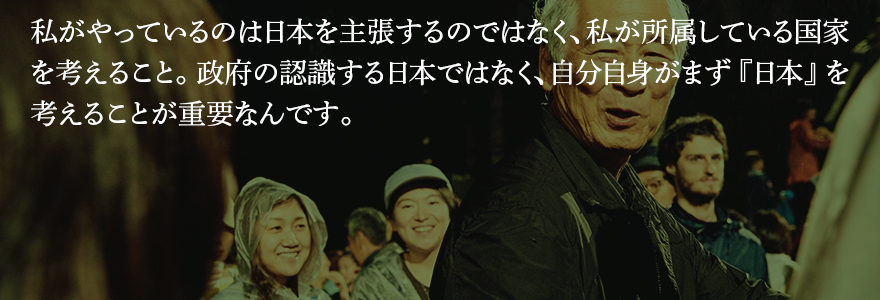
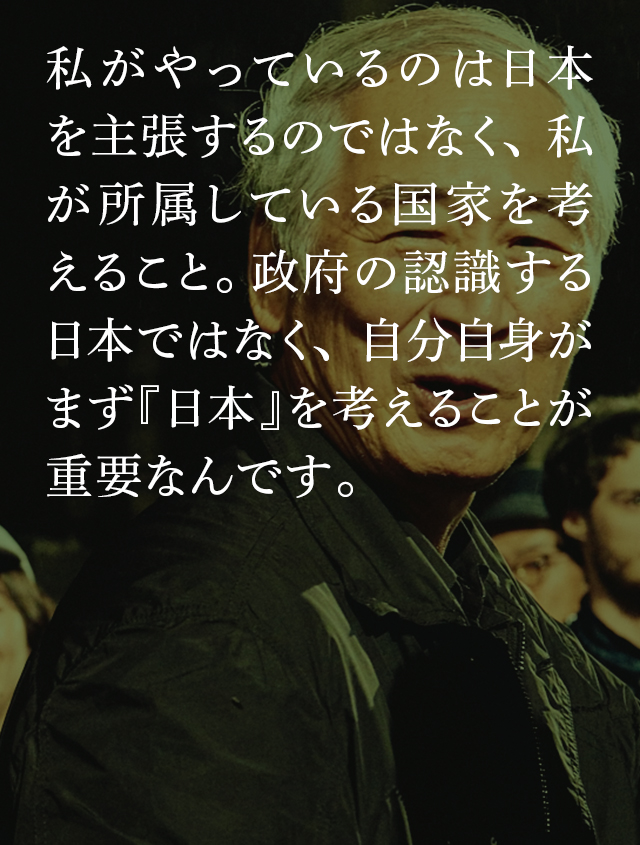
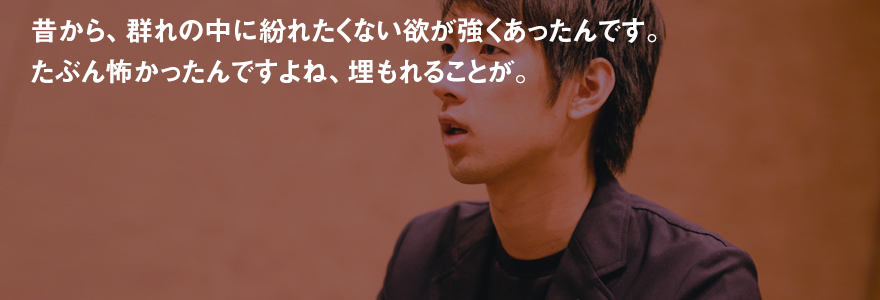
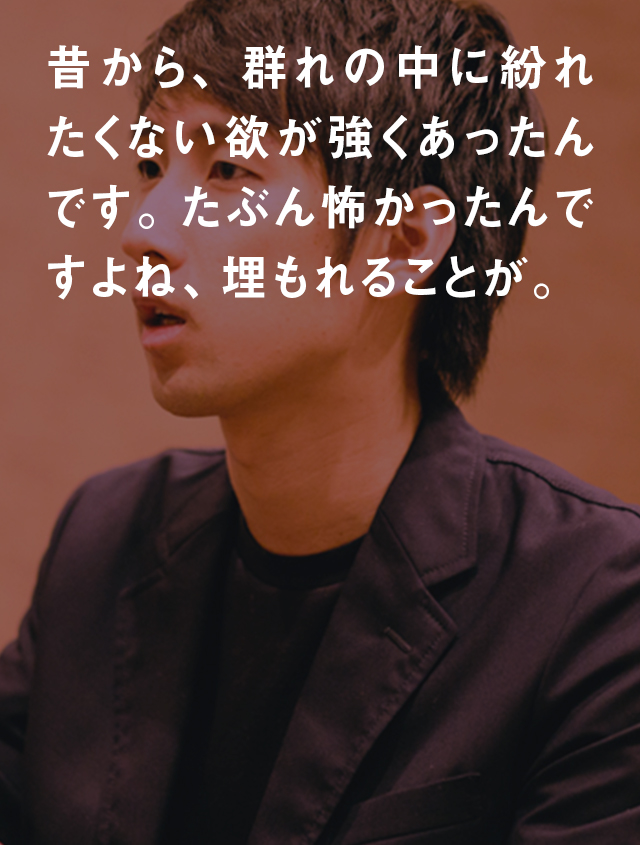
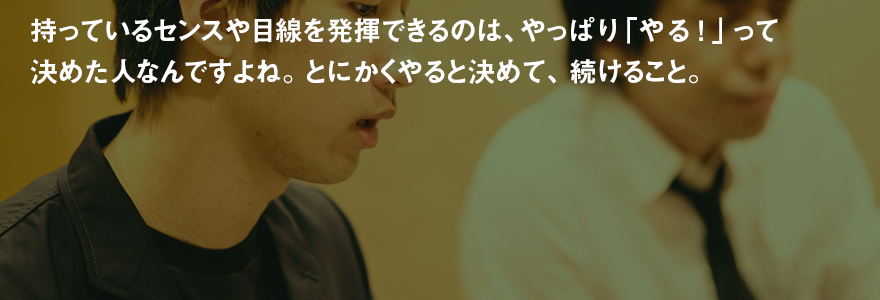
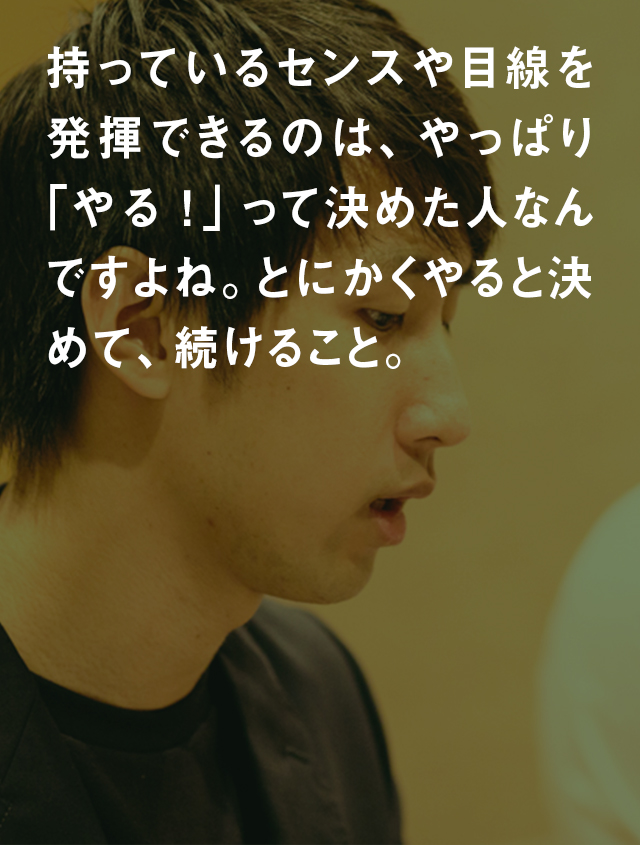
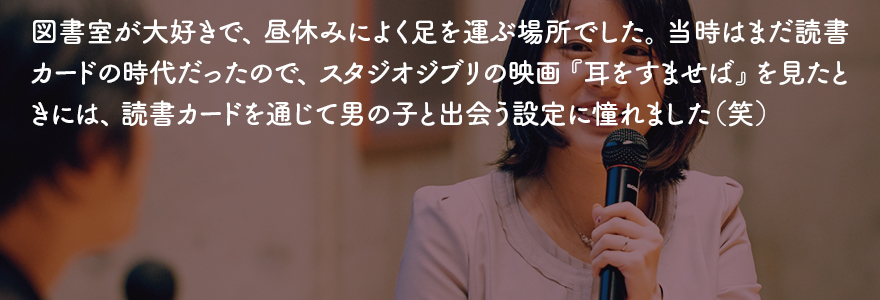

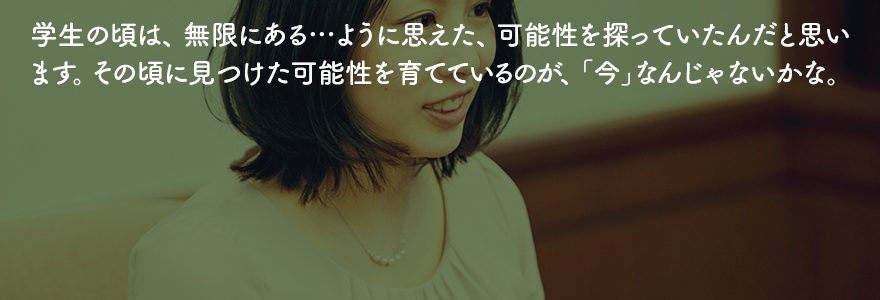
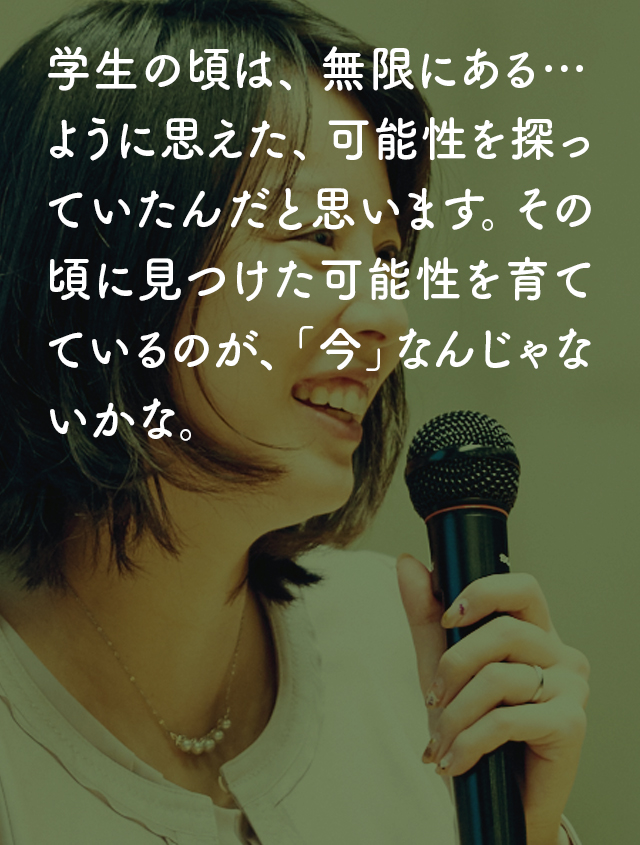
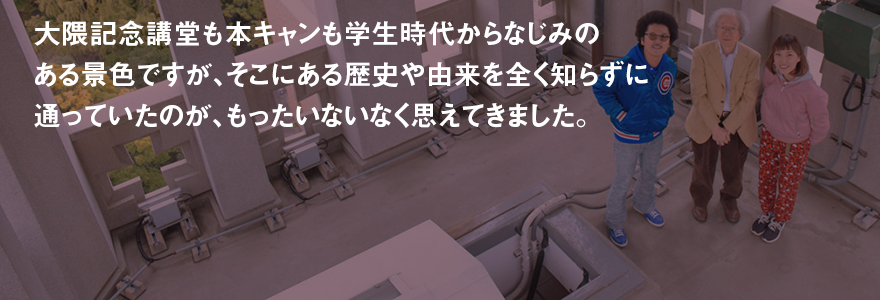
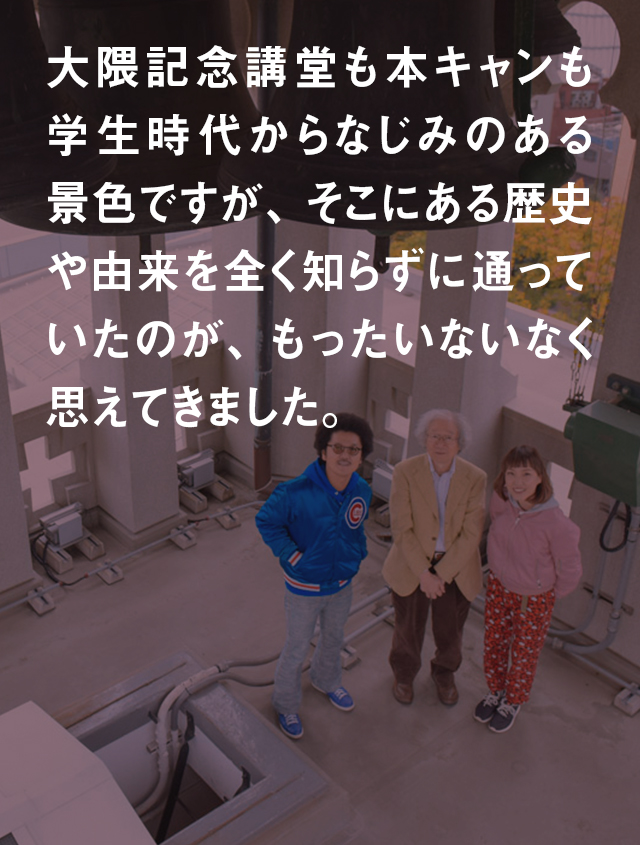
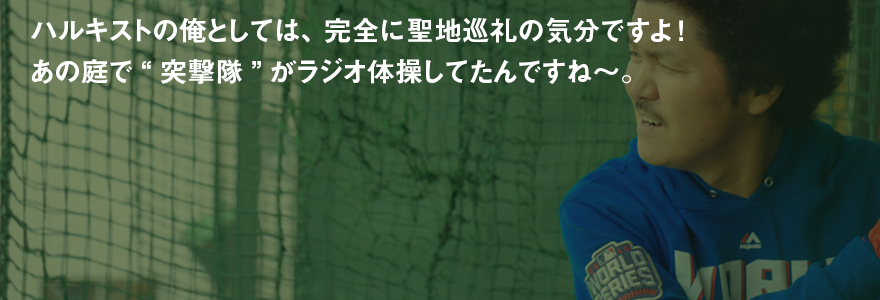
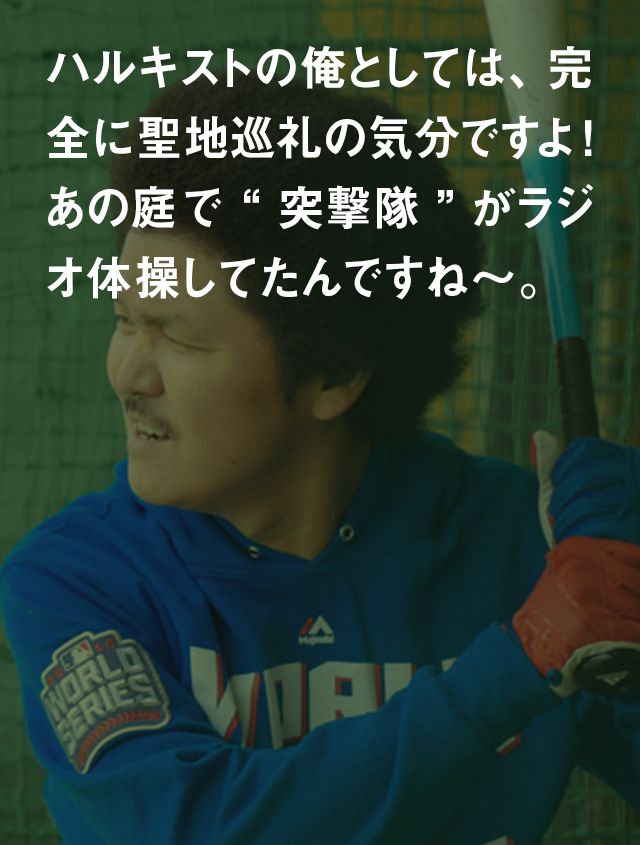
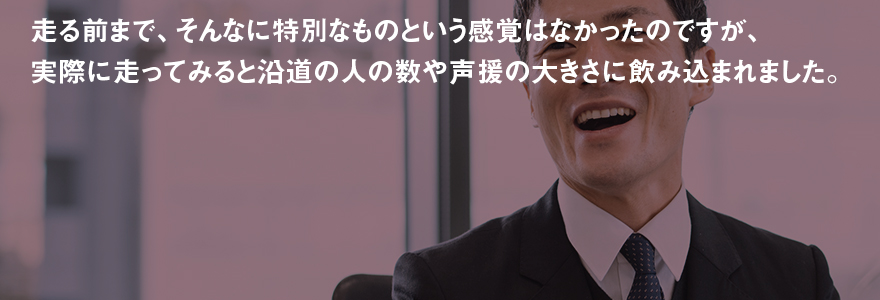
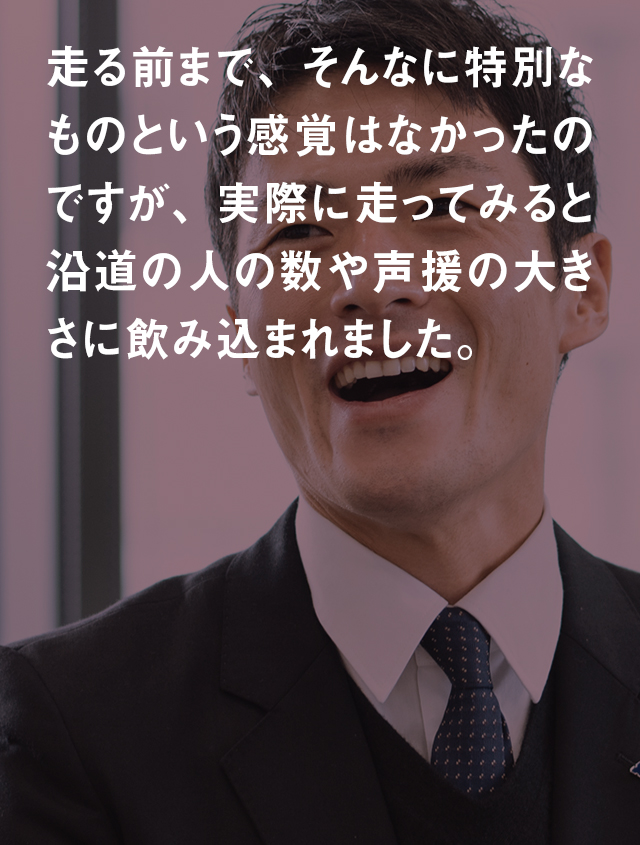
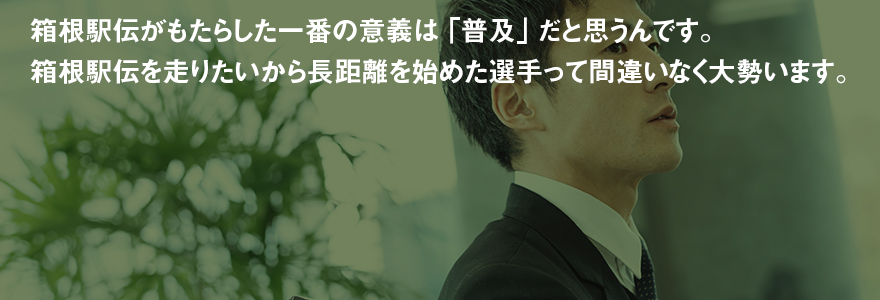
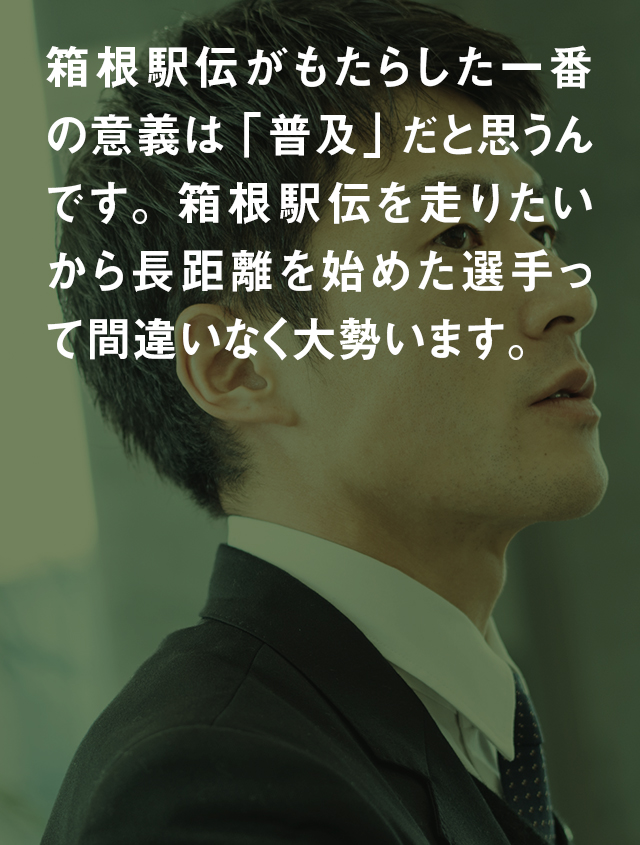
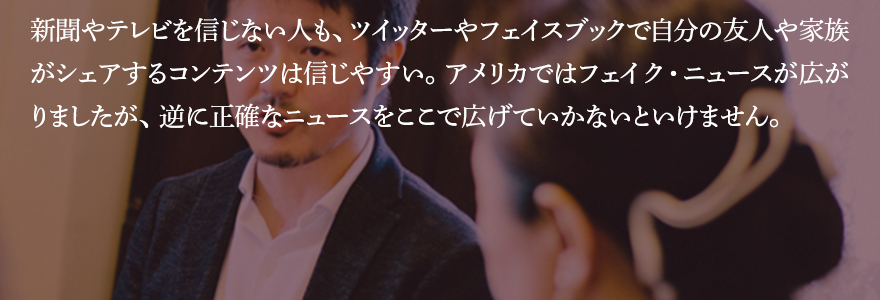
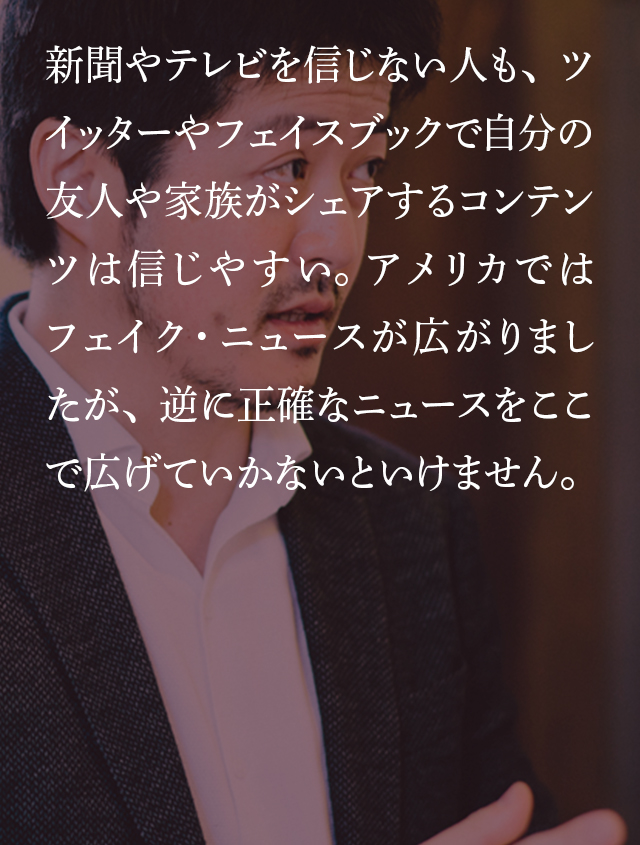
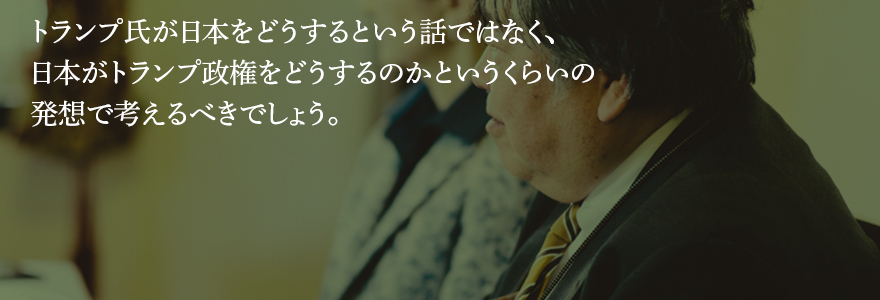
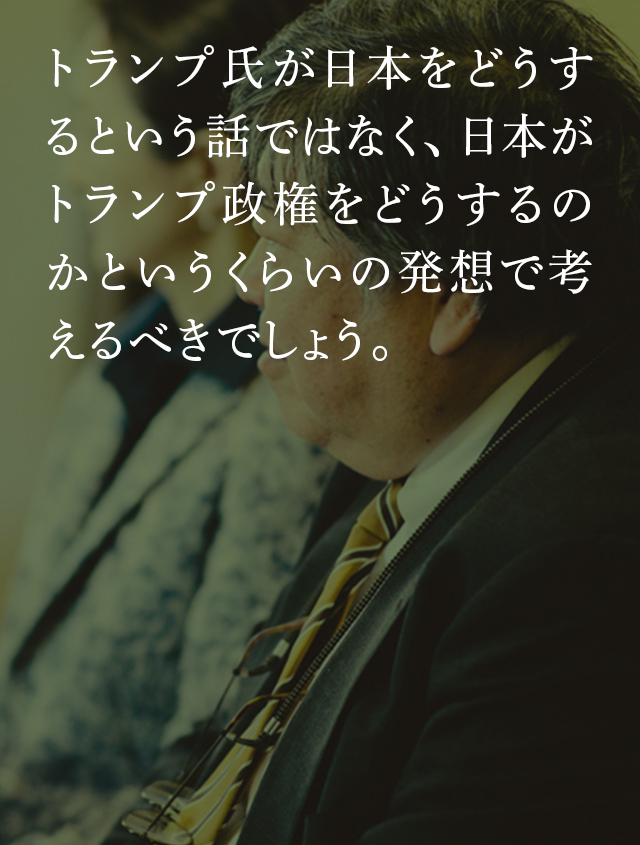
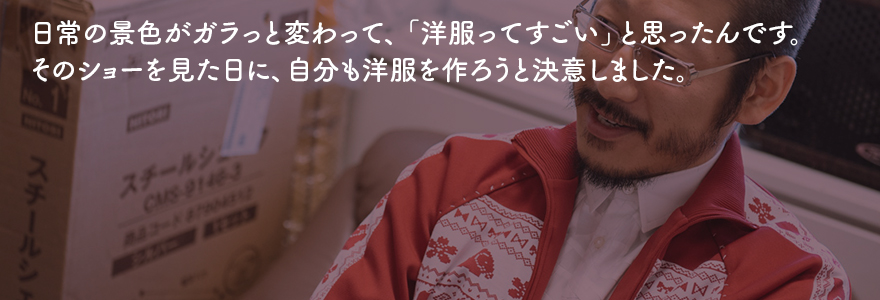
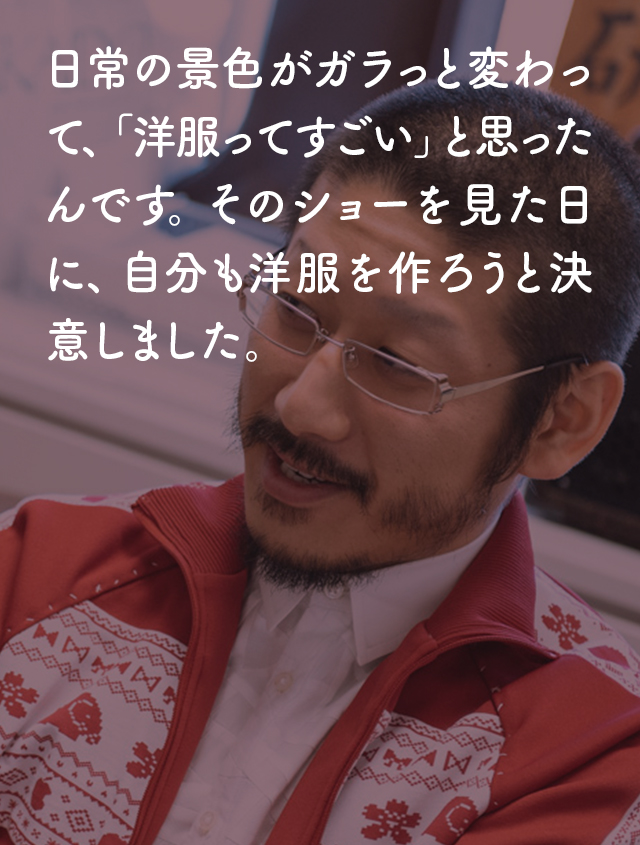

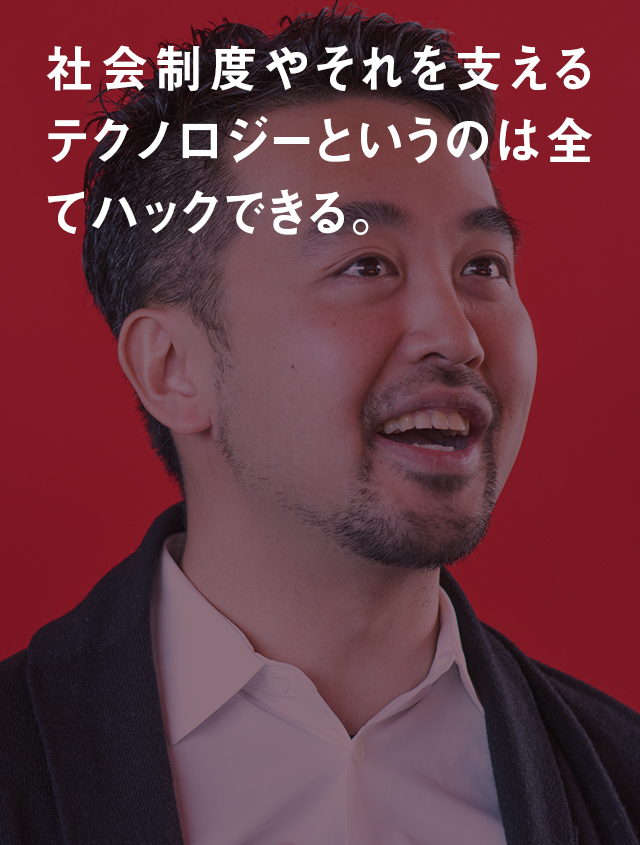
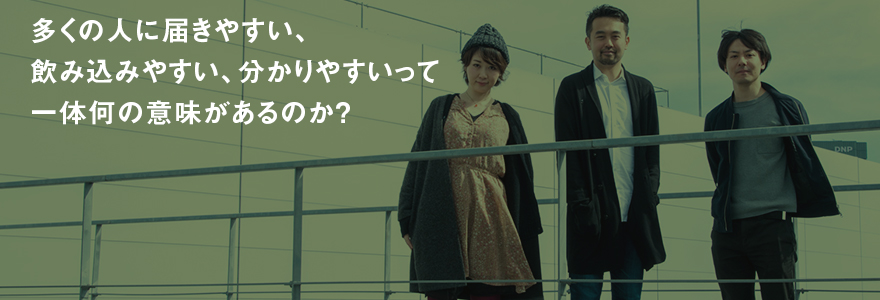
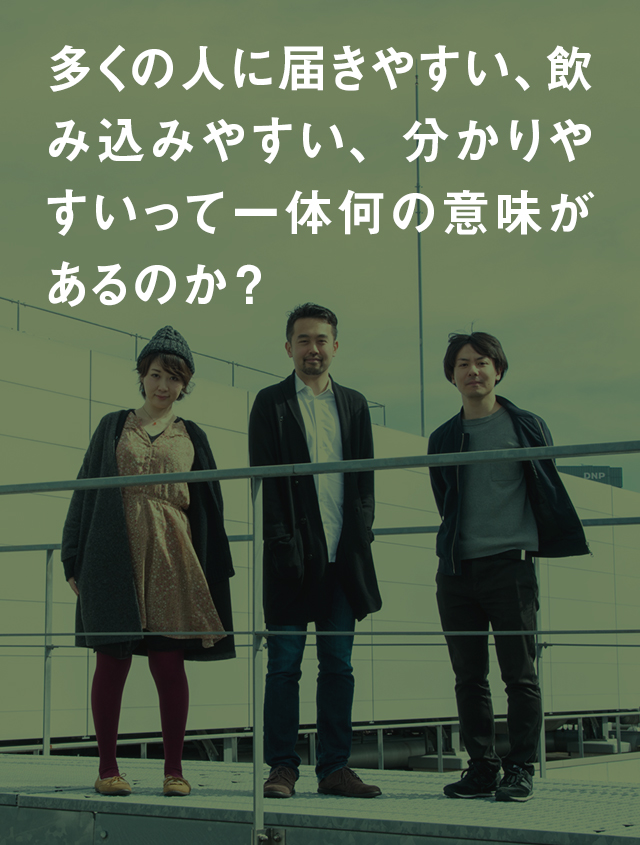


●私自身も構内を一人で動いているので、良い意味で関心を持った。一人の方が自由に気楽に行動できて良いが、やはり講義を休んでしまった時に「ノート貸して」と言える友だちがいないというのはなかなか辛いこと、また図書館やコンピュータルームがいわゆる「ぼっち」には最高の場所だということなど、お二人の対談内容には共感できるところがいくつもあった。教室の空き状況を公開し、一部を「ぼっち」の学生専用の自習教室のようにしてもらいたい。多様性を認める早稲田大学だからこそ、「ぼっち」にもそういった配慮があっても悪くはないのではないか。 (教育学部/2年/男)