

演劇や音楽、映画、小説…そんな表現活動はもとより、話したり、読んだり、書いたり、あるいは考えたりと、人間の生活と「言葉」は密接に結びついています。今回、そんな「言葉」について対談していただいたのは、劇作家で早稲田大学文学学術院教授でもある宮沢章夫さんと、『タモリ倶楽部』(テレビ朝日系)、『共感百景』(テレビ東京系)などのバラエティー番組にも出演し、自身のバンド「トリプルファイヤー」ではユニークな世界観を持つ歌詞を生み出している吉田靖直さん(2011年第一文学部卒)。ともにカルチャーの畑ながら、言葉に強いこだわりを持つ2人は、いったいどのようにして言葉と向かい合っているのでしょうか? そして、言葉にはどのような可能性が秘められているのでしょうか?

ー宮沢さんは劇作家として活躍されていますが、言葉について意識的になったのはいつごろからでしょうか?
- 宮沢
-
最初は、ま、誰でもそうだと思うんですけど、親の言葉、特に母親の言葉に影響を受けて幼少期を過ごしたと思うんですね。しかし、中学生のころに小説を読んだり、音楽を聞いたりすると、それまで聞いたことのないような不思議な言葉に出合います。その衝撃が自分にとってはすごく大きかったですね。
ただ、変だったのは、子供のころから、言葉の定義にうるさかったことかな。例えば、少し年長になってからだけど、みんなが平気で「パロディー」って言葉を使う。 「冗談」を意味するように「パロディー」を使うって、ほんと、気持ち悪かった。「パロディー」って全く違う意味だしね。あと、今だったら、あれだよね、 「サブカル」だよね。「サブカルチャー」ですよ、正しくは。1968年の『美術手帖』2 月号に「サブカルチュア」って言葉が登場して、日本で初めてこの言葉が、金坂健二さんの原稿の中で使われたんですね。まだ「サブカルチュア」ですよ、「サブカルチャ ー」ですらない。「サブカル」はいつ使われるようになったか、それは明確で、1990年の「SPA!」です。中森明夫くんと、山崎浩一さんが特集を組んだ「サブカル最終戦争」が 初め。で、この「サブカル」はね、僕の考えでは「サブカルチャー」とは全く異なるもので、特に90年代になって大きく変化したのが、その底辺を流れる思想なんですね。これを僕は「90年代サブカル」って呼んでるんだけど、「言葉」って、その変化って、「音」だけではなく、その意味内容にも大きく関わってくるよね。
少し話がずれたけど。その後、僕は…というのは、中学生ぐらいからの話に戻すと(笑)、 ボブ・ディラン(※シンガー・ソングライター。2016年度ノーベル文学賞受賞)の詩に触れ、彼の影響でアレン・ギンズバーグ(※1950年代に米国で活躍した、ビート・ジェネレーションの代表的人物。ビート・ジェネレーションとは、1950年代から60年代に現われた、当時の社会体制に反抗した作家たちの総称。英バンド「ビートルズ」などにも影響を与えた)に出会った。日本人では、フォークシンガーで詩人の友部正人さんの詩がとても好きで、そこから金子光晴(※詩人。自伝的エッセー『どくろ杯』などでも知られる)にさかのぼります。それまで知らなかった言葉に出合う。人は、言葉を通じて世界を見てるんですよ。それまで出合ったのとはと全く異なる言葉で世界を見る。これまでとは全く世界の見え方が変わりますよね。
ーでは、演劇の言葉に出合ったのは?
- 宮沢
- 僕は、24歳で芝居を始めましたが、俳優の竹中直人やいとうせいこう、シティボーイズらと「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」として活動し、演劇の世界とは縁のない舞台を作っていました。だから、演劇人としての意識は全くなかったんですね。30歳を過ぎて、といっても年齢は関係ないんですが、ま、ちょっとした出会いがあって「遊園地再生事業団」という集団で舞台を作 るようになった。それから「岸田戯曲賞」を受賞して初めて演劇人としての意識を持つようになります。
ー部外者として演劇に関わり始めた宮沢さんにとって、当時の演劇の言葉はどのように感じられていたのでしょうか?

- 宮沢
- 何よりね、「なんでこんなに大げさなんだろう?」と感じていました。「もっと普通の言葉があるんじゃないか」「言葉はそこまで前に出なくていいんじゃないか」とかね、「なんでも言葉で説明しちゃう」って、疑問だったんです。例えば、時計を見て、「今日は初めてのデート。彼女遅いなあ」なんて語り出してしまう人間はどこにもいないですよね(笑)。
- 吉田
- 確かに大げさですね(笑)。
- 宮沢
-
大げさっていうか、説明的。でも、そんな言葉を劇作家は書いてしまいがちなんです。演劇の言葉はもっと隠してもいいし、省略してもいいはず。また、その上で「定型的な言葉」からどのように逃れるか? という意識もありましたね。以前エッセーに書いたことがあるんですが、死刑囚の中には短歌を詠む人が多い。
連合赤軍のリーダー格の一人で、「あさま山荘事件」(※1972年、テロ組織「連合赤軍」が長野県の山荘に人質を取って立てこもった事件)の首謀者である坂口弘死刑囚が、詩集の中で「被告なれど生ける吾が身はありがたし 亡き同士らの言えざるを思えば」、つまり「同志たちは殺されていくが私は生きている」という歌を作っています。そこに彼の苦悩があるとはいえ、感情や意識を言葉にするとき、普通の言葉で書くと不謹慎になってしまう。だから「仲間は殺されたけど、僕は生きていて、どうも申し訳ないっす」じゃ、 まずいんですよ(笑)。だけど短歌という定形に当てはめると「もっともらしく」なる、っていうことがある。不思議でしょ。

ー演劇の言葉でも、感情を込めたり大声で叫ぶことによって「もっともらしく」なるような定形がありますね。
- 宮沢
- 定形ではない普通の言葉で、内面の感情や意識を吐露できるのではないか? その言葉を話すときはどういう身体なのか? そんな疑問が、その後の演劇論や演劇観につながっていきます。別にでかい声出したら、苦しんでいるとか、悲しんでいるってことにならないでしょ。肉親が死んだ家族はひそやかな声ですよ。
ー宮沢さんをはじめ、岩松了さん、平田オリザさんなどが生み出した、あたかも日常で生活している人々がそのまま舞台に上がったようなナチュラルな演劇スタイルは、90年代に「静かな演劇」「現代口語演劇」と呼ばれ、その後の演劇にも大きな影響をもたらしました。
- 宮沢
-
定形と共に、もう一つ特徴的だったのは、「詩的」といわれるような言葉の在り方を捉え直したことでしょう。美しい言葉だけが詩的かといえばそうではありません。1956年にギンズバーグの発表した『吠える』(思潮社『ギンズバーグ詩集』収録)の言葉がどうして生まれたのか、「サブカルチャー論」の授業で僕は話していますが、何よりギンズバーグにとって大きな転機になったのは、自身の意志で入った精神病院で知り合ったカール・ソロモンから大きな刺激を受けたからです。「人の気持ちを刺激するような鋭いナイフのような言葉が詩である」という薫陶を受けたんですね。
それによって、彼はきれいな言葉だけが詩ではない。もっと乱暴な言葉、下品な言葉であっても美しさをもたらすことがあると気付くんです。ギンズバーグの影響下に60年代の詩があり、その延長線上に…といっても、その間に唐十郎がいて、寺山修司がいて、野田秀樹がいたように、さまざまな言葉の冒険はありましたけどね。それが全て、あるとき恥ずかしくなる。いわゆる詩的であることや、オーソドックスな演劇言語から逃れた先に、また新しい言語的な冒険として現代口語演劇があると思います。


ー吉田さんは、トリプルファイヤーの歌詞や大喜利での言葉などを見ていると、特殊な言語能力に驚かされます。いつごろから、言葉を意識するようになったのでしょうか?
- 吉田
- 小学生くらいのころはお笑いコンビの「ダウンタウン」がとても好きだったので、その影響はあると思います。その後いろんな音楽や本を知っていく中で、意外な言葉同士の組み合わせの面白さを感じていきました。でも僕が今歌詞を作るとき大事にしていることは、言葉をどのように選ぶのかというよりも、どこに視点を置くかということや、どんな角度からモノを見るのかということです。意識して変な言葉を探すというよりも、何か見落としているところはないかと探しているんです。
ー「スキルアップ」では、小沢健二の引用を交えつつ、<以前はこうして棒を突き刺したり 風船を膨らせたりする毎日に 何の意味があるのかなんて 考えたこともあったけど 指導力のある上司や 充実した設備のおかげで 確実にスキルも付き ここまで大きな現場を任されるようになりました ありがとうございます スキルアップ!>といった意味の分からないアルバイトをテーマにしたり、「カモン」では、ライブでいまいちノレないお客さんをテーマにしたり、誰も注目していなかった視点から歌詞の世界を作り上げています。そもそも、初めからこのような歌詞を作っていたのでしょうか?
- 吉田
- やっぱり最初は、歌詞ってかっこいいものだと思っていたので、「月明かりが映る…」「風が窓をノックしたら…」といった、ちょっと詩的でさりげない歌詞を書こうと思っていました。めちゃめちゃしょうもないことしか思い付かない人間なのに、そういったキレイな歌詞を無理矢理考えていたんです。そうしたら、自意識が気持ち悪い感じで言葉になってしまい、吐き気がするような歌詞ばかりになってしまった(笑)。
ーそんな吉田さんの歌も聴いてみたいです(笑)。歌詞が変わっていったのはなぜでしょうか?
- 吉田
- 以前、「言語化されない部分をすくい上げるのが詩人の才能だ」という話を、どこかの本で読んだことがあります。先ほどの宮沢さんのギンズバーグのお話のように、それは汚いもの、乱暴なものかもしれません。そんな発想を知ってから、自分のやることを見つけたという感じがします。

ーお二人は、演劇と音楽というフィールドの違いを持ちながらも、安易に「美しい言葉」や「定型的な言葉」を目指さずに、よく分からない何かを言語化するということに向き合っています。その意味では、言葉に対しての態度が共通しているのではないでしょうか。
- 宮沢
- よく分からないことを言語化することはとても難しいことです。学生にも、授業や発表の感想を書いてもらうときには「何かもやもやした感覚を何とか言語化してほしい」と言っています。書くことによって、自分と向かい合いながら、自分が感じているもやもやに対して言葉を与えていくと、新たな言葉が見えてくる。言語化するという行為はとても大切なことなんですよ。
ー特に人文系学部で学ぶのは、そんな「言語化」の方法かもしれませんね。

- 吉田
- ただ、僕の場合はあまりにもバカバカしいことばかり思い付いているので、宮沢さんと同列ではないような気がします…。
- 宮沢
- 僕もバカなことばかり思い付きますよ。あまりのくだらなさに自分で笑ってしまいます。先日、古いノートを開いて見つけた昔のメモには「崖の上のベトナム人」と書いてありました(笑)。
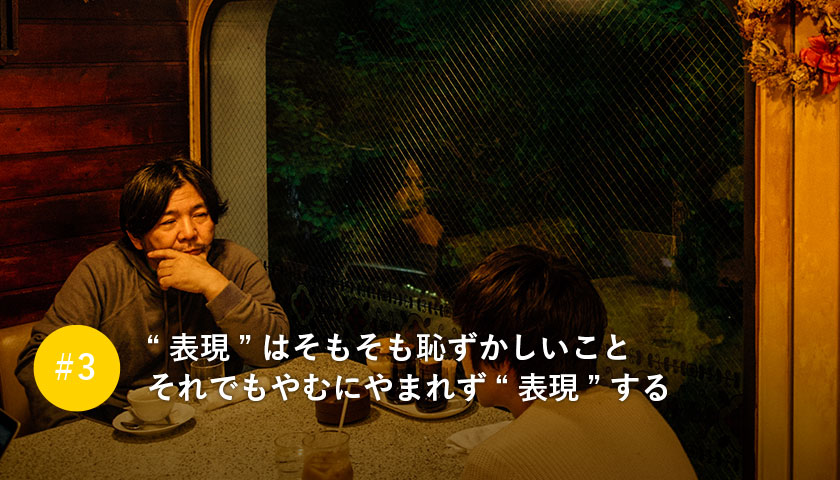

- 宮沢
- 吉田くんは、ステージ上でMCなんかもするの?
- 吉田
- はい。けど、思い付いたことをしゃべっているだけなんですが…。ライブのMCって、かっこいいことを言ったり、盛り上げなきゃいけないといったお約束がありますよね。でも、僕は本当に何の意味もないことをペラペラとしゃべっているだけ。本当は何も面白いことは言ってないのに、なぜかみんな笑っています…。
ーそれも、ある意味すごい才能ですよ!(笑)
- 宮沢
- ライブのMCって「大阪!」と地名を叫んだり、インパクトのあることを言わなきゃいけない、というお約束があるよね。日本人のミュージシャンもそうだけど、大阪で大きなコンサートがあると、 客席に向かってね、「大阪!」ってと地名を叫ぶけど(笑)、分かってると思うんだよね、来てる人はみんな(笑)。大阪の近郊の人が大半だと思うし。あと、フジロックでは、そもそも苗場だからね、富士山なんて見えないのに、外国のミュージシャ ンが、向こうに見える山を見て「フジサーン!」って叫ぶ(笑)。誰か注意したほうがいいよ。あれ、富士山じゃないですって(笑)。
- 吉田
- MCにも様式美というか、定型がありますね。僕らはそういうのが恥ずかしくてできないんです。

ーお約束や、定形的な言葉を使うのは「恥ずかしい」という感覚なんですね。
- 宮沢
- けど、その一方で「なんで恥ずかしいの?」と思う人たちもいますよね。「こういうことは恥ずかしくてできない」と言う僕らのような者に対して「なんで恥ずかしいの?」「恥ずかしいってどういうこと?」と聞いてくるんです。それはもう、センスの違いでしょう。そもそも何かを表現すること自体、何かを書くこと自体、とても恥ずかしいことですよ。だけど、書いちゃうし、歌っちゃうし、俳優だったら芝居するんだよね。 普段普通に付き合ってる知人が舞台に出るんで観に行ったら、とんでもない芝居をしていて、もううつむくしかないよね(笑)。じゃあ、なぜ、人は表現活動をしてしま うかなんですよ、問題は。考えたのはね、恥ずかしいって知っていながら、ついやってしまう、やむにやまれぬ表現欲求ですよ。ただ、重要なのは、表現は恥ずかしいんだって知っているか、そうでないか。恥ずかしくないと考える人の行為は、とことん恥ずかしい。そこで1ミリでも、「表現は恥ずかしい」って分かってる人間が何か表現すると、そこに含羞があり、見ているこちらも恥ずかしくないんですよ。

- つまり、表現が「恥ずかしい」と知っていて、でもやらざるを得ない人と、初めから恥ずかしさも感じずにやる人の違い。ここには絶望的な溝があります(笑)。
ーお二人の表現は、そんな恥ずかしさに向き合って生まれたものなんですね。
- 宮沢
- 少し話がずれるけど、90年代からとくには「それ何?」と驚くようなバンド名が増えていますよね。「水中、それは苦しい」とか(笑)、最近だと「溺れたエビの検死報告書」とかさ(笑)。
- 吉田
- それはやっぱり、かっこつけたバンド名にするようなことが恥ずかしいって思ったんでしょうね。「L’Arc~en~Ciel」とか…。
- 一同
- 笑。
- 吉田
- でも、そんな「恥ずかしい」という感覚に対して、「そのくらいの覚悟でやれよ」という意見も耳にします。「最近のバンドは逃げ道を用意していてダサい」と言われることもしばしばですから。要するに、かっこつけることを引き受けろ、と。かっこつけることも、それはそれで難しいことなんでしょうね。

- 宮沢 章夫(みやざわ・あきお)
- 劇作家・演出家・小説家。早稲田大学文学学術院教授。1980年代半ば、竹中直人、いと うせいこうらとともに「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を開始、すべての作・演 出を手掛ける。90年「遊園地再生事業団」の活動を始める。93年『ヒネミ』で第37回岸 田國士戯曲賞受賞。2005~2013年まで早稲田大学文学学術院にて教べんを執り、2016年 より現職。『ニッポン戦後サブカルチャー史』(NHK出版)他著書多数。
- 吉田靖直(よしだ・やすなお)
- 吉田(vocal)、 鳥居(guitar)、山本(bass)、大垣(drums)からなる4人組バンド、トリプルファイヤーのボーカル。2011年早稲田大学 第一文学部を卒業。トリプルファイヤーはこれまで『エキサイティングフラッシュ』『スキルアップ』『エピタフ』の3枚のアルバムを発表。 局地的な支持を集め、「高田馬場のJOY DIVISION」「だらしない54-71」などと呼ぶ人も現れる。都内を中心に全国各地でライブを行っている。2017年も、バンドに個人に夏フェスなどに出演予定。






