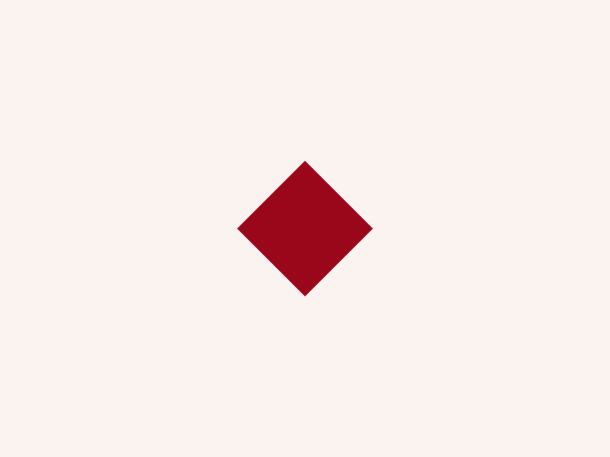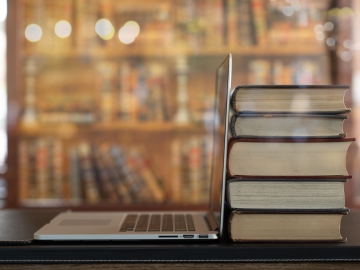Research Theme 研究テーマ
社会的養護の子どもに焦点化した取り組みからはじめ、すべての子どもの状況を改善することを使命とし、実証的研究・評価、実践支援、施策策定への示唆を軸に取り組みを続ける。「子どものために」で終わらせず、「子どもとともに」まで繋げることを常に考え、新たに必要とされる変化を生み出す。
Research Director 所長
Member メンバー
- 荒川 美沙貴 総合研究機構研究助手
- 巖淵 守 人間科学学術院人間科学部教授
- 岡安 朋子 人間科学学術院人間科学部准教授(任期付)
- 桂川 泰典 人間科学学術院人間科学部教授
- 上鹿渡 和宏 人間科学学術院人間科学部教授
- 川村 顕 人間科学学術院人間科学部教授
- 古山 周太郎 人間科学学術院人間科学部准教授
- 田幸 恵美 人間科学学術院人間科学部助手
- 那須 里絵 総合研究機構次席研究員(研究院講師)
- 松原 由美 人間科学学術院人間科学部教授
- 上村 宏樹 総合研究機構客員次席研究員(研究院客員講師)
- 青木 豊 医療法人春乃会・あおきメンタルクリニック理事長・代表
- 安發 明子 日本学術振興会特別研究員
- 河野 洋子 大分大学福祉健康科学部社会福祉実践コース講師
- 國澤 有記 大阪府貝塚子ども家庭センター
- 長田 淳子 社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院副院長
- 中村 豪志 愛知教育大学・助教
- 西野 将史 BONDS東京カウンセリングサービス
- 白田 好彦
- 畠山 由佳子 関西学院大学人間福祉学部教授
- 引土 達雄 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科准教授
- 福井 充 こども家庭庁虐待防止対策課調整係長
- 藤林 武史 西日本こども研修センターあかしセンター長
- 安留 昭人 山梨県中央児童相談所 処遇指導・移行支援課 処遇指導・移行支援課長
- 山岡 祐衣 東京科学大学公衆衛生学分野プロジェクト講師
- 山口 敬子 京都府立大学公共政策学部准教授
- 和仁 里香 徳島文理大学保健福祉学部人間福祉学科教授
研究キーワード
研究概要
家庭養育移行の世界的潮流のなか、日本でも 2016 年改正児童福祉法、2017 年新しい社会的養育ビジョン、2019 年度中の社会的養育推進計画策定を経て 2020 年度より全国の自治体で実践展開が始まった。施設養護を中心に発展してきたわが国において今後 10 年間で家庭での養育を基盤とする新しい社会的養育体制を構築することは大きな挑戦であり、確実に成功を収めなければならない。新しい社会的養育体制は、親子分離の予防も含む家族再構築を第一とし親と社会が共に子どもの育ちを保障することを目指すものであり、すべての子どもと家族に直接・間接的な成果をもたらすものである。
新しい社会的養育ビジョンに示された代替養育の今後の展開(施設多機能化・高機能化やフォスタリング機関創設等)の検討にあたっては英国における家庭養育移行の方法や実践が参考にされている。その英国における家庭養育移行の契機となり、その後の実践を支え続けてきたのが社会的養育に関する研究であり、研究成果が施策や実践に反映され研究・実践・施策の歯車がしっかりとかみ合い連動することで子どもの最善の利益保障が目指されてきた。研究、エビデンスを基盤とするこのような取り組みを進めるため大学に設置された研究所も重要な役割を担っている。国連等国際機関が示す家庭養育優先原則についても各国のこのような研究成果が根拠とされている。
日本の状況をみると、社会的養育における実践・施策を方向付ける研究やエビデンスは不足しており、その必要性は 2016 年改正法や新しい社会的養育ビジョンにも示されている。社会的養育研究所は大きな変革が必要とされるこの時期に、その必要に応じ子どもの最善の利益を保障するため大学研究機関として設置された。当研究所はすべての子どもの状況を、最も厳しい状況に置かれ続けてきた社会的養護の子ども、またその周辺の子どもに焦点をあて改善することを使命とし、「実証的評価・研究」「研究成果をもとにした実践支援」「研究成果をもとにした施策策定への示唆、政策提言」を軸に以下に取り組む。
1. 社会的養育に関するエビデンス・情報の整理・蓄積と提供
2. 必要なプログラム・システム等の開発・導入
3. モデルプロジェクトの準備・実施・評価
4. 関係者ネットワークの構築と人材育成
5. 子ども当事者の意見聴取、研究所事業への助言
6. 関係者・機関、社会全体に向けての発信・協働の呼びかけ
【研究所を同名で設置する理由】
2020 年度から 10 年間の予定で全国の自治体で実践されてきた社会的養育推進計画は、2022年度の児童福祉法改正を反映する形で 2025 年度からの後半 5 年間の新たな計画として実践が継続されることになった。当研究所も前半5年間同様、国や自治体、民間機関による取り組みをサポートすべくこれまで同様の役割を担い続け、さらにこれまで以上に必要とされる状況の中でそれに応えるべく、研究所名を変更せずに、少なくとも後半5年間の設置を継続しなければならないと考えている。