- ニュース
- 第15回アジア太平洋研究センター(WIAPS)研究会
第15回アジア太平洋研究センター(WIAPS)研究会
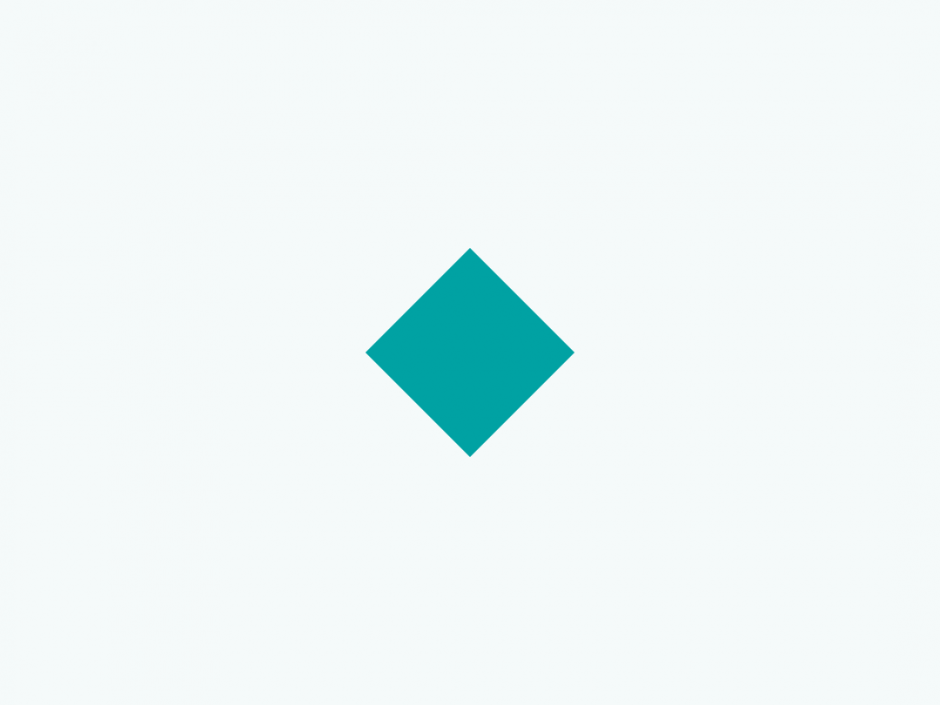
Dates
カレンダーに追加0520
MON 2013- Place
- 早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713会議室
- Time
- 12:15 - 12:50
- Posted
- Mon, 20 May 2013
開催日時
2013年5月20日(月)12:15 – 12:50
場所
早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713会議室
参加資格
WIAPS専任教員・助手, WIAPS受入の交換研究員・訪問学者・外国人研究員, GSAPS修士課程・博士後期課程在学生
報告1
報告者
植木(川勝) 千可子 氏(早大アジア太平洋研究科教授)
報告テーマ
「敵の鞍替え―脅威認識と安全保障のジレンマ」
要旨
米国は、1987年から約5年の間にその脅威認識をソ連、日本、中国と急速に変化させた。これは、なぜなのか?
本発表では、新しい脅威認識が形成される要因について検討し、とくに、ある国の脅威の対象が入れ替わる際のメカニズムについて検討する。主要な事例としては、1980年代後半から米国の脅威認識が変遷したケースを扱う。
これまでの研究では、脅威認識の形成には、相手の能力(capabilities)と意図(perception)に対する認識が関係するといわれている。そして、意図の認識には最近の出来事が影響すると考えられてきた。しかし、米国の事例は、同じようなの出来事に対する評価が時期によって異なることを示している。これはなぜなのか?
本発表は、「戦略的セーフティネット」という概念を用いて、共通の敵に直面する国家が互いに対する脅威認識を抑制するメカニズムを提示する。共通の敵の有無によって、国家は行動を変えると同時に米国の事例は、これまでの同盟理論に対しても新たな示唆を与えるものである。これまで、ある戦争が終わると勝利側の同盟が解体し、敵対するようになるケースがあることが知られている。その理由は、戦利品をめぐる競争によるものだと説明されて来た。しかし、冷戦の場合、戦利品をめぐる対立がなかったにも関わらず、関係が悪化した。これにより、戦後の関係の悪化と新たな脅威認識の形成には、もっと複雑なメカニズムが存在することが推察される。本発表では、そのメカニズムの解明を試みる。
- Tags
- WIAPS研究会
