- ニュース
- 第11回アジア太平洋研究センター(WIAPS)研究会
第11回アジア太平洋研究センター(WIAPS)研究会
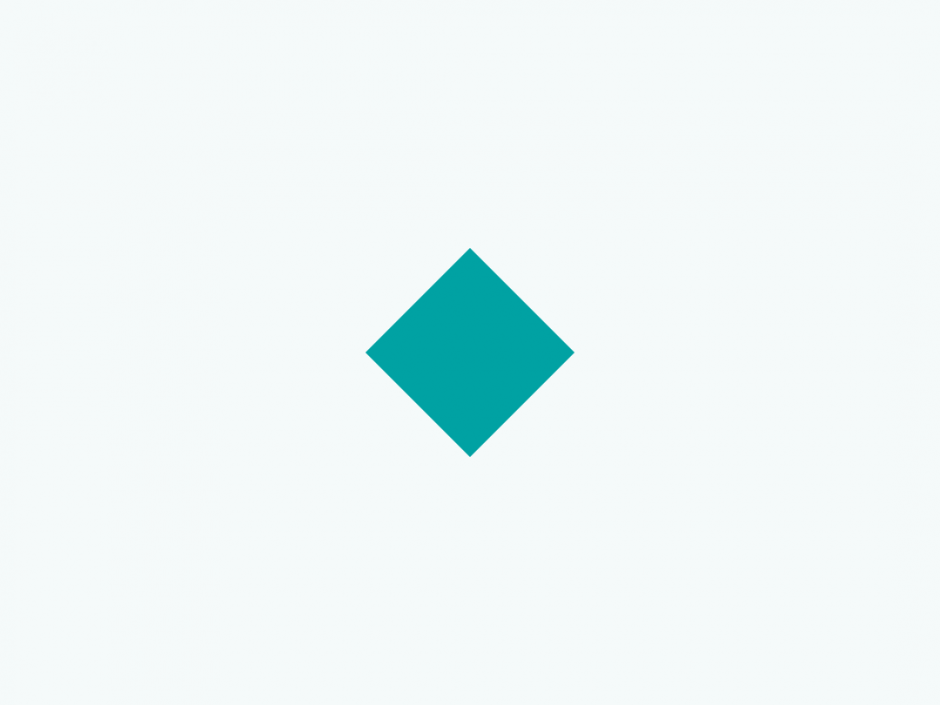
Dates
カレンダーに追加1203
MON 2012- Place
- 早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713会議室
- Time
- 16:00 - 17:30
- Posted
- Mon, 03 Dec 2012
開催日時
2012年12月3日(月)16:00 – 17:30
場所
早稲田大学19号館(西早稲田ビル)7階713会議室
参加資格
WIAPS専任教員・助手, WIAPS受入の交換研究員・訪問学者・外国人研究員, GSAPS修士課程・博士後期課程在学生
報告1
報告者
大橋 史恵 氏(早大アジア太平洋研究科助教)
報告テーマ
現代中国の再生産領域とジェンダー -移住家事労働者の存在を中心に-
要旨
「婦女能頂半辺天」(女性は天の半分を支える)というスローガンによく知られるように、中国は社会主義体制において女性解放の言説を取り込み、とりわけ都市の生産労働の現場において多くの女性労働力を採用していった。建国直後、全民所有制労働者全体に占める女性の割合は13.4%に過ぎなかったが、改革・開放の頃までに30%を超えた。この伸びは市場経済導入以降も継続しており、近年では全労働力人口に占める女性の割合は45%前後を推移している。
女性たちが生産労働の場で働くというとき、労働力再生産のありかた(家事・育児など)も変化してきたことが想像できる。計画経済期については、さまざまな限界をかかえていたとはいえ、職場や居住地域において公共食堂や託児所といった家事の社会化を担う施設があったことが知られる。ところが市場経済導入期以降は、職場における福利制度は一般に縮小しており、地域サービスとしても日本の保育所のような3歳児未満の子どもを預かる施設はほとんどない。この現実において、中国都市部の女性労働力率の高さは、どのように実現されているのだろうか。本報告では改革・開放以降の再生産領域の変容について、農村-都市間移住家事労働者の存在に焦点をあてながら議論する。
報告2
報告者
加藤 裕美 氏(早大アジア太平洋研究センター助手)
報告テーマ
東南アジアにおける持続的な環境開発と先住民社会
要旨
熱帯雨林問題は、現在全世界が関心を持つ地球環境問題のひとつである。東南アジアにおいては、1960年代よりフィリピン、そしてインドネシア、マレーシアと木材伐採、ダム建設、アブラヤシ農園、アカシア植林など経済開発の主眼となる森林開発を継続的におこなってきた。高度成長期における大規模な森林開発は、各国政府にとって重要な財源をもたらした一方で、開発の対象地に暮らす人々の生活に多大な変化をもたらした。さらに近年では、地球温暖化が深刻になるにつれて、石油に代わるバイオ燃料としてアブラヤシが注目されている。「ポスト化石資源時代」において、アブラヤシなどのプランテーション生産はともすれば「地球益」の確保ともいえるが、同時に既存の森林の消失と生物多様性の低下、そして自然資源に依拠した在地社会の生存基盤の脆弱化が危惧されている。従来、熱帯の土地・森林開発と環境依存型経済の維持はトレードオフの関係とみなされてきたが、持続可能な資源開発を展望するためには生態系の保全と同時に伝統的社会システムの存続をいかに両立させるかが鍵となっている。
そこで本報告では以下の3点に着目して、マレーシアにおける事例を取り上げる。まず、熱帯の資源をとりまくグローバル経済の需要と資源に依存した現地の政治構造。そして、人々による自然資源に依存した社会経済システムの変化。さらに持続的な資源開発と先住民社会の安定にはどのような方策があるのかを最後に検討する。
- Tags
- WIAPS研究会
