- 学部について
- 出版物
Publications
出版物
問合せ先:
- 早稲田大学商学部報(e-mail:[email protected])
- 早稲田大学商学同攻会(e-mail:[email protected])
商学部報
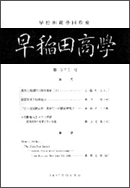 『早稲田商学』は、1925年(大正14年)商学部および専門部商科の教員・学生によって、商学および経済学の研究と発表を目的として早稲 田商学同攻会が組織され、同年6月に創刊された研究機関誌であり、これまで数多くの優れた研究論文を掲載してきました。
『早稲田商学』は、1925年(大正14年)商学部および専門部商科の教員・学生によって、商学および経済学の研究と発表を目的として早稲 田商学同攻会が組織され、同年6月に創刊された研究機関誌であり、これまで数多くの優れた研究論文を掲載してきました。
『早稲田商学』の意義は、早稲田大学商学部の専任教員に対して研究発表の場を提供し、当学の学問的地位を示すとともに、「商学」という学問自体の地位向上に資することにあります。また、『早稲田商学』は一般学生にとって研究の指針・攻学の参考となるばかりでなく、当学出身の校友のみなさんや広く経済界や実業界で活躍する人々にとっても、その実践の場における学問的支援を提供するものとして大いに貢献しています。
『早稲田商学』は現在、年4回発行され、当学の教員・学生の他、全国の大学や研究機関に配布されています。
『早稲田商学』のバックナンバーはDSpace@Waseda University(学術機関リポリトジ)でも検索できます。
早稲田商学 商学部創設120周年記念号(2025年7月発行)
| 企画 | 歴代学部長座談会 | 恩藏 直人 嶋村 和恵 藤田 誠 横山 将義 |
| 寄稿 | 元学務担当職員による寄稿 「職員の視点で振り返る商学部の20年」 |
梅地 一義 林 高史 長尾 洋吉 |
| 商学学術院事務所の事務体制について | 大庭 慎二 |
早稲田商学 第468号(2024年6月発行)
| 論文 | ペットの飼育が消費者の ブランド・ロイヤルティに与える影響 |
芳賀 悠基 恩藏 直人 |
| 消息 | 伊藤嘉博先生のご定年退職にあたって | 横山 将義 |
| 伊藤嘉博先生のご定年退職にあたって | 長谷川 恵一 |
早稲田商学 第467号(2023年12月発行)
| 論文 | 預貯金者保護法に基づく補填金支払請求と 預金者の重大な過失,金融機関の無過失 |
新井 剛 |
| Did InsurTech Promote the Development of Insurance Inclusion? Empirical Evidence from China's Rural Areas |
Jian WU,Jie SHAO |
早稲田商学 第466号(2023年9月発行)
| 論文 | 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)
導入後において問題となりうる課題の法的整理 ── 瑕疵あるインボイスによる仕入税額控除の適用可否を中心に ── |
山下 和博 |
| 2022年度学生懸賞論文・最優秀論文賞受賞論文 ターゲットのリスクは的確に捉えられているのか ── 国内M&Aにおける割引率の影響について ── |
佐伯 宙哉 |
早稲田商学 第465号(2023年6月発行)
| 論文 | 画家の発想から導かれる製品開発におけるアート志向 | 恩藏 直人 藪野 美芽 須永 努 |
| 資料 | 不動産法講義(3) | 新井 剛 |
| 消息 | 武井 寿先生を偲んで | 横山 将義 |
| 武井 寿先生を偲んで | 嶋村 和恵 |
早稲田商学 第464号(2022年12月発行)
| 論文 | 戦略提携研究の現状と方向性 | 藤田 誠 |
| You are coming home: when efficient adoption of corporate governance practices is overturned | Yuki TORIDA | |
| 資料 | 不動産法講義(2) | 新井 剛 |
早稲田商学 第463号(2022年9月発行)
| 論文 | 日本の地方議会における議員報酬と選挙・ 議会活動 ── 報酬額とその自主的な増額が与える影響 ── |
宮嵜 健太 |
| 資料 | 不動産法講義(1) | 新井 剛 |
早稲田商学 第462号(2022年3月発行)
早稲田商学 第461号(2021年9月発行)
| 論文 | 天野為之と唐津 | 池尾 愛子 |
| A study on the characteristics of Chinese modern accounting thought | Tianwei BI | |
| Effects of board gender diversity on firm investment and performance: Empirical evidence from Japan | Thanh Thi Phuong Nguyen | |
| 消息 | 澤田 賢先生を偲んで | 横山 将義 |
| 澤田 賢先生を偲んで | 渡邊 展也 |
早稲田商学 第460号(2021年3月発行)
| 論文 | 日本企業の予算管理の改善に関する 実態調査 |
清水 孝 町田 遼太 上田 巧 |
| 日本における原価企画研究の蓄積状況 ── 書誌学的方法に基づく文献レビュー ── |
荻原 啓佑 | |
| 消息 | 佐々木宏夫先生をお送りするにあたって | 横山 将義 |
| 佐々木宏夫先生のご退職にあたって | 高瀬 浩一 |
早稲田商学 第459号(2020年9月発行)
| 論文 | 天野為之と東洋経済新報 | 池尾 愛子 |
| なぜ紙の本は消えないのか? ── 書籍の媒体選好における影響要因の検討 ── |
權 純鎬 | |
| 資料 | 講演録: 「改正債権法における保証制度のあり様」 |
新井 剛 |
早稲田商学 第458号(2020年6月発行)
| 論文 | 重層的なインタラクションによるプラットホームの拡張 | 鄭 雅方 井上 達彦 |
| 研究ノート | XBRLによる注記情報の記述について | 金 奕群 張 瀟月 奥村 雅史 |
| 消息 | 谷内満先生をお送りするにあたって | 藤田 誠 |
| 谷内満先生のご定年退職にあたって | 中出 哲 |
 この本は、商学部に入学した新入生ならびに早稲田大学商学部への進学を考えている受験生が、商学部で学ぶ内容を知るための手引きとして作成しました。皆さんの中には、商学についてぼんやりとしたイメージはあるけれどよくはわからない、という人が多いのではないでしょうか。
この本は、商学部に入学した新入生ならびに早稲田大学商学部への進学を考えている受験生が、商学部で学ぶ内容を知るための手引きとして作成しました。皆さんの中には、商学についてぼんやりとしたイメージはあるけれどよくはわからない、という人が多いのではないでしょうか。
早稲田大学商学部では、商学を「ビジネスと経済の融合領域であり、ヒト・モノ・カネ・情報等の諸資源の配分に関する機能や制度を国内および国際的観点から考察し、理論的かつ実証的な研究を行う」学問と定義しています。もう少しシンプルにいうと、ビジネスを行う企業に注目し、企業のヒト・モノ・カネ・情報(経営資源と呼ばれます)の活用の仕方を学びます。しかし、企業の行動だけを学ぶだけでは不十分です。まず、ビジネスを行う場所やその時代的背景によって、企業がとるべき行動は変わります。また、ビジネスを行う国や地域の法律や文化によっても、企業の行動は変わります。したがって、企業の行動だけではなく、企業の行動に影響を与える経済、法律、文化なども学ぶ必要があるのです。商学部では、企業の行動を中心として、企業の行動に影響を与える経済制度、法律、文化、コミュニケーション方法などついても包括的に学ぶことになります。
現在、企業で働く上では、ビジネスに関する高度な知識が求められています。また、皆さんの中には、日本にとどまらず世界で活躍したいと考えている人もいるかもしれません。またそうでなくても、海外でビジネスをしなければいけない機会も増えています。高度なビジネスの知識に加え、諸外国の文化に関する理解や外国語によるコミュニケーション力も必要とされます。早稲田大学商学部ではこれらの内容を学ぶことができ、この本では、その一部を凝縮して紹介しています。
この本では、早稲田大学商学部で学ぶ内容を分野ごとに紹介しています。経営分野では、現実の経営を理解し、説明するための理論やツール、考え方を学びます。会計分野では、企業の経済活動を記録・計算し、経営活動の結果を外部に報告する分野である財務会計と、会計データを企業の経営管理に活用する分野である管理会計を中心に学びます。マーケティング・国際ビジネス分野では、市場メカニズムを通じた製品やサービスの創造と供給、そしてそれを可能にするさまざまな資源の流通と交換に関わる理論などを学びます。金融・保険分野では、金融の基本的な仕組みと機能を理解した上に、企業金融、ポートフォリオ理論、家計および企業のリスク処理の体系、保険企業の機能・役割などを学びます。経済・産業分野では、企業や家計など個別の経済主体の行動や全般的な経済環境の動向を理解するためのツールとして、経済学の基礎的な理論と定量分析の手法を学びます。総合教育の授業では、グローバル化する社会に対応できる能力を高め、異文化への理解を深めます。各章において重要な概念や語句は太字になっています。重点的に勉強することでその科目の理解が深まるでしょう。
この本を読み、早稲田大学商学部への進学を考えている受験生は、自身の興味の持てる分野なのかを知ることができるでしょう。すでに商学部に入学した新入生は、これから履修する授業や3年時に所属するゼミを選ぶ際の参考にもなるでしょう。この本から、商学部で学ぶ内容を知り、そしてその面白さの一端を感じてもらえればと思います。
早稲田商学同攻会編集委員会
目次 (各章のタイトルをクリックすると内容に進みます)
| 経営 | 第1章 商学は金儲けのための学問にあらず | 井上達彦 |
| 第2章 『法』について学ぶということ | 和田宗久 |
|
| 会計 | 第3章 実は身近な会計学 | 大鹿智基 |
| マーケティング・国際ビジネス | 第4章 ビジネスにおけるマーケティング | 恩藏直人 大平進 |
| 金融・保険 | 第5章 金融 | 谷川寧彦 |
| 第6章 保険は時代を映す鏡。保険を通して社会について考えよう | 中出哲 |
|
| 経済・産業 | 第7章 ビジネスと経済学 | 片岡孝夫 |
| 第8章 商学へのいざない─ビジネスと経済の融合領域としての商学─ | 横山将義 |
|
| 総合教育 | 第9章 The“ Business” of Business English | ケイト・エルウッド |
 『文化論集』は、1992年6月に行われた早稲田商学同攻会年次総会において、『早稲田商学』のもとで年2回発行されていた「文化特集号」の分離・独立が決定されたのを受けて、上記の名に改題され刊行されるようになった研究機関誌です。
『文化論集』は、1992年6月に行われた早稲田商学同攻会年次総会において、『早稲田商学』のもとで年2回発行されていた「文化特集号」の分離・独立が決定されたのを受けて、上記の名に改題され刊行されるようになった研究機関誌です。
『文化論集』の『早稲田商学』からの独立は、語学・一般教育の文化教育への統合と専門教育からの独立を象徴するもので、わが国の文化教育をリードする代表的学部機関誌として発展しています。
『文化論集』は現在、年2回発行され、『早稲田商学』と同様、当学の教員・学生の他、全国の大学や研究機関に配布されています。
『文化論集』のバックナンバーはDSpace@Waseda University(学術機関リポリトジ)でも検索できます。
文化論集 第64号(2025年9月発行)
| 論文 | Student-generated discussion questions:
Production and engagement |
Kate ELWOOD |
| Grammaire poétique de lʼimaginaire lettré poèmes célèbres dans la poésie et la peinture des lettrés chinois et japonais |
Marguerite-Marie PARVULESCO | |
| 研究ノート | Rural development through remote working in regions rich in rural tourism resources -2-. The case of Ávila and Segovia rural areas in (post) pandemic Spain. |
Santiago LÓPEZ JARA |
| 消息 | 荒井訓先生のご定年退職にあたって | 横山 将義 |
| 荒井訓先生のご定年退職にあたって | 長谷川 恵一 | |
| 森本栄晴先生,アルマラス マヌエラ先生 のご定年退職にあたって |
横山 将義 | |
| アルマラス マヌエラ先生のご退職にあたって | 森本 栄晴 | |
| 森本栄晴先生ご退職あたって | Manuela ALMARAZ |
文化論集 第63号(2024年3月発行)
| 論文 | Artikelsemantik2.0.Quantitative und Qualitative Korpusanalyse zum semantischen Artikelgebrauch japanischer Deutschlernender(JDL)⑴,⑵ |
Manuel Philipp KRAUS |
| 「日清修好条規」の成立過程 ー公使・領事の派遣と李鴻章ー |
白 春岩 |
文化論集 第62号(2023年9月発行)
文化論集 第61号(2022年9月発行)
| 論文 | Wer blau macht. ─表象としてのジーンズ─ |
荒井 訓 |
| 資料 | 新たに公開された周作人檔案文書 ──中国第二歴史檔案館所蔵文書より |
小川 利康 |
⇒執筆要領はこちらから
2015年度 受賞者インタビュー
第一席
生まれ月が小中学生の学習・運動習慣に与える影響
片山 東ゼミ
グループ5名
佳作
『戸籍制度改革を更に進める国務院の意見』が中国農工民に与える影響に関する考察
尹 景春ゼミ
グループ7名
佳作
既存キャラクターと企業のコラボレーション:一致度、好み、ノスタルジアに着目して
守口 剛ゼミ
水上 裕貴
佳作
『道の駅』による地域活性化:ビジネスモデルの観点からの分析
井上 達彦ゼミ
グループ4名
佳作
ブランドを含めたSNS投稿の有効性と投稿要因の解明:自己表現とブランドパーソナリティーに着目して
守口 剛ゼミ
大池 寿人
佳作
サッカーチームの好成績とスポンサー企業価値との関係性:統計的分析
山野井 順一ゼミ
グループ4名
佳作
IPO市場の過熱と主幹事証券の行動:ロックアップ契約からの考察
大村 敬一ゼミ
グループ2名
2014年度 受賞者インタビュー
大学院学生の部
佳作
Social Moodと株価の双方向的影響:株価変動のメカニズムに関する実証研究
豊泉 洋ゼミ
明石 裕太郎
学部学生の部
第二席
生徒教員比がいじめ・学力に及ぼす影響
片山 東ゼミ
グループ6名
第二席
震災は地価評価基準を変えたのか:静岡県の地価を用いて
市田 敏啓ゼミ
グループ6名
佳作
観光は貧困を救うか?:時系列分析による観光の貧困削減効果分析
横田 一彦ゼミ
大野 靖博
佳作
社外取締役の導入意義:他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した実証分析
広田 真一ゼミ
グループ4名
佳作
イベント消費のメカニズム解明:参加者の動機と心理的財布に着目して
守口 剛ゼミ
渥美 志織
佳作
買収防衛策が企業価値に与える影響:長期イベントスタディと長期パフォーマンススタディによる考察
広田 真一ゼミ
グループ4名
佳作
ライバルブランドのブランド評価形成メカニズム:どっち派キャンペーンに着目して
守口 剛ゼミ
田部 裕馬
2013年度 受賞者インタビュー
第一席
授業科目の選択と配分の問題における公平性と誘因両立性について
佐々木 宏夫ゼミ
西山 諒
第二席
恋人を満足させる効果的な方法:距離と通信が恋愛満足度に与える影響の計量的分析
片山 東ゼミ
グ
ループ4名
佳作
投票力指数への非対称性導入について
佐々木 宏夫ゼミ
田
中 健人
佳作
若者佳作の投票率と政府による社会保障費支出の関係
横田 一彦ゼミ
グ
ループ5名
佳作
ソーシャルメディアによる誇示行動と満足度の関係:投稿者本人への快楽と正当化に着目して
守口 剛ゼミ
吉
村 善治
佳作
現代的贅沢消費の実態解明: 佳作プチ贅沢消費における概念規定と動機の解明
守口 剛ゼミ
松
本 裕子
佳作
毎月分配型投資信託の本質的問題点
大村 敬一ゼミ
グ
ループ4名
佳作
人員削減が企業価佳作値に与える影響:株価の反応とその後の業績
広田 真一ゼミ
グ
ループ5名
佳作
新聞広告におけるオノマトペの内容分析:オノマトペ教育への示唆
嶋村 和恵ゼミ
伊
藤 茉莉奈
2012年度 受賞者インタビュー
第二席
日露戦後経営における鉄鋼業保護育成政策の効果:官営八幡製鉄所拡張計画と日本の
重工業化
花井 俊介ゼミ
井上
雄介
佳作
空売りが株価形成に与佳作える影響:日本の株式市場における実証分析
広田 真一ゼミ
グル
ープ5名
佳作
戦略マネジメントからみた組織間管理会計
長谷川 惠一ゼミ
井上
慶太
佳作
我が国における公募増資について:増資発佳作表による株価への影響と長期パフォーマンス
大村 敬一ゼミ
長谷
部 倫也
奨励賞
The Cycle of Hate as the Origin of “the Troubles”
ケイト・エルウッド プロゼミ
川口
慧太
2011年度 受賞者インタビュー
第一席
裁判員制度の投票力指数による分析
佐々木 宏夫ゼミ
岩﨑
康平
第二席
IPO における株価のアンダーパフォーマンス現象について
大村 敬一ゼミ
野津
大介
佳作
日本的企業財務のリスクヘッジ機能:東日本大震災を通して
広田 真 一ゼミ
グル
ープ5名
佳作
カテゴリー不確実性に関する一考察:カテゴリーの認識方法の違いが購買後満足に与える影響
守口 剛ゼミ
横井
雄史
2010年度 受賞者インタビュー
佳作
社外取締役の導入は外国人投資家を引きつけるのか
広田 真一ゼミ
グル
ープ5名
佳作
日米比較を通じた資本予算評価技法の日本における実務的特徴
清水 孝ゼミ
大西
智之
利用上の注意
- 本サイトで公開されている『早稲田商学』・『文化論集』の論文等の内容の著作権等は早稲田商学同攻会に帰属し、著作権法および国際条約によって保護されています。
- 利用者は、個人の研究・調査等に係る正当な目的で、かつ利用に必要な範囲内に限り、内容をダウンロードないしプリントアウトすることができます。ただし、禁止・制限を定める場合もあります。
- 利用者は、早稲田商学同攻会による事前の承認なしに、個人利用以外の目的でその内容を複製、頒布ないし改変するなど、著作権を侵害する行為を行うことはできません。
- これらの事項に違反する悪質な利用を行うと、法律により罰せられることがありますので、くれぐれも適正な利用をお願いいたします。
2015年度 受賞者インタビュー
| 第一席 | 生まれ月が小中学生の学習・運動習慣に与える影響 | 片山 東ゼミ グループ5名 |
| 佳作 | 『戸籍制度改革を更に進める国務院の意見』が中国農工民に与える影響に関する考察 | 尹 景春ゼミ グループ7名 |
| 佳作 | 既存キャラクターと企業のコラボレーション:一致度、好み、ノスタルジアに着目して | 守口 剛ゼミ 水上 裕貴 |
| 佳作 | 『道の駅』による地域活性化:ビジネスモデルの観点からの分析 | 井上 達彦ゼミ グループ4名 |
| 佳作 | ブランドを含めたSNS投稿の有効性と投稿要因の解明:自己表現とブランドパーソナリティーに着目して | 守口 剛ゼミ 大池 寿人 |
| 佳作 | サッカーチームの好成績とスポンサー企業価値との関係性:統計的分析 | 山野井 順一ゼミ グループ4名 |
| 佳作 | IPO市場の過熱と主幹事証券の行動:ロックアップ契約からの考察 | 大村 敬一ゼミ グループ2名 |
2014年度 受賞者インタビュー
大学院学生の部
| 佳作 | Social Moodと株価の双方向的影響:株価変動のメカニズムに関する実証研究 | 豊泉 洋ゼミ 明石 裕太郎 |
学部学生の部
| 第二席 | 生徒教員比がいじめ・学力に及ぼす影響 | 片山 東ゼミ グループ6名 |
| 第二席 | 震災は地価評価基準を変えたのか:静岡県の地価を用いて | 市田 敏啓ゼミ グループ6名 |
| 佳作 | 観光は貧困を救うか?:時系列分析による観光の貧困削減効果分析 | 横田 一彦ゼミ 大野 靖博 |
| 佳作 | 社外取締役の導入意義:他のガバナンスメカニズムとの関係を考慮した実証分析 | 広田 真一ゼミ グループ4名 |
| 佳作 | イベント消費のメカニズム解明:参加者の動機と心理的財布に着目して | 守口 剛ゼミ 渥美 志織 |
| 佳作 | 買収防衛策が企業価値に与える影響:長期イベントスタディと長期パフォーマンススタディによる考察 | 広田 真一ゼミ グループ4名 |
| 佳作 | ライバルブランドのブランド評価形成メカニズム:どっち派キャンペーンに着目して | 守口 剛ゼミ 田部 裕馬 |
2013年度 受賞者インタビュー
| 第一席 | 授業科目の選択と配分の問題における公平性と誘因両立性について | 佐々木 宏夫ゼミ 西山 諒 |
| 第二席 | 恋人を満足させる効果的な方法:距離と通信が恋愛満足度に与える影響の計量的分析 | 片山 東ゼミ グ ループ4名 |
| 佳作 | 投票力指数への非対称性導入について | 佐々木 宏夫ゼミ 田 中 健人 |
| 佳作 | 若者佳作の投票率と政府による社会保障費支出の関係 | 横田 一彦ゼミ グ ループ5名 |
| 佳作 | ソーシャルメディアによる誇示行動と満足度の関係:投稿者本人への快楽と正当化に着目して | 守口 剛ゼミ 吉 村 善治 |
| 佳作 | 現代的贅沢消費の実態解明: 佳作プチ贅沢消費における概念規定と動機の解明 | 守口 剛ゼミ 松 本 裕子 |
| 佳作 | 毎月分配型投資信託の本質的問題点 | 大村 敬一ゼミ グ ループ4名 |
| 佳作 | 人員削減が企業価佳作値に与える影響:株価の反応とその後の業績 | 広田 真一ゼミ グ ループ5名 |
| 佳作 | 新聞広告におけるオノマトペの内容分析:オノマトペ教育への示唆 | 嶋村 和恵ゼミ 伊 藤 茉莉奈 |
2012年度 受賞者インタビュー
| 第二席 | 日露戦後経営における鉄鋼業保護育成政策の効果:官営八幡製鉄所拡張計画と日本の 重工業化 | 花井 俊介ゼミ 井上 雄介 |
| 佳作 | 空売りが株価形成に与佳作える影響:日本の株式市場における実証分析 | 広田 真一ゼミ グル ープ5名 |
| 佳作 | 戦略マネジメントからみた組織間管理会計 | 長谷川 惠一ゼミ 井上 慶太 |
| 佳作 | 我が国における公募増資について:増資発佳作表による株価への影響と長期パフォーマンス | 大村 敬一ゼミ 長谷 部 倫也 |
| 奨励賞 | The Cycle of Hate as the Origin of “the Troubles” | ケイト・エルウッド プロゼミ 川口 慧太 |
2011年度 受賞者インタビュー
| 第一席 | 裁判員制度の投票力指数による分析 | 佐々木 宏夫ゼミ 岩﨑 康平 |
| 第二席 | IPO における株価のアンダーパフォーマンス現象について | 大村 敬一ゼミ 野津 大介 |
| 佳作 | 日本的企業財務のリスクヘッジ機能:東日本大震災を通して | 広田 真 一ゼミ グル ープ5名 |
| 佳作 | カテゴリー不確実性に関する一考察:カテゴリーの認識方法の違いが購買後満足に与える影響 | 守口 剛ゼミ 横井 雄史 |
2010年度 受賞者インタビュー
| 佳作 | 社外取締役の導入は外国人投資家を引きつけるのか | 広田 真一ゼミ グル ープ5名 |
| 佳作 | 日米比較を通じた資本予算評価技法の日本における実務的特徴 | 清水 孝ゼミ 大西 智之 |
利用上の注意
- 本サイトで公開されている『早稲田商学』・『文化論集』の論文等の内容の著作権等は早稲田商学同攻会に帰属し、著作権法および国際条約によって保護されています。
- 利用者は、個人の研究・調査等に係る正当な目的で、かつ利用に必要な範囲内に限り、内容をダウンロードないしプリントアウトすることができます。ただし、禁止・制限を定める場合もあります。
- 利用者は、早稲田商学同攻会による事前の承認なしに、個人利用以外の目的でその内容を複製、頒布ないし改変するなど、著作権を侵害する行為を行うことはできません。
- これらの事項に違反する悪質な利用を行うと、法律により罰せられることがありますので、くれぐれも適正な利用をお願いいたします。

