- Featured Article
歴代学部長による座談会
-商学部創設120周年記念特別企画-
Tue 04 Mar 25
-商学部創設120周年記念特別企画-
Tue 04 Mar 25
早稲田大学商学部は、2024年9月18日に創設120周年を迎えました。
これを記念して、2025年3月8日(土)に記念シンポジウムが開催されましたが、それに先立ち、2024年12月には歴代学部長4名による座談会が行われました。
その内容は、2025年6月発行の『早稲田商学』に掲載予定ですが、今回はその一部を先行公開します。

- 座談会出席者(学部長在任期間)
-
-

横山 将義(2020年9月~現在)
-

藤田 誠(2016年9月~2020年9月)
-
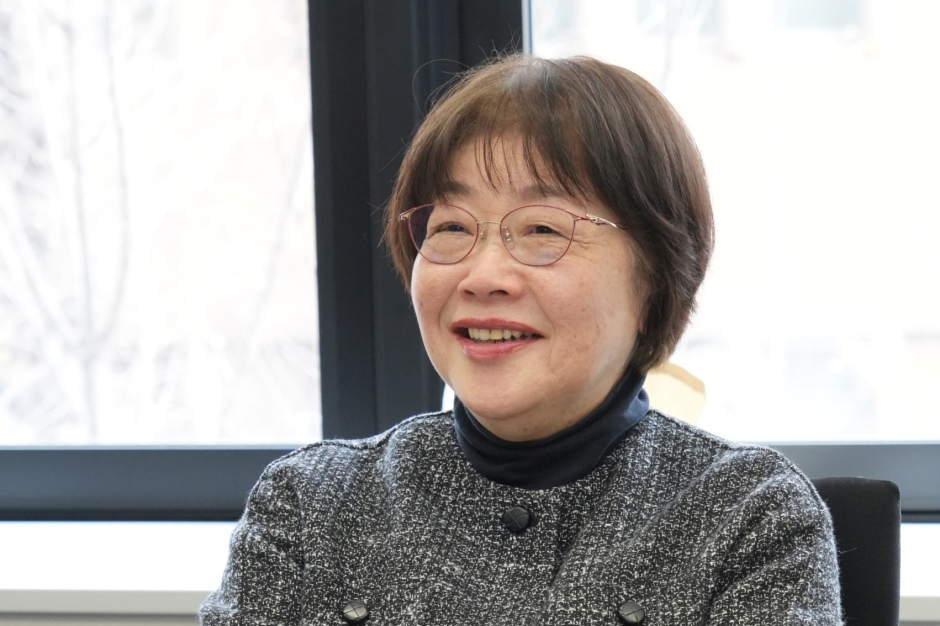
嶋村 和恵(2012年9月~2016年9月)
-

恩藏 直人(2008年9月~2012年9月)
-
- 司会・進行
-
-

梁取 美夫(商学学術院・教授/教務主任)
-

新井 剛(商学学術院・教授/教務主任)
-


学部長在任時の思い出
座談会の冒頭では、在任時の社会の状況を交えた当時の状況をお話いただきました。

新たな11号館でのスタート~東日本大震災による混乱の日本でグローバルリーダーをどう育成するか

恩藏 直人:
私が2008年9月に学部長に就任したときは、ちょうど旧11号館を建て直している最中でした。そのため、事務所が今の1号館の2階であったことをよく覚えています。間借りをしているような状況で、スペース的にも狭いところでぎゅっと圧縮されたような形で、職員も我々執行部もいろいろと作業をしていました。
その後、2009年3月に現在の11号館に移りました。年度末、年度始のタイミングだったので、引っ越しを滞りなく済ませることが、一つの大きな仕事で、事務所の職員の方と連携しながら引っ越しをしたというのが最初の思い出ですね。
その後の大きな思い出というと2011年3月の東日本大震災です。私は震災発生時には11号館3階の学部長室におりました。揺れがかなり強かったのですが、何か安心感がありました。というのも、東京は震度5ぐらいだったと思いますが、11号館は建てて間もないことから耐震基準を満たしており、そんなに心配はありませんでした。
ただその後、帰宅できなくなってしまった。建物はほとんどダメージもないし、問題なかったのですが、職員の方も含めて帰宅困難者が相当出ました。これは学部というより大学の判断だったのですが、大隈講堂を開放するなど、学内外の避難者を受け入れました。そうした中で我々は学部運営を行ったわけですが、一つは、すぐに被災者、あるいは学生たちをどう支援するかということを大学本部と連携して検討しました。
授業はそんなに混乱はありませんでしたが、日本全体が甚大なダメージを受けたので、そうした中、滞りなく授業を進めていくのが私の学部長時代を振り返ると一番大きなことだったと思っています。
教育システムについては、嶋村先生から補足していただきたいのですが、当時、ビジネスの実務だけでなく、学問も含めて大きく変わってきていて、見直さなければいけない時期でした。また、グローバル化にどう対応していくかということも重要で、政治経済学部や社会科学部は英語による学位プログラムを始めようとしていました。一方で商学部では、英語学位プログラムは私の二代前の学部長のときに議論はしていたのですが、まだその時期ではないとの判断で、導入されていませんでした。
そうした流れの中で、グローバル化を意識しながら、嶋村先生を委員長とした教育システム構想委員会を立ち上げました。2010年10月ですので、就任して翌々年ですね。何に取り組んだかというと、一つは委員会の答申を受けて、専門教育の体系を6つに再編しました。それまでのコースを根本的に見直しました。「商業・貿易・金融」を①「マーケティング・貿易」と②「金融・保険」に、「経済・産業」を③「理論経済(ビジネス・エコノミクス)」と④「応用経済(経済政策・経済史)」に分け、⑤「経営」、⑥「会計」とあわせて、6つに再編するというのが一番大きな変更です。これは、最終的に2014年度からトラック制として、導入されました。
もう一つが国際化への対応です。それまで商学部には、いわゆる英語による専門科目は二つか三つしかありませんでした。いくつかの学部で英語によるプログラムが進んでいる中、商学部でもある程度「英語で専門知識を学べる」下地はつくりたいという思いがあり、英語による科目を増やしていきました。
英語による専門科目数の目標値を20にしていたように思います。英語による専門科目が設置されていくたびに、学部長室のホワイトボードに書いていった記憶があります。いろいろな先生にお願いしましたが、なかなか引き受けてもらえない。それでも、中にはやってくれる先生もいて、それこそ星取りのように、一つ一つ科目を書いていき、20は達成したいですねと執行部内で語っていました。最終的に、17、18科目くらいまでは設置でき、目標値までかなり近づけたという記憶があります。
あと、オナーズ制の導入も答申で頂いたのですが、これは在任中には実現できませんでした。学生たちのモチベーションになるので、成績優秀者に対する表彰制度は本当にやりたかった。卒業生が歳を取って大学を訪れたとき、孫や子供に「私はこんなふうに頑張ったよ」というのを語れたらいいなと。そういう子がまた将来、早稲田を目指してくれたらいいなという思いを持っていました。これは、のちに「ディーンズリスト」という形で実現しましたね。
嶋村先生の下で議論してもらった教育システム構想委員会の答申では、プロゼミの改編も盛り込まれており、これものちに実りました。私の学部長時代に答申を受けて、ある程度成果を上げることができたと思っています。
コース制からトラック制への再編と5年一貫教育の導入
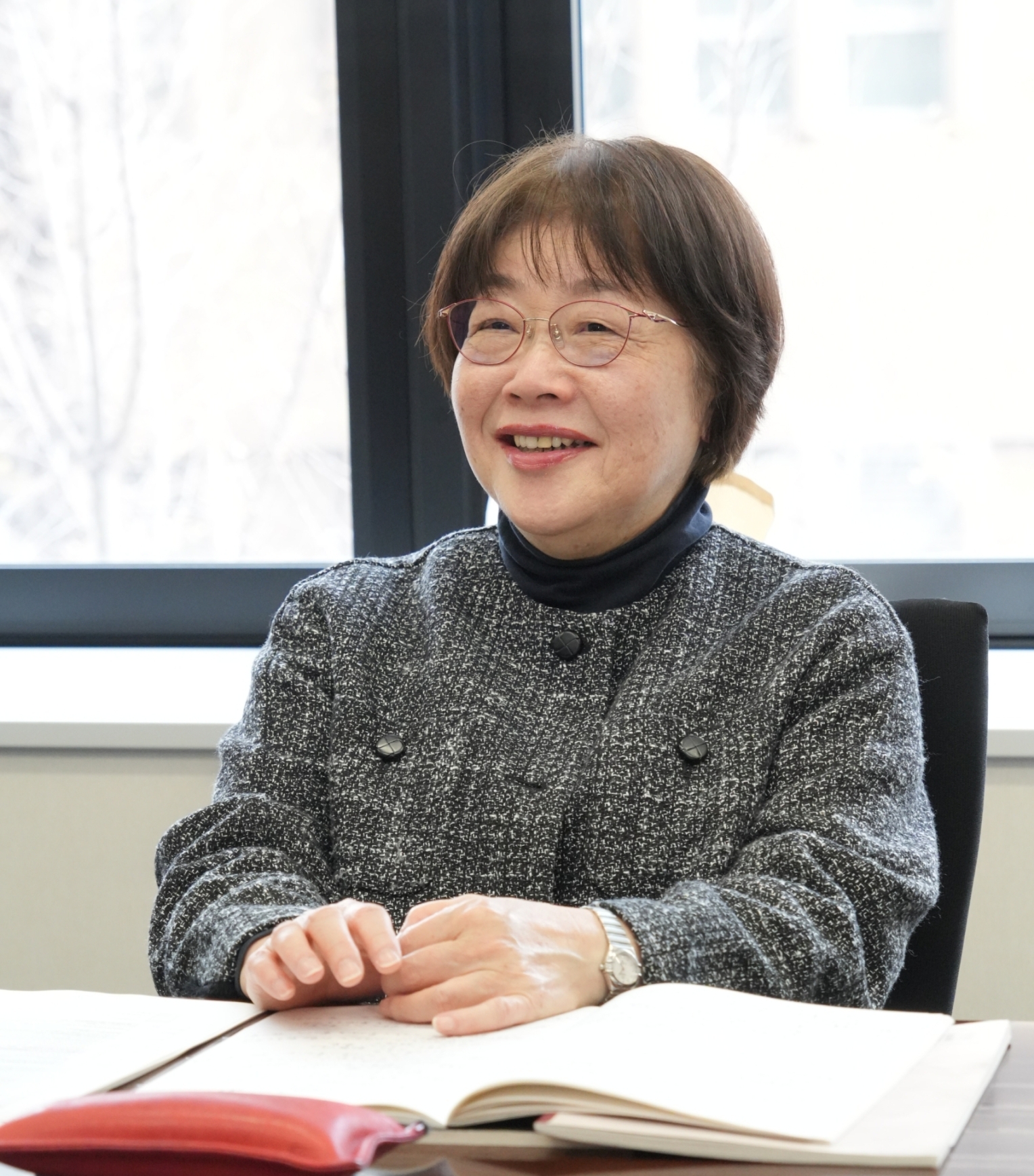
嶋村 和恵:
単発的に覚えているのは、Tutorial Englishとか、学術的文章の作成といった当時のオープン教育センター(現在のグローバルエデュケーションセンター)の科目の導入です。Tutorial Englishは英語の先生方からの意見もいろいろあったのですが、3人1組で英会話ができるということは、学生にとっていいだろうということで導入することを決めました。学術的文章の作成も、論文の書き方などの基本を教えることが必要だということで、導入しようということになりました。
あとは、コース制をトラック制という名前に変更したのは私が学部長の時だったと思います。恩蔵先生が学部長の時に、それまで4つのコースと言っていたのを、6つに再編することが決まり、それまでのコースとの違いを明確にするために、名前をコースからトラックに変えました。ただ当時、学生にうまく伝わっていなかったこともあり、例えば「マーケティング・国際ビジネス」というトラックは、学生には全部マーケティングだと思われてしまいました。それまで商業、貿易、金融と分かれ、金融は独立していたのですが、商業、貿易を合わせて「マーケティング・国際ビジネス」としたことも学生はうまく理解できていなかったかもしれません。学生にはなかなかうまく伝わらないということを感じました。
オンラインと対面の科目をうまく使っていきたいという思いはあったのですが、例えば学生はオンライン科目の統計などをきちんと勉強できているのか、効果の検証が必要だと思っています。
恩藏:
5年一貫制度(2014年度開始)について説明してもらえますか。私の認識では、当初、この制度の学生は少なかったのですが、ここ数年、多くなっていますよね。学生に浸透したのか、世の中のニーズなのか分かりませんが、5年一貫制度で修士の学位を取って就職するという学生が増えている実感があります。
嶋村:
5年一貫制度導入のきっかけは、9月入試を導入した際に、9月に入って3年半で卒業できるような制度を実現したのですが、この3年半卒業という権利が9月入学生だけにあり、4月入学生に権利がないのは不公平ということで、4月入学生にも3年半で卒業できるということにしたのです。実際のところ、9月入学した学生で3年半卒業した学生はほとんどいなかったのではないでしょうか。4月入学者にも3年半卒業を認めることにすると、成績優秀で9月卒業を希望する学生がすぐに出てきました。商学研究科の早期修了制度を活用することで、商学部4年+商学研究科1年の計5年で修士学位が取得できる5年一貫制度とも結びついて、1年間の短縮は学生にとって魅力的なようです。この制度で勉強する学生も増えてきましたね。
意思決定プロセスの見直しとコロナ禍における危機をどう乗り越えるか

藤田 誠:
2014年度にカリキュラムが新しくなり、私は2016年9月から学部長に就任したので、取りあえずはカリキュラムを大きくいじらずに、管理委員会の方式を変えたりとか、教員制度検討委員会を廃止したりとか、むしろそういった意思決定のシステム、教員の採用方式、テニュアトラック、訪問教員、ジョイントアポイントメントなどの要望もあったので、これらの制度を導入したというのはありますね。
2020年の新型コロナウイルス感染症については3月、4月ぐらいのときは、誰もまだよく分からない状況でした。授業が始まったのは結局5月の連休明け、2週目ぐらいでしたね。Moodleの導入年度だったこともあって、教員同士で、メールで「どうやるんだ?」みたいなことをしょっちゅうやりとりしていました。
Moodleがちゃんと使えるのか、そっちのほうが怖かった。リアルタイムでやっても動画を展開しなければならないじゃないですか。あの頃は容量が小さかったから、結構時間がかかりましたよね。

120周年を迎えた早稲田大学商学部のこれから

横山 将義:
自分が学部長を引き受けたときに最初に思ったことは、これまでの総決算をやろうということですね。大森郁夫先生、横田信武先生、恩藏先生、嶋村先生、藤田先生が学部長として取り組んできたことに、何らかの形でいろいろと関わってきたので。
カリキュラムに関して言うと、2014年度に新しいカリキュラムが始まって、一番初めに問題意識をもったのが選択必修科目の多さだったんですよ。2017年の終わりぐらいのときに、事務所に学生の履修状況を調べてもらったら、3年生になってまだ1年生向けの選択必修科目を履修している学生が多くいた。2年生向けの科目を全然取れていない。僕が担当している経済政策は、Ⅱ群科目なんですが、それまでは150人ぐらい取っていたんですよね。ところが、2014年度のカリキュラムが始まって2016年度のときには履修者数が半減していた。2年生がほとんど取っていない状況だった。これは何でだろうと思って、他のⅡ群の先生に聞いたら、やっぱり同じようにⅡ群の科目をほとんど2年生が取っていないことが分かった。
先ほど申し上げたように、2014年度のカリキュラムの改編のときは、学生の自由度がかなり高かったので、易きに流れるところがあったから、しっかり基礎を身に付けさせようと、選択必修科目を6科目取るようにしたのです。ところが、それによってⅡ群科目がごっそり抜けてしまって、1年生の基礎科目の次に専門性の高いⅢ群以上に進んでしまうという状況だったのです。これはおかしいなというのがありました。
それから、トラックのくくりについても検討の余地がありました。先ほど嶋村先生が言われたように、マーケティング・国際ビジネストラックは、履修状況を見ると、マーケティングの科目を取る学生が多く、国際ビジネスの科目をあまり取っていなかった。トラックとして、そのくくりが本当に適当なのかどうかということを考える必要があった。また、経済系を見ても、それまでコース制のときには経済・産業で1つのコースだったのですが、経済トラックと産業トラックという形で分かれてしまって、名前も含めてすごく不自然だったのです。この辺のところを何とかしなくちゃいけないというのがありました。
また、語学教育について、恩藏先生の教育システムのときにも、嶋村先生の構想委員会のときも手をつけることができなくて、少し整理をしないといけないかなと。総合教育もいろんな形で乱立しているようなところがあったので、体系的に整理しないといけないのではないかということで手をつけたのです。
ですから、まずは必修科目を時代に合った形に見直していくということと、選択必修科目を見直していこうということが出発点。トラック再編は、現行の経営、会計、マーケティング、ファイナンス、保険・リスクマネジメント、ビジネスエコノミクス、6分野にうまい具合に形づくることができたと思っています。
かつて我々が学んだ経営、会計、商業学A・B、経済学などの科目は、他大学の商学系の学部の模範になったと言われています。それから、コース制を導入したときにも、他大学の模範になったと言われていたわけで、まず、国内の大学の模範となるようなカリキュラムをつくろうというのが背景にありました。
それをこのような形で、学部創設120年以降の方向性を示すことができたかなと思っています。大学院のほうでもこれからカリキュラムの改革に取り組んでくれると思うのですが、学部のカリキュラム改革を前提にして、専修の再編につながっていくと思いますし、必修科目でも、数学と統計の他にも情報系の科目を設定するなど、基盤教育のところに厚みを持たせる形にできたかなという感じはしています。
それから、総合教育も見直しを図りました。語学もいろいろと紆余曲折あったのですが、英語は必修化を維持し、いわゆる第2外国語については、1年生の必修はそのままにしながら2年生を自由化していくという形で対応しました。
あと、これまで懸案となっていた、基礎演習を導入するとか、2026年度からは、語学や総合教育の先生方の専門ゼミを3年生以降で始めることになるため、これまで手つかずのところ、あるいは少し課題として残っていたところなどを、ある程度解決できたかなというのが、この2年間、あるいはこの4年間の取り組みと思っています。
【全編は2025年6月発行の『早稲田商学』に掲載予定】


