Laboratory work education
実験教育

実験教育
伝統を引き継ぎ、探究する力を育む実験教育
 早稲田大学理工では、実際にものに触れ現象を体験する「実験教育」を教育の原点として重要視し、創設当初から教育体制を整え、充実させてきました。 実験・実習を中心とした体験型の授業により、教室での講義内容をより理解するとともに将来必要な技術の基礎を身につけることができます。また、「実際に創り上げる過程」を経験することが自ら進んで課題に取り組む力を育みます。 この伝統的な実験教育の特徴は現在にも引き継がれています。
早稲田大学理工では、実際にものに触れ現象を体験する「実験教育」を教育の原点として重要視し、創設当初から教育体制を整え、充実させてきました。 実験・実習を中心とした体験型の授業により、教室での講義内容をより理解するとともに将来必要な技術の基礎を身につけることができます。また、「実際に創り上げる過程」を経験することが自ら進んで課題に取り組む力を育みます。 この伝統的な実験教育の特徴は現在にも引き継がれています。
充実した実験・実習カリキュラムと教育環境
理工3学部には、新入生全員が履修する理工学基礎実験をはじめ各学科の教育プロセスに沿って特色ある専門実験科目が設置されています。実験・実習科目は100科目を超え、それぞれの科目は工夫されたユニークな内容となっています。
これらの実験・実習科目では、担当教員を中心に助手やティーチング・アシスタント(大学院生)、専門技術を有する職員がそれぞれの特徴を生かした多角的な指導をしています。また、専門分野ごとの大規模実験室には、学生一人ひとりが直接触れて実験できるよう多くの設備が設置されています。 このような充実した実験教育環境だからこそ、科学技術の発展を担った多くの人材が巣立ってきたのです。
視点とセンスを磨く豊富な基礎実験
豊富なテーマで基礎知識を習得
全1年生が物理系14、化学系6、生物系2の全22テーマの基礎実験を経験、理工学的センスを磨きます。高校時代に物理・化学・生物のいずれかを学習してこなかった学生も、理工系分野の基礎知識を習得します。
ものづくりの楽しさや遊びの要素も取り入れ、自主性を育成
身近な題材を扱った実験や、ものづくりや遊びの要素を取り入れたユニークな実験などを通して、21世紀に必要な幅広い視野や独創的な発想力を養い、自主性を伸ばします。
試行錯誤を重ね、解決方法を発見する力を体得
多くの友人とともに試行錯誤を重ね、高学年時に、自分の専門性が発揮できるよう考え抜く力を身につけます。
五感を磨き探究心を育てる
知識としての学問と最新テクノロジーを融合した実験も多数。五感を使って、従来のやり方にとらわれない柔軟な視点や学問的な探求心を育てます。
基礎実験の一例
エアホッケーの物理(物理系)
エアホッケーゲームを利用し、円盤同士の衝突や円盤と壁との衝突、跳ね返り運動を調べます。円盤の動きをビデオカメラで録画、運動量や角運動量、力学的エネルギーを算出し、自らの手と目で物理的関係を考察します。
電磁誘導(物理系)
磁石がコイル内を通過すると発生する誘導起電力。電磁誘導と自由落下する物体の運動をコンピュータを使って解析します。磁石がコイルを通過する時に発生する電圧を測定。またコイルに流れる電流から生まれる磁束が、磁石の運動にどういう影響があるかについても考察します。
レンズを作る(物理系)
レンズの中心から離れても焦点のズレが少なく薄い非球面レンズ。この実験では、大学独自に開発した装置を使ってアクリル棒を削り、約20倍の倍率を持った非球面レンズを作成、ものづくりの楽しさや大切さを実感し、光学技術の基礎を学びます。
細胞の顕微鏡観察(生命科学系)
光学顕微鏡の基本的操作や種類による鏡像の違いを学習します。人間の口の上皮細胞を用い、細胞が分裂によって自己増殖することを理解します。
ナイロンの合成(化学系)
ナイロンを使って繊維やマイクロカプセルを作成、その構造や引っ張り強度の相関を調べます。人口赤血球モデルを用いて界面張力、浸透、透過の物理化学現象を観察、酸素運搬機能を理解します。
エレクトリックギター(物理系)
身近な楽器のひとつエレキギターは、弦の振動をどのように電気信号に変換しているのか?実際にピックアップを組み立て変換の原理を理解します。得られた電気信号を加工し、音質の変化の様子を観察。それが物理的にどのような意味を持つのかを考察します。弦の振動周波数と、弦の長さおよび線密度との関係も定量的に解析します。
技術者・研究者としての素地を養う多彩な専門実験
実践力の体得
各専門分野では、時代の最先端に触れる実験が用意されています。文献では到底得ることのできない実践力を体得。「知っていること」と「できる」は違うことを体感します。
知識から知恵を生み出す
多彩で専門的な実験科目を通し、知識から知恵を生み出す力を育みます。卒業論文では、その知恵を絞って解決困難な課題を自ら解決する経験を積みます。
研究分野を支える支援体制
技術スタッフは卒業・修士論文のための技術相談など、最先端の研究をバックアップ。安全に研究ができる環境も整備しています。
専門実験の一例
基幹理工学部 表現工学科 〈プロジェクト学習〉
表現工学科が掲げる芸術表現の探求と芸術活動を実現する、あるいは開発するための技術の追求を目的としたプロジェクトです。「各論」の授業で習得した知識や技術を、実際の作品制作や、技術研究に役立てるための実践的プログラムによる基礎演習で、自分の特性、将来の希望に応じて参加することができます。
創造理工学部 総合機械工学科 〈メカトロニクスラボ〉
機械(メカ)の性能はエレクトロニクスとの組み合わせによって飛躍的に向上させることが可能です。各種のセンサやアクチュエータを活用したメカの製作も容易であり、メカトロニクスに必要な基礎的な点を理解し、設計法を学ぶことができます。 実際にLine Following Robot(LFロボット)を作成し、ロボットを構成する電子部品、半導体素子やセンサなどの特性を基礎実験として実施し段階的に理解していきます。
先進理工学部 応用化学科 〈無機・分析化学実験〉
実験の安全教育から化学分析に用いる実験器具・試薬の基本操作を習得します。容量分析は古典的な分析手法ですが、現代でも重要な手法です。この手法を用いて化学分析の概念や各種機械分析の手法を学びます。講義で修得した化学の原理や理論が具現化されます。
実験・実習を支える技術職員
理工3学部・研究科のある西早稲田キャンパスでは充実した研究環境のもとで理工系分野を中心とした研究活動が活発に行なわれています。
先端的研究を進める上で必要な大型研究設備が多数設置され、その多くは公的補助金により毎年導入されています。これらの設備は専門の技術者によって管理され、研究者や大学院生を中心とした学生に広く利用されています。
また、設備の利用者を対象とした講習会やセミナーなどを年間を通して随時開催し、リサーチリソースの有効活用を促進しています。
経験豊かな技術スタッフ
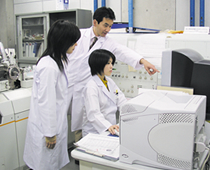 理工3学部の大きな特徴として約100名の専門技術を有した職員の存在があります。これら技術スタッフは教育実験の指導、研究活動の支援、安全な環境の確保などの重要な役割を担っています。
理工3学部の大きな特徴として約100名の専門技術を有した職員の存在があります。これら技術スタッフは教育実験の指導、研究活動の支援、安全な環境の確保などの重要な役割を担っています。
実験教育においては、学生が興味をもって学べるようその実験内容の立案から実施まで深くかかわっています。卒業・修士論文のための実験においてもその専門性を発揮し技術指導にあたっています。 また、新入生の生活面、勉学面などをケアするアドバイザーとしての役割も担い、学生の有意義なキャンパスライフを支援しています。
さらに2006年度からは、複数の大手企業と連携した「テクニカルエキスパート制度」を導入しています。これは、企業から早稲田大学に迎え入れた技術者が実験教育の一端を担うことにより、学生が実社会で活躍している技術者に直接触れることができる画期的な制度です。
安全な環境
西早稲田キャンパスには教職員・学生合わせて約1万人が日々学習・教育・研究活動を続けており、さまざまな実験設備や化学物質を取り扱っています。こうした活動が安全に行われることはもちろんのこと、健康の維持や環境の保全も大学にとって重要な課題です。
本学独自のシステムによる薬品管理や高圧ガスボンベ管理、X線装置安全管理、「環境保全センター」による薬品廃棄物の回収や排水管理など法令を遵守した管理を行っています。
また、定期的な総合防災訓練の実施、自衛消防隊審査会への参加、学生および教職員を対象とした各種安全教育の実施などを長年実施し組織的に安全意識の啓発に取り組んでいます。






