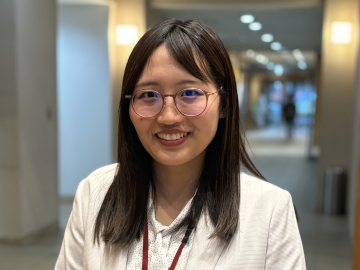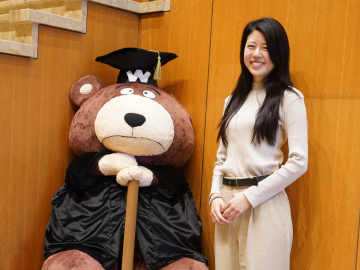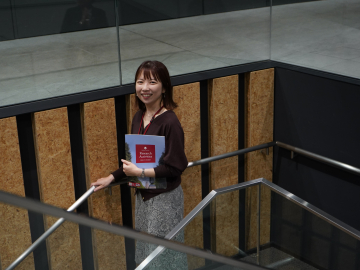社会人の皆さんのキャリアに新たな可能性を提供する
-現在どのような業務を担当されているのか、お聞かせください。
早稲田大学教務部コンティニューイング・エデュケーション推進室にて、全学のノンディグリー教育*の推進と、日本橋キャンパス(COREDO日本橋5階)で展開する教育事業である「WASEDA NEO」の事務局として、ノンディグリー教育事業の具体的な企画・運営業務および日本橋キャンパスの管理業務等を担当しています。WASEDA NEOは2017年に開設され、現在は、社会人に対して時代の変化に即した学びと交流の場を提供し、新しい社会をつくる人材を育成することを目指し、早稲田の強みを活かした学びを意識しながら、様々な教育プログラムの企画・開発・運営を行っています。展開するプログラムの例として、合計履修時間60時間以上で構成される一定のまとまりのあるプログラムである「履修証明プログラム」があげられます。現在、リーダーシップやデータサイエンス、マーケティング等、社会人の方が実務現場で活かすことを主眼としたプログラムを開講しています。WASEDA NEOには専任の教員がおらず、各プログラムの企画に際しては、学内外の教員や著名なビジネスパーソンとネットワークを構築し、個別の講師依頼を経た上で進めています。事業の歴史が浅いこともあり、プログラム開講中は、実際に職員も教室に入り、講義や受講生の様子を観察し、必要に応じて開講期間中でも軌道修正をかけることもあるなど、具体的な教育内容に深く関わる点も特徴です。
*ノンディグリー教育:学位を取得することを目的とせず、知識・技術の習得を目的とする課程
-現在の業務のやりがい・魅力について教えてください。
学びの仕組みや環境づくりを通して、社会人の皆さんのキャリアに新たな可能性を提供できることが大きなやりがいであり、魅力です。また、大学内で職員は事務に関わる事項に注力することが一般的であるのに対し、WASEDA NEOではプログラムの具体的な企画から参加する機会も多く、より幅広い業務に携わることができる点も魅力だと感じています。

-本学に応募されたきっかけを教えてください。
学部2年の時に参加した本学主催の国際交流イベントに引率職員として同行していた職員の方から大学職員の仕事についてお話しいただき、「大学職員は学びの場や人との出会いの場を創り、提供することができる。それによって未来ある学生のキャリアの後押しもできる魅力的な仕事である」と感じたことがきっかけです。魅力を感じた背景として、当時の私は、所属していた音楽サークルの活動の中で、演奏技術の勉強会や学年や大学をまたいだ交流会といった「学びと交流の場」の企画をすることが多く、参加した学生のサークル活動がより充実したものになっていくことに大きな喜びとやりがいを感じていました。このサークルでの活動が、大学職員の業務内容とリンクし、大学職員を志すに至りました。

大学の制度を活用し、自らキャリアを掴む
-在職中に学位取得支援制度を利用して経営学修士(MBA)を取得されたと伺っています。なぜ大学院に通われたのでしょうか。また、業務とはどのように両立されましたか。
大学職員として働き始めて5年ほど経つ頃、自分が社会人として提供できる価値が見いだせず、漠然とモヤモヤした気持ちを覚え、大学院での学びや出会いが何かを変えてくれるのではないかと期待を抱いたところから大学院進学を視野に入れました(今思うとかなり安直だったように思います苦笑)。その上で、経営学・経営管理の分野を選択したのは、それまでの実務経験から、職員が経営管理の知識を持って大学運営に携わることの重要性を強く感じたためです。大学運営における意思決定機関の委員自体は教員で構成されることが多いのですが、意思決定の過程において、職員の立場からも、適切な経営管理の考えに基づいた情報の提供、観点の提供を行うことで、より適切な意思決定を促すことができるのではないかと感じたことから、経営学に関する課程を選択しました。業務との両立については、所属先の管理職および同僚に進学する旨を伝え、理解を得た上で、可能な限り効率よく業務を進めることを意識しました。業務と大学院の課題が立て込む時期もありましたが、朝時間の活用など、自分にマッチする生活リズムを見つける等して、何とか修了することができました。
-学位取得支援制度以外にも学内公募制度や育児休職制度など、本学の展開する様々な制度を活用されたと伺っています。それぞれの制度活用について詳細を教えてください。
大学院での学びを活かし、一事業体の経営・運営の全体に関わりたいという想いから、学内公募制度を利用してコンティニューイング・エデュケーション推進室への異動を希望しました。冒頭にご紹介したWASEDA NEOは、これまでにいくつかの事業変遷を経て、私が着任する少し前に、現在の「社会人への学びと交流の場の提供」に力を入れ始めたところでした。そのため、WASEDA NEOとは果たして何者で、どこを目指すのか、といった事業の基本理念の再確認から、取り組む事業ポートフォリオの全体像と各事業間の繋がりのデザイン、各事業における具体的な戦略、単年・複数年の収支計画等、まさに一つの事業体の運営に関わることができています。学内公募制度を通じて、これまでの業務経験や自己啓発の経験を活かせる部署への異動が叶ったことは自身の大きなモチベーションに繋がりました。加えて、具体的な教育事業の現場では、プログラムに参加される社会人の方々が生き生きとした様子で学びと交流に没頭し、成長していく場に立ち会うことができ、この点でも本制度を活用させていただけたことに感謝しています。また、育児休職制度を利用し、実質2か月程度、育児に専念することができました。本学では、女性の産休・育休はもちろん、男性の育休も当たり前のものとして受け入れられていると感じています。男性が産後直後に育休を取得することは、休職期間中はもちろんですが、「育児のはじまり」を家族と共に支え合うことで、復職後の育児への関わり方も、育休取得が叶わない場合と比べ、大きく異なるものになるのではないかと感じました。これから入職される皆様にも、これらの学内の各種制度を存分に活用されることをお勧めします。

より良い教育・研究の場づくりを目指して
-早稲田大学職員を目指す皆さんへメッセージをお願いします。
大学は、そこに集う人々の人生が変わるきっかけに満ちた場所であり、大学職員という仕事は、その環境を土台から支えるとともに、さらに発展させることのできる仕事です。基本的な職務内容上、ミクロな視点では「地味な」仕事が多いと感じる側面もあるかもしれませんが、それらは組織の大きな目的・目標を達成するために必要な「地道な」仕事であると考えています。ミクロとマクロの両方の視点から、より良い教育・研究の場づくりを目指して、同じ志を持つ皆様と一緒に働けることを楽しみにしています。
参考リンク:
コンティニューイング・エデュケーション推進室ウェブサイト https://www.waseda.jp/inst/oce/
WASEDA NEOウェブサイト https://wasedaneo.jp/