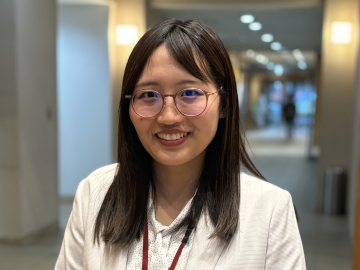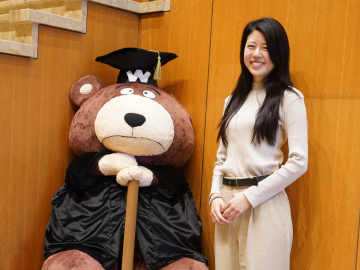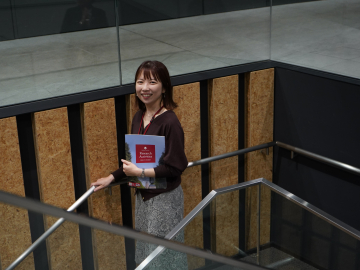ICT・遠隔教育を基盤とした、教育手法の研究開発・普及促進
―これまでの経歴、現在の業務について教えてください。
本学を卒業後、新卒で早稲田大学に入職しました。まず総務部法務課に配属され、本学が締結する様々な契約書のチェックといった法務対応等を行いました。その後、商学学術院商学研究科に異動となり、大学院の学務業務全般(科目登録、学科目、成績等)を担当しました。その後、商学学術院内の新しい研究科である経営管理研究科やビジネス・ファイナンス研究センターの立ち上げに従事したのち、現在の大学総合研究センター(以下、大総研)に異動となりました。
大総研は、本学の創立150周年である2032年に目指すべき姿を示した「Waseda Vision 150」の実現に向けて、2014年に設立された比較的新しい組織です。本学の教育、研究、経営の質的向上に向けた大学改革を推進することが目的で、その中で私は、ICT・遠隔教育を基盤とした、教育手法の研究開発・普及促進を担当しています。具体的には、2020年4月から運用を開始しているLearning Management System(学修管理システム)であるWaseda Moodleを活用した授業の運営支援や、Waseda Moodleへの新しい機能の追加検討等を行っています。その他、大総研で管理している教室が学内にいくつかあり、当該教室へのアクティブラーニング型ハイフレックス授業(学生参加型かつ対面/オンラインの同時進行型授業)を前提としたマイク、Webカメラ等の最新機器の導入や、管理・運用を担当しています。また、2020年4月に早稲田キャンパス7号館1階に開設した CTLT(Center for Teaching, Learning and Technology)において、主に教員向けにWaseda MoodleやICT機器の授業での利用相談や使い方に関するセミナー等を行っています。
本学では、Waseda Moodleの導入やCTLTの設置準備を、新型コロナウイルス感染症が拡大する以前から進めていたため、手探りの状況ではありましたが、これらのツールや拠点を活用して、対面授業からオンライン授業への切り替えを行うことができました。

―本学に応募されたきっかけを教えてください。
大学時代は地方自治のゼミに所属しており、教育行政に興味がありました。地方自治体のインターンシップを通じて教育の仕組みづくりに携わることに魅力を感じ、また教育実習を通して学生と近い距離での仕事にも興味をもちました。そんな中、大学職員という仕事を見つけ、その両面の仕事をできることに魅力を感じ、応募しました。
学生や教員のために何ができるか
―職員の仕事のやりがいは何ですか。
本学では、異動すると転職したように感じるほど、多種多様な業務があることに難しさと面白さを感じています。総務部法務課では、契約書のチェックや著作権の相談といった専門的な業務もあり、法学部出身ではなかったため色々と勉強することができました。商学学術院商学研究科では、新研究科設立というタイミングで大変なことも多くありましたが、修了要件の設定や授業科目の配置といった、基礎的な部分から教員とともに作り上げることができました。教員と職員が協働して業務にあたることができる点にもやりがいを感じています。現在は大総研において、デジタルキャンパスコンソーシアム(DCC)という企業との産学連携プロジェクトも担当しており、新たな教育手法や授業改善につながるICT機器を試験的に導入する取り組みに携わっています。企業の方と議論を交わしながら、プロジェクトを進められることもやりがいです。
その中でも、人の成長に携わることができる点に最も魅力を感じています。大学として利益を求めることももちろん大切ですが、学生のために何ができるかに力点を置きながら働くことができています。東日本大震災の際は早稲田大学 平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)が主催するボランティア活動として、学生を引率して夜行バスで被災地に赴き、がれき撤去等の活動を行いました。また、通常業務とは別にプロフェッショナルズ・ワークショップ(現:企業連携ワークショップ – 早稲田大学 教育連携課 (waseda.jp) )の運営にも参加していました。このように学生と共に活動することができる仕組みが整えられているのも本学の良さであると感じています。教育行政的な仕組みを考える仕事、学生と直接関わることができる仕事のどちらも経験でき、職員として働くことの魅力を感じています。

―職場の働きやすさはいかがでしょうか。
部署や担当業務によって忙しさや繁忙期が異なるため、一概には言えない部分がありますが、一般的にはワークライフバランスを実現しやすい環境だと思います。
商学学術院事務所時代に新しい研究科や研究センターの設立を担当していた際は忙しかったですが、第一子が生まれた以降は業務も落ち着き、ワークライフバランスが改善したことで、子育てにも取り組みやすくなりました。現在は、第二子の保育園送迎のために始業時30分の育児時短制度を活用しています。
男性でも育児休職が取りやすい環境なのも良いことですね。第二子が生まれた際は1カ月間、育児休職を取得しました。家事に貢献できたとまでは言えないかもしれませんが、コロナ禍で色々と制約がある中、子供と長く居られる時間は貴重でした。育児時短や育児休職について、周りの方も快く受け入れてくれる環境です。
―早稲田大学職員を目指す皆さんへメッセージをお願いします。
学生と関わったり、人の成長に携わりたい方は是非検討してほしいです。早稲田大学は校歌にもある「進取の精神」のもと、「とりあえずやってみよう」という風土があり、色々なことに挑戦できる環境があります。
2026年以降は18歳人口の減少に伴い、大学進学率が上昇しても大学進学者数は減少局面に突入すると予想されています。また、「事務職」と言えども、業務は非常に幅広い上、専門性を求められる分野もあります。
このような状況の中、安定ばかりを追い求めず、早稲田大学をより良くしたいと自ら考えて行動できる方、成長し続けられる方に是非来ていただきたいです。みなさまからのエントリーを心からお待ちしています。