- Featured Article
文学学術院事務所
仁平さん(2009年 新卒採用)
先輩からのメッセージ
Mon 24 Nov 25
先輩からのメッセージ
Mon 24 Nov 25
研究教育の環境を整える
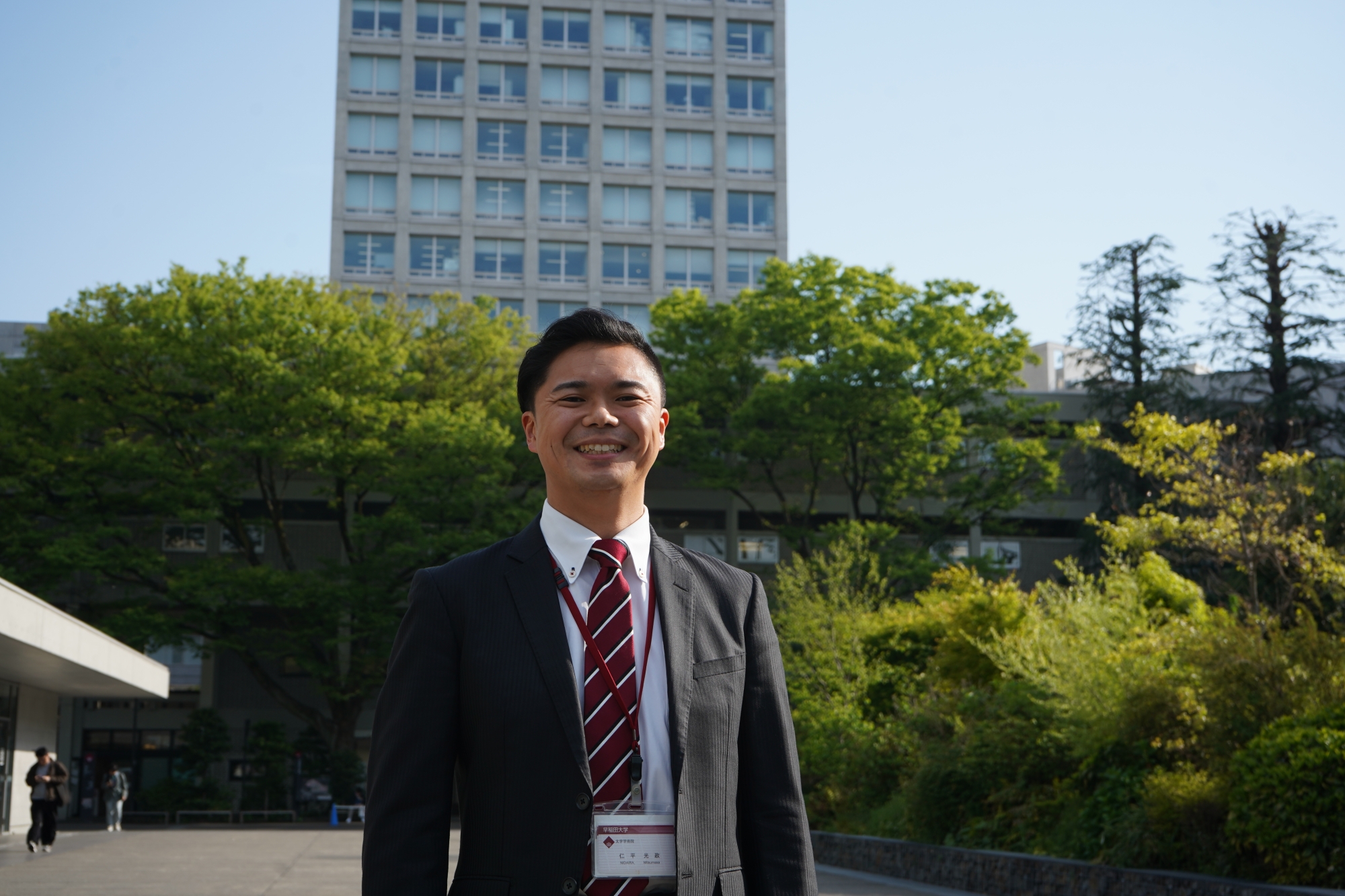
現在はどのような業務を担当されていますか。
文学学術院事務所に所属していて、科目や教室の配当を担当しています。文学学術院には文化構想学部・文学部そして大学院文学研究科という二学部一研究科が設置されています。学部と研究科はそれぞれ論系やコースに分かれており、別個のカリキュラムがあります。私はカリキュラムごとに必要な授業の曜日・時限や教室要望等の情報を確認し、それらを取りまとめる業務をしています。
科目の配当は、パズルのような感じです。たとえば卒業に必要となる必修科目間で時間が被らないように設置する必要がありますし、可能な限り選択科目や資格取得に関連する科目との重複を避けなければなりません。各論系・コースへ学科目配当アンケートを展開して情報を集約するのですが、その結果、バッティングしてしまう時もあります。その際は、個別に各論系・コースの先生方と相談して調整しています。
教室の配当作業では、たとえば「この授業は必修科目」「これは語学科目だから定員40名」等、それぞれの科目の特性に合わせ、教室をアテンドしています。予め配慮して配当しても、実際に授業が始まると、先生方から「もう少し広めの教室でお願いします」や「常設PCがある教室で実施したい」といった要望を受けることもあります。今は、ちょうど春学期の1週目が始まったところなので、まさにその教室変更の個別相談、調整が動いている最中です。
文学学術院の前は、どのような部署で業務をされていたのですか。比べて、違いなどはありますか。
文学学術院に配属される前は研究推進部研究支援課で研究費関連業務を、その前は所沢キャンパスでスポーツ科学学術院の学部・大学院入試業務を担当していました。思い返すと、研究支援課時代は先生方と直接やりとりするよりも、学術院の職員を介す形が主でした。そのため、学術院の職員と密に連携を取り、業務に臨む機会がとても多かったです。比べると現在は、先生方や学生たちと直にやりとりする業務が圧倒的に多いです。そのため、接する相手の年齢層が幅広いという特徴があります。
研究支援課時代は職員のその先にいる先生や研究員を意識して、「真に求められていることは何か」を意識して、学術院で対応されている職員の話を傾聴することを心がけていました。現在、学術院事務所で業務に携わっている今、その姿勢は間違っていなかったと感じています。
忘れられない仕事がありましたら教えてください。
新しい制度の立ち上げに携わったことです。一つは大学院スポーツ科学研究科の春期入試の新設です。大学院への進学を促進すべく、入試の機会を増やすという目的で、当時、入試業務を担当されていた先生方と業務のシミュレーションをいろいろと行いました。新たに実施を検討した時期は、学部の入試や各種処理等とのスケジュールとも平行しており、その調整にとても苦労しました。結果的に入試の機会が増え、大学院志願者、進学者増に繋がったと感じています。
もう一つ、研究支援課時代にPI飛躍プログラムという次世代を担う初期段階のPI(Principal Investigator:独立した研究室を主宰する研究者)を重点的、かつ総合的に支援する支援制度の立ち上げに関わらせていただきました。採択されると、研究活動を促進する環境整備等に充てることが可能な研究促進費を三年間に渡って、人文・社会科学系であれば200万円/年、自然科学系であれば400万円/年を支給するという学内制度です。どのような成果が期待できるかの説明やその根拠付け、いかに本学の研究者にとって資する制度であるかということを関連する学内の各箇所間に伝え、調整することに苦心しました。最終的に経営執行会議や理事会等で審議・決定となるので、研究戦略センターの先生方と議論しながら制度を練らせていただきました。「世界で輝くWASEDA」の実現につながる、本学の研究の国際的なプレゼンスを高められるような研究者支援制度が立ち上げられたと思います。
さまざまな業務を経験されてきた中で、特にどういった点にやりがいを感じますか。
学生と先生から感謝の言葉をいただいた際、自分がしたことがきちんとつながっていると感じることですね。入試業務を担当していた頃、全国の様々な会場で進学説明会や相談会を行ったのですが、個別相談を行った高校生と保護者の方が私を覚えていてくださっていて、その高校生の方が見事を合格され、入学式で「ありがとうございます!」と声をかけられたときは大変うれしかったです。
文学学術院では映像や写真等を授業の資料で使われる先生が多くいらっしゃるので、それら把握することで、教室設備を考慮に入れながら教室配当を行っています。先生方から「お陰さまで授業が円滑にできました」とお礼のお言葉をいただくこともあり、細かな要望にも一つ一つ真摯に対応することの大切さを感じています。

多様な方と関わる、アクティブな仕事
大学職員に興味を持ったきっかけはなんでしたか?
学部二年生のときに、早稲田大学エクステンションセンターでアルバイトを始めたことがきっかけです。エクステンションセンターでは社会人向けの講座を開講していて、私は講座運営のサポートをしていました。そこで大学職員の方々の業務を見聞きする中で、興味を持つようになりました。
エクステンションセンターは、幅広い年齢層の方が講座を受けに来るので、いろいろな方と触れ合える刺激的な環境でした。大学を職場として認識し、また大学職員という仕事を志望するに至りました。
実際に入職してみて、イメージと違ったことはありましたか?
入学式や学園祭等、色々な行事を通じて季節の彩りや変化を感じられます。また、高校を卒業して間もない学生の方と接する機会もあれば、学術研究の第一線で活躍される先生方と交流を深めることもできるので、さまざまな世代の方々と触れ合えることが利点です。想像以上にアクティブな仕事だと思いました。
早稲田大学職員を目指す皆さんへメッセージをお願いします。
大学職員として働く醍醐味は、いろいろな人々と関わりながら大学の教育・研究活動、社会貢献、経営に携わるのが可能なことだと私は思います。大学職員は想像以上にアクティブな仕事だと感じています。学生の方や教員はもちろん、学外の方など、さまざまな立場の方々、ステークホルダーと関わりを持ち、フットワークよくキャンパスをかけめぐり、大学へ寄せられる意見やご要望を傾聴する姿勢が求められます。
積極的に自ら動き、考え、発信する力を持った方と共に仕事ができたらうれしいです。


