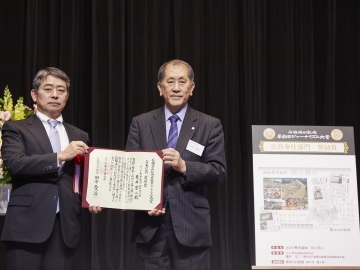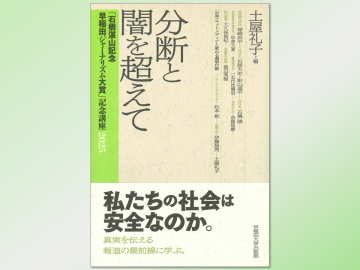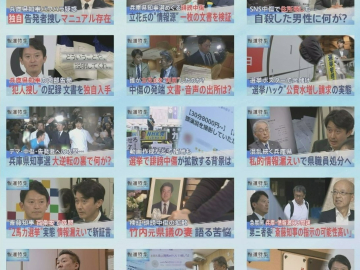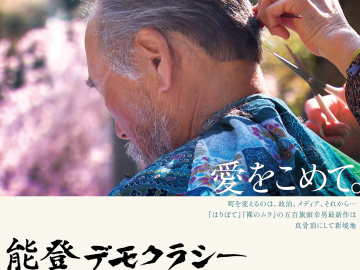【公共奉仕部門 奨励賞】
2020 熊本豪雨 川と共に
熊本日日新聞(朝夕刊、電子版)
2020熊本豪雨取材班 代表 亀井 宏二氏の挨拶

今回は多数の応募作品の中から奨励賞というご評価をいただきました。取材班、直接執筆したのは34人ですが、豪雨災害の発生から約1か月間、熊本県内におります記者を全部集めまして、毎日ほぼ10人から20人現地に入って取材をしておりました。その全員の気持ちを代表しまして感謝申し上げます。ありがとうございます。こんな華やかな場所に立たせていただいているのですが、実は、扱ったテーマが災害ですので、なかなか大喜びできないと言いますか、ちょっと複雑な思いでいます。思いが溢れるものですから、ペーパーにまとめてきました。
昨年7月の熊本豪雨では、日本3大急流と言われる球磨川が氾濫しました。当日65人の方が命を落とされ、今なお、お二人が行方不明です。そしてその後、関連死という形でまたお二人が亡くなっております。さらに、最新の集計なのですけれども、まだ3288人の方が仮設住宅などで仮暮らしをされております。改めてこの場をお借りして、犠牲になられた方、ご遺族、被災された方々にお悔やみ、お見舞いを申し上げたいと存じます。
熊本ではこの5年間で県民の記憶に刻まれる日にちが増えました。2016年4月14日、熊本地震の前震があり、2日後、4月16日に本震がありました。いずれも震度7です。そして今回、去年の7月4日、熊本豪雨。地震、そして豪雨の時には新型コロナが拡がっておりました。その中での豪雨災害。災禍が続く中で私たち取材班は、大切な命をもう失いたくない、そして亡くなった方たちの犠牲を無駄にしたくないという、そういう思いで取材をスタートしました。避難生活の中で命を落とされる方もいらっしゃいます。そういう方たちも含めて、災害から命を守るにはどうすればよいのか、私たちは何をすべきなのか、それを考えながら、特に水害については去年の7月に起きましたけれども、1年後の今年の7月、また起こるかもしれない、来ないという保証はない、そういう焦りに似た危機感を持ち、とにかく今年の梅雨までをデッドラインに、この連載を書き上げました。
そしてこの連載を通じて見えてきたことがあります。よく言われるのですが、早期避難の難しさや、避難指示などの災害情報の伝達の難しさ、そして、被災地における復興事業に、どう民意を反映させるかという課題も見えてきました。これはいずれも全国共通の課題だと思います。当然われわれ、これからも取材を続けていくテーマだと思っております。やがて豪雨から1年半経ちます。連載の中で取り上げているのですが、14人の高齢者が亡くなられた特別老人ホームは、今は建物が解体され、更地になっています。その隣にある渡小学校はそのまま残っておりまして、その校舎の壁には濁流の跡が、まだそのまま残ってさらされています。被災地である人吉市と八代市の間を結ぶJR肥薩線というローカル線はまだ再開のめどすら立っていません。
ニュースでご案内かと思いますが、一昨日の7日、国土交通省は正式に球磨川の支流の川辺川にダムを造る方針を表明しました。国内最大級の治水専用ダムといわれています。当然、このダムを巡っては再び地元は振り回されることになると思います。熊本日日新聞として、地元に根差した報道機関として、これからも被災者の方々の声を聞きながら、共に復興の道筋を模索していきたいと思っております。同時に災害というのは発生した段階から風化が始まると言われますが、風化に抗いながら、今回の受賞を励みに災害から命を守る方策を考えていきたいと思っております。
私事ながら、30年前にこの大学を卒業してこの道を歩き始めました。今、新聞各社、ご存知の通り、厳しい状況ではありますが、この賞を頂いて、歩いてきた道のりは誤りじゃなかったかなとちょっとほっとしているところです。こういう壇上に立たせていただいて、感謝しております。ありがとうございます。