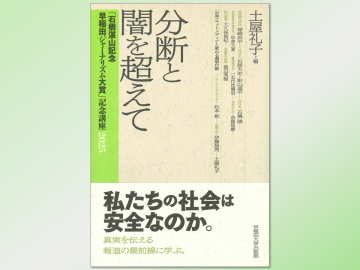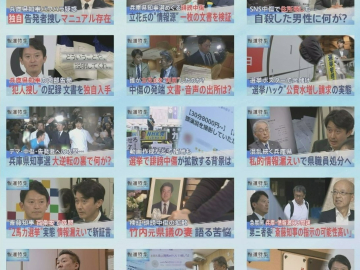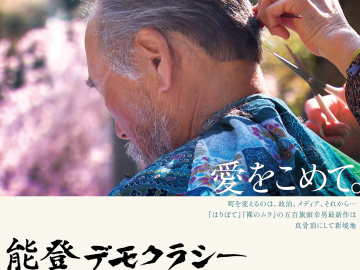※第20回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式 式辞・講評 はこちら
【文化貢献部門 奨励賞】
サクラエビ異変 (静岡新聞、静岡新聞ホームページ「アットエス」)
静岡新聞社「サクラエビ異変」取材班代表
坂本 昌信(静岡新聞社編集局社会部)氏の挨拶

このたび、取材班としてこのような大きな賞を受賞でき、一同、喜び、感謝しております。
幸いにも文化貢献部門奨励賞に選んでいただいた「サクラエビ異変」は2018年11月から2年以上も続けている記者有志による「取り組み」です。私はいま「取り組み」と申し上げましたが、この「サクラエビ異変」は単なる「新聞連載」なのではなく、もはや「取り組み」なのだと考えております。
ところで、みなさん、サクラエビという食材はご存じかと思います。いまは高級食材として扱われることが多い駿河湾産のサクラエビはかつて、沿岸の港町ではどこでも安価で食べることができた「朝食のお供」でした。実際、私の子供のころにもそうでした。
なぜいまわれわれの食卓に上らなくなってしまったのか―。
地球温暖化や黒潮大蛇行、乱獲、不法投棄による川の汚れなどさまざまなことが考えられます。
取材班としては、地元の静岡大学などの研究者10人によって発足した「サクラエビ再生のための専門家による研究会」と連携し、かなり科学的な腰を据えた議論を記事化する一方、乱獲や不法投棄による川の汚れといった自分たちの地元で起き、人間による解決ができる問題についてはジャーナリストとしてそこにある「社会問題」を発掘し、日々挑んでいる状況です。
私たちがいま注目している、駿河湾奥の主産卵場に注ぐ富士川の河川環境は、壊滅的です。皆さんは、東海道新幹線で富士川を渡る際に雄大な富士山に目を奪われるかと思いますが、鉄橋の下を流れる富士川は、戦時期から続く巨大水利権と強制的に働かされた朝鮮人により作られた導水トンネルなど発電施設をいわば〝悪用〟したアルミ加工会社による売電により水はほとんど流れておらず、上流域の堆砂の進んだダムや砂利採石業者による凝集剤入り汚泥の不法投棄により濁りがひどく、アユがほぼいません。
かつては文豪の井伏鱒二が愛した「尺アユの川」は「死の川」そのものです。富士川沿いは反骨のジャーナリストである石橋湛山先生が早稲田大学入学前、過ごされた場所です。恐らくまだ水量が豊富で美しいこの「日本三大急流」を見ながら、東京での生活に思いをはせていたのではないでしょうか。私たちは湛山先生の名前を冠するこのたびの大きな賞をいただき、その賞の名に恥じぬ「取り組み」を続けていきます。
冒頭、取材班の活動はもはや「取り組み」である、と申し上げました。これは、志ある記者が、自らが置かれた境遇にかかわらず一人の人間として、活動していくという意味です。ここにわれわれが掲げている取材班の理念であるカントの「理性の公的利用」があるのです。
最後に。私どもの静岡新聞社に関する報道で、このたびこのような表彰式に招いていただいた早稲田大学様に本当に申し訳ない思いでいっぱいでここに来ました。私どもの社是である「不偏不党」を体現していくのはこれからだと思っております。