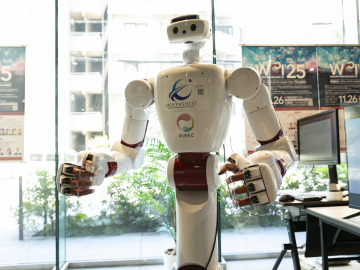ケネス・J・アロー教授は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれた。1940年ニューヨーク市立大学シティカレッジを卒業し、その後コロンビア大学大学院でハロルド・ホテリングとエイブラハム・ワルドの下で数理統計学を学んだ。1941年に修士号取得、1951年に博士号を取得している。この間、1947~49年シカゴ大学コウルズ委員会においてヤコブ・マルシャックの下で研究助手を務め、後の経済学研究の基礎を培った。コウルズ委員会での2年間を経てランド研究所に移り、国際紛争や戦略のゲーム理論的分析を研究テーマとした。国家のような集合体が個人と同様の効用関数を持つための条件を考察し、博士論文『社会的選択と個人的評価』を書いた。その後スタンフォード大学で教鞭を執ることになり、1968 年から 1979 年までのハーバード大学在籍時期を除いて、長くスタンファード大学に在籍し、現在はスタンフォード大学名誉教授である。
アロー教授の現代経済学への重要な貢献は、正統的なミクロ経済学の殆ど全分野にわたっている。これらの貢献は、3つの類型に分類することができる。
第1の類型は、研究課題としては既知であったものの、正確な論証が完成していなかった命題を正確に表現して、精緻な証明を完成した決定的な貢献である。その代表的な例は、正統的な一般均衡モデルと呼ばれる経済均衡の基本モデルを緻密に完成して、このモデルにおける競争均衡の存在定理を確立した業績である。ジェラール・ドブリューと共同で完成した研究は、19世紀にレオン・ワルラスによって構想され、その後ヴィルフレッド・パレート, ジョン・ヒックス, ポール・サミュエルソンによって精緻化された経済モデルの論理的な整合性を最終的に確立した業績として、不滅の評価を得ている。
第2の類型は、正統的な経済理論の枠内で、新鮮な問題提起を行うとともに新たな理論の基礎構造を構築することによって、その後長期にわたって膨大な後継研究を誘発した先駆的な貢献である。その代表的な例は、リスク、情報、不確実性を初めて経済学の分析対象とし、その分野の先鞭をつけると同時に自らも独創的な研究成果を残したことに示されている。1950年代に開始された氏の貢献は、その後1970年代以降の情報の経済学や医療経済学の基礎をも提供して、応用ミクロ経済学の諸分野の発展に計り知れない影響を及ぼしてきた。また、不確実性を含む一般均衡理論の発展にとって決定的に重要な契機となった条件指定付き財及び証券という氏の着想は、学界に鮮烈な驚きを与えた。
第3の類型は、従来は問題の所在すら明瞭に理解されていなかった重要な研究領域を開発して、最も本質的な基礎定理を論証した革新的な貢献である。この貢献とは、アロー教授による社会的選択の理論の創造と、その中枢的な命題である一般可能性定理(アローの不可能性定理)の確立である。思想的にはコンドルセの投票の逆理、ベンサムの「最大多数の最大幸福」という功利主義思想の系譜を引く氏の新たな理論は、厚生経済学と政治経済学の概念的な大飛躍をもたらした記念碑的な業績であり、数理政治学という新たな学問分野の誕生に不可欠な貢献をなした。これにより、公共政策の分析における数理的かつ理論的アプローチを可能にする重要な方法論的基礎を確立したのである。端的に言えば、現代における政治経済学の基礎を築いたと言えよう。
このように、アロー教授の研究教育上の業績は、日本で最初に政治経済学を教え始めた本学の教育と密接に関係しており、本学の多くの教員ならびに多くの学生がアロー教授の学術的貢献に、直接的・間接的な影響を受けて研究を進めてきた。このことからも早稲田大学はアロー教授の偉大な研究業績に敬意を表するものである。
ここに早稲田大学総長、理事、監事、評議員ならびに全学の教職員は一致してケネス・J・アロー氏に名誉博士(Doctor of Laws)の学位を贈ることを決議した。
学問の府に栄えあれ!
大学が栄誉を与えんとする者を讃えよ!
(Vivat universitas scientiarum! Laudate quem universitas honorabit!)