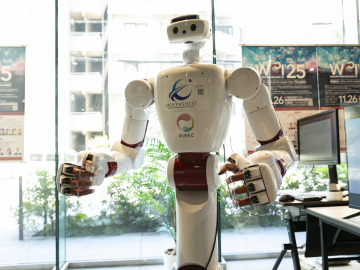早稲田大学では、11月14日、第14回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の贈呈式を行いました。鎌田薫総長の挨拶に続いて、大賞3名・奨励賞1名の受賞者に賞状とメダル・賞金を贈り、その成果を称えました。本賞および授賞作等についてはこちらをご覧ください。
第14回を迎えた今年の贈呈式には、受賞者と共に取材・報道に尽力した取材チーム等の方々をはじめ、報道・メディア関係者、ジャーナリストを志す本 学学生など約100名が出席。選考委員を代表して新井信氏から講評が述べられ、その後に続いた受賞者および関係者の熱いスピーチに、来場者は熱心に聴き 入っていました。
贈呈式後のレセプションは、第一線で活躍するジャーナリスト同士が意見を交換したり、学生たちが受賞者にお話を聞いたりと、和やかながら活気あふれる会となりました。

鎌田総長(前列中央)と受賞者、選考委員
講評 新井信委員
今回は計137作品の応募から選ばれた11作品が最終選考に残りました。新聞、テレビ、書籍、映画、写真集という作品以外に、これまで挙がってきたことがない『東日本大震災の記録と津波の災史』の展示図録というものまで最終候補に挙がってきて、他のジャーナリズム賞にはない幅広い対象作品を議論することになりました。今回の授賞作品はすべて、ジャーナリズム作品として優れているだけでなく、「現代性」という意味においての重要問題を取り上げ、その背景にも大きな広がりを持つテーマにそれぞれが挑んでいます。地道な取材で積み上げたジャーナリズムの大きな成果だと思います。
受賞者のコメント
公共奉仕部門 大賞
NNNドキュメント取材班 代表 ディレクター 大島千佳氏

やりきれない思いを抱いたことが取材のきっかけとなり、内部告発をした現役の三等海佐の取材を始めました。彼の告発によって裁判の展開が変わっていき、遺族側の逆転勝訴となる様子を見てきました。内部告発がいじめの証拠とみとめられ、彼の勇気によって裁判が動くという瞬間に立ち会うことが出来ました。立ち上がる勇気を持つことで世の中は変えられるんだ。そのような感動を取材を通じて感じることができました。三等海佐と出会えたことは一生の宝となりました。この賞を励みに、メディアに関わる人間として、おかしいものはおかしい、伝えるべきことは伝える、意義のある番組を発信していきたいと思います。
草の根民主主義部門 大賞
下野新聞社編集局子どもの希望取材班 代表 下野新聞社編集局社会部長代理 山崎一洋

貧困状態に置かれた人は引きこもってしまいます。アポをとってもすっぽかされてしまう。取材しても話してくれない。そんな状況が続きました。その中で、報道していけるのだろうかと悩まされる日々が続きました。しゃべってくれない、また、本当のことを話しているのだろうかと疑問を持ちつつ、取材班は体温や空気を感じてきました。知った以上、逃げられない、伝えることが使命だと思いました。60回の連載で少しは伝えられたのかなと思う。貧困に置かれた子供たちが社会と隔絶されています。少しでも今回の報道が、子供たちの役に立てればと思います。栃木県内の地方紙なので、この賞により、全国の方に目を向けていただけるかと期待しています。
文化貢献部門 大賞
与那原恵氏

琉球王国崩壊から今日までの時間、そして沖縄学の系譜を描く試みでした。歩くことで見えてくるもの、聞こえてくる声があることを度々実感しました。ジャーナリスティックな手法といえるかもしれません。沖縄は今も困難な状況にありますが、琉球とは、沖縄とは何か、自分たちは何者なのか、私は、その問いを手放したことはありません。自らに問い続けながら坂道を歩んでいきたい。その時、この賞は大きな励みになると思います。(写真は与那原恵氏の代理:長嶋美穂子氏)
草の根民主主義部門 奨励賞
有限会社ホームルーム ドキュメンタリー・ディレクター 伊藤めぐみ氏

高校生の時にイラク戦争を報道でみて、この戦争を止めたいという思いから、イラクに関心をもつようになりました。「自己責任」を問う報道に強い違和感を持ち、どうにかしたいという思いで、この映画を制作しました。自分勝手な要求、思い上がりもありました。どのように受け止められるのか、一種のかけでもありました。最近の集団的自衛権の議論、日米関係の報道を目にすると、イラク戦争の体験から学べることがたくさんあると、考えさせられる材料を提供されていると感じます。