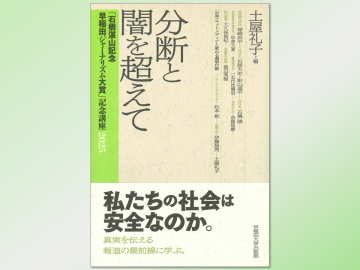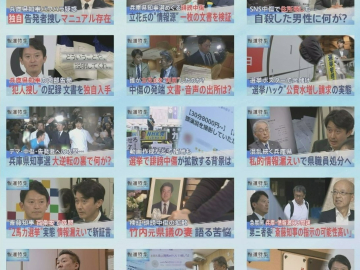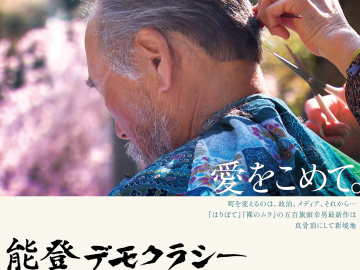【公共奉仕部門 奨励賞】
神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄スクープと一連の報道
神戸新聞、電子版「神戸新聞NEXT」
霍見 真一郎 氏の挨拶

歴史というのは、後の世の人がきちんと検証できるように残しておかなければならないと、この度の神戸連続児童殺傷事件あるいは事件記録廃棄問題を取材する過程で痛感しました。社会が判断に迷ったとき方向性を指し示す裁判所には、歴史を作っているという感覚がありませんでした。
事件記録廃棄問題の報道は、改正少年法の長期連載取材のなかで、私が神戸家裁に連続殺傷事件の記録について確かめたことから始まりました。職員が隠す様子もなく、淡々と「すべての記録は廃棄しました」と言うのを聞いたときに、これは大変なことだと思いました。最高裁に取材しても、「見解を申し上げるのは差し控える」「記録の廃棄経緯が不明である点も問題はない」「当時の神戸家裁の職員に聞き取り調査を行うことは、個人の見解や記憶の範囲にとどまる」と、取りつく島もありませんでした。東京に出張し、最高裁に取材したこともあります。事前にやり取りもした上で来たのですが、最高裁の職員は、屋内ではなく、門から出た公道で私の名刺を受け取りました。
神戸新聞は地方紙です。それほど大きな組織でもありません。東京の司法記者クラブにも足場がありません。そんな中で取材班を組織し、100本以上の記事を重ねてきました。とりわけ、この事件記録廃棄の発端になった神戸連続児童殺傷事件のご遺族の思いは、丁寧に報じました。
観念的な最高裁の考え方と、地元・神戸における神戸連続児童殺傷事件の受け止め方、これを両輪として回していくために、分かりやすく、五感で感じられる情報の伝え方を大切にしました。そして、初報から約7か月後に最高裁は責任を認めて謝罪し、このほど、事件記録は国民共有の財産であると銘打った規則をつくりました。ここに至るまでの長期にわたる報道は、地方紙の意地であったと考えております。
ただ、この神戸連続児童殺傷事件の記録が廃棄された2011年2月28日は、地元紙神戸新聞の司法キャップを私が退任する日でもありました。まさに私自身がこの記録に目を向けていなかった。これは大いに反省するところだと思っております。
事件記録廃棄問題を報じたことに、審査員の方々から望外に評価いただき大変誇りに思います。30年前、早稲田大学の入学式で私はこの大隈講堂の2階席に座っていました。この大学での学びをきっかけに頑張ってきたことが、30年後にこういった賞をいただけるまでになり、大変うれしく思います。
このたびは、栄えある石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞奨励賞をいただきまして、本当にありがとうございました。