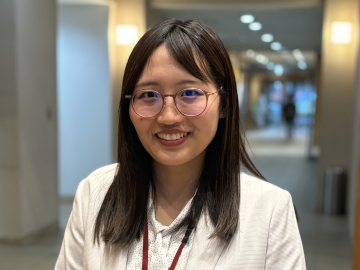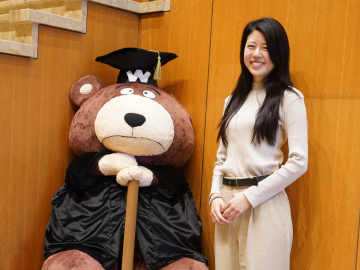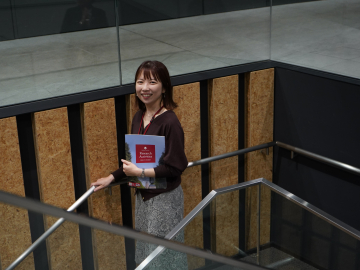大学構成員のダイバーシティ理解に向けて
―現在どのような業務を担当されていますか。
私は学生生活課とスチューデントダイバーシティセンター(GSセンター)の2部署を兼務しています。学生生活課の業務は多岐にわたりますが、特に力を入れているのはWaseda Vision 150の核心戦略5「教育・研究への積極的な学生参画の推進」と「学生参画の仕組み創設PJ」そして学生参画・ジョブセンターに関連する業務です。早稲田大学の学生参画を推進するべく、大学全体の学生参画活動を取りまとめ、計画を策定し、実行しています。学生参画・ジョブセンターでは、学生スタッフと協働して様々なイベントの企画運営や委員会活動等を行っています。学生一人ひとりの能力に合わせて仕事の割り振りをすることや、学生スタッフの意見を活かしながら、より良い企画が実現できるようにサポートすることを意識しています。学生の声を大学運営に反映させるためには色々な苦労がありますが、自分たちの提案が実現され、満足げな学生の姿を見ていると、やっていてよかったと思います。学生参画活動は年々増加傾向にありますが、今後は量的拡大に留まらず、質的な拡大も視野に入れて、業務にあたりたいと考えています。
また、兼務で所属しているスチューデントダイバーシティセンターは、大学生活全般において不利益を被りうる多様なマイノリティ学生が、安心して学業に専念できる学生生活環境の確保や、大学に集う全構成員が多様な価値観や生き方を受容するキャンパスづくりの推進を目的とする部署です。GSセンターはその中でもジェンダー・セクシュアリティに関するリソースセンターです。私は主に学生スタッフの管理や、財務・経理、GSセンター主催イベントの運営、教職員向け「ALLY養成研修」 (※) の企画運営等に携わっています。
(※)ALLY=LGBTQ+を理解し、支援する仲間のこと。

―特に思い入れのあったプロジェクトについて、具体的にお聞かせください。
一番思い入れがあるのは立ち上げから携わっていた教職員向けの「ALLY養成研修」ですね。海外研修でアメリカの各大学におけるLGBTQ+の学生支援の取組を調査してきた職員から、現地では無料で公開されているALLY養成プログラムがあると聞きました。ぜひ早稲田大学でも導入しようと決意したものの、この過程が色々と大変で、実現までおよそ1年半かかりました。単にプログラムを日本語に翻訳すれば良いというわけではなく、日本人に馴染みのある表現を加筆修正したり全体の流れやワークの内容を変えたり、様々な工夫が必要でした。スチューデントダイバーシティセンター(GSセンター)の職員はもちろんのこと、有志の職員や学生スタッフとも協働し、体験会を行ってはプログラムの内容を調整する作業を繰り返しました。また、研修の実現にあたっては、人事課やダイバーシティ推進室と対象者や実施時期など細かな調整を行いました。一からプロジェクトを立ち上げ、実現するには様々な苦労がありましたが、それでも実現までの過程が本当に楽しく有意義だったと感じています。現在、このALLY養成研修は年3回実施されることになり、大学全体のダイバーシティ&インクルージョンに寄与していると自負しています。
「早稲田」だからこそできる挑戦
―職員に応募したきっかけをお聞かせください。
学生時代に学習塾でアルバイトをしていて、高校生のキャリア支援に関わる仕事をしていました。就職活動時に教育業界へ進むか迷いましたが、新卒では違う業界に進みました。しかし、社会人6年目に、改めてその後のキャリアを考える中で、やはり教育業界の道に進もうと決意しました。もう一度キャリア支援の仕事がしたいと考え、キャリアコンサルタントの国家資格を取得し、大学職員を選びました。数ある大学の中でも早稲田大学を選んだのは、早稲田大学で働くことで日本の教育水準の向上に関わることができると考えたからです。早稲田大学は学生数も多く、他大学への影響力も強い大学です。早稲田大学の取り組みが大学業界全体の指針となることが期待されています。そういった環境で働くことで、日本全体の教育水準向上に貢献できるのではと考えました。

―現在の業務を担当するまでにどういった経緯を辿ったのでしょうか。
入職後、初めて配属されたのが学生生活課です。先述のとおりキャリア支援に関わる仕事をしたいと考えていたため、学生と密接に関わることができる職場に配属されたことを、とても嬉しく感じたことを覚えています。そして、入職3年目からスチューデントダイバーシティセンター(GSセンター)と兼任することになりました。当時、LGBTQ+という単語自体に聞き覚えはありましたが、ジェンダー・セクシュアリティに関してはまるで知識のない状態でした。しかし、GSセンターで働くからには専門知識なども知っておかなければいけないと思い、実際にセンターに赴いておすすめの本を貸してもらい、勉強しました。一度勉強してみると、非常に奥の深い分野で、学べば学ぶほどもっと知識をつけたいと思うようになりました。今でも月に何冊かはセンターで本を借りているほか、外部の講演会や研修プログラムに参加するなど、自主的に勉強する機会を設け、業務に生かしています。また、同じ志を持つ職員同士で切磋琢磨できる場が欲しいと考え、GS職員勉強会という勉強会を立ち上げ、だいたい月1回の頻度で開催しています。
―現在の担当業務のやりがいは何ですか。
一番は学生の成長を身近に感じられた時です。担当業務の性質上、学生と一緒に仕事をすることが多いのですが、一人一人の個性を見極めながら、どこまでアシストするかを考え、成長をサポートしています。メールもまともに書けなかった学生が、企画書を作って企画内容を説明したり、堂々とプレゼンしたりできるようになった姿を見たとき、この仕事に取り組んでいてよかったと感じます。また、GSセンターの仕事を兼務するようになって感じたことは、いかに自分が小さな世界で生きてきたのかということです。マイノリティかどうかは関係なく、生きづらいと思うこと、おかしいと思うことを社会の問題として捉えてよいのだということ、声をあげることがいかに大切なのかを学びました。LGBTQ+の方々の支援はもはや私のライフワークの一つであり、GSセンターを離れても続けていきたいと考えています。また、学生生活課として担当していたWASEDAスポーツ・健康月間 の一環で性教育やメンタルヘルスに関するイベントを企画するなど、兼務をしていたからこそできた仕事もあったと感じます。

―早稲田大学職員を目指す皆さんへメッセージをお願いします。
本学の職員になって驚いたのは、現場の職員の裁量が大きいということです。どうしても大学職員というと、前例主義や上の指示に盲目的に従う、というイメージが強かったのですが、本学にはやりたいことがあれば挑戦させてくれる土壌があると思います。大学職員になってからいくつものプロジェクトを立ち上げてきましたが、そのほとんどが頭ごなしに否定されるということはありませんでした。また、他大学から本学の取り組みについて勉強させてほしい、という依頼を度々受けている中で、早稲田だからできる、ということがたくさんあるのだと感じています。早稲田大学の職員というのは、これからの教育業界、ひいてはこれからの日本社会を作る仕事だと思います。誰もが生きやすい明日を作りたい、という気概のある方に是非挑戦してほしいと思います。