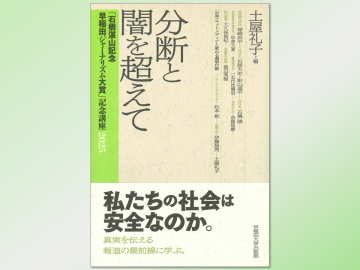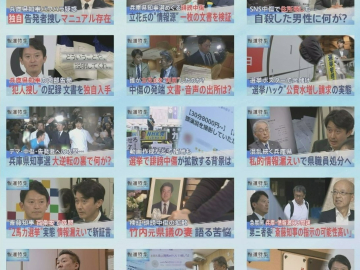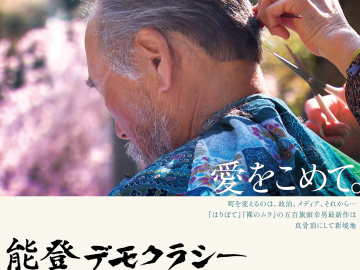【公共奉仕部門 大賞】
『ルポ入管ー絶望の外国人収容施設』
書籍(筑摩書房)
平野 雄吾氏の挨拶

※平野 雄吾氏エルサレムにて活動中のため、当日はオンラインでご挨拶いただきました。
※本式典会場には、ちくま新書編集部の藤岡 美玲氏に代理でご出席いただきました。
みなさん、こんにちは。エルサレムはいま昼間の正午です。この度は名誉ある賞をいただきどうもありがとうございます。仕事の都合とコロナの関係で、授賞式に参加できずとても残念です。今回、高度な公共性を帯びた全地球的レベルの課題として入管収容問題を取り上げてくださったこと、とても嬉しく思っています。あらためて取材に協力してくださった外国人の方や支援者の方たちに御礼申し上げます。ありがとうございます。
司法審査のない無期限収容を特徴とする入管施設の施設を私が初めて訪れたのは2017年の秋です。面会した収容者は車椅子姿のパキスタン人の男性でした。「80㎏あった体重が2年強で45㎏まで減った」と話すこのパキスタン人の声を聴いて、この時、この施設内で何か大変なことが起こっているに違いないという直感が働き取材を始めました。暴力や暴言、医療放置や自殺・自殺未遂、信じがたい実態が次々と収容者たちの話から出てきます。そして、調べてみるとさらに驚くことに、戦後直後に入管制度が始まってから70年以上、同じようなことが繰り返されていました。近年の一時的な現象でない以上、そこには何らかの構造的な問題があります。目には見えないけれど確かに存在する何か。日々の取材のなかで、暴力があった、医療放置があった、と報じるかたわら、入管問題の本質とは何だろうか、と考え続けていました。それをまとめたのが「ルポ入管」という書物です。
異質なものを排除し、周囲に同調を求める世間の文化。強い立場の者が意思決定をすれば良い、とするパターナリズム或いは父権主義、そしてそれに付随する身分制意識。「人権」をともすれば「人道」や「思いやり」とみなしがちな社会の土壌。外国人を通して眺めてみるとこの国の形が良く見えてきます。入管施設は在留資格のない外国人、という社会的に脆弱な立場の人たちを拘束する密室のため、多くの問題が見えてきます。けれど、実は入管施設で浮かび上がる諸問題は、程度の差は様々ですが、日本社会の多くの場所で生じていることではないでしょうか。その意味では、入管収容問題は入管当局と外国人の問題ではなく、日本社会全体の問題を浮き彫りにしています。いま入管難民法の改定が再び議論されそうですが、問われているのは長期収容ではなく、この国の在り方だと感じています。
今回、公共奉仕部門として「ルポ入管」が選ばれたのは、早稲田大学が入管問題を通じてこの国の在り方をもっと議論しよう、と社会全体に呼びかけている、そんなメッセージではないか、と私は受け止めています。そうしてそうした議論の一助となれるよう、今後も記者として努力を続けたいと改めて気を引き締めています。
今回はどうもありがとうございました。