- ニュース
- 未来の理工生へ(3)〜 Round Talk 若手研究者が見る未来
未来の理工生へ(3)〜 Round Talk 若手研究者が見る未来
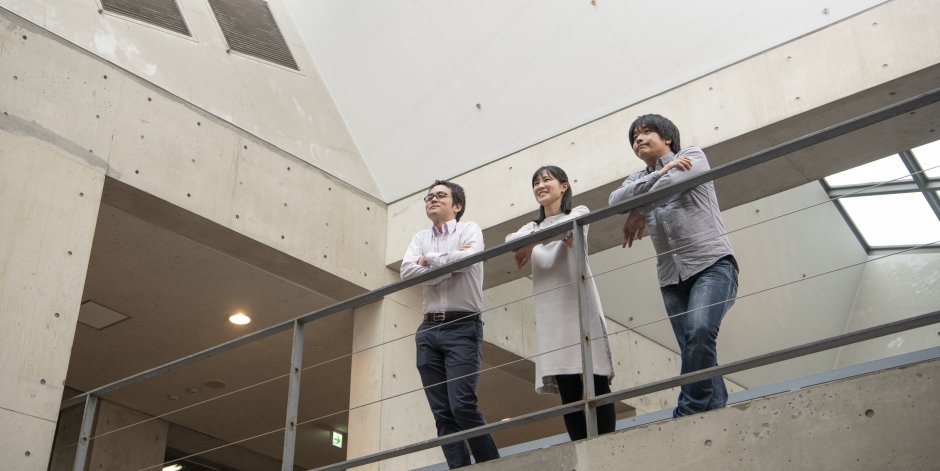
- Posted
- 2020年6月1日(月)
理工学術院総合研究所が若手研究者を支援する「アーリーバードプログラム」。同プログラムに採択されている若手研究者3名が、研究の魅力やそれを支える理工学術院の魅力について語り合いました。
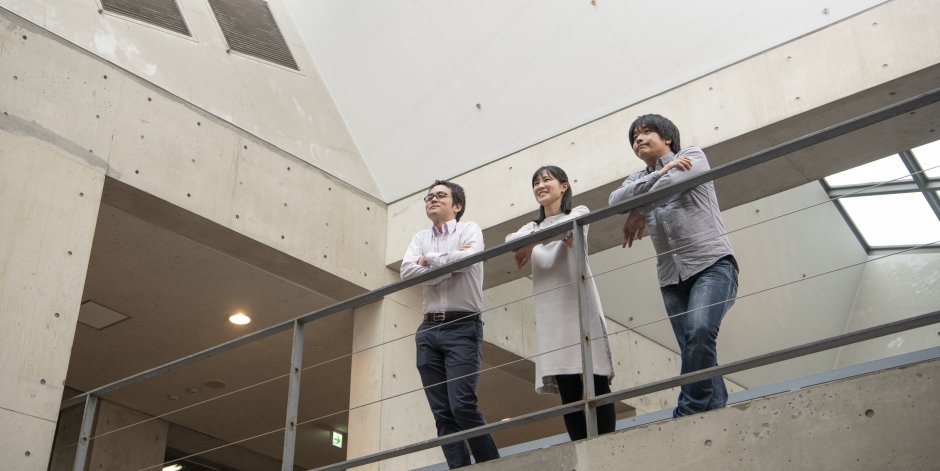
| アーリーバードプログラム 理工学術院総合研究所が実施する、若手研究者育成・支援を目的とする事業。2011年に始まって以来、毎年15名程度、これまでにのべ148名が採択されています。採択者には研究助成金が交付され、自身の研究活動や、アーリーバードの活動を通じて生まれた、異分野の研究者との融合領域研究にも役立てることができます。 |
座談会参加者プロフィール
※参加者のプロフィールは取材時(2019年12月)のものです。
 田中 一成さん
田中 一成さん
理工学術院総合研究所 数理科学研究所 次席研究員 博士(工学)
基幹理工学部 応用数理学科卒業
[田中さんの研究テーマ:計算機援用証明]
数学の未解決問題の一つ、ナビエ・ストークス方程式の解の存在について、精度保証付き数値計算を用いて解き明かそうとしています。数学の難問に対して、異分野であるコンピュータサイエンスの考え方をもって挑むのが、持てる武器を総動員して戦う総合格闘技みたいで面白いと感じています。

對馬 聖菜さん
理工学術院 創造理工学部 建築学科 講師 博士(工学)・一級建築士
創造理工学部 建築学科卒業
[對馬さんの研究テーマ:快適で省エネな室内環境制御法]
「より少ないエネルギーでより空間を快適にする」というテーマのもと、人の皮膚から発散される物質がどんなときに部屋の空気の快適性に影響するのか調べています。工学でありながら物質の化学分析もするので、異分野の人と共同研究できるのが面白いところです。

中山 淳さん
理工学術院 先進理工学部 生命医科学科 助教 博士(理学)
先進理工学部 生命医科学科卒業
[中山さんの研究テーマ:乳がん転移の仕組み解明]
乳がんは乳腺細胞が変化してできるがんですが、がん細胞は乳腺に留まらず、肺や骨へ転移していきます。その仕組みを、最先端の遺伝子操作技術を用いて明らかにしようとしています。がん細胞にとって、最初に発生した場所が最適な環境のはずなのに、なぜ違う環境に転移するのか。がん細胞の「生存戦略」がカギになるはずです。
皆さんはなぜ、研究の道に?
中山 小さい頃から、人や動物の体の構造、進化について考えるのが大好きで、理工学、生命科学、基礎医学を複合的に学ぶ生命医科学科に進学しました。今は乳がんの転移の仕組みについて研究しています。「なんで、どうやって私たちは生きているんだろう」ということを突き詰める、不思議で面白い学問分野だと思っています。
田中 私は高校生の頃から先生になりたくて、いずれは大学の運営に携われる教員を目指しています。そのために、まずは得意な数学の分野で成果をあげるのが目標です。今のテーマは、コンピュータサイエンスに用いられる精度保証付き数値計算を、数学の証明に応用することです。
對馬 私のきっかけは幼稚園の頃にありました。周りの子が将来の夢としてケーキ屋さんやスポーツ選手を挙げる中で、友達が「設計士になりたい」と言ったのです。かっこいいなあと思いましたね。もちろん、私自身もずっとものづくりが好きだったためこの道に進みましたが、原点はこの記憶かもしれません。大学では建築の中でも環境工学を学び、現在は生体発散物質の臭気に着目し、良好な室内空気環境を省エネルギーで実現するための原理と手法を追求しています。
研究を支える環境として、理工学術院の良いところは?
田中 まずは研究者として、アーリーバードプログラムには助けられています。資金面はもちろん、他の大学と比べて良いと思うのは、研究者同士の交流の機会が設けられていること。研究者同士の交流によって、さまざまな研究分野を知ることができるので勉強になりますし、人間形成に役立つと思います。
對馬 アーリーバードに限らず、多様な専門分野を持つ教員や学生が周りにたくさんいるので、普段から有意義な意見交換ができるのはいいところですよね。早稲田は建築分野に関して、私立大学の中で最も歴史のある大学なので、校友のネットワークが広いことも研究に役立っています。
田中 早稲田は数学もすごいですよ。特に解析学では科研費の採択件数が多く、教員にも世界的権威がそろっているので、最高レベルのアドバイスが受けられます。
中山 生命医科学については、伝統ある医学部を抱える大学と比べれば、早稲田はまだまだ駆け出しの状態です。だからこそ、自分たちで道を切り開いていける面白さがあると思います。それに、研究室のあるTWIns(東京女子医科大学と早稲田大学の連携による医理工融合研究教育拠点)をはじめ、さまざまな研究設備が充実しています。ここでしかできない研究もたくさんあります。
学生生活を通じて成長したと思えることは?
對馬 一番成長したと感じるのは、研究室に入ってからです。与えられた課題ではなく、テーマを自分で設定して考える経験を通して、何事にも主体的に関わるようになりました。また、田邉新一先生の後押しもあってデンマークへ留学し、日本と異なる生活文化を体験したことは、建築環境研究に対する視野を広げる大きな機会となりました。
中山 私も、研究室で仙波憲太郎先生に出会って研究に対する姿勢が変わりました。世紀の大発見を夢見て研究の道を志す私たちに、先生は「いきなり大発見はできない。でも、小さな発見を積み重ねていけばそれが大発見につながる」と教えてくださいました。その言葉が、毎日地道な研究を進めるモチベーションになっています。
 田中 私は、授業の専門性が一段上がった3年次の頃から、授業がグンと面白く感じるようになりました。その時に出会ったのが大石進一先生です。先生の研究室で、がむしゃらに、でも自由に研究をさせてもらえたことで今の自分があると思います。
田中 私は、授業の専門性が一段上がった3年次の頃から、授業がグンと面白く感じるようになりました。その時に出会ったのが大石進一先生です。先生の研究室で、がむしゃらに、でも自由に研究をさせてもらえたことで今の自分があると思います。
中山 恩師との出会いは大きいですよね。学生の皆さんにもたくさんの教員の中から「この先生の話を聞きたい」という先生を見つけ、その先生を訪ねてほしいです。
今後の目標は何ですか?
對馬 国際的な活躍ができる女性理工学研究者として、自身の研究・教育能力を高めていきたいと思っています。より良い住環境の実現に向けて、まずは多くの人に認められる価値ある論文を書くことが目標です。教員としては、まだ模索段階ですね。将来の日本を担う学生を社会に送り出す責任ある立場なので、何をどう教えるべきか日々試行錯誤しています。
田中 私は数学を武器として、最低3つは新しい概念をつくりたいと考えています。例えばコンピュータ黎明期からあったディープラーニングは、長らく日の目を見なかった技術ですが、今や最もホットな技術の一つです。私も同様に、後の世に役立つものをつくりたいです。そのチャレンジした経験を基に、学生を指導していきたいですね。
中山 自分が何もしなくても、「サイエンス」は日夜進歩しています。その中で自分なりのサイエンスを突き詰めることで足跡を残したいですね。そしていずれは、研究室を主宰する規模で研究を進めたいと思います。大変ですが、楽しみながら研究の道を究めるつもりです。
未来の学生へのメッセージ
田中 恐れずに、やりたいことを何でもやってみてほしいです。全力で何かをやった経験が成長につながります!
中山 学生生活は長いようで短い時間。学業はもちろん、趣味や友達との交流も大切にして、何事も楽しんでください!
對馬 早稲田に集まる人は、出身も専門もさまざま。たくさんの人と仲良くなれば、きっと自分の助けになるはずです!
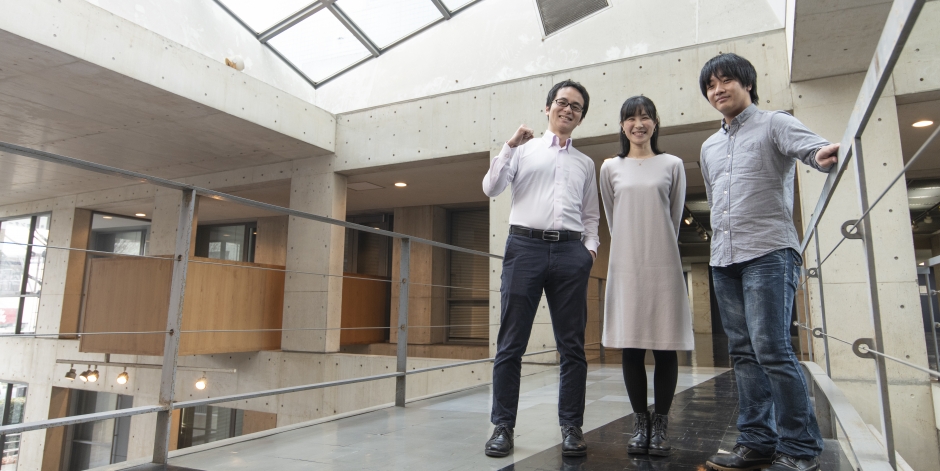
(「理工学術院パンフレット」2020年発行号より)





