- その他
- モジュール「人材・組織マネジメント」責任者:杉浦 正和教授
モジュール「人材・組織マネジメント」
責任者:杉浦 正和教授
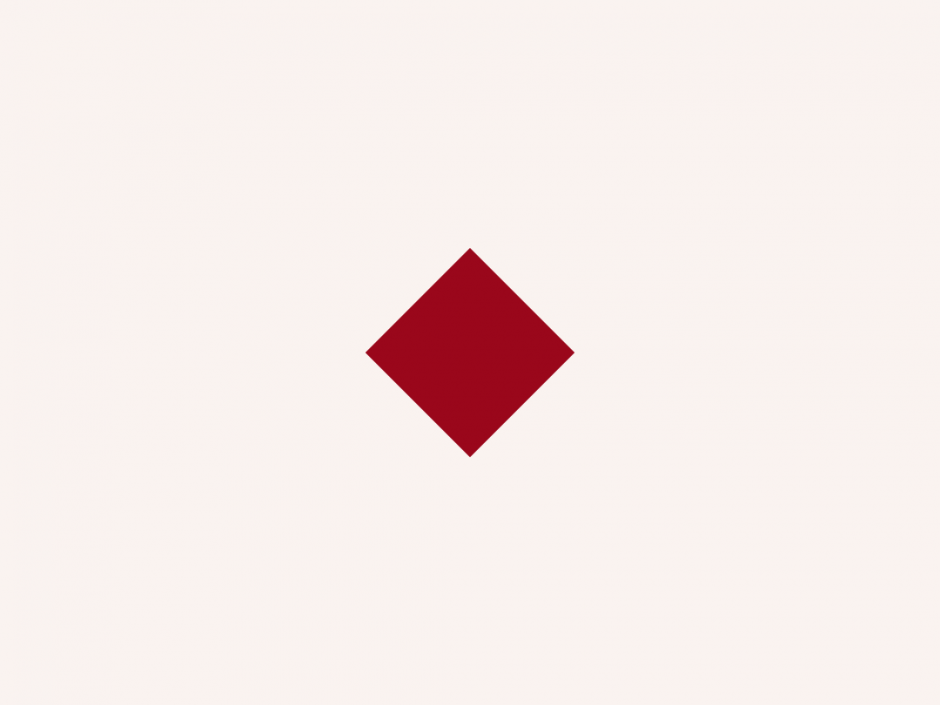
- Posted
- 2015年2月19日(木)
モジュール「人材・組織マネジメント」
責任者:杉浦 正和教授
ゼミのホームページ:www.jinzai-zemi.jp
ゼミのフェイスブック:www.facebook.com/WBS.jinzai
1.目的
「人材・組織マネジメント」は、「経営はつまるところ『ひと』と『組織』である」と考えている方に最適のモジュールです。通称「プロの人材ゼミ」と呼ばれているこのモジュールは、「人材・組織マネジメント」の分野における高度な専門性を獲得し、経営の様々な課題について「ひと」と「組織」の観点からの問題解決力を身につけることを目的としています。
このモジュールにおいては、まず、日本企業および海外の企業を中心に一般的となっている人材・組織マネジメントについての現状を把握します。次に、それぞれの視点を超えて、今後企業が持続的競争優位を築くための戦略的人材・組織マネジメントの考え方を探求していきます。
このモジュールの基本姿勢は、「実践」と「理論」の融合にあります。ビジネススクールの目的は「本物のマネジャー」を育成することですから、実務にどう応用できるかという「how の問い」を大切にします。同時に、皆さんが学ぶのは「大学」ですから、なぜそのような現象が起きるのかという「why の問い」も大切にします。当モジュールでは、ビジネスにおける「実践」に立脚しつつ、キャンパスの中心にある大隈銅像の間近で「学問」をする意味も問い続けながら「専門職学位論文」を仕上げていきます。
モジュールの参加者は「コア科目」「モジュール専門科目」および「選択科目」を通じて、思考の枠組を獲得していきます。同時に、活発な議論を通して実際のビジネス活動の場で、いかに活用し、効果的な人材・組織マネジメントにつなげるかについての知識の使い方を習得します。また、専門職学位論文の執筆を通じてそれぞれのメンバーが抱える問題意識に沿った個別のテーマについての調査・分析を行い、結晶化していきます。
このモジュールにおいて専門職学位論文を書くとは 1自分の問題意識を明確にし 2先達の知恵を借りて足元を固め 3自ら調べ 4調査結果について考察し 5実務的応用可能性を考える ということです。この仕事にもそのまま活かせるプロセスを通じて、現実の企業活動の中で問題を発見・分析・解決する総合的な能力を養うことが、当モジュールの主たる目的です。
同時にモジュール参加者は、ゼミ活動を通じて縦横にネットワークを広げていくことができ、そこに大きな価値の源泉があります。ゼミは「兄弟ゼミ」と位置づけられる「総合の人材ゼミ」や「親戚ゼミ」と位置づけられる留学生を中心とする全日制グローバルのゼミを通して横に広がります。またOB/OG とのネットワークを通して縦に広がっていき、また修了後も継続し発展していきます。ゼミを核として早稲田で「結び・拡げる」経験を楽しんでほしいと心から願っています。
豊富な人的資源を相互に結びつけることによって価値を創出することは、「人材マネジメント」の実践でもあります。「プロの人材ゼミ」では、これをむしろ自らのミッションのひとつと考え、質の高いネットワーキングを促進するための様々な機会を用意していきます。
2.内容
■ モジュール専門科目
夜間主プロフェッショナルにおいては、「モジュール専門科目」として用意される科目群から3科目以上を履修することが義務付けられています。期待を裏切らない関連科目を取り揃えていますので、5科目程度は受講してほしいと思っています。
モジュール専門科目においては、戦略的人的資源マネジメントやビジネス・リーダーシップなどが広く学べる構成としています。それらに加えて、2011年度に開始した枝川義邦先生による「経営と脳科学」は他のモジュール生にも人気の高い授業となっています。2012年度からはスターバックス・ジャパン前CEO の岩田松雄先生等との共同授業、2013 年度からは谷益美先生による「ビジネス・コーチング」もスタートしました。
それぞれの科目を通して、人事制度・組織構造などのハード面と、組織文化・経営スタイル・リーダーシップ・創造性などのソフト面の双方からアプローチし、理論的フレームワークと生きた実例の双方について、理解を深めてほしいと願っています。私自身は、ゼミ・コア科目・選択科目を担当します。いずれの授業においても「参加型・巻き込み型」を心がけていますが、同様の方針の授業が多いことが当モジュールの特徴です。
双方向型の授業においては、討議や演習を含めた多様な教育形式を通じてクラス参加者が既に蓄積してきた知をアクティブなクラス討議の場を通じて共有し、相互に新たな視点を提示しあうことが重視されます。皆さん自身が「生きたコンテンツ」なのです。また、ケースメソッド・事例研究・アクションラーニング・ゲストの招聘など、現実に即応した学習方法を積極的に取り入れる授業が多いのも特徴です。授業やゼミのレギュラーのゲストとしては、指揮者の桜井優徳先生を定期的に招聘しています。これにアカデミックな「理論」を中心とするアプローチの講義を組み合わせることで、自ら課題設定し、分析し、意思決定し、実行するための総合力を養って頂きたいと思っています。
授業においては、学習効果を最大化するために、自己の問題意識を明確に持って発言・行動すること、参加者間の主体的交流のプロセスから相互に学びあうことを最も重視します。そして、クラスという組織を共に創っていくことがより高い次元の「メタ学び」だと思っています。
■ 演習(ゼミ)
モジュールの核となるのがゼミ(演習)です。プロフェッショナル・プログラムのゼミは土曜日に行われます。
ゼミは、色々な顔を持っています。学びの場であることは言うまでもありませんが、同時にゼミ生が学生生活を充実させて行く上でのホーム・グラウンドであるとも位置づけられます。ゼミはWBS ネットワークの中心となります。このような同心円的広がりを「縁リッチメント」とゼミ内では呼んでいます。
ゼミの場では、人的資源マネジメント論や組織行動論を中心に討議すると共に、リーダーシップ、モチベーション、クリエイティビティーなど、「ひと」に関わる共通テーマを設けて掘り下げていきます。標準的な進め方は下記の通りです(Mはマスターの略でM1は1年目、M2は2年目です)。
| M1春学期: | まず人材ゼミ内のノウハウを集約した「てびき」をもとに「専門職学位論文とはなにか」についての認識を揃えます。並行して、既に論文執筆に入っている先輩(M2)の発表を聞きます。これらをもとにして、春学期の中盤以後には自らの問題意識を整理していきます。 |
| M1秋学期: | 同期生の問題意識を共有しあい、論文執筆に向けての地盤固めをしていきます。このゼミをご支援いただいているゲストをお呼びすることもあります。教科書を参考に発表・討議することもあります。 |
| M2春学期: | 新しく入ってくる新M1に対して先輩として発表を行いつつ、業界調査や理論のパート、先行研究などについてのドラフトを書き始めます。質問票を配布したりインタビューを行ったりする場合には、質問項目を考えていきます。 |
| M2秋学期: | いよいよ論文の執筆です。分析と考察を行い、毎年11月11日までにドラフトを作成し、12月12日までには最終形に近づくようにしています。正月明けに正式な提出となります。その後主査(モジュール担当)と2名の副査(うち1名は例年大滝令嗣先生にお願いしています)による口述試験が行われています。 |
■ 縁リッチメントと学習する組織の実現
当モジュールのゼミは、夜間主総合プログラムおよび全日制グローバルプログラムにおける人材・組織マネジメントゼミと強固なアライアンス関係を持っています。ゼミは修了後も継続するネットワーキングの強固な地盤となることから、縦横にネットワークを広げていくことができるのですが、これをわたしたちは「縁リッチメント」と呼んでいます(enrichment のもじりです。)ゼミ合宿においては、「学び」と「楽しみ」の双方の活動を集中的に行います。ゼミ合宿の場所は国内が多いですが、人材ゼミはその源流を全日制に持ち世界12 カ国に修了生ネットワークがありますので、それを活用することも可能です。
毎年1月末には、修了予定者の論文提出とプロの新入生と総合の人材ゼミの内定者の参加を祝い、OB/OGも参加する大規模な「冬の納会」が行われます。そのため、プロフェッショナル・プログラムの新入生は入学前には既に相互に親しい関係となっています。夏には現役生を中心とする「夏の納会」が行われます。そのほか学生が主体となる活動は頻繁に行われています。
ゼミの運営は持ち回りのリーダーシップによって行われます。このゼミ自体を、全員参加によって「学びの共同体」を創り「学習する組織」を体現していくのが人材ゼミ全体としての目的です。
3.対象とする学生
このモジュールは広く「ひと」と「組織」に関わる問題意識を持つ方、人材・組織マネジメントの方面にキャリアを展開して行きたい方、あるいは戦略・マーケティング・ファイナンス・R&Dなどの分野を「人材・組織」の観点から究めたいひとにとって有用なコースとして設計しています。ですから、修了生および現役学生(人材ゼミ全体で合計66名:設立5年目)のバックグラウンドは人事・人材開発関連の経験者と未経験者でほぼ半々となっており、営業やR&Dの経験者の比率は意外と高くなっています。業種については、製造業・サービス業からプロフェッショナルファームまで多岐にわたります。
■ ダイバーシティー
このモジュールには、2010 年度に設立されて4 年で合計34 名の「学習者精神」溢れるメンバーが参加してきました。上述したとおり、ビジネス経験としては人事関連部門での直接的な経験を持つ方と、企画・営業・技術・国際・R&Dなどの領域において「ひと」と「組織」に対して問題意識を持つ方のバランスが取れていることが理想であると考えています。また、より広く、実際にチームや組織を率いるために当該分野での見識を深めたいひとも対象としています。
指導教員である私自身は、早稲田での教職(9年)の前に、製造業での企画/ マーケティング(9年)、コンサルティングファームでの戦略/ 人事(4年)、外資系金融機関の人事/ 法人営業(9年)の実務経験を有するため、比較的広い分野に土地勘や人的ネットワークを持っています。
■ 共通点とゼミ文化
それらのダイバーシティーに対して、共通性の高い点もあります。それは、穏やかで和やかな「人材ゼミ生」独特のパーソナリティーです。WBS 学校説明会(夏・秋)に来ていただけると、1年生のほぼ全員と会っていただけますから、その独特のゼミの雰囲気を実感してもらえると思います。科目の特性も反映していると思うのですが、それが人材ゼミの「ゼミ文化」を形成しています。後輩を迎えるにあたっても最初からホスピタリティー全開のゼミ生が多いのが特徴です。(どのゼミもそうだと思いますが少なくとも人材ゼミは間違いなくそうです。)同時に「いいたいことはちゃんと言う」というアサーティブネスを備えています。
過去の実績については、性別については、男性約5 割・女性約5 割、人事の経験の有無については有りが約5割・無しが約5割とバランスよく拮抗しています。理想的なバランスをとっています。大学での専攻については文系約7 割・理系約3 割、是非今後ともこの「理想的ポートフォリオ」を継続していきたいと考えています。
全日制の大滝令嗣教授には副査の立場でご指導いただき、「親戚ゼミ」の大滝ゼミから主として日本語も理解するバイリンガルの留学生が常時参加し、国際的な色彩を添えています。そのため、異文化を理解したい気持ちがあるとさらにこのゼミを楽しめると思います。
4.二つの人材ゼミ
前述のとおり、夜間主総合プログラムの「戦略的人材マネジメント(2年次のみ)」とは「兄弟ゼミ」の関係となりますが、その違いは次の通りです。
■ 夜間主プロフェッショナルの「人材・組織マネジメント」(略称:「プロの人材ゼミ」)
ゼミは2年間あり、入試の時点で決定しています。ですから、入学が決定する年明けにはウェルカム・イベントにご招待します。そして2年間ゼミを満喫することになります。コア科目の比重は相対的に小さく、その分モジュール専門科目や選択科目を多く履修することが可能です(もちろんその枠でコア科目を履修しても構いません)。専門性と視野の広さを兼ね備えた人材を「T型人材」と表現することがありますが「相対的に縦棒が長いT」といえます。特にこの領域に興味の焦点が絞られていて、入学前にゼミを確定し、2年間ゼミ活動を行いたい方はこちらがより適性があると思います。専門職学位論文は2年間をかけて書き上げますから、先行研究や独自の調査も踏まえていきます。WBS フェアの説明会などでは、先輩たちとじっくり話ができる機会をもうけます。彼ら彼女らのなるほど人材ゼミ!と思える、知性+優しさ+アサーティブネスの程よいブレンド具合を実感してほしいと思います。
■ 夜間主総合プログラムの「戦略的人材マネジメント」(略称:「総合の人材ゼミ」)
ゼミは1年間で、ゼミは入学後に時間をかけて決定します。春学期の「プレゼミ」を通してゼミ担当の指導教員(私を含む)の話をそれぞれオムニバス形式でじっくり聞いたあとで自分の問題意識に適合するゼミを選択します。コア科目の比重が高いのが特徴で、「相対的に横棒の長いT」といえます。M2で書く「プロジェクト研究論文(略称PP)」は、専門職学位論文と比較すると枚数は少なく、より実務上の問題意識に軸足を置いたものです。現段階では分野を決めきることができず、入学後にゼミ選択の自由度を担保しておきたい方には、こちらのほうがよりフィットがあると思います。
5.ゼミの運営原則とホームページ/フェイスブックのご紹介
最後に、人材ゼミの5つの運営原則を紹介します。
- 「学びを、楽しむ。(Enjoy learning)」
人材ゼミでは「楽しみつつ学ぶ」ことを何よりも大切にしています。いつも笑いの絶えないゼミにしていきたいと考えています。 - 「リーダーシップを、共有する。(Share leadership)」
人材ゼミでは、それぞれのメンバーが持ちまわりでリーダーシップを発揮していきます。参加者のアイディアやイニシアティブが最も尊重されます。 - 「理論も実践も、追求する。(Seek both theories and practices)」
人材ゼミでは、学術的・理論的なアプローチとビジネスの現場における応用可能性の両方に価値を置き、同時に目指していきます。 - 「超えて、繋げる。(Bridge, span and connect)」
人材ゼミでは、あらゆる壁を越え、異質のものをつなげ、ネットワークを拡げていきます。学問の壁を越えて広く知を吸収し、連携するゼミと積極的に交流します。 - 「未来を、創る。(Create the future)」
私たちは、過去と現在に学ぶと共に、自ら未来を創っていく主体(=己)でありたいと希求しています。志は熱いが、「熱血」ではなく、むしろ穏やかで、相互の気遣いと支援を第一とする ―それが、人材ゼミのカルチャーです。そのようなゼミのありかたにフィットを感じる方にとっては、このモジュールで学ぶと早稲田の価値やWBSの価値が更に増すのではないかと思います。
「人材ゼミ」の略称は私が名づけたものではありません。自然に学生たちにそう呼ばれるようになったものです。そのことを、私は本当に誇らしく思っています。もしこのモジュールの先輩たちが「人材」と認識されていなければ、そんな風に言われることはなかったはずだと思うからです。
6.参考情報
人材ゼミは、「人材の、人材による、人材のためのモジュール」となりたいと思っています。「人材ゼミの人材」として一緒に創り上げていききたいと思われる方は、是非応募を検討してみてください。より具体的な情報については、下記をご参照ください。
- 人材ゼミのホームページ:www.jinzai-zemi.jp モジュール全般についての詳細な情報を掲載しています。
- 人材ゼミのフェイスブック(www.facebook.com/WBS.jinzai):最新の活動と「息吹」をご案内しています。
- ゼミ紹介の小冊子
- WBS フェアの資料
7.モジュール専門科目
- 戦略的人材組織マネジメント
- グローバル人事管理
- 人的資源マネジメントの国際比較分析
- ビジネス・リーダーシップ
- ビジネスコーチング
- 経営と脳科学
- ミッション経営と人的資源マネジメント






