- その他
- MOT:イノベーションと価値創造戦略担当教員:長内 厚准教授
MOT:イノベーションと価値創造戦略
担当教員:長内 厚准教授
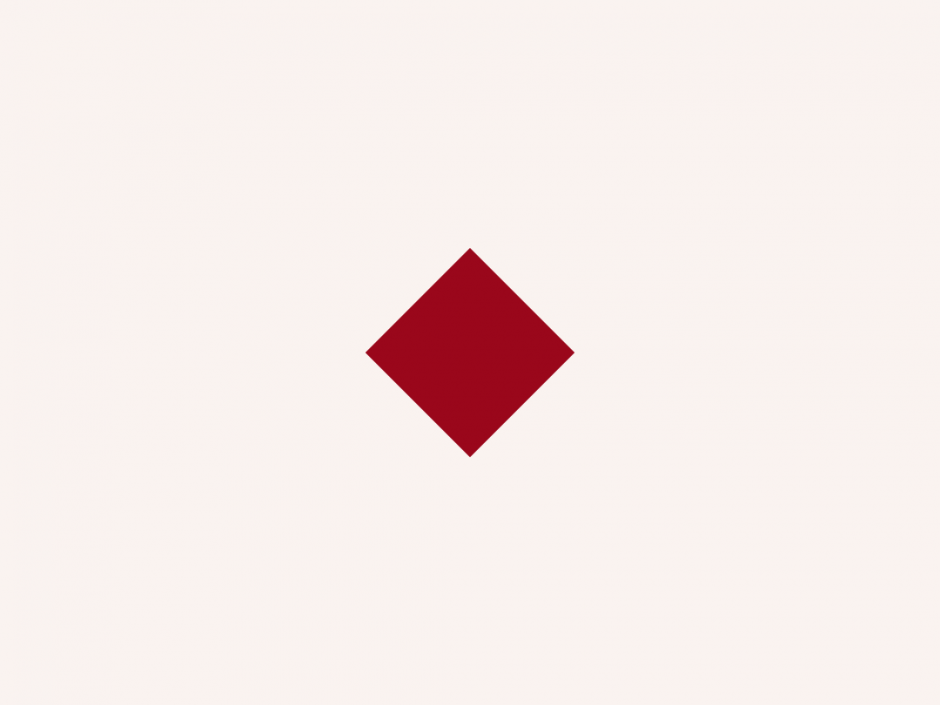
- Posted
- 2015年2月19日(木)
MOT:イノベーションと価値創造戦略
担当教員:長内 厚准教授
内容
当ゼミでは、(A)「技術がどのような価値を生み出し、企業に収益をもたらしているのかについて戦略論・組織論をベースに研究する」というテーマのもとで、(B)ケーススタディなどの定性的な研究法と論文執筆のテクニックを学び、研究成果をプロジェクト研究論文としてまとめあげるための研究と論文執筆の指導を行う。
このテーマの前提にあるのは、技術的な成果は必ずしも事業成果に結びつかない、という認識である。新しい技術は企業の競争優位の源泉となるものであるが、企業が事業としての成功を収めるためには、技術を応用した製品・サービスが顧客にとって価値のあるものであること(価値創造)と、創造した価値に見合うだけの見返り(収益)を企業が得られること(価値獲得)が必要となる。例えばDVD を例に考えてみると、レンタルビデオ店のVHSカセットがDVD ソフトに駆逐されたことで明らかなように、多くの消費者がDVD に価値を見いだし、日常的に利用している。しかし、DVD プレーヤーの価格は、登場以来十余年で10 分の1 以下になり、開発を主導してきた日本の家電メーカー各社は、激しい価値競争の末、早々に市場から撤退を余儀なくされている。「価値創造可能だということ」イコール「価値獲得可能である」、とは言えないのである。
また、新たな製品の価値が「より高速処理ができるPC」、「より低燃費な車」といった機能的・性能的な価値であれば、技術的な成果は顧客価値向上に結びつきやすい。しかし、デザインや操作感といった、その製品固有の所有欲をくすぐる個性が顧客の評価の決め手になるような場合、機能的・性能的進化(単なるスペック向上)は顧客価値の向上にはつながらない。iPod より音質がよく連続再生が長いと言われるウォークマンがiPod に勝てない理由もこのあたりにあると考えられる。新たな価値をどのように定義し、そこに技術がどのように介在するのか、これらを考えることが、当ゼミの大きな課題である。
上記の例ではエレクトロニクス産業を取り上げて説明をしたが、当ゼミは、方法論オリエンテッドに行うので、扱うテーマ(研究対象)は受講者自身の希望や自身の業務との関連などで自由に選んでいただきたい(例:IT、自動車、産業材、食品、アパレル、出版、サービスなど)。
次に、(B)の研究成果をまとめ上げる方法についてであるが、企業活動の現場で起こる事象は様々な環境条件の違いに左右される複雑な因果関係の連鎖であるので、専門職学位課程の院生諸氏には、企業の内部に入り込んでいるメリットを最大限活用して、「そこにどのような複雑な因果関係が存在しているのか」をつぶさに観察してもらうことを期待している。また、面白い研究計画は、料理にたとえれば上質な食材であり、どんな高級食材でも調理が下手だとおいしい料理にはならない。優れた研究成果を論文という形でまとめ上げるためには、理路整然とした論理構成を考え、それを読み手に誤解を与えないよう読みやすく論述することが必要である。「良い論文」を書くスキルを身につけることもこのゼミで学習するもう一つの目標である。
※具体的なゼミの授業計画については変更の可能性があるので、上記内容は大まかな方針とご理解いただきたい。






