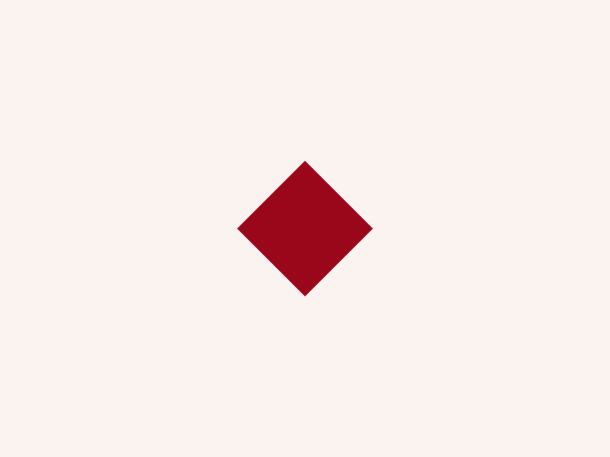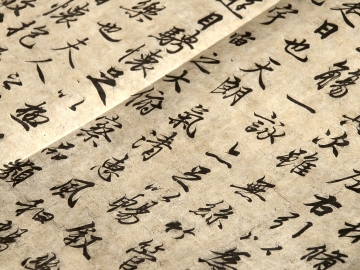研究キーワード
研究概要
日本宗教文化研究所は、2006年に設立された。本研究所の設立企図は、津田左右吉以来、早稲田大学が育んできた日本宗教文化の研究を、いっそう充実発展させ、さらには国際的に展開・発信することにある。日本の宗教文化を多面的に発信するために、従来積み重ねた信用の蓄積を生かすことが最適と考える。
日本宗教文化にはさまざまな分野があるが、本研究所では研究員の専門性を鑑み、前近代、特に日本古代・中世における宗教文化全般の研究を目的とする。浄土教思想・南都仏教・平安仏教・聖徳太子信仰・中世神道・本地垂迹説・寺社縁起・唱導文化・葬送文化・聖地巡礼・知識人の信仰・敦煌学・美術史学・中国思想・比較宗教研究などを、重点的に追求するとともに、広い視野による学際的研究を目指している。
本研究所は、2006年以来中国浙江省杭州市浙江工商大学東亜研究院(もと日本文化研究所、江静院長)と学術協定を締結し、毎年1~2回の国際シンポジウムを開催した。2012年度より、韓国蔚山広域市蔚山大学校人文大学日本語日本学科(洪聖牧学科長)がこれに加わり、三機関持ち回りで「東アジア文化交流」と題し、副題は各研究機関が決定する国際シンポジウムを開催している。今後5年間も、これを継続することを合意しており、引き続き海外に成果を発信し続けていきたい。
本研究所は、前近代の日本宗教思想研究に特化しているが、学内研究員は、仏教学・中国古典学・美術史学・日本文学・日本思想史などの専門を持っている。それぞれの立場から個別の研究を深化していくと同時に、多彩な専門を持つ招聘研究員、あるいは国内外の研究者との共同研究によって、さらに広い視野による学際的な日本宗教文化研究を目指したい。
特に以下の研究項目を重点的に研究する。
- 聖徳太子信仰の研究、特に太子伝の代表作『聖徳太子伝暦』の校訂・註釈作成
- 南都仏教の研究
- 浄土教思想・平安仏教の研究
- 天神信仰の研究
- 中世神道の研究
- 本地垂迹説の発生と展開に関する研究
- 善光寺信仰の研究
- 伊勢信仰・八幡信仰・熊野信仰等、神社信仰の研究
- 古典籍註釈の研究
- 寺社縁起の研究
- 大江匡房の思想研究
- 中国宗教文化と日本宗教文化の比較研究
- 中国美術と日本美術との比較研究
- 敦煌学と日本宗教の関係研究