- ニュース
- 中村 民雄教授が『EU法の参照可能性』を上梓しました
中村 民雄教授が『EU法の参照可能性』を上梓しました
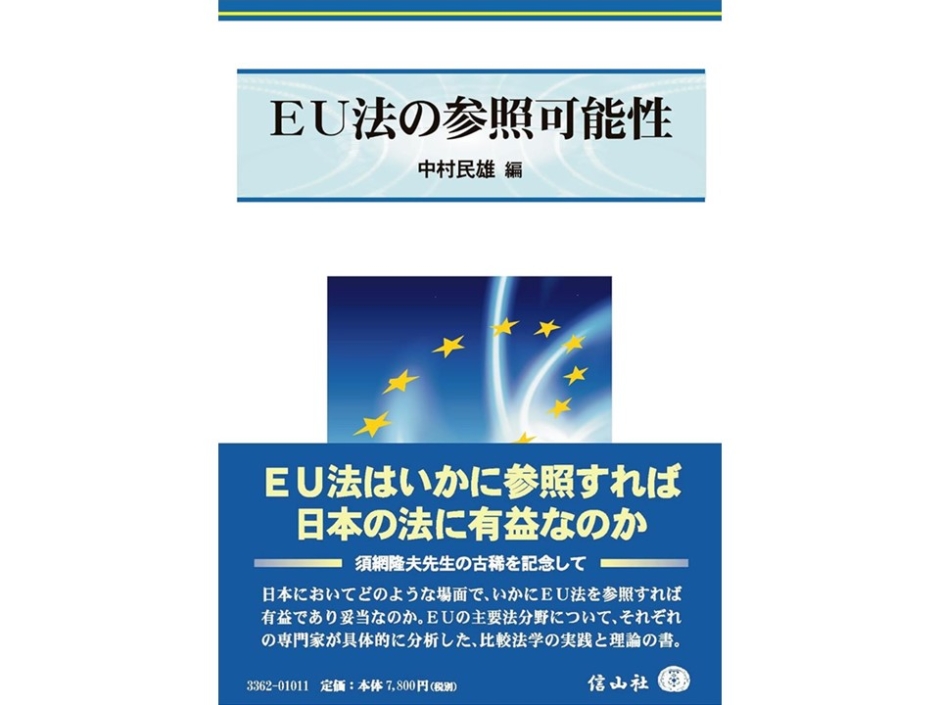
- Posted
- Thu, 03 Jul 2025
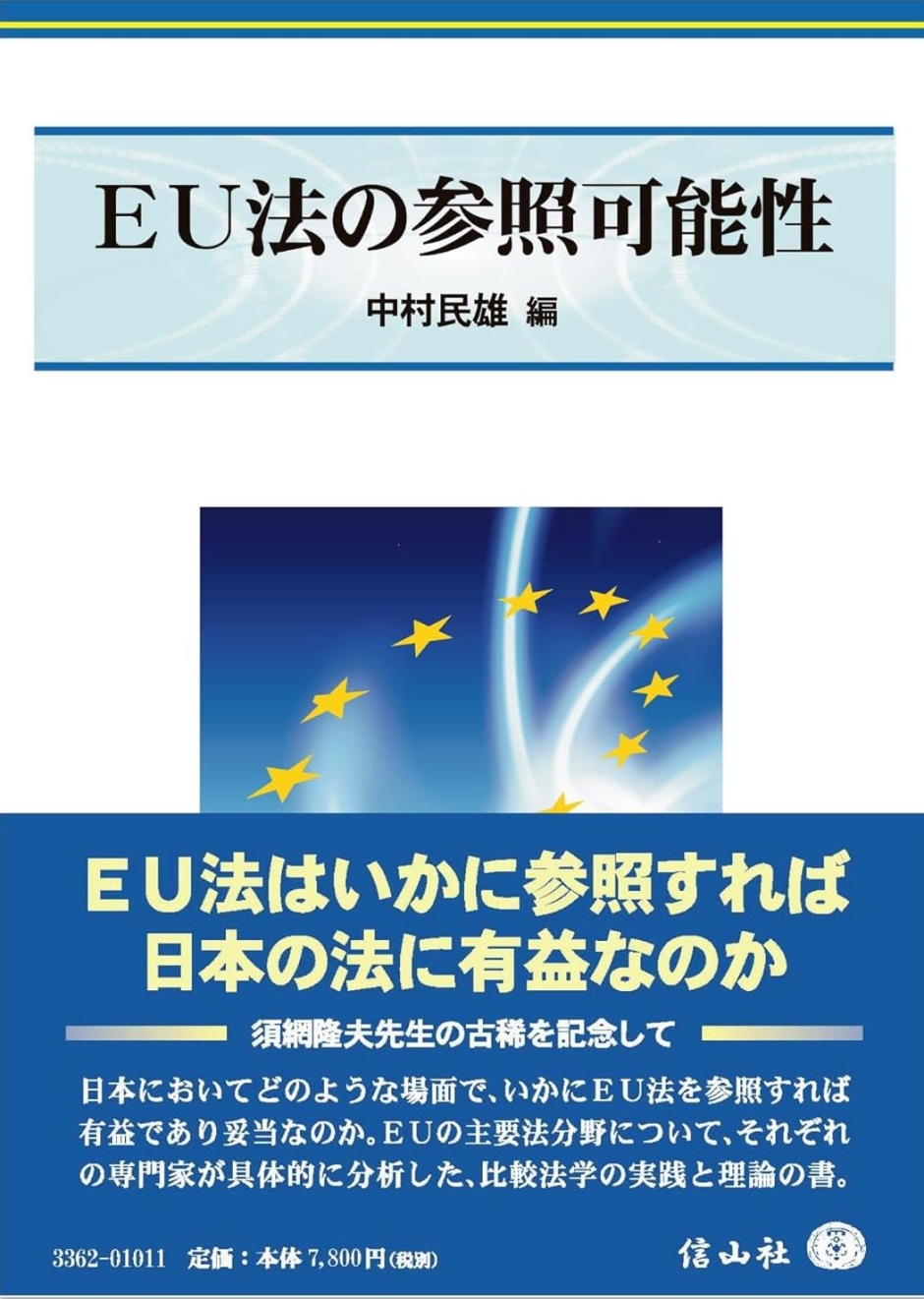
中村 民雄教授の編著『EU法の参照可能性』が2025年6月に信山社より刊行されました。
【著者】 中村 民雄
【出版社】 信山社
【出版年月】 2025年6月
【ISBN】 9784797233629
*出版社のリンク:EU法の参照可能性/中村民雄編/信山社
中村 民雄教授による紹介文
この本は、日本にある我々が、外国の法の一つであるEU法を日本での立法や法解釈において参照して役立つことになるのか、もしなるとして、どのように参照すれば役立つのかを考える本です。
法学部や大学院法学研究科では、外国法(英米法など)と並んで、EU法に関する講義も提供されています。これはいったいなぜでしょうか?我々の国際取引の相手がいる国や場所の法だからでしょうか?それもあるでしょう。しかし大学ではそんな実践的な細かい外国法までは教えません。
だとすると何が目的なのでしょう。よく世間では「人の振り見て我が振り直せ」といいます。法学も同様です。同じような課題を抱えた外国の社会は、どう法的にそれに対応しているのかを知ることで、日本の現在の法的対応の特徴や限界や問題点に気づけます。そのことを学ぶために提供されているのです。これを比較法による法批判の視座といいます。日本の現在の法がつねに正解であり万全であるというのは、あまりに思い上がった考えです。我々はつねに謙虚かつ建設的ながら批判的に、今の法でいいのだろうか?と検証しつづけなければならないのです。そのような作業の入門として、大学の講義では外国法の講義があります。
さて、この本はそうした比較法による法批判の視座を、EU法はほんとうに提供してくれるだろうか?してくれるとしても、EU法固有の特徴をきちんと理解して参照しなければ、思わぬ落とし穴にはまりはしないだろうか?という問いを発します。これがこの本の序章です。というのもEUはふつうの外国の国家の法とは違うからです。EUというのは国家ではないが、ヨーロッパ27カ国に共通する、連邦的な共同統治体という特殊な存在です(→その点は拙著『EUとは何か(第4版)』を参照してください)。その固有の特徴をきちんと理解してEUが作り出す法を参照しなければならない場面があることでしょう。だからこそ、EU法については、ふつうの外国法の参照よりもさらに気をつけなければならないでしょう。これが先の「思わぬ落とし穴」があるのではないか、という問いの真意です。
さて本書の冒頭で示された問いを共有した様々の法分野の専門家たちが、本書では、それぞれの分野でのEU法の参照可能性について論じていきます。具体的には、個人情報保護法、スマホソフトウェア競争促進法、労働法、入管法、国際裁判管轄に関する法、憲法、刑事手続法、国家補助規制、性差別規制、会社法とジェンダーバランス、難民認定、国際法の要請をうけた個人に対する制裁措置など、具体的な法的論点や課題について、各著者が考察を進めます。それがこの本の第1部(主に立法の場面での参照)と第2部(主に法解釈の場面での参照)の全部で12の章です。
最後に私は編者としてそれらの各論的考察を総論的にまとめて、最初の問い、参照可能性はあるのか?どう参照すれば有益に参照できることになるのだろうか?に対する暫定的な答えをだしています。それがこの本の結章となっています。
皆さんも、EUの振り見て日本の振り直せ、ができるのか、どうすればできるのか、どこまでできるのかを本書のどの章でもいいですからつまみ読みしてみて、考えてみませんか。
- Tags
- 出版 研究活動 Publications Research
