- ニュース
- 大場浩之教授が「物権債権峻別論批判」、「物権法」を上梓しました
大場浩之教授が「物権債権峻別論批判」、「物権法」を上梓しました
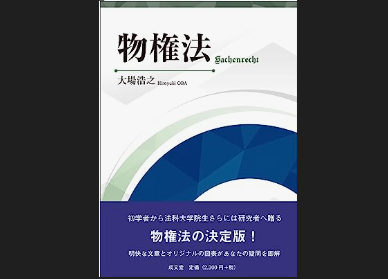
- Posted
- 2023年7月12日(水)
大場浩之教授著の「物権債権峻別論批判」が2023年2月に、また、「物権法」が2023年7月に刊行されました。以下、大場教授より内容の紹介です。
「物権債権峻別論批判」
【出版社】成文堂 出版社WEBサイト
【出版年月】2023年2月
【ISBN】978-4-7923-2793-4
【内容説明】
 物権とはなにか。債権とはなにか。物権と債権を分けるメルクマールはなにか。この問いは民法学における古典的なテーマです。一般的には、物権の性質は直接性・絶対性・排他性にあり、債権は間接性・相対性・非排他性にある、といわれてきました。しかし、この違いはあくまで判断の目安にすぎず、決定的な基準となるものではありません。
物権とはなにか。債権とはなにか。物権と債権を分けるメルクマールはなにか。この問いは民法学における古典的なテーマです。一般的には、物権の性質は直接性・絶対性・排他性にあり、債権は間接性・相対性・非排他性にある、といわれてきました。しかし、この違いはあくまで判断の目安にすぎず、決定的な基準となるものではありません。
私は、これまで、『不動産公示制度論』(成文堂・2010)と『物権変動の法的構造』(成文堂・2019)の2冊の研究書を公表してきました。いずれも、本書と同じく、比較法としてドイツ法を研究対象としたものです。また、この間、共訳書である『ドイツ物権法』(成文堂・2016)も刊行しました。
『不動産公示制度論』においては、不動産登記制度の歴史・土地債務と登記の公信力・仮登記と不動産物権変動論について論じ、登記に公信力を認めるべきとの立法論を示すとともに、不動産所有権移転にあたって意思表示の必要性を前提としつつもその効力発生時を原則として登記時と解すべき、との民法176条の解釈論を提示しました。
『物権変動の法的構造』においては、物権行為・ius ad rem(物への権利)・両概念の関係性について論じ、物権行為の独自性を肯定するとともに、二重譲渡における背信的悪意者性を判断するにあたって物権行為の成立をその判断基準として用いるべきこと、また、ius ad remの法的性質を明確化するとともに、各権利とius ad remの関係性を明らかにしました。
本書も、これら研究成果をうけたものにほかなりません。これまでの研究において、私が一貫して念頭においていたテーマは、物権債権峻別論とそれに対する批判について、でした。そこで、本書において、正面から物権債権峻別論を批判的に検討することを目的としつつ、その理論的支柱であるドイツ法における物権債権峻別論を分析することにしました。したがって、本書は、私がこれまで行ってきたライフワークとしての研究の集大成を示すものであり、研究生活に入った大学院生の頃から描いていた研究計画が、この3部作をもって完結することになります。
物権と債権は、所与の概念ではありません。このため、物権と債権の区別もまた、絶対視される考え方ではありません。本書における私の主張は、物権債権峻別論を所与の前提としてではなく、それを批判的に検討することによって、物権債権峻別論の必要性に疑問を投げかけること自体にあります。その上で、物権と債権の概念を維持するのであれば、それぞれの法的性質をより明確な内容とし、両者の狭間にある諸概念については、それらがなぜ物権にも債権にもカテゴライズできないのかを明らかにすることが重要である、と私は考えます。
あらゆる法分野において立法活動が盛んになっている今日において、皆さんも一緒にこの古典的かつ現代的なテーマについて考えてみませんか。
「物権法」
【出版社】成文堂 出版社WEBサイト
【出版年月】2023年7月
【ISBN】978-4-7923-2798-9
【内容説明】
 本書は、物権法の教科書でもあり、体系書でもあります。また、民法の学修にあたっての入門書として利用することもできるよう、工夫しました。このため、論じるべき内容を厳選しつつも重複をいとわず、文章をできる限り平易なものとし、図表も大きめに作成して多用しました。また、余白もあえて広めにとっています。いずれも、読者の理解を助けるため、民法・物権法に関心をもってもらうためです。
本書は、物権法の教科書でもあり、体系書でもあります。また、民法の学修にあたっての入門書として利用することもできるよう、工夫しました。このため、論じるべき内容を厳選しつつも重複をいとわず、文章をできる限り平易なものとし、図表も大きめに作成して多用しました。また、余白もあえて広めにとっています。いずれも、読者の理解を助けるため、民法・物権法に関心をもってもらうためです。
本書の対象範囲は、民法典第二編の第一章から第六章までです。したがって、本書は物権法を対象としつつも、その範囲は担保物権法と称される領域を除いた部分ということになります。本書の対象となる物権法の分野のことを、物権法総論と呼ぶこともあります。物権法総論と担保物権法は、いずれも物権編に属する領域ではありますが、その理論や実務における位置づけは、大きく異なっています。また、私自身は民法学の研究者として、比較法としてドイツ法を用いつつ、これまで主として物権法総論の分野を考究してきました。このため、私自身の単著としての教科書・体系書である本書においては、物権法総論に的を絞って講述することにしました。
物権とは、物を対象とする権利です。このことを前提として、物権法においては、財産の帰属および支配に関する一般的な規範が整序されています。その中で理論的にも実務的にも重要なのが、物権種類論・物権効力論・物権変動論と称される問題群です。そこで、本書においては、これら3つのカテゴリーに大きく分けて議論を展開しています。この分析スタイルは、類書にほとんどみられない本書の際立った特徴と考えています。この点において、本書は、物権法に関する標準的な教科書であるとともに、私の物権法に関する体系書ともいえるでしょう。このため、各論点によっては、判例や通説とは異なる私見を提示している部分もあります。
読者の皆さんには、まずもって判例や通説をきちんと理解してほしいと思います。しかし、それだけでは、学問とはいえません。私見の部分を読むことを通じて、判例や通説とは異なる見解の存在とその意義を学ぶとともに、学問上の刺激を受けてほしいと願っています。
また、大学における大人数講義は、受講者の予習を前提とした上で行われています。予習の有無によって、教場での理解度には大きな差が出てくるでしょう。そこでの充実度もまた、前提知識の多寡によって大きく左右されると思います。受講生の皆さんにとっても教員にとっても講義の場で有意義な時間を過ごすことができるようにするため、受講生の皆さんには予習を行った上で講義に出席することを強く勧めます。本書は、そのような講義の予習用にも使用されることを想定しています。もちろん、独習書としても大いに活用してほしいと思います。これにより、司法試験などの各種試験の対策としても利用することができるでしょう。
物権法はとても面白い学問分野だと思います。私も読者の皆さんと一緒に引き続き考究を深めていければ、と期待しています。
- Tags
- 出版 研究活動 Publications Research
