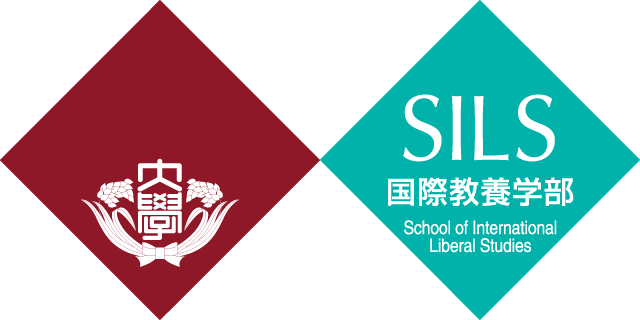- ニュース
- 【卒業生インタビュー】高橋 郁也さん:取材を通して感じたSILSの多様性
【卒業生インタビュー】高橋 郁也さん:取材を通して感じたSILSの多様性

- Posted
- Fri, 07 Mar 2025

- 向上高等学校 2011年3月卒業
- 早稲田大学国際教養学部 2016年9月卒業
― 現在の仕事について教えてください。
私は今、雑誌や書籍、コミックなどを手がける総合出版社「株式会社 文藝春秋」で勤務しています。昨年末、自社の持つブランド力やコンテンツをフル活用した動画編集部が立ち上がりました。私は立ち上げメンバーとしてスタートから編集部に加わり、動画番組の企画立案から、司会進行まで業務として取り組んでいます。
人に話を聞き、体裁を整えて世の中に発信するという意味で、紙媒体と動画番組の作り方は似ていますが、最近感じるのは、「書かれた言葉」と「話された言葉」の違いです。雑誌や書籍を編集する際、言葉は紙に印刷されて残ることから、校閲を重ねて事実関係や誤字脱字はもちろん、言葉の用法まで細かくチェックした上で校了し、書店に置かれます。一方、話された言葉はすぐに霧散するので、仮に間違ったことを言っても人は会話に集中してしまい、結果的に誤りはなんとなく正されないまま話が終わってしまうことが多い気がします。番組としての面白さを維持しつつ、いかに正確な情報を提示できるか、という点に苦心する日々です。
― 今にして思う、SILSの魅力、強みについて教えてください。
私は学生時代、英語があまり得意ではありませんでした。カリキュラムとして必修の海外留学も病気により断念し、挙句留年。ようやく卒業し、一年半の空白期間を経て就職したものの、先輩たちに「出身は早稲田の国際教養学部です。ただし留学はしていません」と自己紹介することに気後れする日々でした。
自分にとって転機となったのは昨年のこと。稲葉学部長にインタビューする機会に恵まれました。恐る恐るOBであること、留学しなかったことを伝えると「全然いいじゃないですか!」と一笑に付してくださったのです。そして、先生ご自身も、学生時代は実は英語が苦手だったということを堂々と語ってくださいました。
もちろん、先生がその後努力されて英語を修められたことは疑いようもないですが、そんな方が学部長を務めているということ自体が、SILSの多様性と、懐の深さを何より物語っているのではないでしょうか。
受験生の皆さんは、おそらく英語を流暢に話し、社会に求められる人材になること、あるいは国外で活躍することを希望してSILSの門を叩くのだと思います。ただ、そうしたイメージや“あるべき理想“とは裏腹に、まったく予想だにしなかった世界に飛び込む可能性もあります。繰り返しになりますが、SILSの懐は想像以上に深いのです。
― SILSでの学びと現在の職業の関係性、役立っていることを教えてください。
SILSにいた当時を振り返ってみると、望めばあらゆる情報にアクセス可能で、かつ自らの学びを突き詰めることができる点で恵まれていました。リベラルアーツを謳うSILSでは、あらゆる領域の講義を受けることができます。「大学に入って何をしたらいいのか……」と迷ったとしても、必ず自分の興味に合う分野が見つかるはずです。
仕事では、どんな人・モノ・コトが注目されているのかを念頭に置いて取り組んでいます。学生時代にSILSで多様な学びのあり方を知ったことが、知的好奇心を絶やさずにアンテナを高く張り、時流を捉える力になっていると感じます。
― 受験生に向けてメッセージをお願いします!
SILSの講義は非常に双方向的で、学生同士のディスカッションやプレゼンも多いです。もしここに来ることになったとしたら、教授や学友とのやりとりでふと感じた違和感を大切にしてほしいです。そうした違和感に向き合うことから、新たな学びが生まれてくるのだと思います。受験生の皆さんにも、そんな知的好奇心をかき立てられるSILSの文化を体験してほしいです!
※掲載情報は、取材時点のものになります。