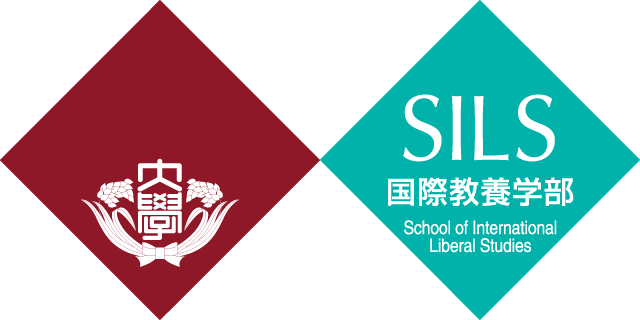- ニュース
- 授業紹介:First Year Seminar A 65
授業紹介:First Year Seminar A 65

- Posted
- Tue, 25 Apr 2023
 |
||||
|---|---|---|---|---|
上杉 勇司
|
||||
| First Year Seminar(FYS)では、大学1年生が早稲田大学国際教養学部での学びを深めることを達成目標にしています。FYSでは、私の専門である「平和」と「紛争」を題材に用いながらも、学生たちが仲間とともに切磋琢磨する環境づくりを心がけています。
学生たちには、私の提供する知識や見解は、あくまでも一つの見方でしかないので、本当に鵜呑みにしていいのか、常に疑問をもって聞くようにお願いしています(批判的思考)。同時に、他人の意見や疑問に耳を傾けるように勧めています(複眼的思考)。自分とは異なる見解や自分が思ってもいなかった考えに接することは、私たちの世界観を豊かにしてくれるでしょう。異なる意見を論破するのではなく、傾聴し、対話することで、視野を広げ、理解を深めることを大切にするように説いています(対話重視)。 対話を重ねる方法を学び、知の探求の楽しさを実感してくれるように工夫しています。学期末には、試験の代わりに、「平和の種の一粒になる」ための宣言を提出してもらっています。それは、「平和」は考えるだけでなく、実践してこそ意味があると考えるからです。 |
||||
ーどうすれば世の中が平和に一歩でも近づくのかー
First Year Seminar Aとは約20人という少人数で行われる一年生のためのゼミです。SILSの中では唯一日本語で行われる授業でもあり、高校のホームルームのような雰囲気なのが特徴です。この授業では週に一度、平和や紛争解決に興味を持っている人間が集まり、ディスカッションを行いながら、「どうすれば世の中が平和に一歩でも近づくのか」ということを考え続けています。
私はSILSの授業の中でも、FYSが一番好きです。なぜならば、人との距離がとても近いからです。中でも上杉先生の授業には3つの特徴があります。一つ目は、学生同士の距離が近いこと。二つ目は、先生との距離が近いこと。そして3つ目がゲストの方との距離が近いことです。これらを順に紹介していきます。
上杉先生の授業では生徒同士の距離が特に近いと感じます。FYSでは、教授が講義するという形ではなく、生徒同士が主体的に話し合っていくからです。毎週、「紛争の定義は何か」、「紛争はどうすれば解決できるか」などのテーマについてお互いの意見をぶつけ合います。特に印象的だったのは「正当な暴力は存在するのか」についてディスカッションした際に、皆それぞれが自分なりの意見を発するのはもちろん、相手の意見も取り入れながら、一つの答えに辿り着いたことです。仲間と本気で語り合えるのはFYSの良いところです。上杉先生は、このように本音で話せる環境づくりが上手です。授業が始まる前に必ず一人ずつ「先週の出来事」を発表したり、天気がいい日には大隈庭園に出て授業を行ったりしてくれるので、自然と仲が深まっていきます。
また、先生との距離が近いという点において、FYSに勝る授業はありません。通常の講義などでは、大教室に生徒が50人以上いることも多い中、FYSは最大でも20人しかいません。そのため、教授と話したり質問したりすることが容易にできます。さらに、授業後にはSLACKという アプリを用いて授業の振り返りを提出するのですが、上杉先生は各生徒にコメントしてくるため、授業外でも先生と繋がっているのも嬉しい点です。
最後に、上杉先生のFYSでは先生と繋がりのあるゲストの方々ともたくさん触れ合う事ができます。実際に、社会起業家である平原依文さんや国境なき医師団日本事務局長の村田慎二郎さんなど、実社会で活躍されている方々が授業に訪れてくださいました。普段なら、講演などでしか話を聞くことができないような方々と一緒の教室で話し合いができたのはとても良い経験になりました。
私は来年、国際関係や安全保障を学ぶためにロンドンに留学します。これらの学問の目的も国家、そして世界を平和にするためにあるはずです。この授業で学んだことを胸に、これからも平和について考え続けていきたいです。
 |
This article is written by…
黒田 宏太
|
||||
※この記事は2023年3月時点のものです。
※この科目は毎学期開講されない場合があります。