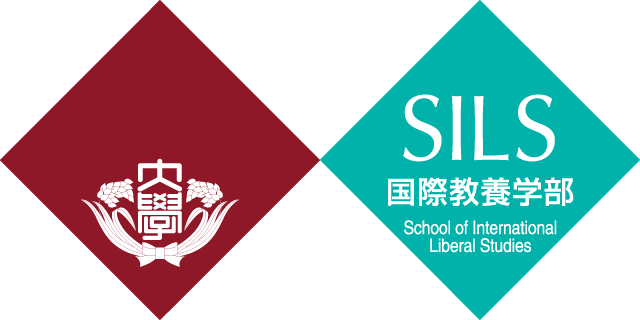- ニュース
- 授業紹介:First Year Seminar B 76
授業紹介:First Year Seminar B 76

- Posted
- Tue, 25 Apr 2023
王 怡人(WANG, Yijen)
|
||||
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| This seminar was designed for students who are interested in second/foreign language teaching and learning. We learned about various language teaching approaches from both theoretical and practical perspectives. As students were encouraged to practice their critical thinking skills in this seminar, all viewpoints were welcomed and accepted. I tried to make a comfortable environment for students to share their experiences and exchange ideas through group discussions and peer work. During the semester, we practiced how to create teaching materials and design classroom activities based on the different approaches. The students also gave teaching demonstrations based on the techniques they had learned in the course, and I was very proud to see the students developing their teacher beliefs of language and pedagogy. By observing the students’ class contribution, I believe they can be good teachers in the future if they choose to. Their creativity and critical perspectives on the teaching methods also shows their capacity to become good leaders in the future. | ||||
― 英語を『学ぶ立場』ではなく『教える立場』になってみたい ―
人生の1/3を米国で過ごし、日本と海外両方の教育を受けてきた私は、日本と海外の『教育の違い』について深く興味を持ち、王怡人先生 (国際学術院助教) の 『First Year Seminar B 76』 を履修することを決めました。
国際教養学部では基礎演習が1年次の必修科目として設置されており、さまざまな分野の基礎演習を履修することができます。そこでは『Second Language Teaching Methods』について学ぶことができます。私にとって、第2言語 (英語)を取得するのは簡単なことではありませんでした。もしかしたらもっと効率の良い英語の学び方があったのかもしれないと思い、今度は英語を『学ぶ立場』ではなく『教える立場』になってみたいと思っていました。そんな時に、偶然にもこの基礎演習に巡り合うことができました。
ここでは主に、『第2言語の教え方』について学びます。約10個ほどの教え方をクラスで学習していきます。ここで特に私が面白いと思った教え方を紹介していきます。それは『Desuggestopedia』という教え方です。この教育方法は主に生徒の学習に拍車をかけることを目的としてあります。その例として、クラスにユニークなポスターを貼ったり、音楽を流したり、生徒のモチベーションを上げながら第二言語を学習していくのです。私自身、海外の現地校に通っていて、英語をESLの生徒として学んでいた頃に、まさに壁がカラフルであったり、生徒のモチベーションをあげるポスターが貼ってあったり、授業中に音楽を先生が流していたりと、当時私はその教え方で英語を学習していたのだと気づきました。
このクラスは生徒が意見交換する機会がたくさんあり、10名ほどの小規模のクラスではありますが、常に生徒の意見が飛び交っています。生徒の意見が尊重される雰囲気があり、みんな積極的に意見交換をしています。また、とてもアットホームな雰囲気で、生徒の笑い声もよく聞こえてきます。
この授業の面白いところは、自分自身で実際に25分程度の授業を行うところです。生徒の数、生徒のレベル、どんな教材を用意するか、どんな言語を教えるか、どの教え方で生徒に学習させるか、全て自由に授業の構成を組んで、実際に行う機会があります。これほど面白くて貴重な機会を得られる授業はないと心から思っています。
 |
This article is written by…
河村 想太(KAWAMURA, Sota)
|
||||
※この記事は2023年1月時点のものです。
※この科目は毎学期開講されない場合があります。