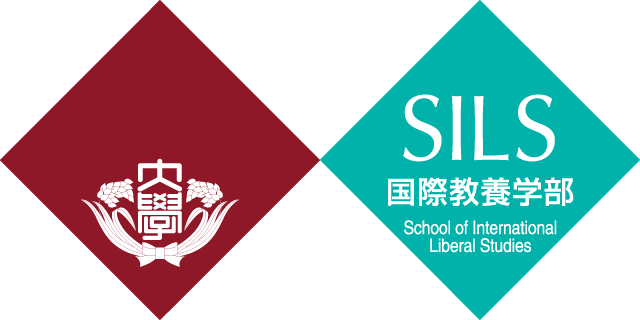- ニュース
- 【卒業生インタビュー】河合 優悟(KAWAI, Yugo)さん:SILSから東京大学大学院へ
【卒業生インタビュー】河合 優悟(KAWAI, Yugo)さん:SILSから東京大学大学院へ

- Posted
- Mon, 06 Feb 2023
 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2017年3月卒業
東京学芸大学附属国際中等教育学校 2017年3月卒業- 早稲田大学国際教養学部 2022年3月卒業
- National University of Singapore, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Communications and New Media 2022年7月卒業(ダブルディグリー)
- 東京大学大学院総合文化研究科 2022年4月入学
留学中の授業をきっかけに、稲葉 知士先生のゼミ(演習)で天文学をまなび、大学院に進学した河合さん。進学を決意した経緯や、SILSでの学びが研究生活にどのように活きているか、お伺いしました!
― SILSを卒業後、現在の進学先での様子を教えてください。
現在は東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻にて、太陽系外惑星の研究をしています。太陽系外惑星というのは、文字通り我々の住む太陽系の外にある惑星のことです。1995年に初めて発見されて以来、まだまだ解明を待たれる謎の多いエキサイティングな研究テーマです。
そんな太陽系外惑星の中でも、私は「軌道が傾いた惑星」を研究しています。地球をはじめとする太陽系の惑星の軌道は傾いていません(全て太陽の自転と同じ向きに公転しています)。これに対し太陽系外には、軌道が少し傾くどころか星の自転に対して完全に逆向きの惑星も発見されています。そして、こうした惑星の進化の過程はまだ多くが謎に包まれています。
そこで、研究室の観測装置を駆使し、夜空を見上げながら、実際にどのくらいの惑星の軌道が傾いているのか、どのような惑星は軌道が傾くのかといった惑星の進化の謎を追求しています。

国立天文台ハワイ観測所岡山分室にある188cm反射望遠鏡の装置交換の際の写真
― 現在の進路はどのように決めたのですか。
SILS入学時はジャーナリストになりたいと考えており、留学先のNational University of Singapore (Double-Degree Program)でもコミュニケーションを専攻していました。しかし、留学先でふと受けた宇宙と哲学についての授業に感銘を受け、この広い宇宙についてもっと知りたいという気持ちが芽生えました。
帰国すると就職活動の時期に差し掛かっており、大学院入試までもあと一年という状況で、数学や物理の知識では他学部の学生と比べ圧倒的なハンディキャップがあったため非常に悩みましたが、相談した先輩にも強く背中を押され進学を決意しました。
以後はSILSで理系科目を中心に履修し、天体物理のゼミに入りました。勉強や入試で必要だった研究計画書の提出は、初めてのことばかりで苦労しましたが、教授や先輩に親身にご指導いただき、やり遂げることができました。
― 今の進路に進んで、やりがいを感じていることは何でしょうか。
研究を通して「まだ誰も答えを知らない問い」の解明に工夫を凝らすことに、大きなやりがいを感じます。
― SILSでの学びは、現在どのように役立っていますか。
天文学では数学や物理ももちろん重要ですが、論文を読むことに英語は必須ですし、問いを立てるための論理的思考力も大きく問われると感じます。
こうした視点からSILSでの学びを振り返ると、理系科目にとどまらず、数々の文献を読みこなしながらエッセイを書き、発表をするという他分野の授業でのトレーニングは、現在の研究の確かな基盤となっています。
― 今振り返ってみて思う、SILSの魅力や強みはありますか。
SILSの強みは、非常に多くの学問への扉が開かれた中、学部生活を送ることができることだと感じます。例えば、コミュニケーションを勉強していたら宇宙について興味が湧いてきたりすることもあるし、その逆もあり得ると思います。
そんなとき、文系理系で区切ってしまえば入学した段階で選択しえない方向に、いつからでも舵を切れる環境がSILSにはあります。リベラルアーツという学際的な環境だからこそ、知的好奇心のままに学問を深めることができます。
― 最後に、SILSを目指す受験生の皆さんへのメッセージをお願いします!
当時の私もそうであったように、現在SILSへの進学を検討しているみなさんは、「SILSでは何を学べるのだろう」、「卒業したらどのような場所に行けるのだろう」と漠然とした期待と不安を抱えていると思います。
SILSではグローバルで開かれた環境で、仲間たちと切磋琢磨することができます。その中で培うことのできる多種多様なスキルは、時代や進路を問わず一生の糧となるものだと確信しています。
SILSの卒業生として私の体験談が、みなさんのSILS進学への後押しとなることがあれば、これ以上の喜びはありません。
掲載情報は、取材時点のものになります。