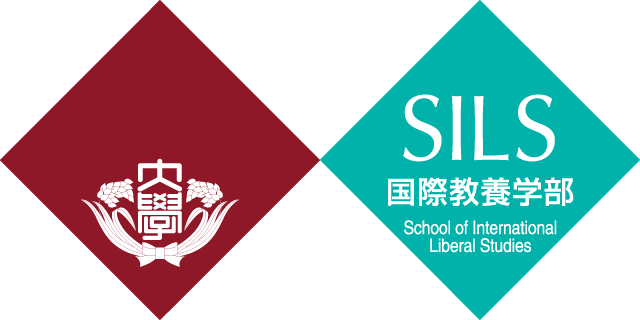General Questions about SILS
国際教養学部全般
国際教養学部(SILS)はどのような学部なのでしょうか?
SILSのコンセプトを参照してください。
国際教養学部では何が学べますか?
特色I : 考える力を養うリベラルアーツ教育を参照してください。
また、開講科目一覧 を参照することができます。
※すべての科目が毎年、毎学期開講されているわけではありません。
国際教養学部の募集人員は何人でしょうか?
正規生の募集人員は年間で600名です。各入試の募集人員については、入試情報・入学試験要項を参照してください。また、これとは別に、世界中から、半年~1年の交換留学生等(大学3年生が中心)を毎年約300名程度受け入れています。
国際教養学部にはどのような入試制度がありますか?
こちらの資料のとおりです。各入試制度の詳細は入試要項をご確認ください。
帰国生ばかりの学部ですか?
国際教養学部では、帰国生のみを対象とする入試は行っておりません。主に日本の高校を卒業した方が対象となる入学試験の募集定員は、全体の約6割にのぼります。 海外経験のある方の人数は他学部と比べると多い傾向にありますが、一度も海外で教育を受けた経験がなく、日本の高校を卒業された方も多数入学しています。
受入留学生はどこの国の人が多いですか?
現在、国際教養学部で学士号の取得を目指す外国籍学生(4年間在籍)は、入学者全体の約3割を占めています。その国籍は、韓国や中国など、日本の近隣諸国である東アジア地域各国からが最も多くなっていますが、東アジア以外の地域からの留学生も年々増えており、他のアジア諸国、欧米、アフリカなど50ヵ国・地域におよびます。さらに、カリフォルニア州立大学バークレー校、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、マギル大学、パリ政治学院、北京大学など、世界のトップクラスの大学を含む協定校から毎年約300名の交換留学生が集まっています。
9月入学は可能ですか?
可能です。国際教養学部は4月入学と9月入学の2度の入学時期を設定しています。
国際教養学部の「Study Plan」について教えてください。
2つのStudy Planを参照してください。
国際教養学部の「セメスター制」について教えてください。
国際教養学部では、セメスター制(学期制)を採用しています。具体的には4年間を半年ごとに8つの学期に分けて考えます。第1学期~第3学期は基本的な教養と英語力(Study Plan2の学生は日本語)を身に付ける期間です。日本語を母語とするStudy Plan 1の学生は、主に第4学期~第5学期に海外の大学に留学します(Study Plan2の学生の留学は任意)。身に付けた語学力や教養を実際に生かす期間です。第6学期~第8学期は留学の経験をもとに、学習をさらに深め、総まとめをする期間になります。 このように、4年間の学生生活を大きな流れの中で捉えることによって目標を立てやすくするとともに、個々の学期では興味のある分野の科目を集中的に学習することによって、教育効果を高めることが可能になります。
留学は必須ですか?
日本語を母語とする学生(Study Plan1)は、カリキュラム上、1年間の留学が必須です。
※入学後のStudy Planの変更は認められません。
※日本語を母語とする学生でも、日本語による科目履修が困難な場合や、長期にわたり日本国外に在住していた場合等はStudy Plan2を選択することが可能です。詳細は2つのStudy Planを参照してください。
国際教養学部で取得することが可能な教員免許状は何ですか?
中学校1種免許状・英語および高等学校1種免許状・英語を取得することができます。詳しくは教職/資格を参照してください。
国際教養学部で取得することが可能な教員以外の資格は何ですか?
教育学部設置科目を履修することで、「図書館司書」および「博物館学芸員」の資格を取得することができます。ただし、国際教養学部のStudy Plan 1の学生は、1年間の海外留学が必須となりますので、4年間で他学部の科目を履修し所定の単位を得ることは困難を伴う場合があります。
国際教養学部への編入制度について教えてください。
他大学等からの編入・社会人入学制度、学士入学制度は実施しておりませんが、早稲田大学の他学部から国際教養学部への2年次転部の編入制度を実施しております。2年次転部については、転部入学試験を参照してください。
国際教養学部の外国語教育について教えてください。
1年間の留学(日本語を母語とするStudy Plan 1の学生のみ必須)に必要な英語力を養成するための英語教育、日本語以外を母語とするStudy Plan 2の学生のための日本語教育、そして20以上の言語から選択可能な第二外国語教育の3つに大きく分けられます。詳しくは、カリキュラムポリシーおよび特色IV:グローバル化に対応した語学教育を参照してください。
授業は原則英語で行われるということですが、授業についていけるか心配です。具体的にどの程度の英語力が必要なのでしょうか?
英語能力試験のテストの点数で一概に判断することはできませんが、入学後の授業についていくだけの能力を有しているとみなされる方に入学試験の合格が与えられますので、自信を持って入学してください。 なお、入学後の第1~3セメスターに英語で考えて表現する力を少人数クラスで徹底的にトレーニングします。「読む」「聞く」「話す」「書く」それぞれのスキルによって習熟度別のクラスが編成されるため、自分の弱点を強化することが出来ます。
英語力が高い学生でも、語学の授業において英語を学ぶ必要はありますか?
英語力を問わず、一部の英語語学授業(English Academic Writing)は必修ですが、入学前に英語のクラス分けの試験を実施し、習熟度に応じた授業を履修します。
TOEFL(iBT)79点、TOEFL(ITP)550点、TOEIC750点、IELTS6.5点、英検1級以上の学生は、一部の英語科目の受講が免除され、他の科目で単位を充足することが可能です。
国際教養学部ではどのような専門性を身に付けられますか?
国際教養学部は「教養を学ぶ」ことを一つの軸として掲げており、幅広い分野から科目を履修することができます。
学習を進め、留学(Study Plan1の学生は必須)にも参加して徐々に自分の興味・関心を絞り込み、最終的に卒業研究等で専門性を身につけることもできます。
また、特定の分野を体系的に学べるよう、「コンセントレーション」という制度を設けています。各コンセントレーション(分野)の指定科目群から履修し、必要単位数以上修得した場合は、卒業時に当該コンセントレーションの修了証明を受けることができます。
また、途中から新たな分野に触れることも可能ですので、自分の興味・関心に合わせて専門性を深めたり、幅広く学んだりと学びのスタイルを自由自在に変えることができるという点が大きな特徴です。したがって、「色々なことに興味・関心があるが、大学入学時では一つに絞り切れていない」方や、「さまざまなバックグラウンドを持つ人々に囲まれた環境で学びたい」方に適した学部といえます。
自分の専門以外の興味・関心のある授業を受けることができますか?
国際教養学部の専攻科目は幅広い分野から構成されております。受講に際して一定のルールはありますが、分野を超えて幅広い科目を受講することが可能です。また、他学部やグローバルエデュケーションセンターの設置科目を受講したり、国内の協定大学の提供科目を受講することもできます。
国際教養学部は授業が非常に難しいと聞きましたが?
当学部は、英語で授業を行うことに加え、1年次からの演習科目をはじめとする多くの授業において、少人数教育を実施している点が特色の一つです。そのため、授業の中で発言を求められたり、 発表・討論をする機会が多く、その分、授業の準備や復習にかける努力も求められます。 このように、当学部では常に緊張感をもって授業に臨むことを求められますが、学生に対するサポート体制を以下のとおり整えています。
- 学生と教員、学生同士のコミュニケーションを十分に図ることができるよう、低学年の演習科目においては、教員と学生の比率の上限を1:20としています。
- 各学生には「アカデミックアドバイザー」として特定の専任教員が割りあてられ、履修・留学の計画や学生生活での様々な問題について、修学上のサポートをしています。
- SILS生のニーズに沿った情報を提供するグローバルネットワークセンター(GNC)があります。当センターでは主に留学やキャリアに関するイベントを開催し、SILS生に役立つ情報を提供しています。
- 留学や学生生活に関する相談ができる「SILSアドバイジング」というサービスを提供しています。
- 必修科目である統計学授業のフォローアップのための「チュータリングサービス」を提供しています。
- 先輩学生が主体となり、新入生が入学後すぐに学部の環境に馴染めるようにサポートするボランティア団体「SILS Sempai Project」があります。
卒業後の進路を教えてください。
卒業生の活躍の場は国内に留まらず、世界中に広がっており、さらなる研究を進めるために国内外の大学院へ進学したり、日本企業や外資系企業に就職しています。 業種も特定の分野に限らず、金融・メーカー・マスコミ・国際機関・公共機関・教育など幅広い領域で活躍しています。これは当学部のカリキュラムの特徴を反映した結果といえるかもしれません。国際教養学部で身に付く語学力とコミュニケーション能力以外にも、異文化への寛容な理解と強いイニシアティブ、枠にとらわれない発想力はこれからの社会でますます必要とされるようになるでしょう。 卒業後の実績は卒業後の進路を参照してください。卒業生へのインタビュー記事もあわせてご覧ください。
大学院への進学について教えてください。
国際教養学部では、現代的な教養を幅広く身に付けることを目標にしています。更に専門的な研究を深めたい場合は、大学院に進学することも可能です。 過去の卒業生は、国内外の名門大学院の様々な分野に進んでいます。 卒業後の進路を参照してください。
入学後、学部を変えること(転部)はできるのでしょうか?
他学部への転部制度はありますが、全学部で受け入れを行っているものではありません。詳細については、転部希望先の学部事務所にお問い合わせください。
兵役に従事しなくてはならないですが、この場合どのようにしたらよいですか?
原則として、2年間までは休学の申請ができます。