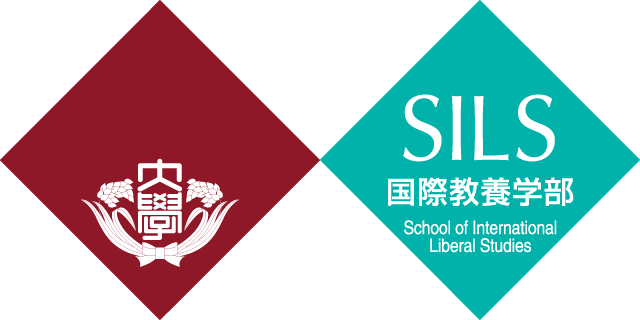- ニュース
- 【卒業生インタビュー】矢部あずさ さん:宇宙開発をもっと身近に
【卒業生インタビュー】矢部あずさ さん:宇宙開発をもっと身近に

- Posted
- 2023年12月18日(月)
- 聖徳学園高等学校 2005年3月卒業
- 早稲田大学国際教養学部 2009年3月卒業
- 早稲田大学大学院政治学研究科 科学技術ジャーナリスト養成プログラム 2011年3月修了
- 筑波大学計算科学研究センター 研究員 2011年4月~2015年6月
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所 宇宙科学広報・普及主幹付 招聘職員 2015年7月~2018年3月
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 広報部 2018年4月~現在
― 現在はどのようなお仕事をされているのでしょうか。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の広報部で働いています。
当初は主にJAXAの取り組みの中でも宇宙科学・宇宙探査に関する報道・メディア担当として、研究成果や注目の高いイベントをメディアの皆さんにお知らせするプレスリリースの調整や、記者会見の運営、メディア対応などを主にしていました。
2021年からは、企画・普及課という部署で、JAXA全体の方針を年間の広報計画への落とし込みや、予算や契約などの管理などをしています。他の職員と協力しながら、国内外のイベントの出展や、学校などでの講演、ウェブサイトの更新、お問い合わせの対応などの対応をすることもあります。
― SILSに入った理由を教えてください。
海外経験はほとんどありませんでしたが、高校生の頃から文系と理系両方の学問に興味があったので、文理問わず幅広く勉強できるSILSを選びました。
―SILSでの学生時代はどのように過ごされていたのですか。
学生時代は、広い意味で勉強に力を入れていました。
授業に関しては、元々興味の強かった理系分野(物理や統計、情報系など)と語学を中心に履修していました。他学部聴講制度を積極的に活用して、教育学部や理工学部、文学部の授業を受けたりもしていました。3年の秋からは宇宙物理学等を扱う、稲葉知士先生のゼミに入りました。ゼミは私たち4人が1期生で、力学や量子力学の教科書は内容が難しくついていくのが大変でしたが、今となってはいい思い出です。
1年生の夏には、第二外国語で選んだロシア語を肌で学ぶため、ロシアのウラジオストクへ短期留学に行きました。早稲田から一緒に留学した先輩、現地の学生、他国・他大学からの留学生と楽しく過ごすことができ、ロシア語はあまり上達しませんでしたが、非英語圏で過ごすことへのハードルが下がりました。
ロシア語の入門は国際教養学部の設置科目でしたが、ロシア語の上級や、モンゴル語やアイヌ語も他学部提供のオープン科目として履修しました。どの語学の授業も、先生方は言語だけではなく、文化や歴史についても教えてくださり、有志の課外授業として、モンゴル料理を食べに行ったり、北海道へ行ったりしたのも良い思い出です。
また、スポーツが盛んな早稲田ですが、太極拳、バスケットボールなど、全学部から履修可能な保健体育科目も履修しました。学べる言語の多さ、有名な教授の授業、授業を通して他学部の学生との交流機会が多いのは、早稲田の魅力ですね。
授業以外では、SILSの理系科目のTA(授業における教授の補佐役)や、読書に時間を費やしていました。読書は小さい頃から好きで、在学中は一年で1000冊近く本を読んでいました。授業や研究に役立つものからライトノベルまで、とにかく空き時間は本を読み耽っていました。早稲田は図書館が複数あり蔵書数も多いので読書好きにはたまらない環境でした。加えて、生協ブックセンターや、大学周辺の古書店など、新しい本も、古い本も、いくらでも本が手に入ります。本を買うだけであれば、ネットでも購入することができますが、常に大量の本が周辺にある生活ができるのは、早稲田ならではだと思います。
― そこから大学院に進学したきっかけや理由を教えてください。
当時、科学ジャーナリスト養成コースとSILSの共通科目として、学部3年生の時に履修した「サイエンスジャーナリズム」という授業で、その分野に興味を持ちました。その後、大学院が提供していた科学ジャーナリズムのブートキャンプに参加したことが大きなきっかけとなりました。研究の最前線を常に追いかけて、高い倫理感と建設的批判精神が必要になる分野です。SILSで文理両方学んできた事も活かせそうだと感じた上、有名ジャーナリストをたくさん輩出している環境への憧れもあり、大学院進学を決めました。
― 大学院時代はどのような生活だったのでしょうか。
ジャーナリストの卵として、取材のために、いろいろな場所に出かけて行くことが多かったです。それ以外の時間は機材・ソフトウェア環境等が充実した学生室に入り浸っていました。研究者への取材や、学会発表の聴講のために、遠方まで出かけて行くこともありました。そのときの記事の一部は、いまもジャーナリズムコースのブログで読むこともできます。
ライターとして、早稲田先端研のウェブサイトに掲載する研究紹介の執筆や、現在働いているJAXAに足を運んで「はやぶさ」や国際宇宙ステーション関連の記事を雑誌に書いた事もありました。
科学技術ジャーナリスト養成コースでは2つのゼミに籍を置くこととなっており、メディア研究の先生のゼミと、技術史の先生のゼミに所属して、毎週議論をしていました。このコースは社会人学生が多く、同年代との会話とは全く違う視点や、多くの経験を吸収させていただきました。
ジャーナリズムを勉強しながら進路を考えたとき、自分はジャーナリズムよりも、研究機関に所属して、科学広報をやりたいのだと気付きました。
― JAXAに入るまでの経緯を教えて下さい。
大学院卒業後は、筑波大学計算科学研究センターで広報の仕事をしていました。ここでは、宇宙や気象などスーパーコンピュータを使ったシミュレーションや、スーパーコンピュータ自体の研究開発を行っていました。最初の1年は週4日の非常勤勤務だったので、残りの1日は国立天文台で質問対応のアルバイトをしていました。3年ほど経った2015年、JAXA宇宙科学研究所の広報の募集に応募し、採用されました。宇宙科学の世界は国際協力で進めるのが当たり前の業界ですので、英語で仕事ができるかも問われましたが、SILSを卒業しているというのは、英語で交渉を行い、専門知識を学ぶことができる能力があるということを裏付けてくれます。大学、大学院、社会人経験の全てが、宇宙科学の広報ができる人材という需要とマッチしていたのかなと思います。
―今の仕事のやりがいはどのようなところにありますか。
人工衛星やロケットの打ち上げ成功時、ミッション達成時にみんなで喜びを分かち合えるところにありますね。打ち上げ前後は、やはり仕事が一番大変な時期なのですが、その喜びのために日々の業務を頑張れますし、ロケットや人工衛星はその分自分の子どものような存在に感じます。ロケットや人工衛星は「もの」ですが、それを作り上げたり、支えたりしているのは「ひと」です。広報の仕事は、自分が誰のために、何のために頑張っているかを思い浮かべやすいので、やりがいを感じやすいと思います。
―宇宙産業の「いま」や今後について教えて下さい。
いま、人工衛星の利用先は、宇宙農業やエンタメ、無人遠隔操作など様々な分野で高まっています。人類が宇宙で暮らしていくための研究やビジネス利用も一気に進んでいます。JAXAでは、既存の業界に縛られずに、宇宙データ利用や企業の宇宙参入を促しており、宇宙での技術実証や実験を行えるよう手助けをしています。宇宙ビジネスの時代はもう始まっていますし、宇宙旅行が現実となるのも目前と迫ってきているので、私自身としては宇宙をもっといろんな人にとって身近なものにしたいですし、そう感じさせる機会をたくさん提供したいですね。
―今振り返ってみて感じる、SILSの魅力や強みを教えて下さい。
学べる分野の幅広さ、学生の多様性はSILSの大きな魅力だと思います。文系から理系まで興味のある学生には理想的な環境だと思いますし、ここまでいろんなバックグラウンドを持った人と出会える環境はなかなか無いと思います。また、英語での授業や、海外留学などを通して得られた語学力や国際リテラシーは今の仕事にも活きていますし、どの分野でも重宝される素養が自然と身についたと感じます。
―受験生や在校生にメッセージをお願いします!
自分が興味を持ったものに、どんどんチャレンジしてください!その中で何か自分の得意な事を身につける事が出来れば、将来の大きな武器になるはずです。
興味がある分野の学会や展示会に参加してみるのも良いと思います。最先端の発表をたくさん聴講すると、世界が広がりますよ。
掲載情報は、取材時点のものになります。