- Featured Article
トップ企業リーダーから見たAI
WOI’23「日本が世界に誇るトップ企業の社長によるパネル・ディスカッション」レポート
Fri 08 Dec 23
WOI’23「日本が世界に誇るトップ企業の社長によるパネル・ディスカッション」レポート
Fri 08 Dec 23
WOI’23「日本が世界に誇るトップ企業の社長によるパネル・ディスカッション」レポート
2023年11月9日、10日、大隈記念講堂およびリサーチイノベーションセンター(121号館)にて、「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023(WOI’23)」を開催しました。WOIは、「研究の早稲田」実現に向け、産学官連携の推進、大学発ベンチャーの紹介、文理融合の研究・社会変革につながる研究等の紹介ならびに企業等のご関係者の皆様との連携に向けたマッチングを目的とした産学官連携イベントです。
大隈記念講堂ではさまざまなゲストを迎え、講演や座談会を実施。その一つ「日本が世界に誇るトップ企業の社長によるパネル・ディスカッション」では、トヨタ自動車、パナソニック、ソニーグループ、ボストン コンサルティング グループのトップが一堂に集結。世界をけん引する企業のトップ4人が、AIや企業経営、人材育成のあるべき姿について、若い世代に向けて語り合いました。本記事では、このパネル・ディスカッションの様子について、レポートをお届けします。
※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです
《登壇者》
佐藤恒治氏 トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長CEO(理工学部卒業)
品田正弘氏 パナソニック株式会社 代表取締役社長執行役員CEO(商学部卒業)
十時裕樹氏 ソニーグループ株式会社 代表執行役社長COO兼CFO(商学部卒業)
《ファシリテーター》
秋池玲子氏 ボストン コンサルティング グループ日本共同代表(大学院理工学研究科修士課程修了)


生成AIの台頭と、人間が担うべき役割
秋池氏「約1年前から、急速に私たちの暮らしの中に浸透しているAI。あまりにも急な変化であるがゆえ、社会全体がAIをどのように活用していくか、方向性を模索しています。皆さんはどのように捉えていますか?」
品田氏「どこか万能感がある生成AIですが、現時点でのレベルは、入社3年目の若手社員だといわれています。ようやく一人で仕事ができるようになり、少し自信過剰な時期ですね(笑)。当社でも活用を進めていますが、顧客ニーズの分析などはかなり的確です。しかしリーダーシップのような部分は、まだまだ苦手という感触です。その二面性をどのように上手に使うかがポイントになるでしょう」

パナソニック株式会社 品田正弘氏
佐藤氏「生成AIに、2050年のモビリティ社会の絵を描かせたところ、未来的でダイナミックな作品に仕上がりました。しかし一つだけ欠けている要素があって、それは“意外性”でした。どことなく予定調和的で、予測していないものが、そこには描かれていない。突き詰めて考えてみると、意外性というのは、知能や理性と反対側にある、感情や遊び心なんですね。自動車も理詰めでつくるだけでは必ずしも面白くいものにならないように、そこは人間の創造性が担うべき部分だと感じます」
十時氏「人間の感性やクリエイティビティにあたる領域は、重要でありつづけますね。ソニーグループではゲーム事業を展開していますが、世界中を見渡すと同じようなゲームがあるにもかかわらず、売れるタイトルと売れないタイトルの差が大きく出ます。AIに類似した事例を学習させても、時代は常に新たなものを求めるからでしょう。その新規性に、人間の力が必要になると思います」

ソニーグループ株式会社 十時裕樹氏
企業経営から見た、ビジネスにおけるAIの可能性
秋池氏「AIを使用している際には、人間が問いかけ、答えをAIが出します。少し違う答えが出た場合、修正を加えることでズレを小さくしていくわけですが、そこにも人間が介在します。どのデータの領域を対象に扱うか、判断を下すのも人間です。人間がAIに介在する仕事はまだまだ多いですが、企業経営という観点ではどうでしょうか?」

ボストン コンサルティング グループ 秋池玲子氏
品田氏「タスクが明確な仕事の場合、効率が飛躍的に向上するのは間違いありません。製造業などにおいては、設計におけるリードタイムが大幅に短縮されるでしょう。だからこそ、目先の業務、急いでやらなければならないような短期的な仕事はAIに任せ、人間はもっと長期的な未来を考えることに時間を費やしていく。そうした役割分担が有効だと考えています。」
佐藤氏「条件が有限な領域で推定を行うのが、AIが得意とする世界。例えばAIが材料組成を分析することで新材料の開発スピードが飛躍的に上がります。また、自動車の二律背反する要素への最適解を求める時、例えば空気抵抗(※)を下げつつ、かっこ良いデザインにしたいという時、AIはある段階までは比較的スピーディに解を返してきます。ただ限界はあって、やはりどこか“かっこ良くない”ものになっていたりもします。新しいものを生み出すプロセスにおいても、効率性とは反対側にある、意外性や創造性が重要です。ただし、将来的にAIが感情を取り込むことができるかどうかは、未知数ですよね」
※走行中の自動車や飛行中の飛行機が空気の流れから受けるさまざまな影響を指し、前後、左右、上下(揚力)にかかる力に加え、ヨーイング、ロール、ピッチングなどのモーメントがある。また、風切り音や機体表面の整流作用、横風に対する安定性などを含める場合もあります

トヨタ自動車株式会社 佐藤恒治氏
十時氏「そうですね。神経細胞を伝わった電気信号が人間を動かすと考えるならば、AIが感情を持つことも、理屈上は可能なのでしょう。ただし現実的な壁として、例えば結婚式のスピーチをAIに代替してもらう場合、そこにお金を払わなければならなかったら、皆が使うでしょうか。処理に対してコストとエネルギーも発生するので、サステナビリティとの両立も議論されていくのではないでしょうか」


AIによって、私たちの仕事は失われるか
秋池氏「人間とAIの狭間で何が起こるのかは、予測できないことも多いですが、少なくとも人間の仕事のあり方は大きく変わりそうですね。AIの台頭により、人間はより忙しくなるのか、暇になるのか、どう考えますか?」
十時氏「インターネットもリモートワークも、ビジネスの効率を飛躍的に高めました。しかし人間はクリエイティビティへの欲求があるため、忙しく働きつづけています。AIが登場 し、製品やサービスの開発を学習させても、時代は常に新たなものを求めるでしょう。その新規性の領域では、人間が活躍しつづけるはずです」
品田氏「現在、多くの社会人が“こなさなければならない仕事”に、膨大なパワーをかけています。しかし働いている人が幸せか、本当に脳が活性化しているかというと、微妙なところです。創造性は、先々の未来、急がずに解決すべき課題に対して発揮されます。そこを考える時間が増えるならば、社会全体は幸せな方向へ進むと思います」
佐藤氏「同感です。AIに置き換えられる仕事はどんどん増えていくので、創造力を高めていく時間も増やせるはずです。『なぜ車をつくるのか』『何のために働くのか』といった、哲学的な領域まで、私たちは存在意義を深掘りすべきかもしれません。その繰り返しの先に生まれるのが、新たな価値です。時間の使い方が変わるのは、人類の大きな転換点になるでしょう」

ディスカッションの様子:左から秋池氏、佐藤氏、十時氏、品田氏
時代が大きく変わる中で、学生に期待する力
秋池氏「トヨタ、パナソニック、ソニーは、創業以来、強いクリエイティビティで時代の変化を乗り越えてきました。AIによる社会変革が起こる中で、学生に期待することを教えてください」
佐藤氏「今日、日本ではどの産業でも構造改革に向き合いながら、世の中に向けて新しいものを生み出す挑戦をしています。そのエネルギーになるのは、多様性や意外性です。学生の皆さんはそれぞれが持っている“自分らしさ”をそのまま大事にしてほしい。その一つ一つが、クリエイティブな日本の未来を形作っていくのだと思います」
品田氏「やはり未来を見てもらいたいですね。そして“失われた30年”を越えた今、再び世界のナンバー1を目指してほしいです。ただし、これからの時代の問題解決においては、単独の企業だけで障壁を乗り越えることが困難になります。会社や業界の垣根を越えた共創、オープン・イノベーションが重要になるでしょう。オールジャパンで衆知を集め、一人一人をリスペクトしながら、次なる時代に挑んでいただきたいです」
十時氏「今の若い世代は、情報への感度が高く、よく勉強をしていて頼もしいです。できるだけ自分を小さな枠に閉じ込めず、人とつながりながら多様性を磨いて、世界に向けて勝負してもらいたいと思います。今日よりもより良い世界をつくるような志を抱き、未来へと進んでください」
秋池氏「テクノロジーは目まぐるしく進化するため、1年後には私たちに見える技術も変わるでしょう。しかし人間の本質的なところは、永遠に変わりません。学生の皆さんには、“論点”を探し、考え続けることを大切にしていただきたいと思います。絶対的な正解のない世界で、人間だけにできる大切なことに、チャレンジしてください」
座談会では最後に、田中愛治総長より総評が述べられました。

本パネル・ディスカッションを企画した田中総長からの総評
田中総長「生成AIは、大量のデータを瞬時に解析することで人間の論理的な領域を予測することを可能にしました。しかし現時点では、AIも人間の経験の膨大な量のデータを解析しているので、人間が経験していない未知の問題の解決策は出せないレベルだろうと思われます。皆さんがご指摘の通り、今後人間はAIを使い、創造的な仕事に費やせる時間を増やしながら、自分を鍛えていかなくてはならないと思います。AIがシンギュラリティに到達した場合の世界は私には想像が難しいです。しかし、登壇者の皆さんの深い洞察は、学生にとって大変に刺激的だったと思います」
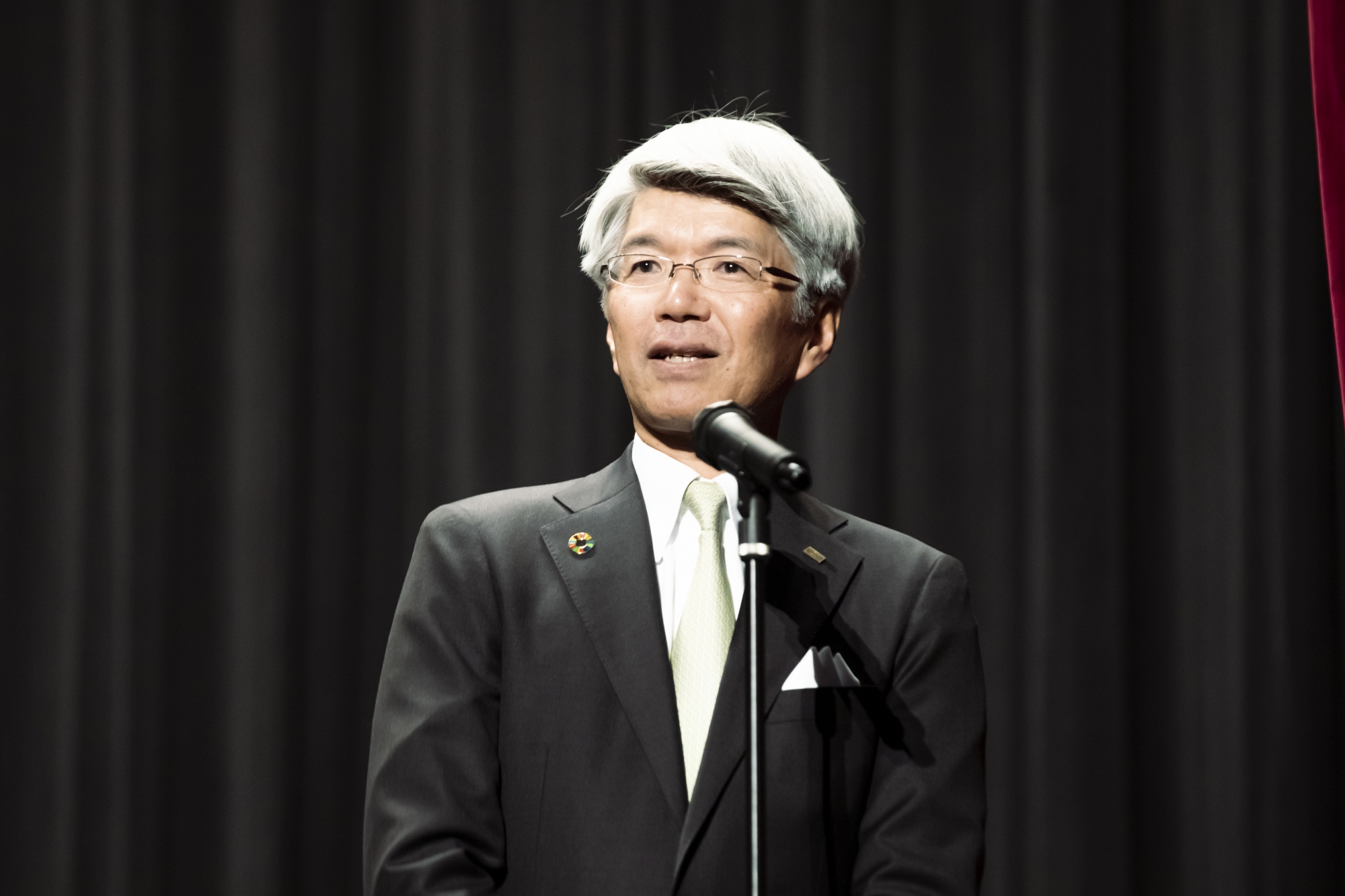
ディスカッションの趣旨を説明する藤原理事(株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 早稲田大学 経営・産学連携担当理事)

回廊での記念写真:左から藤原理事、佐藤氏、十時氏、田中総長、秋池氏、品田氏


