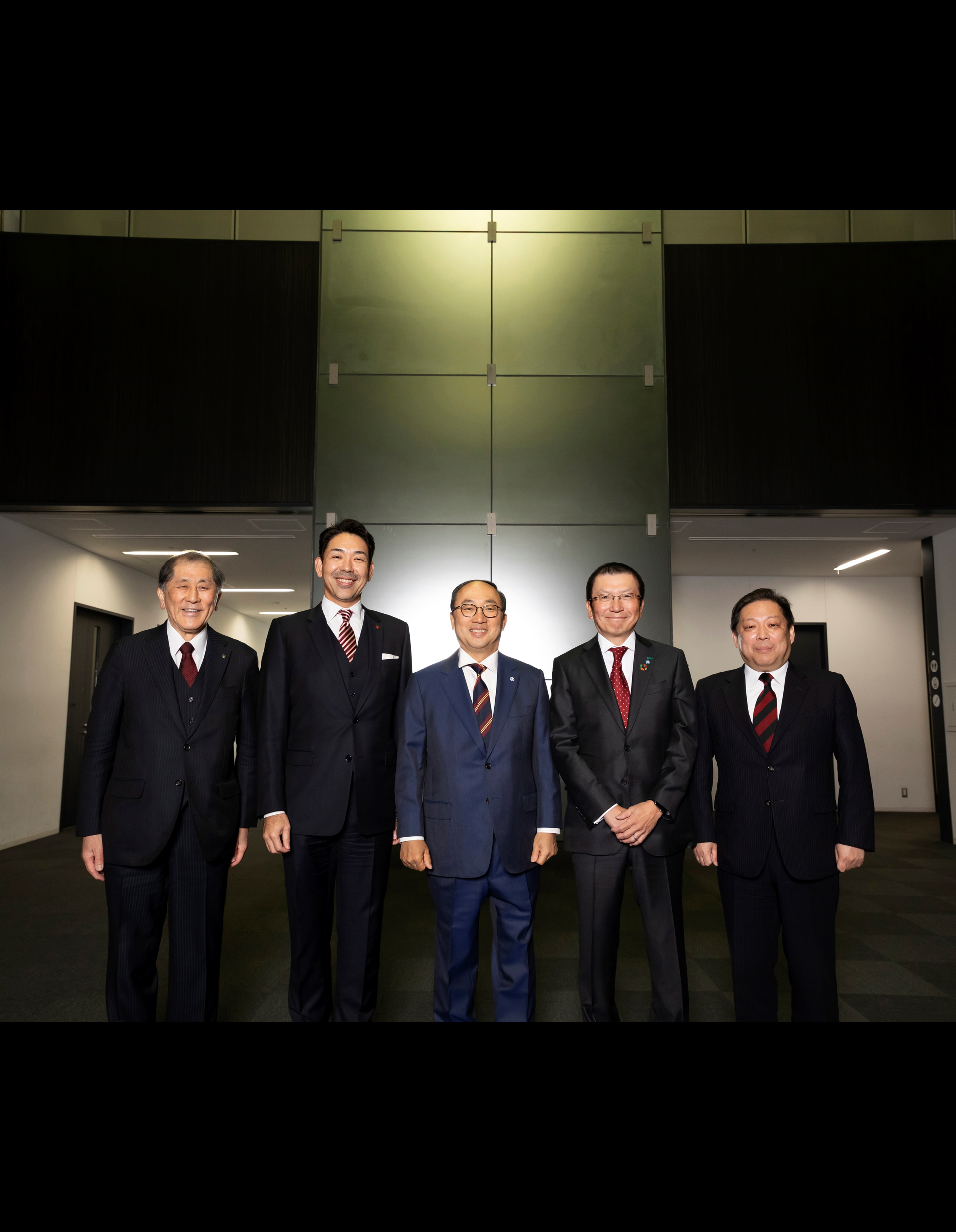- Featured Article
“学識ある実業家”とは何か
商学部創設120周年記念シンポジウム開催レポート
Wed 19 Mar 25
商学部創設120周年記念シンポジウム開催レポート
Wed 19 Mar 25
2025年3月8日、早稲田キャンパス11号館にて、「商学部創設120周年記念シンポジウム」を開催しました。本シンポジウムは、商学部が2024年に120周年を迎えたことを記念し、教育・研究・社会貢献の三つの視点から「早稲田大学商学部のこれから」を展望すべく企画されたイベントです。商学学術院の研究者に加え、実業界の第一線で活躍する商学部卒業生も迎えた当日は、約250名の方々が参加(※)。ビジネスと大学における知見が共有されたシンポジウムの内容について、本記事ではレポートをお届けします。
※来場者約200名の他、オンライン参加者を含む

歴史の中で受け継がれてきた、商学部の理念
商学部の前身にあたる『大学部商科』の創設は、1904年に遡ります。以来、120年におよぶ歴史の中で、産業界のみならず、政治・文化・芸術など多方面にわたり、10万人以上の人材を輩出してきました。シンポジウムの冒頭では、学部長を務める横山将義教授が開会の辞を述べ、創設時より受け継がれる理念を強調しました。
「今日の商学部は、多くの先人の努力や功績の上に成り立っていることを、私たちは忘れてはなりません。商科の初代科長・天野為之博士は、学者には『原理・原則を研究して敢て之を実地に応用する目的のない学者と、学び得た原理・原則を実際の有様に応用しようという』学者の2種があり、理論と経験的事実の相互作用の中で学問を進展させることを主張しています。また、商科新設に伴う学生募集には、『学識ある者は実業の修養に乏しく、実業の修養ある者は多く学識を欠く、乃ち本科の目的は此二者の調和を計り高等の学識ある実業家を養ひ、実業の修養ある学者を出すにあり』という記載が残されています。この考えは現代にも受け継がれ、『“学識ある実業家”を育て、社会に送り出す』は商学部の教育理念として掲げられています。また研究面ではイノベーション・サイエンスの国際拠点化を目指すなど、新たな取り組みも推進中です。今後も皆様のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」

横山 将義(商学学術院教授/学術院長/学部長)
つづいて、田中愛治総長が祝辞とともに、大学としての展望を伝えました。

田中 愛治 早稲田大学総長
「日本をリードする企業のトップには、商学部の出身者が多数います。一方、現代社会が直面するのは、明確な答えがない問題です。我が国が戦後進めてきた画一的な教育は行き詰まりを見せており、学生たちは自分の頭で解決策を考える必要に迫られています。実践力を強みとする商学部は、この『たくましい知性』を先駆的に取り入れていた学部であり、『世界で輝くWASEDA』に向けた本学の成長を牽引するでしょう。本日、商学部の発展のために皆様にお集まりいただいたことに、心より感謝いたします」
商学学術院が目指す、イノベーション・サイエンスの国際研究拠点
今回のシンポジウムは、教育、研究、社会貢献の3部により構成されています。1つ目のセッション「これからの商学部の研究」では、イノベーションにアプローチする2人の研究者が活動内容や成果を報告しました。冒頭では山野井順一准教授が、商学学術院が注力する「イノベーション・サイエンス」の内容と意義について説明します。
「イノベーションは『既存の方法とは異なる方法による価値創造行為』と定義できますが、個人、企業、制度が相互に影響し合うことで起こるため、多角的な研究が欠かせません。総合大学である本学は、人文社会系、理工系とのスピーディーな共同研究が可能であり、産業界や海外研究機関との連携にも強みを持ちます。商学学術院がイノベーション・サイエンスの国際研究拠点として、世界でのプレゼンスを確立することで、企業や社会に貢献したいと考えています」

山野井 順一(商学学術院准教授)
また、山野井准教授は個人の研究成果として、「経営者の心理的特性と企業のイノベーションの関係性」を発表しました。
山野井准教授「さまざまな研究者と協力し、経営者の心理的特性が、企業レベルの意思決定に与える影響を研究しています。企業経営者への質問票調査をベースに、パーソナリティ特性の分類法である『Big5(特性5因子モデル)』や、『リスク選好』『時間選好』に着目して分析を進めてきました。結果として、企業のパフォーマンスやイノベーションの創出に対し、経営者個人の心理的特性が一定の影響を与えることが判明しています」
つづいて、清水洋教授が「ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション」というテーマで研究発表を行いました。

清水 洋(商学学術院教授)
「『ジェネラル・パーパス・テクノロジー(GPTs:General Purpose Technologies)』とは、さまざまな領域への波及効果を持つ、汎用性の高い技術のことです。蒸気機関や電気、コンピューター、半導体、AIなどが該当しますが、創造的破壊の程度が極めて高く、企業の生産性や競争力を大幅に向上させる特徴があります。では、ジェネラル・パーパス・テクノロジーはどのように生み出され、波及し、社会に影響していくのか。これらを解き明かしていくのが、私が進めようとしている研究プロジェクトです。メカニズムが明らかになることで、より効果的な研究開発投資やオープンイノベーションに役立てられるでしょう」
教養、国際適応力、企業家精神を強化する、商学部の新カリキュラム
第2部「これからの商学部の教育」では、商学部の教育体制と先進事例が共有されました。2024年度に改定された新カリキュラムの内容と特徴を説明したのは、教務主任を担当する梁取美夫教授です。
「2025年度に商学部で提供する科目数は1,114に上りますが、カリキュラムの構成には3つの特徴があります。1つ目は『専門知識と幅広い教養』です。専門知識においては、専門トラックを世界の潮流に合わせて『経営』『会計』『マーケティング』『ファイナンス』『保険・リスクマネジメント』『ビジネスエコノミクス』に再編。また必修科目ではデータサイエンス関連の科目を強化しています。一方で幅広い知識を身につけるべく、『思想と人間』『社会と歴史』『科学と技術』に関連する総合教育科目を整理しました。2つ目の特徴は『国際適応力』です。グローバル化するビジネス環境で活躍する人材を育成すべく、外国語でビジネスを学ぶ『外国語専門』の拡充、国際教育プログラム『Global Management Program(GMP)』の提供などを推進しています。3つ目の『企(起)業家精神』では、起業や経営、新規事業創出の能力の養成を目指しています。実践的な学習プログラムの他、ビジネスプランコンテストの開催するなど、価値創造につながる力を養う環境を整備しています」

梁取 美夫(商学学術院教授/教務主任)
つづいて、「Global Management Program(GMP)」のプログラムディレクターを務める広田真一教授が登壇し、プログラムの内容を説明。またGMPの学生である吉村龍二さんと栁千晴さんによる、英語でのプレゼンテーションも行われました。
広田教授
「現代の世界においては、海外ではもちろん、国内においてもグローバルな知識と能力を備えたリーダーが求められます。またビジネスは、各国の政治や文化、宗教などと同様に、社会を動かすドライビングフォースになりつつあります。そうした中で国際社会に貢献するグローバルビジネスリーダーを育成すべく、GMP を2022年度にスタートしました。現在GMPは、主に3つのプログラムを提供しています。3〜4年生を対象にした『GMPゼミ(専門教育科目演習)』、英語で行われるビジネスの専門科目『GMPコア科目』、4年間を通じた英語教育と海外合宿を含む学習機会です。また、学生自らがプログラムの企画を立案・実行する『GMPStudent Committee』も特長であり、参加者は組織運営を通じてリーダーシップを高めています」

左より栁千晴(商学部4年)、広田真一(商学学術院教授)、吉村龍二(商学部4年)


学生2名による英語でのプレゼンテーション。GMPの活動内容や魅力が報告された
実業界のリーダーが語る、社会に接合した商学教育
3つ目のセッション「これからの商学部の社会貢献」では、パネルディスカッション「商学教育と実業との融合に向けて」を実施。商学部の卒業生である漆間啓氏(三菱電機株式会社 取締役 代表執行役社長 CEO)、新納啓介氏(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長)、宮原漢二氏(ウエインズトヨタ神奈川株式会社 代表取締役社長)、横山将義教授がパネリストとして、意見を交わしました。
漆間氏
「早稲田大学に入学したのは1978年。11号館地下にあった貿易学会で活動を始め、それがきっかけで近代貿易理論の田中喜助先生のゼミに入りました。ゼミでは古典書の読み込みやレポートの作成が、大変厳しかった思い出があります。三菱電機へ入社後は、品質管理や電話対応に奔走しており、貿易理論とは無縁の日々でした。しかし10年ほど経つと自分でレポートをまとめるケースが増え、商学部での経験が生かされ始めます。『何を、どのような切り口で書くか』『他のレポートをどのように読み解くべきか』という視点は、大学で養われたのだと実感しました。他にも、語学や国際的視点、経営分析など、学生時代に意識が芽生えた領域が、結果として役立った経験が多々あります」

漆間 啓 氏(1982年商学部卒業)
新納氏
「大学時代に私を成長させたのは、外国為替を深く学んだゼミと、幅広い科目が用意されたカリキュラムです。損害保険会社のビジネスは、さまざまな業種のお客さまに対し、多角的な視点からリスクとソリューションを提言するものです。広範な知識に触れた経験は、大いに役立てられています。現在、商学部のカリキュラムは進化し、『保険・リスクマネジメント』が専門トラックとして設置されました。リスクがどこに存在し、どのようにマネジメントできるのか。その中で保険はどのように機能するのかを体系的に学べる環境は、大変貴重だと思います」

新納 啓介 氏(1988年商学部卒業)
宮原氏
「私は大学時代、横山将義先生のゼミで国際経済学を学び、『社会では、自ら物事を考え、伝える力が大切になる』と指導を受けたのを覚えています。文献の内容をゼミのメンバーが理解するまで説明するという、厳しい課題もありましたが、今振り返ると非常に重要だったと感じます。現在私はトヨタ自動車の販売店を経営していますが、クラシカルな業態である分、変革を起こせる可能性も広がっています。しかし変化を起こす場面には、反対の立場をとる人も現れるものです。相手に理解を求める中で、横山ゼミで培った力を活かせないかと、日々模索しています」

宮原 漢二 氏(2002年商学部卒業)
横山教授
「『学識ある実業家』とは、単なる専門知識だけではなく、総合的な教養を備えた人材を指します。天野為之博士も経済や商業だけでなく、道徳や倫理の重要性を訴えていました。現在の商学部における人材育成の目的は、最終的にはビジネスマインドを涵養することですが、その過程では商学の専門科目はもちろん、データや統計の分析力、語学や国際感覚、幅広い教養を身につけられるよう設計しています。学生自身も、社会との接合を意識しながら学習しているので、今後も寄付講座の提供などをはじめ、産業界との連携も強化していきたいと考えています」

横山 将義 教授
新納氏「海外の人々とコミュニケーションをとりながらビジネスを推進する力を、若い時代から肌感覚で鍛えておくのは、非常に重要です。グローバルビジネスリーダーを育成するGMPをはじめ、商学部の教育が充実することを、非常に嬉しく思います」
宮原氏「リーダーとして会社を動かす際には、人材の育成、モチベーションの向上、それらを体系的に実現させる組織づくりなど、さまざまな能力が必要です。行動心理学や組織論、リーダーシップ論などが充実する商学部では、リーダーになる人材が増えていくのでしょう」
漆間氏「答えのない世界の中で、判断を下さなければならない現代。答えを自ら創り出す力を、早稲田大学で訓練できれば、実社会においても必ず力を発揮します。また近年のグローバルビジネスにおいては、市場のある地域の現地に出向き、ニーズに応じて開発を進めるプロセスも重要です。商学部の学生が海外の人々と交わり、国際的な議論の方法論を身につけることに、大きく期待します」
※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです