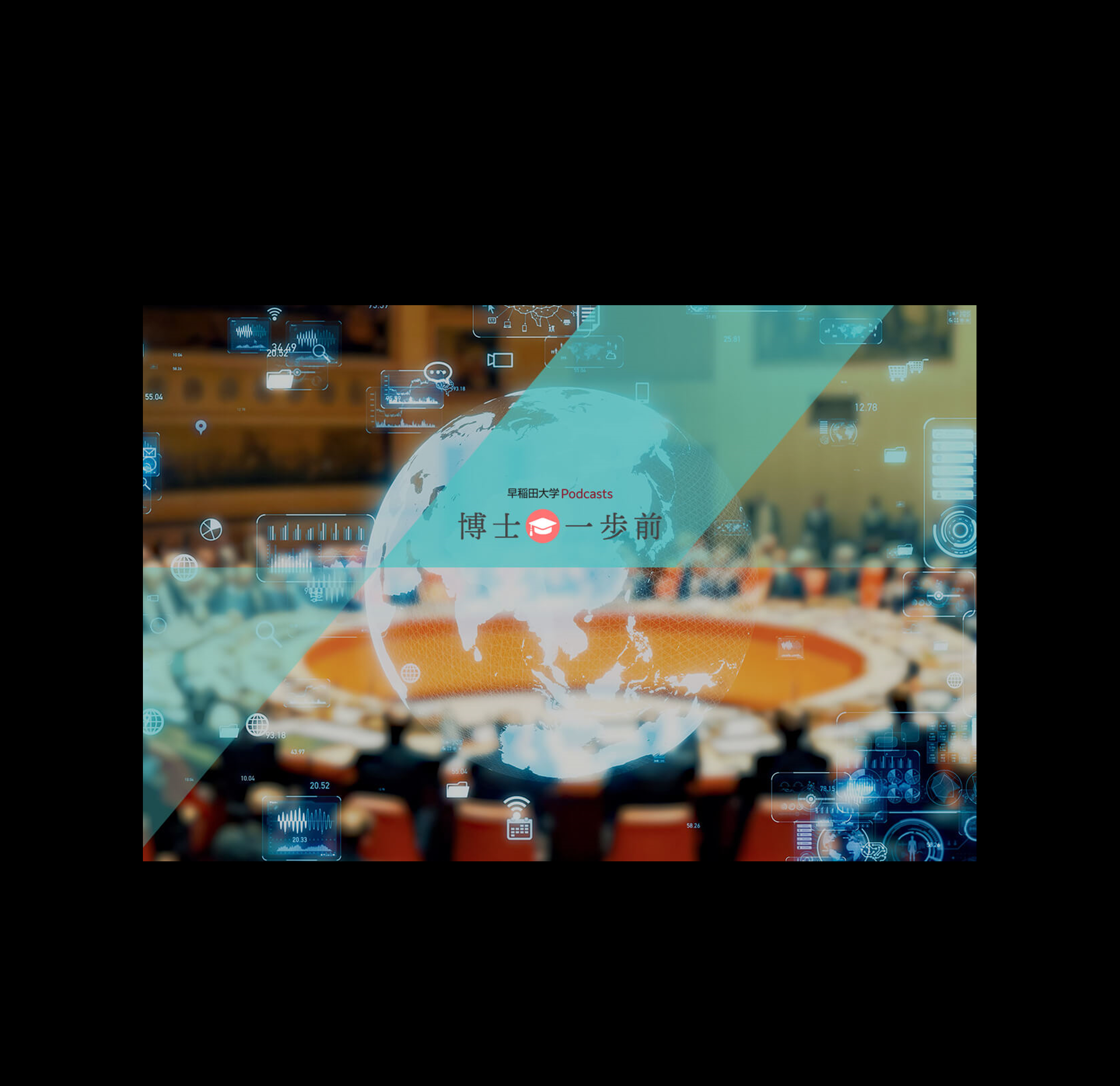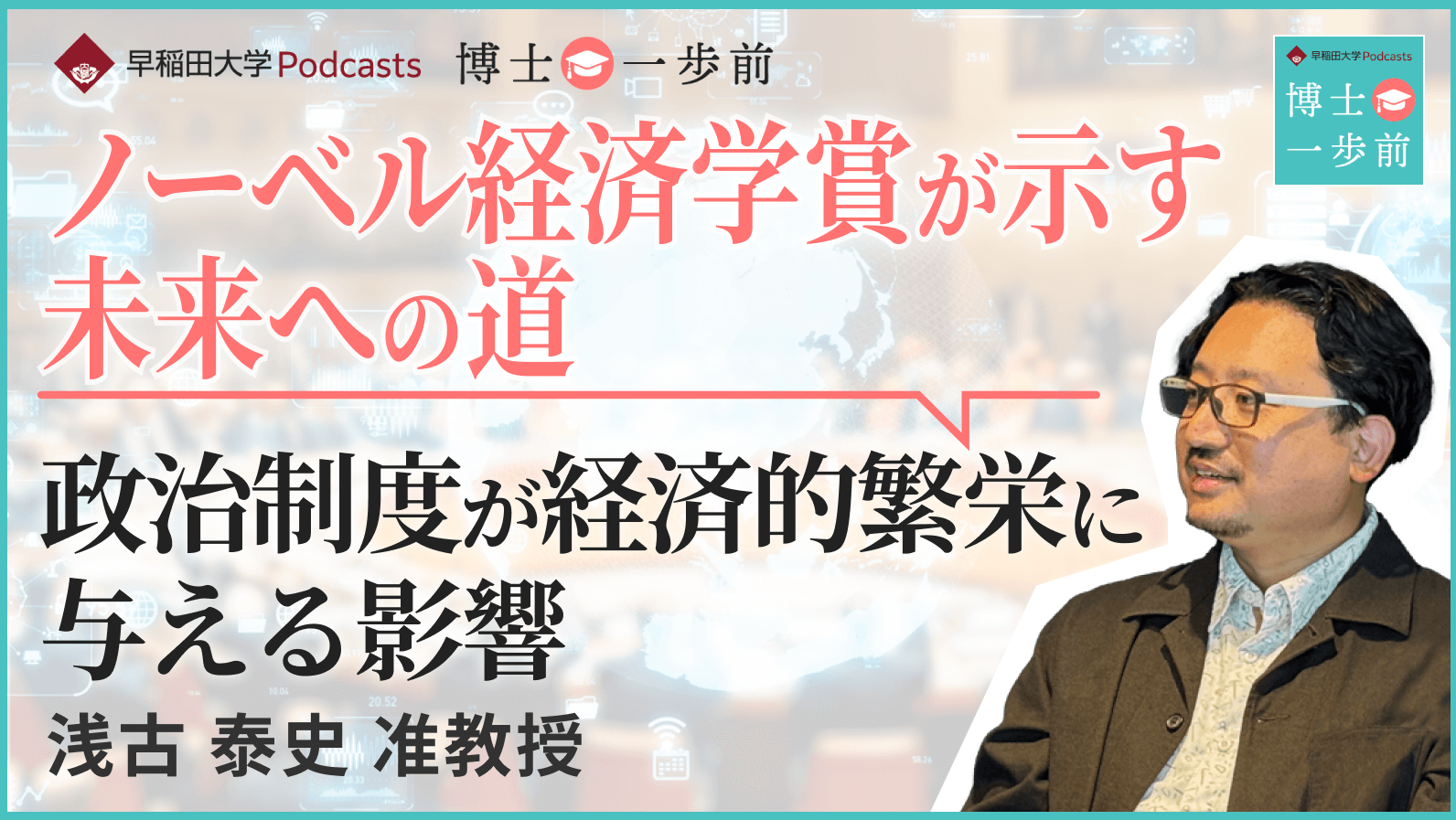- Featured Article
【Podcastコラム】ゲーム理論で制度を分析
Tue 21 Jan 25
Tue 21 Jan 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、政治経済学術院の浅古泰史准教授に制度分析にゲーム理論をどのように活用するか、アメリカ大統領選挙を例に番組内でお話いただいたので、その部分を抜粋してご紹介いたします。
Q. 制度を冷静に分析する手法としてゲーム理論が活用されているが、具体的にどのような制度研究に用いられているのか?
浅古 泰史 准教授: 制度研究として、ゲーム理論が応用されている制度分析はトピックとして非常に幅広く、民主主義から権威主義独裁制の制度、あるいは選挙に関しても単純な小選挙区の選挙からあらゆる種類の選挙手段みたいなところで幅広く分析されています。
その中から具体例で最近起きた事例といえば、アメリカではドナルド・トランプの人気が高く、この前の大統領選挙でも選挙に勝ちました。一方でトランプは極端な政策、移民排斥とか環境問題はあまり重視しない、極端な政策を提言実行する人になります。
問題は多くの人がこれは極端なことを言っているなと感じていたとしても、トランプは人気があり、選挙に勝つことができる。一部の人から人気があるだけではなく、当然選挙に勝っているわけなので、極めて多くの人がトランプを支持していたわけです。それを考える時に人によってはトランプを支持する人は愚かだ。トランプを支持する人たちは騙されているといった言い方がされる向きもあります。
ただゲーム理論を使って考えていくことによって、そのような結論ではなく、もう少し冷静に状況分析できるという部分はあります。こういうトランプ自身もそうですし、極端な政策をわざわざ掲げてアピールする政治家や政党の行動はポピュリズムと言われています。ポピュリズムに共通してみられることが「私は既存の政治家とは違う」ことをアピールしている点です。
特に私は既存の腐敗した、あるいは利益団体と癒着した政治家とは違うことをアピールしたいわけです。ただ言葉だけでは仕方がありませんし、やっていることが既存の政治家や政党と同じことでは既存の政治家とは違うと信じてもらえません。信じてもらうためには、既存の政治家や政党が絶対に口にせず実行しない政策を提言して差別化を図るという戦略をとっていくことになります。

移民排斥など人権にも関わる極端な政策を実行する、あるいは支持することで今までの腐敗してきた政治家とは違うと信じてもらおうとするわけです。自分は既存の政治家とは違うというメッセージ、言い換えればシグナルを有権者に送って信じてもらおうとする行動であるため、ゲーム理論ではシグナリングと呼ばれています。
この前の大統領選挙におけるトランプの支持者たちのインタビューから政策が極端であり、そしてアメリカに分断を引き起こすことを不安視している声も多くありました。ただ一方で政治を変えたいがために支持していると答えたりもしています。既存の政治家とは違う人を選びたいという思いが極端な政策は嫌であったとしても、そのような政策を掲げる政治家を支持する理由と言えます。
このポピュリズムの研究で、既存の政治家とは違う差別化を図りたくて極端に走ることを示した研究がいくつもあって、その中の一つに先ほど話していたノーベル賞のアセモグルの研究も含まれています。私の行ってきた研究と関わるものとしては、多選禁止制があります。多選禁止制は何度も選挙に出る、勝利することを禁止する制度です。
例えばアメリカの大統領では一期二期まで務めたら三期目は選挙に出ることができません。これが多選禁止制になります。アメリカでは多選禁止制は大統領だけではなく、一部の州では知事、衆議会議員にも課されているものになります。これはアメリカでは国民の大きな支持を得て住民たちが強くこの多選禁止制の導入を求めて自分たちで法案を提案し、住民投票で可決した州が多くあります。

根底にある考え方はベテランの政治家は腐敗しているというイメージです。ベテランになればなるほど、利益団体と癒着をして汚い政治をしているに違いないと考える人が多くいて、ベテランの政治家を一層して新しい人に取り換えればいいと考えていました。そうすることによって無駄な支出も減り、減税もできるはずだと議論されていたわけです。
しかし実際に州知事や州議会で多選禁止制が導入した後、データ分析してみると、むしろ財政支出が増えて増税が行われたということが示されています。つまり当初意図したことと反対のことが起こっていることになります。ゲーム理論的な解釈としては、当然多選禁止制は政治家が次の選挙に出ることを禁止するだけではなく、有権者が選挙においてその人を選ぶ権利も奪っていることになります。
例えば政治家にとっては次の選挙がもうない、最後の任期がすぐくるわけですから、それなら好き勝手やろうと思ってしまうかもしれません。選挙に勝つ必要はもうないからです。有権者も本当は有能な人を選挙で選抜していきたいのに、その人が引退してしまったら、もう一度新しい人から選ばなければいけなくなります。そういう選挙の機能をなくしてしまっているという意味で多選禁止制は、むしろ政治家に好き勝手なことをさせて、その質を下げているのではないかということが指摘されています。
多選禁止制の例は我々市民が政治家に対して持っているイメージ、あるいは先入観が結果としてはあまり良くない結果を導き出している例の一つだと思います。それに対してゲーム理論的な手法やデータ分析の手法を通して冷静に見ていくことによって、その制度のあり方を考えることができることを示している事例の一つだと思います。
浅古 泰史 准教授
1978年生まれ。2001年に慶應義塾大学経済学部卒業。2003年に一橋大学で修士号(経済学)取得後、2009年にウィスコンシン大学マディソン校でPh.D.(経済学)取得。日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て、2015年から早稲田大学政治経済学術院准教授として現職。現在の専門は、政治経済学、数理政治学、および応用ゲーム理論。主著に『政治の数理分析入門』(2016年/木鐸社)や『ゲーム理論で考える政治学』(2018年/有斐閣)、『やさしい経済学:政治のゲーム理論分析』 (2021年/日本経済新聞)、『この社会の「なぜ?」をときあかせ!謎解きゲーム理論 (未来のわたしにタネをまこう) 』(2024年/大和書房)など。

城谷 和代 准教授(番組MC)

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。