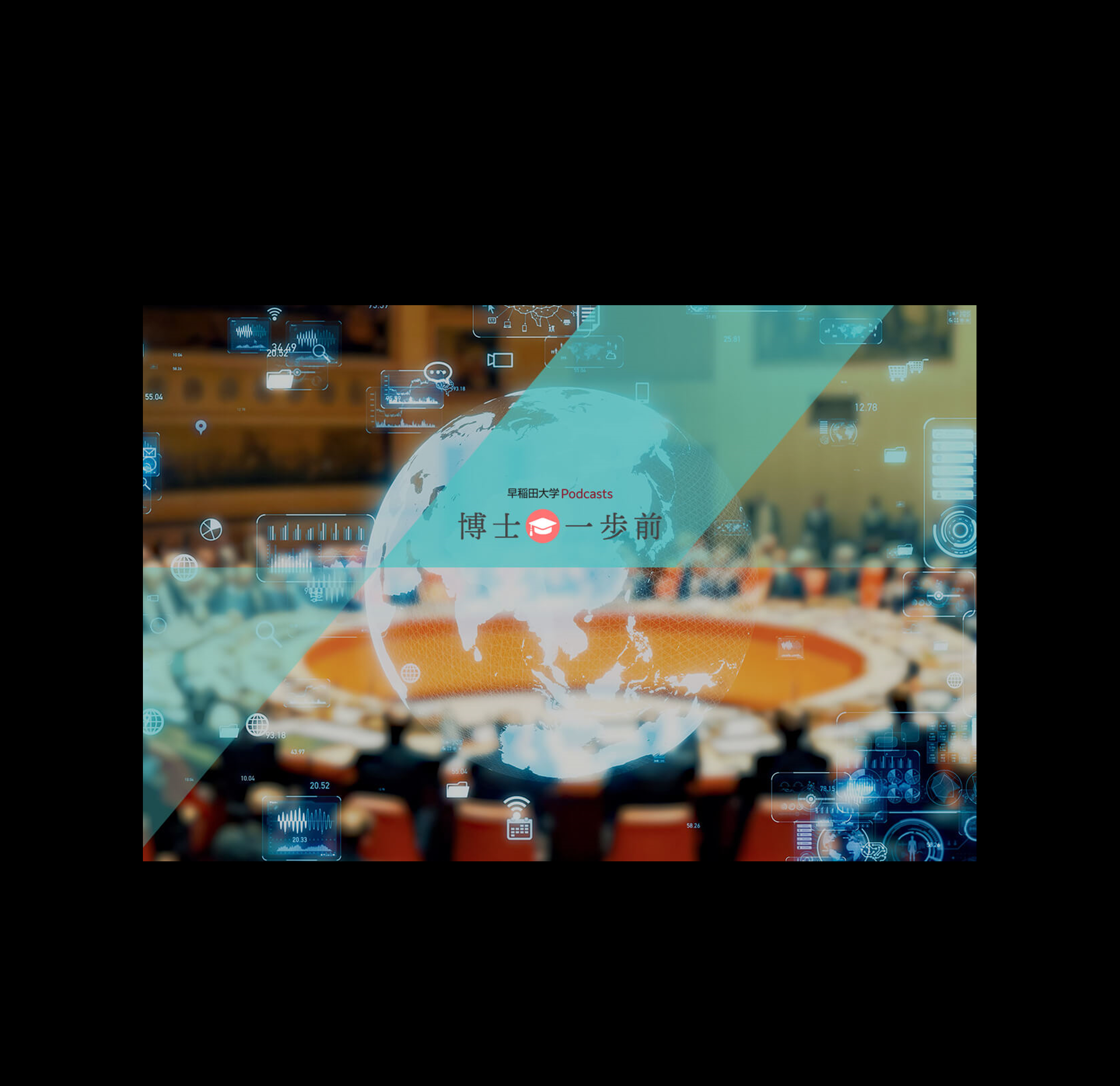- Featured Article
Vol.8 政治経済学(2/2)/【政治と経済に垣根は必要か?】冷静な社会制度分析の重要性/ 浅古泰史准教授
Thu 19 Dec 24
Thu 19 Dec 24
早稲田大学政治経済学術院の浅古泰史准教授をゲストに、「理論で紐解く政治と経済の結びつき」をテーマにお届けします。
後編では、浅古先生がゲーム理論を政治学に応用する道に進み、政治のゲーム理論を一生の研究トピックにすると決意した経緯や政治学と接点を持ったきっかけ、さらに現在のリサーチクエスチョンについてお話しいただきます。
「政治は社会とか人間の営みの中で、一番人間の善良な部分と醜悪な部分が出てくるところだと考えている」と語る浅古先生。
ドナルド・トランプの当選や、少数党政権としての石破内閣などを例に、現在研究している政治的分極化と、独裁下における政治的エリートたちの行動の分析について解説し、さらにこれからの「政治経済学」の今後の展望・期待感についてもお聞きします。
政治と経済の密接なつながりを踏まえ、これらの問題が社会全体にどのような波及効果をもたらすのか?数多くの書籍出版を通じて世の中に伝えたい思いなどについても語っていただきました。
配信サービス一覧
ゲスト:浅古 泰史
1978年生まれ。2001年に慶應義塾大学経済学部卒業。2003年に一橋大学で修士号(経済学)取得後、2009年にウィスコンシン大学マディソン校でPh.D.(経済学)取得。日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て、2015年から早稲田大学政治経済学術院准教授として現職。現在の専門は、政治経済学、数理政治学、および応用ゲーム理論。主著に『政治の数理分析入門』(2016年/木鐸社)や『ゲーム理論で考える政治学』(2018年/有斐閣)、『やさしい経済学:政治のゲーム理論分析』 (2021年/日本経済新聞)、『この社会の「なぜ?」をときあかせ!謎解きゲーム理論 (未来のわたしにタネをまこう) 』(2024年/大和書房)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-

この社会の「なぜ?」をときあかせ! 謎解きゲーム理論
出版社 : 大和書房
著 者:浅古 泰史
出版年月 : 2024年2月15日
言語 : 日本語
ページ数:320ページ
ISBN:9784479394228
-
エピソード要約
-浅古准教授が現在の研究分野に興味をもったきっかけ
浅古准教授は大学で経済学を専攻し、応用ゲーム理論を用いた企業統治(コーポレートガバナンス)を専門に勉強していたが、大学院留学時に指導を予定していた応用ゲーム理論の研究者たちが大学を去り、進路に迷う中、政治学研究科のスコット・ゲイルバック教授の講義ノートを読んだことがきっかけで政治学への関心が高まった。ゲイルバック教授との出会いにより、ゲーム理論を政治学に応用する道に進むことを決意した。
-研究トピックと特に関心を持っている分野
浅古准教授は、政治は人間の善良さと醜悪さが交差する場であり、数理的分析によってその本質を明確に描き出すことに魅力を感じ、政治をゲーム理論やデータ分析することを一生の研究トピックにしたいと考えている。現在は政治的分極化に特に関心を持ち、同じ情報を共有しているにもかかわらず意見が対立する現象や、誤った情報が分極化を促進するメカニズムを論理的に解明することを目指している。
-著書で伝えたいこと
浅古准教授は一般向け書籍や研究を通じて、次世代の研究者や読者に新しい視点を提供したいとの思いを持っている。著書である『この社会の「なぜ?」をときあかせ!謎解きゲーム理論 』は、謎解きの要素を取り入れるなど、一般読者にも親しみやすく、数理的なテーマを分かりやすく伝える工夫がなされている。また自身の著作が学生の政治へのゲーム理論の応用を志すきっかけとなる話を耳にすることがあり、その影響を実感していると述べている。著書を通じて、政治経済学やゲーム理論を通じて社会を冷静に見つめる視点を広めることが、次世代や一般社会にとって価値あるものとなることを願っている。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以下、城谷):
前編までのお話で政治経済学という研究分野におけるゲーム理論を用いた政治制度、経済制度の研究について具体的なイメージが湧いてきましたが、浅古先生はもともと経済学の修士号を取得された後、2009年にウィスコンシン大学で経済学の博士号を取得されています。
そもそも研究者を志すに至った経緯や経済学者である浅古先生が政治学と接点を持たれたきっかけについて教えていただけますでしょうか。
浅古准教授(以下、浅古):
高校生ぐらいから選挙速報などを見るのが大好きで、選挙のニュース、特に総選挙など大きな選挙があった時はずっと見ていました。日本史でも戦国時代といったたくましい時代ではなく、どちらかというと幕末や明治時代など政治的駆け引きが多い時代が大好きで、特に幕末はたくさん本を読んだりして楽しんでいました。ただ、大学に入った時は経済学部にいて、その後、大学院に進学しますが、応用ゲーム理論に興味があって、特にその当時、たくさん行われていた企業の分析、具体的にはコーポレートガバナンスという企業の中に経営者、投資家、労働者、あるいは取引先など、いわゆるステークホルダーといわれている関係者がたくさんいる中での関係を分析し、そういう関係を踏まえた上でどう企業を統治するか、運営していくかという企業の制度な話、コーポレートガバナンスを専門にしようと考えていました。
前半でお話した伊藤秀史先生もこの企業の分析の専門家でいらっしゃって、伊藤先生に「アメリカに留学してみないか」という話を持ちかけられて、いくつか出願した先でウィスコンシン大学マディソン校に進学しました。
進学した段階では、いわゆる応用ゲーム理論を企業に使う人、あるいは公共経済学というNGOみたいな公共の問題を考える人とか、複数いらっしゃったのですが、留学して1年生が終わる時、応用ゲーム理論の研究者たちがこぞって大学を去ってしまいました。
アメリカの大学は特にですが、大学間を研究者が行き来することは頻繁にあって、この人に着きたいと思って留学先を選んでもいなくなることはよくある話ですが、こぞっていなくなってしまい、どうしようかと途方に暮れてしまいました。
その中で経済学研究科にいらした先生から政治学研究科にスコット・ゲイルバックというゲーム理論を主に用いて政治を分析している先生がいるという話を聞きました。
その日のうちに彼のウェブサイトに行って、そこに貼ってあった彼の講義ノートをダウンロードして読みましたが、ものすごく面白くて、2日、3日で全部を読み切り、この人に指導を仰ぎたいなと考えました。
実際にゲイルバック先生のところに行くと、先生も私を快く迎え入れていただいて、政治にゲーム理論を応用していく研究をしていこうと。元々高校生の時から政治的な駆け引きや選挙とかが大好きで、それを専門にしようとは思っていませんでしたが、専門とする先生がいらしたので。ゲイルバック先生自体はどちらかというと権威主義、独裁性、ロシアあたりを分析対象とされている方でしたが、そういう理由で政治にゲーム理論を応用していこうと決めました。
城谷:
2、3日で急展開だと感じましたが、そんな感じでしたか。どうしようと思っていましたか。
浅古:
本当にどうしようと思っていて。もともとゲーム理論や数理的な分析が好きで、正直言うとあまりデータを使うのは得意ではありませんでした。そこまで好きではなかったですが、その時は研究者が全員いなくなったので、もうデータをやるしかないだろうなといくつか授業を受けましたが、やはり難しいというか私の中ではしっくり来なかったので、どうしようかと本気で2年生の間は悩んで右往左往していましたが、その後半ぐらいだったと思いますが、ゲイルバック先生との出会いが大きかったと言えます。
城谷:
急展開の出会いからやはり研究者として応用ゲーム理論を政治学に応用していくという歩みを決意されたということですね。
浅古:
実際にこの分野に入ってみて、いろいろやっていく中で冷静に政治を見つめていく視点が面白くて、政治は社会や人間の営みの中で、一番人間の善良な部分とある意味醜悪な部分がものすごく出てくるところだと思います。
特に政治的な状況は、経営など投資家、経営者、労働者は対立しつつ、ある程度同じ方向を向くと思いますが、政治だとやはり全然違う方向をみんなが向いている中でバラバラな人を取りまとめていく話になる。
そうするともう政治はものすごく得体の知れないものになっていくし、我々の目からはあまりちゃんと見えないものになっていく。それを数理的分析で明確に綺麗にそして説得的に見せられるものなのだと特にそのゲイルバック先生の授業とその他の論文とかを読み進めているうちに理解していって、そういう人間の営みの本質的な部分を明確に描き出す作業にワクワクするようになって、この分野を一生のトピックにしていこうと考えるようになりました。
城谷:
経済学と政治学の垣根を越えた研究を行ってこられた浅古先生の研究キャリアについて興味深くお聞かせいただきました。改めて現在の浅古先生が抱かれている政治経済学の今後の展望、期待感、そして当分野で浅古先生が特に関心を持って研究されている現在のリサーチクエスチョンについて教えていただけますでしょうか。
浅古:
政治のゲーム理論を使った分析という意味で言えば、実際の我々の社会でも政治でも常に新しく意外なことが起こっていく。よく事実は小説より奇なりと言いますが、現実の政治の世界でも様々な問題や出来事が起こっていく。
例えばアメリカではドナルド・トランプが選挙に勝つとか、あるいは日本でも2024年の衆議院総選挙では、選挙の結果、石破内閣は維持されましたが、少数党政権になりました。
少数党政権とは議会の中で過半数に満たない政党、あるいは複数の政党が連立を組んで政権を維持するという状況で、ヨーロッパではよく見られる話ですが、日本ではあまり経験のないことで、みんな結構衝撃を持って選挙結果を見ていたと思います。
ただその少数党政権自体も実は昔からある程度の数理的な分析もされており、データを使った分析もされているので、こういう新しい出来事が政治の世界で起こるたびにトピックが増えていく。
前回お話したドナルド・トランプの登場は、ポピュリズム研究をより深めることにもなりましたし、その現実に起こった出来事の良し悪しは別にして、我々が考えないといけない問題を常に社会や政治は新しくもたらしてくれると考えています。
その中でも最近は主に2つのことに興味を持って研究しています。
1つは政治的分極化です。分極化とは人々の意見や好みの政策が大きく離れていくことです。例えばアメリカでも民主党とドナルド・トランプが率いる共和党の支持者の間で大きな意見の対立が起こっています。コロナ禍以降では日本でもこういう意見の分極化、政治的分極化が目立ってくるようになりました。当然人種や宗教、年齢など個々の背景が異なることで意見や好みの政策が違ってくることはあります。
ただ近年では背景がそんなに変わっていない、かつ同じ情報を人々が見ているにもかかわらず、意見が大きく隔たっていく分極化が生じています。
例えば政府が同じ情報を何度もアナウンスして広げようとしても、全くその意見の隔たりがなくならないような状況です。なぜ同じ情報を見ているのに意見や好みの政策が変わってくるのか。分極化をもたらすような誤った情報が広がりやすいのはなぜか。そういう問いに対して愚かな人々がいるからだと単純に答えを出すのではなく、分極化をもたらす状況を論理的に説明していきたいと思っています。
2つ目として民主主義ではない独裁制、権威主義とも言いますが、その独裁下における政治的エリートたちの行動を分析していくことにも興味があります。
民主主義とは違って政治的エリートたちを制約するような法律が独裁の国にはないため、政治的競争、選挙などの政治的リーダーの選び方、政策の決め方などに明確なルールはなく、かつお互いにいつ裏切られるか分からない疑心暗鬼に満ちたものです。
権威主義は明確なルールの中で人々がゲームをすると考えるゲーム理論では分析しにくい対象でしたが、近年になって研究が一気に進みました。
ちなみに前半で少しお話させていただいたダロン・アセモグルもそういう研究を行っている一人です。権威主義には色々なタイプがありますが、それが共通するような特徴を考えていこうと研究がなされています。
その中でも特に政治的リーダーが力を強めて安定的な政権を築く過程に個人的には興味があります。
一人の力が高まっていけば、他の政治的エリートたちは危機感を感じて引きずり下ろそうとするでしょう。それにもかかわらず一人が力を強めて個人独裁化していくケースは多くあります。なぜ一人が力をつけていくことを許されるのか。そしてどのように安定的な政権を築いていくのかに関して興味を持って研究しています。
城谷:
他の政治学の分野の先生と一緒にコラボされているとのことでしたが、例えば、先生のご著書である『ゲーム理論で考える政治学 — フォーマルモデル入門』の中のコラムで触れられている2009年にノーベル経済学賞を受賞したエリノア・オストロム氏は政治学と経済学の間に垣根を作ることは不毛だと示した、とありますが、まさにそういったところでしょうか。
浅古:
オストロムさんという方は、もともと政治学者で政治学のバックグラウンドを持っていて、政治学界でも活躍されている方でした。一方でノーベル賞の方は、ノーベル経済学賞と言われていて、その経済学賞を政治学の方が受賞されたということで、話題になっていた年になります。
ちょうどこの年、私自身も大学院を卒業して博士号を取って、ちょうど就職活動していた年になります。やはり経済学的な手法を、特にゲーム理論やデータ分析を使って政治を考えることには一定の批判はあると思います。
ただ一方で、特にこの2009年の前後からアメリカ、そしてその後は日本でも、こういうゲーム理論やデータ分析を使って政治を考えていこうという人は急激に増えていきました。
その中でこういう手法に関しても、政治学でも受け入れられて、広がっていると言えます。
同じように我々のこの社会を見た時には政治だけ考える、あるいは経済だけ考える、ということではなく、やはり政治も経済も幅広く我々の社会で起こっていることを理解していくのは大切だと思います。
そういう意味では、同じ社会科学をやる人たちとして向いている方向は一緒であるはずなので、そういう経済学と政治学の垣根を外して交流していくことは大事だと思いますし、私自身も経済学だけではなく、政治学の学会に参加させていただき、議論する、あるいは政治学者の方々と一緒に研究ができていて、とても楽しいと思っています。
城谷:
浅古先生は一般向けから専門を志す人向けに直近の大和書房から『未来のわたしにタネをまこう』のシリーズで刊行されている『この社会の「なぜ?」をときあかせ!謎解きゲーム理論 』をはじめ、これまでいくつかの書籍を出版されています。
一般の読者の皆さんや当分野に関心を持つ次世代の研究者の皆さんに対して、これらの書籍を通じ、どのような思いを伝えていきたいか浅古先生のメッセージをいただけますでしょうか。
浅古:
先ほど政治学の中でゲーム理論などの数理分析を用いることが広がっていると言いましたが、日本と欧米、特にアメリカと比べると、日本ではそれほどまだ広がっていないのが事実です。
経済学のようにデータを用いて分析している政治学者の方はたくさんいらっしゃり、そのような方々と数理モデルをデータで検証するタイプの研究はできていますが、数理分析をメインの分析手法とされる政治学者の方は現状でも数えるほどしかいらっしゃいません。
私は政治を冷静に考えるために、あるいはデータ分析に向けての仮説を提示するために、数理分析の視点はとても大切だと思いますし、数理分析自身もとても重要だと思っています。
また私自身が政治を数理的に分析する研究がとても楽しいというか、大好きという思いが強いので、その重要性とか楽しさを広げたい思いで社会の一般の方々や若い研究者、志願の方々へのアウトリーチとして書いてきました。
特に経済学では、こういう日本語で書いた本は業績として数えられないことが多いですが、本を書ける機会を多くいただけたこと、かつ政治への応用を話せる研究者の方が少なかったので、そういう輪を広げていきたいなという思いから私が書くべきだろうと思って書いてきました。
最近になって大学院生や若手の研究者の方々からゲーム理論の政治への応用研究を志すことになったきっかけは私の本であったと聞いたことが2回くらいあって、それはとてつもなく嬉しくて、私自身が留学先でゲイルバック先生の講義ノートを読んで、大きなきっかけになったようなことが少なからずでき始めているのかなと感じて、とても嬉しく思っています。
城谷:
浅古泰史先生とともに『理論で紐解く政治と経済の結びつき』をテーマにお話をお届けしてきました。最後に浅古先生から今日の収録への感想を一言お願いできますでしょうか。
浅古:
自分のことを話すのは得意ではないのですごく恥ずかしかったですが、同時に先ほども言ったように政治経済学の視点やゲーム理論で政治を考える視点というのは今研究者の方向けでお話しましたが、今回の『(この社会の「なぜ?」をときあかせ!)謎解きゲーム理論 』とかは一般の方向けでそういう数理的に政治を考えるとか社会を見つめる視点は冷静に物事を考える上でとても大切だと思っていて、そういうことを広げていく一環になれば嬉しいなと思っていたので、恥ずかしさを感じながらもお話させていただきました。
城谷:
『謎解きゲーム理論』、私も拝見させていただきましたが、色々な理論のご説明の他にとっつききやすい探偵物語というストーリーも入っているので、一般の読者にもすごく手に取りやすいかなと思いました。
浅古:
一応各章のトピックに合うようなミステリー小説の抜き書きみたいな形で入れていこうと、最初に本を書くときに私からアイデアを出して、いいですねとなったのですが、最終的にここが一番大変だったというか、つながりのある形で書き慣れないミステリー小説を抜き書きとはいえ書かなければいけないのはだいぶ時間を費やしましたが、そこも含めてぜひ見ていただければ嬉しく思います。