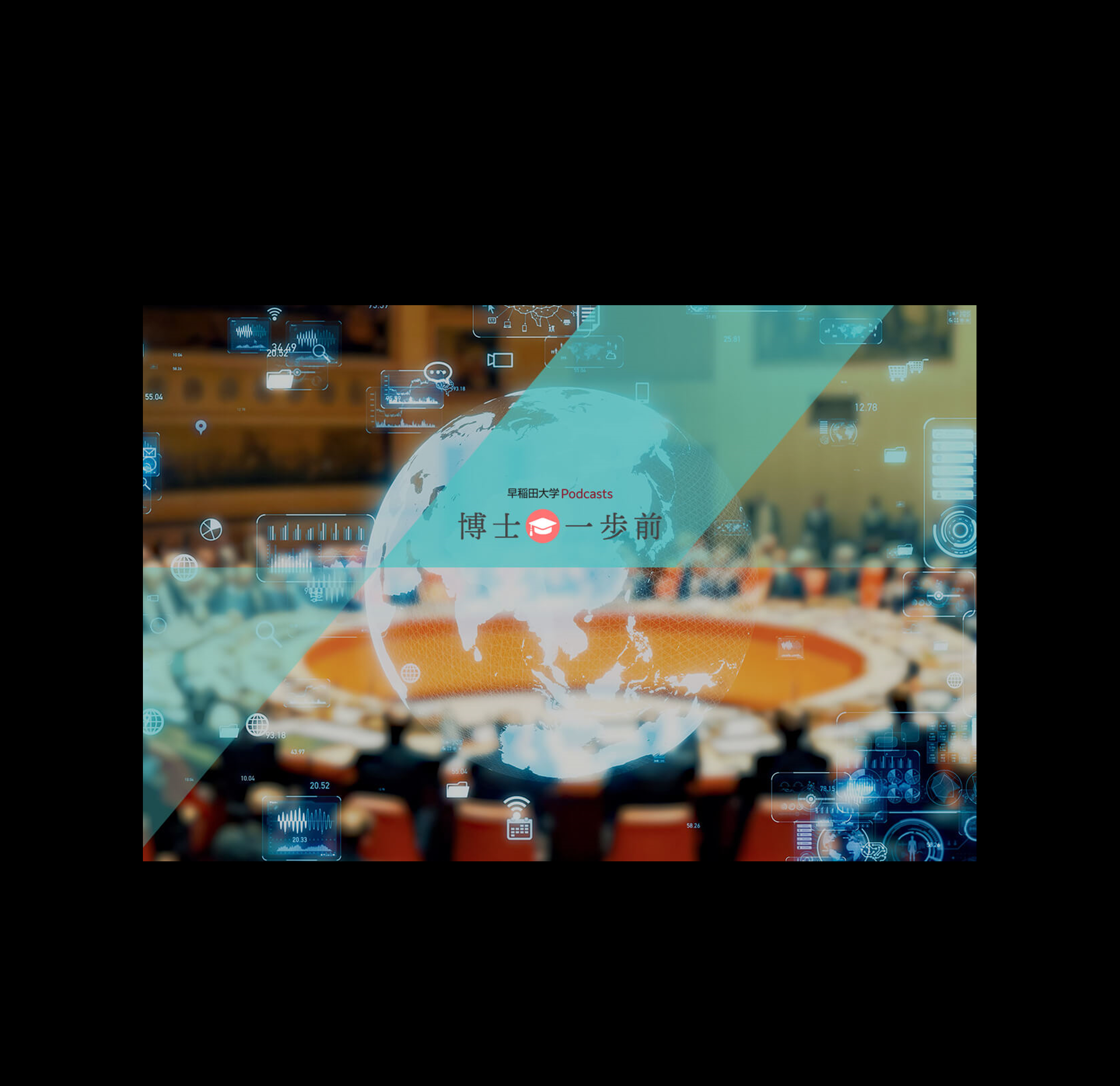- Featured Article
Vol.8 政治経済学(1/2)/【ノーベル経済学賞が示す未来への道】政治制度が経済的繁栄に与える影響/ 浅古泰史准教授
Thu 12 Dec 24
Thu 12 Dec 24
今回と次回の二回に渡り、早稲田大学政治経済学術院 の浅古泰史准教授をゲストに、「理論で紐解く政治と経済の結びつき」をテーマにお届けします。
2024年、ノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル教授らの『社会制度が国家の繁栄に与える影響及び制度の形成に関する研究』によって、政治経済学という分野が世界的に大きな注目を集めています。
「政治制度がどのように経済の発展に影響を与えるか」
政治経済学の研究における数理的アプローチの意義と、その応用例として、政治制度、民主化のプロセス、ポピュリズム政治家の行動原理、多選禁止制の影響などをゲーム理論を使って解説。さらに、数理分析を通じて現代社会の課題にアプローチし、制度改革の哲学的背景やその限界についても考察します。
配信サービス一覧
ゲスト:浅古 泰史
1978年生まれ。2001年に慶應義塾大学経済学部卒業。2003年に一橋大学で修士号(経済学)取得後、2009年にウィスコンシン大学マディソン校でPh.D.(経済学)取得。日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て、2015年から早稲田大学政治経済学術院准教授として現職。現在の専門は、政治経済学、数理政治学、および応用ゲーム理論。主著に『政治の数理分析入門』(2016年/木鐸社)や『ゲーム理論で考える政治学』(2018年/有斐閣)、『やさしい経済学:政治のゲーム理論分析』 (2021年/日本経済新聞)、『この社会の「なぜ?」をときあかせ!謎解きゲーム理論 (未来のわたしにタネをまこう) 』(2024年/大和書房)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-

この社会の「なぜ?」をときあかせ! 謎解きゲーム理論
出版社 : 大和書房
著 者:浅古 泰史
出版年月 : 2024年2月15日
言語 : 日本語
ページ数:320ページ
ISBN:9784479394228
-
エピソード要約
-数理分析の魅力
数理分析の魅力として、社会や政治の現象に対して曖昧な解釈ではなく、なぜそうなるのかを具体的に突き詰めて論理的に考える視点を提供する点を挙げている。数理分析の手法であるゲーム理論やデータ分析を用いることで、ポピュリズムや多選禁止制などの制度に対する先入観を排除し、その本質や影響を冷静に考察できる。
-ノーベル経済学賞を受賞したアセモグル氏の研究内容について
今年(2024年)のノーベル経済学賞を受賞したアセモグル氏らの研究では、政治制度と経済制度が国家の繁栄に与える影響を分析する重要性について触れ、その中で政治的リーダーへの制約が経済成長や国家の安定にどのように寄与するかを解説している。この研究は、新しいデータや手法を用いて、制度が国家の繁栄に与える影響を従来よりも明確に抽出し、制度形成における因果関係を解明した点で画期的である。
– ゲーム理論と応用ゲーム理論の違い
ゲーム理論は複数の意思決定が相互に影響を及ぼす状況を数理的に分析する手法(道具)であり、応用ゲーム理論はその道具を現実社会に適用して具体的な問題を分析することに焦点を当てている手法である。またゲーム理論には協力ゲーム理論と非協力ゲーム理論があり、非協力ゲーム理論は現実社会での意思決定が協力不可能な状況で役立つため、応用が多い。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以下、城谷):
浅古先生は2001年に慶応義塾大学経済学部を卒業、2003年に一橋大学で経済学の修士号を取得後、2009年にウィスコンシン大学マディソン校で経済学の博士号を取得されました。その後、日本銀行金融研究所エコノミストなどを経て、2015年から早稲田大学政治経済学術院の准教授に就かれています。現在のご専門は政治経済学、数理政治学、及び応用ゲーム理論です。改めまして浅古先生からご専門分野の概要と、この収録を通じてリスナーの皆さんにお届けしたい研究領域の魅力について、簡単にご説明をお願いしたいと思います。
浅古准教授(以下、浅古):
皆さんこんにちは、浅古泰史です。私の専門分野は政治経済学、数理政治学、応用ゲーム理論です。政治経済学とは、政治だけとか、経済だけで分析していくのではなくて、政治と経済の相互関係を考えながら分析していく分野になります。その中で一つの方法として取られているのが、ゲーム理論などを使った数理分析、数学を使った分析です。あるいはデータを使った分析になります。数理モデルで仮説を示して、データ分析で事実を知っていく形で分析をしていきます。その中で私は特に数理分析の部分をやっている研究者です。これらの数理モデルやデータ分析を使って客観的に、かつ論理的に事実を基に政治を見ていこう、あるいは政治と経済の関わり合いを見ていく視点を持つことになります。特に数理分析はなぜこんなことになるのかという疑問を社会に対して持った時に、それに曖昧な答え方をするのではなく、なぜそうなるのかをきちんと今起こっていることを突き詰めて、論理的に考えていく部分が魅力的な分野かと思います。
城谷:
社会は人間くささがたくさんあると思っています。その中では曖昧なところも出てくるかと思いますが、応用ゲーム理論を用いることで、客観的であるとか、論理的になぜかというところをつめていけると理解しました。
浅古:
例えば、「永田町の論理」と言って、政治家は得体の知れない存在だと考える。あるいは有権者なり政治家が自分にとって、納得がいかない行動をとっていた時に、彼らは愚かであるみたいな形で片付けるのではなくて、なぜそのような行動をとるのか、どうしてこういうことになるのかを論理的に考えていく。それを人間が生きている社会に当てはめて、しっかりと考えていくことになると思います。
城谷:
ありがとうございます。前半では浅古先生の研究分野について深掘りしていきたいと思います。浅古先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
浅古:
よろしくお願いします。
城谷:
2024年秋を迎えていますが、秋といえばノーベル賞受賞の話題が一つ上がってくるかと思います。今年のノーベル経済学賞はダロン・アセモグル教授、サイモン・ジョンソン教授、そしてジェームズ・ロビンソン(ジェームズ・A・ロビンソン)教授のお三方が受賞されました。彼らは社会の制度が国家の繁栄に与える影響及び制度の形成に関する研究への功績で受賞されましたが、政治制度が経済成長にどれほど深い影響を与えているかを解明した彼らの研究は浅古先生のご専門にも関わりが深いとお聞きしております。具体的にどのような研究だったのかご説明いただけるでしょうか。
浅古:
最初の制度が国家の繁栄に与える影響の分析に関してですが、制度は主に政治制度と経済制度、この二つに焦点を当てています。政治制度は端的に言えば、どれだけ政治的リーダーの権力あるいは権限に制限が与えられているかどうかになります。例えば選挙、議会の強さ、あるいはメディアや司法などからの監視などが強ければ強いほど、それだけ政治的リーダーは自由に意思決定できなくなります。そういう制約がどのくらいあるのかが政治制度になります。もう一つが経済制度。経済制度もいろいろありますが、一番焦点を当てているところは所有権の保障です。例えば誰かが一生懸命働いて稼いで新しい事業を起こして、新しい富を得た場合、その富を政府が奪う可能性は特に独裁制の国とかでは多いと思います。そういうことはなく、きちんとあなたの富を保障してあげるよと所有権が保障されているか否かになります。そのため、こちらの経済制度の方も多少その政治的な部分もある制度になります。そして例えば政治制度でリーダーの力に制約があるほど、経済制度の方で所有権が保障されているほど民主的な政治になっていると解釈でき、またその逆の場合は独裁的になっていると解釈できます。彼らはより民主的な制度であればあるほど、経済成長にプラスである。つまり国民所得などを高めることができることをデータにて示しました。二つ目のその制度の形成の部分ですが、その制度で彼らが示したのはより民主的な制度というのを政治的リーダーが導入する状況があって、それはどういう状況で生じ得るかを数理的に分析しています。つまり民主化が起こるときには当然革命のようなボトムアップで民衆の側から起こす場合もありますが、歴史上多くのケースでは政治的リーダー、大統領なり政治家たちが自らの手で民主化を許していく、参政権など民衆の権限を拡大していきます。なぜトップダウンの民主化が起こるのか、彼らは数理的に分析していくことになります。そして彼らが示しているのは、端的に言えば、民衆の革命を避けるために自らの手で民主化をトップダウンで行っていくと指摘されています。特に革命の機運が高まってくると再配分などを通して、彼らに富を分け与えることによって革命を抑えようとします。それでも今の時点で革命の機運が高まっていて富の分配によってそれを抑えることができたとしても、民衆の側からしたら明日もしくは将来に革命の機運はもう来ないかもしれない、革命のチャンスはもう来ないかもしれないと考えます。そうすると政治的リーダーはより多くの富を民衆に与えないと革命を抑えることができません。しかし国の富には限りがあるので、そこで革命を抑えきれないときに政治的リーダーは自らの手で民主化することが指摘されています。以上の二つが主に彼らがノーベル賞を受賞した理由とされている研究になります。
城谷:
少しお話が戻ってしまいますが、社会制度の中で民主的な制度の対極として、独裁制度というお話があったと思いますが、それを民主的な制度、独裁制度と見るのはグラデーションがあるのでしょうか。それとも二極化しているものなのでしょうか。
浅古:
基本的にはグラデーションで見るものだと思います。民主主義の指標のデータはいくつかあります。グラデーションで見ていないものもありますが、ほとんどが何段階かのグラデーションで民主化の度合いを測ることになります。ここでもリーダーの力にどれだけの制約があるかに関して、選挙がどれだけ競争的か、メディアの自由がどれだけ守られているかなど、ある程度の段階を踏むものなので、そういう意味ではグラデーションがあると思います。
城谷:
彼らの研究は従来の定説に比べて、どのような点が画期的だったのでしょうか。彼らのどういった点にインパクトがあったのかについて、先生の視点からご説明いただけますでしょうか。
浅古:
最初の制度が国家の繁栄に与える影響の部分に関しては、当然、政治制度が民主的になれば国家を繁栄するという因果関係と、国家が繁栄したから国民がより多くの権利を政府に求めて交渉力を持つようになってくるから、民主化が行われるという両方の因果関係があると思います。彼らはその当時としては新しいデータや手法を通して、その因果関係を明確にする、つまり制度が国家の繁栄に与える影響を抽出する手法を使って研究をしています。後者の制度の内政的な形成に関しても、新しい形でゲーム理論を構築しているという意味では当時としてはかなり新しかったものです。ただし、このデータ手法や仮説そのものに関してはその後、反論が多数出ています。そのため、今の時点から見ると当然色々な問題点はありますが、実際に政治と経済の関わりをしっかりと考えていく、しかも同時に制度の中でも特に政治制度の形成。つまりどのように人々や政治家がその制度を選んできたかという過程をしっかりと分析していこうという先駆的な研究の一つでした。その後、政治学、経済学でも政治と経済の関わりにもっと着目し、制度の選択に関してもっときちんと分析していこうという機運は高まっていきます。もちろん同時代にいくつか同じような研究はありますが、アセモグルたちの研究が一番インパクトや影響力が大きかったと言えると思います。
城谷:
今の時点では議論の余地が出てきているとのことですが、当時では新しい研究の流れを作ったと考えてもよろしいですかね。
浅古:
そういうことになりますね。例えば経済学において、それまでは発展途上国で経済的に貧しい国があった場合、それは地理的な問題だとか、純粋にお金がないから資金を投入して助けてあげようというような考えを持っていましたが、彼らが示したのは政治制度そのものに問題があれば、それだけでは解決できないかもしれないという視点であり、その視点は大きく広く共有されるようになっていますし、政治制度に関しても、従来の研究では政治制度とは例えば選挙がありますよ、議会がいますよということを与えられたもの、変えられないものとして分析することが多かったのですが、それは政治家の手によって変えられるものではないかという考え方が一般的になり、研究も行われています。
城谷:
今回の受賞について、先生の研究分野の方々はどういった反応でしたか。
浅古:
実際のところ、今回の受賞はなんとなく予想されていたところがありました。特にアセモグルはいつか取るだろうと去年ぐらいから言われていたのと、今年はノーベル賞の審査員の方にも同じ分野、政治経済学の人が入っていたので可能性は高いと予想はされていましたが、自分の分野が着目されるようになったのは純粋に嬉しいと感じている人は多いです。
城谷:
これまでの話の中でゲーム理論という言葉が何回か登場しています。浅古先生のご専門である応用ゲーム理論とゲーム理論はどのような使い方の違い、定義があるのでしょうか。
浅古:
ゲーム理論とは一般的にたくさんの人々の意思決定の中で、お互いの意思決定がお互いに影響し合うような、まさしく社会にありうることを分析している数学的手法になります。一般的にゲーム理論を専門にして、論文を書きますといった場合、この分析の数理的手法の開発をしていくことになります。言い換えれば道具の開発です。その開発された手法、道具を使って、現実に当てはめて分析するのが応用ゲーム理論です。ゲーム理論自体の基本的なモデルに関しては、曖昧な戦略やプレイヤーなど具体的な登場人物も具体的な名前も与えずにやりますが、それを現実に応用する時に一部設定を変えながら、道具の開発としてはそこまで大きくない貢献だったとしても、その道具を使って現実の社会に当てはめた時にどういう結論を導けるかを分析しているのが応用ゲーム理論になります。
城谷:
ゲーム理論の研究者と応用ゲーム理論の研究者の割合はどうでしょうか。ゲーム理論もしながら応用ゲーム理論もすることはありますか。
浅古:
もちろんあります。ゲーム理論を現実に応用するツールであることはみんな分かっていますので、ある程度、現実への応用と一緒に発展することはあります。例えば90年代とか2000年代にゲーム理論の中で情報の非対象性、ある人は情報を持っているが、他の人は情報を持っていないといった状況を分析するゲーム理論のモデルがたくさん開発されましたが、その時は例えば経営学への応用が強く意識されながら同時に道具も発展していく、そういう経済学では数理分析もデータ分析も両方、ある程度何を分析したいかに合わせて、新しい道具を作りましょうとなるので、重なってやっている方もたくさんいらっしゃいます。
城谷:
少し話がずれてしまいますが、ゲーム理論の応用の多くは非協力ゲーム理論に基づいていると先生のご著書を拝見して、書かれていたところですが、この点について、お話いただいてもよろしいでしょうか。
浅古:
ゲーム理論には協力ゲーム理論と非協力ゲーム理論という大きく分けて二つのタイプに分けられています。協力ゲーム理論はお互いに協力をして協調し合えた場合、どういう結果になるかという意味で、お互いの協力を与えられたものとして、その協力ができる状況を考えた上で分析しているものです。非協力ゲーム理論はそれを考えずに分析します。ただしみんな自由に協力せずに意思決定をした結果、みんな協力することを選びましたという結果は当然あり得ます。応用としては協力できるものだと最初から考えるよりかは、実際の社会でもお互いに協力ができない状況の方が多いので、非協力ゲームの方が使いやすいことになります。
城谷:
制度を冷静に分析する手法としてゲーム理論が活用されていることを理解できました。具体的にどのような制度研究に用いられているかについて教えていただけないでしょうか。
浅古:
制度研究として、ゲーム理論が応用されている制度分析はトピックとして非常に幅広く、民主主義から権威主義独裁制の制度、あるいは選挙に関しても単純な小選挙区の選挙からあらゆる種類の選挙手段みたいなところで幅広く分析されています。その中から具体例で最近起きた事例といえば、アメリカではドナルド・トランプの人気が高く、この前の大統領選挙でも選挙に勝ちました。一方でトランプは極端な政策、移民排斥とか環境問題はあまり重視しない、極端な政策を提言実行する人になります。問題は多くの人がこれは極端なことを言っているなと感じていたとしても、トランプは人気があり、選挙に勝つことができる。一部の人から人気があるだけではなく、当然選挙に勝っているわけなので、極めて多くの人がトランプを支持していたわけです。それを考える時に人によってはトランプを支持する人は愚かだ。トランプを支持する人たちは騙されているといった言い方がされる向きもあります。ただゲーム理論を使って考えていくことによって、そのような結論ではなく、もう少し冷静に状況分析できるという部分はあります。こういうトランプ自身もそうですし、極端な政策をわざわざ掲げてアピールする政治家や政党の行動はポピュリズムと言われています。ポピュリズムに共通してみられることが「私は既存の政治家とは違う」ことをアピールしている点です。特に私は既存の腐敗した、あるいは利益団体と癒着した政治家とは違うことをアピールしたいわけです。ただ言葉だけでは仕方がありませんし、やっていることが既存の政治家や政党と同じことでは既存の政治家とは違うと信じてもらえません。信じてもらうためには、既存の政治家や政党が絶対に口にせず実行しない政策を提言して差別化を図るという戦略をとっていくことになります。移民排斥など人権にも関わる極端な政策を実行する、あるいは支持することで今までの腐敗してきた政治家とは違うと信じてもらおうとするわけです。自分は既存の政治家とは違うというメッセージ、言い換えればシグナルを有権者に送って信じてもらおうとする行動であるため、ゲーム理論ではシグナリングと呼ばれています。この前の大統領選挙におけるトランプの支持者たちのインタビューから政策が極端であり、そしてアメリカに分断を引き起こすことを不安視している声も多くありました。ただ一方で政治を変えたいがために支持していると答えたりもしています。既存の政治家とは違う人を選びたいという思いが極端な政策は嫌であったとしても、そのような政策を掲げる政治家を支持する理由と言えます。このポピュリズムの研究で、既存の政治家とは違う差別化を図りたくて極端に走ることを示した研究がいくつもあって、その中の一つに先ほど話していたノーベル賞のアセモグルの研究も含まれています。私の行ってきた研究と関わるものとしては、多選禁止制があります。多選禁止制は何度も選挙に出る、勝利することを禁止する制度です。例えばアメリカの大統領では一期二期まで務めたら三期目は選挙に出ることができません。これが多選禁止制になります。アメリカでは多選禁止制は大統領だけではなく、一部の州では知事、衆議会議員にも課されているものになります。これはアメリカでは国民の大きな支持を得て住民たちが強くこの多選禁止制の導入を求めて自分たちで法案を提案し、住民投票で可決した州が多くあります。根底にある考え方はベテランの政治家は腐敗しているというイメージです。ベテランになればなるほど、利益団体と癒着をして汚い政治をしているに違いないと考える人が多くいて、ベテランの政治家を一層して新しい人に取り換えればいいと考えていました。そうすることによって無駄な支出も減り、減税もできるはずだと議論されていたわけです。しかし実際に州知事や州議会で多選禁止制が導入した後、データ分析してみると、むしろ財政支出が増えて増税が行われたということが示されています。つまり当初意図したことと反対のことが起こっていることになります。ゲーム理論的な解釈としては、当然多選禁止制は政治家が次の選挙に出ることを禁止するだけではなく、有権者が選挙においてその人を選ぶ権利も奪っていることになります。例えば政治家にとっては次の選挙がもうない、最後の任期がすぐくるわけですから、それなら好き勝手やろうと思ってしまうかもしれません。選挙に勝つ必要はもうないからです。有権者も本当は有能な人を選挙で選抜していきたいのに、その人が引退してしまったら、もう一度新しい人から選ばなければいけなくなります。そういう選挙の機能をなくしてしまっているという意味で多選禁止制は、むしろ政治家に好き勝手なことをさせて、その質を下げているのではないかということが指摘されています。多選禁止制の例は我々市民が政治家に対して持っているイメージ、あるいは先入観が結果としてはあまり良くない結果を導き出している例の一つだと思います。それに対してゲーム理論的な手法やデータ分析の手法を通して冷静に見ていくことによって、その制度のあり方を考えることができることを示している事例の一つだと思います。
城谷:
ポピュリズムのところで一つ質問ですが、政治を変えたいという有権者の気持ちが反映されているとお話いただいたかと思いますが、変えたいとは改革なのか革新なのか、または他の何かなど、どういうイメージでしょうか。それは有権者それぞれの考えなのでしょうか。
浅古:
例えばトランプの場合、既存の政治家がやはり利益団体と癒着し、きれいごとしか言わないイメージがあるので、それと違うものを選びたい。それは多分国や時代によって違っていて、既存の政治家がどういうイメージかによると思います。ただ多くの場合、既存の政治家は利益団体と癒着、あるいは一般の労働者や普通の市民の人たちの思いとは別のところで政治を行っている。つまり「永田町の論理」とか、あるいは永田町には鵺(ぬえ)がいるみたいな感じで、アメリカでも同様にワシントンを巣くう得体の知れない人たちといったイメージがあって、それをより分かりやすい人に変えたいという思いはアメリカではあったと思います。日本の場合だと小泉純一郎とかがポピュリズムの例でよく挙げられていて、あれは端的に自民党ぶっ壊すみたいな形で出ていて、それはどちらかというと既存の政治家は自民党政治家、いわゆる永田町とか料亭のイメージがあって、そういう利権にまみれた政治家を排除しようというところで、いわゆる郵政民営化が小泉純一郎には極端な自民党にとって自民党の政治家があまり言わないような政策をとるという意味で、ポピュリズムの一つだと言われています。そのため、やはり日本とアメリカ、あるいは他の国それぞれで既存の政治家のイメージは違ってきます。ただ既存の政治家のイメージと私は言いましたが、それが正しいかどうかは別の話です。有権者がどう思っているかであって、本当かどうかは別として、彼らが持っている政治家のイメージが悪く、それを取り替えたいと思っている状況に当てはまるということになります。
城谷:
政治経済学を研究する手法にはここまでご説明いただいたゲーム理論の他にもさまざまな切り口があるものと理解していますが、その中でゲーム理論の限界ですとか得意不得意についてもお聞きできればと思います。
浅古:
まずゲーム理論を用いることで何かとてつもなく斬新な結果が出るわけではありません。あくまでゲーム理論をはじめとした数理分析は自身の考えを見せて、説得する手法の一つです。数理モデルを用いずに言葉だけで議論することもできますし、場合によってはその方が適切なこともあります。一方で数理的な手法を用いることの大きな利点はその厳密性です。置かれている過程は何か、その過程からどのような論理を経て結論が導かれるかを明確に示すことができます。論理的矛盾は許されませんし、おかしな過程があれば明確にわかります。言い換えれば自分の感情や思いを最小限にして冷静に物事を考えることができます。そこが一番大きな利点だと思います。私が一橋大学の大学院に行った時の指導教員であった伊藤秀史先生からの受け売りの言葉ですが、「制度を憎んで人を憎まず」という言葉があります。政治汚職など何か政治で問題が起きた時に問題の本質は政治汚職をした人の人間性にあるのではなく、そのような政治汚職を引き起こすような制度に問題があるのではないかという考えです。ゲーム理論では一定のゲームのルールの下で人々がどのような行動をとるかを分析します。この場合、ゲームのルールは社会における制度と考えることができます。政治汚職などの問題が生じた場合、問題を生じさせた人物を責めるだけではまた同じ問題を繰り返すかもしれません。まずはなぜそのような問題を生じさせるに至ったかに関して、制度的背景を検証することで、その欠陥を見つけて修復していくことで汚職を防げるかもしれないことになります。一方でその限界に関してですが、数理分析は例えば選挙や議会とは何か、議会ではどういう交渉が行われているか、といった広い問いを考える時には有用です。現実を単純化あるいは抽象化して考えるわけですから国や時代に関わらず成立する問いに答えていくことが得意といえます。一方でドナルド・トランプという政治家個人を考えるなどの特定個人や特定の出来事だけを分析したい場合には数理分析を用いずにもっと他の手法を用いた方が適切かもしれません。ただし近年ではこういう特定のケースを突き詰めて分析し、そこにゲーム理論を当てはめていく研究も行われています。またゲーム理論にせよ経済学にせよ、価値判断に関しては弱い部分が多くあります。ゲーム理論や経済学でなぜ今の事態になったのかという問いはゲーム理論とかデータ分析を使って理解できますが、どうするかという点に関しては強く踏み込めない部分は多くあります。もちろん数理分析の中には集団の意思決定を分析する社会選択論などで哲学とか大きく関わることもあって価値判断を評価することもあります。ただ多くのゲーム理論の応用ではそれを行いません。一方で政策決定には大きな価値判断が必要です。例えば少子化対策に有効な政策を経済学的にあるいは理論的に示したとしても、その政策に他の予算を削った上で予算を費やすかどうかは政治的判断です。あまりに予算がかかりすぎる場合は判断に迷うところでしょう。政治判断は何を重視するかという決定ですからゲーム理論を超えた思想や哲学が必要になってきます。