- Featured Article
トップ経営者が示すサステナビリティ
WOI’23「早稲田出身のリーディング企業経営者による座談会」レポート
Wed 13 Dec 23
WOI’23「早稲田出身のリーディング企業経営者による座談会」レポート
Wed 13 Dec 23
WOI’23「早稲田出身のリーディング企業経営者による座談会」レポート
2023年11月9日、10日、大隈記念講堂およびリサーチイノベーションセンター(121号館)にて、「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2023(WOI’23)」を開催しました。WOIは、「研究の早稲田」実現に向け、産学官連携の推進、大学発ベンチャーの紹介、文理融合の研究・社会変革につながる研究等の紹介ならびに企業等のご関係者の皆様との連携に向けたマッチングを目的とした産学官連携イベントです。
大隈記念講堂ではさまざまなゲストを迎え、講演や座談会を実施。その一つ「早稲田出身のリーディング企業経営者による座談会」では、三菱電機株式会社、明治安田生命保険相互会社、清水建設株式会社、大和証券グループ本社の早大出身経営者が登壇し、サステナブル経営や人的資本、人材育成における企業が果たすべき責務、日本企業の可能性を探っていきました。本記事では、この座談会の様子について、レポートをお届けします。
※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです
《登壇者》
根岸秋男氏 明治安田生命保険相互会社 取締役会長・早稲田二十日会※会長(理工学部卒業)
井上和幸氏 清水建設株式会社 代表取締役社長・早稲田二十日会副会長(大学院理工学研究科修士課程修了)
漆間啓氏 三菱電機株式会社 取締役 代表執行役社長CEO・早稲田二十日会副会長(商学部卒業)
中田誠司氏 大和証券グループ本社 代表執行役社長CEO・早稲田二十日会副会長(政治経済学部卒業)
《ファシリテーター》
入山章栄 早稲田大学ビジネススクール教授
※早稲田二十日会は、早稲田大学卒業の企業経営者・役員、そのOBなどで構成され、大正14年創立以来、毎月二十日に講師を迎えての勉強会等を行い、早稲田大学と密接な協力関係を推進して大学の学生・教員の社会的な評価を高めることを支援する会です。


激変する時代における、サステナブル経営
入山教授「本日は日本を代表する4社の経営者にお集まりいただきました。日本が抱える課題や早稲田大学が担うべき役割、学生への期待などについて自由に語っていただきたいと思います。パンデミックに始まり、ウクライナやイスラエルで起こっている地政学的問題、地球規模の気候変動など、現代は激変の時代といえます。そうした中で注目されるのが、環境や社会、経済の持続可能性に配慮し、事業の持続可能性を高める『サステナブル経営』です。各社取り組まれていると思いますが、課題や指針についてお聞かせください」
漆間氏「サステナビリティの課題に対し、私たち製造業は、より一層、本格的に取り組まなければならない時期に差し掛かっているのでしょう。世界中の気温上昇や社会の課題に対し、自社の事業が課題解決の方へと向かっているかを、真剣に見つめ直しています。家電から宇宙まで、さまざまな事業で培った技術を持つ三菱電機は、それらの知見を組み合わせることを重視しています。かつて企業価値と社会貢献は、どこかトレード・オフのように捉えられていたのかもしれません。それを“トレード・オン”の関係と捉え直し、両立させながら事業を推進させていく。そうした姿勢も大切にしています」

三菱電機株式会社 漆間啓氏
根岸氏「企業が社会的課題に対して責任を持つ上では、パーパス経営※に見られるように、理念やビジョンの中にサステナビリティへの姿勢を組み込むことが第一歩になるでしょう。また、各社が本業の強みを生かす視点もポイントです。全国に営業拠点のある明治安田生命ならではの取り組みとして、私たちは健康寿命の延伸や地域創生の推進に注力しています。そして、自分たちでできる事業範囲は限られているので、産官学ならびに社会のさまざまな方と協業しながら、広範かつ複雑な問題に対し、知恵を共有することが重要だと考えています」
※企業の存在意義を明確にし、社会に貢献する経営を実践すること。
井上氏「建設業界では、2024年に時間外労働の上限規制が設けられる一方、人口減少に伴う次世代の担い手不足が深刻化しており、いっそうのサステナビリティ強化が求められています。ただし持続性の確保や社会貢献の重要性は、今日突然生じたわけではありません。かつて当社で相談役を務めた渋沢栄一は、「論語と算盤」の理念、道徳と経済の合一を説いており、これは現代のサステナブル経営と一致します。物事を150年、200年といったスパンで考えなければ、本当の意味での持続性を確保することはできないのでしょう。社会インフラなど長期的な事業を担う建設会社として、未来に大きく貢献したいと考えています」
中田氏「金融の世界から見ても、国際的潮流は、株主資本主義からサステナブル経営へとシフトしています。営利企業である以上、利益は高めなければならなりません。しかし、その収益源となる事業は、社会にも貢献しているという前提がスタンダードになっている。上場企業においては、もはや“入場チケット”といっていいでしょう。投資家の視点もそのように変わっていることを感じます。そして現在、社会全体にもサステナビリティが根付きつつあるため、そうした環境で育った若い世代の力を生かすことも大切です」

大和証券グループ本社 中田誠司氏
人的資本経営を、どのように動かしていくか
入山教授「近年、人材を“資本”として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値を向上させる『人的資本経営』も重視されています。日本中の企業が人材という価値に注目する流れは明白ですが、皆さんは人材育成や多様性について、どのようにお考えですか?」
井上氏「これまで従業員は会社の“資源”でありましたが、これからは“資本”と捉えるべき。パフォーマンスを高める投資を行い、会社の業績向上につなげていく視点が重要です。清水建設では、人材戦略やダイバーシティ推進を、人事問題ではなく経営問題として捉え、活動を進めています」

清水建設株式会社 井上和幸氏
中田氏「2022年に政府が公表した『人的資本可視化指針』により、上場企業は有価証券報告書において、人的資本や多様性に関する開示が義務付けられるようになりました。女性の管理職比率や男性の育児休暇取得率が重視される流れは加速しています。日本は労働生産人口が減少しているため、人材の数と質、両方が課題視されています。突破口としては、女性の働きやすさ、DX※におけるシニア人材の活躍などがカギになるのではないでしょうか」
※デジタルトランスフォーメーション。業務プロセスのデジタル化・IT化にとどまらず、データおよびデジタル技術を活用してビジネスモデルや企業文化などを根本から変革していくこと。
漆間氏「DXは欠かせない視点ですね。三菱電機は海外事業の比率が高く、エンジニアが多いのが特徴です。今後DXを推進する中では、女性の活躍は非常に重要になってきます。多彩な人材、グローバルな考えを持った人材を集め、その中でデジタルや国内外事業のバランスを形成していく、そうしたマネジメントも必要だと考えています」
根岸氏「人材育成は企業の経営課題であり、会社としてはチャレンジする機会や学ぶ環境の提供、処遇や制度の充実を積極的に推進しています。そうした中で私たちが求める人材は、“自立・自律”した人間です。チャレンジには必ずリスクも伴います。失敗しても立ち上がる、そうした人材に集まってほしいと思います」
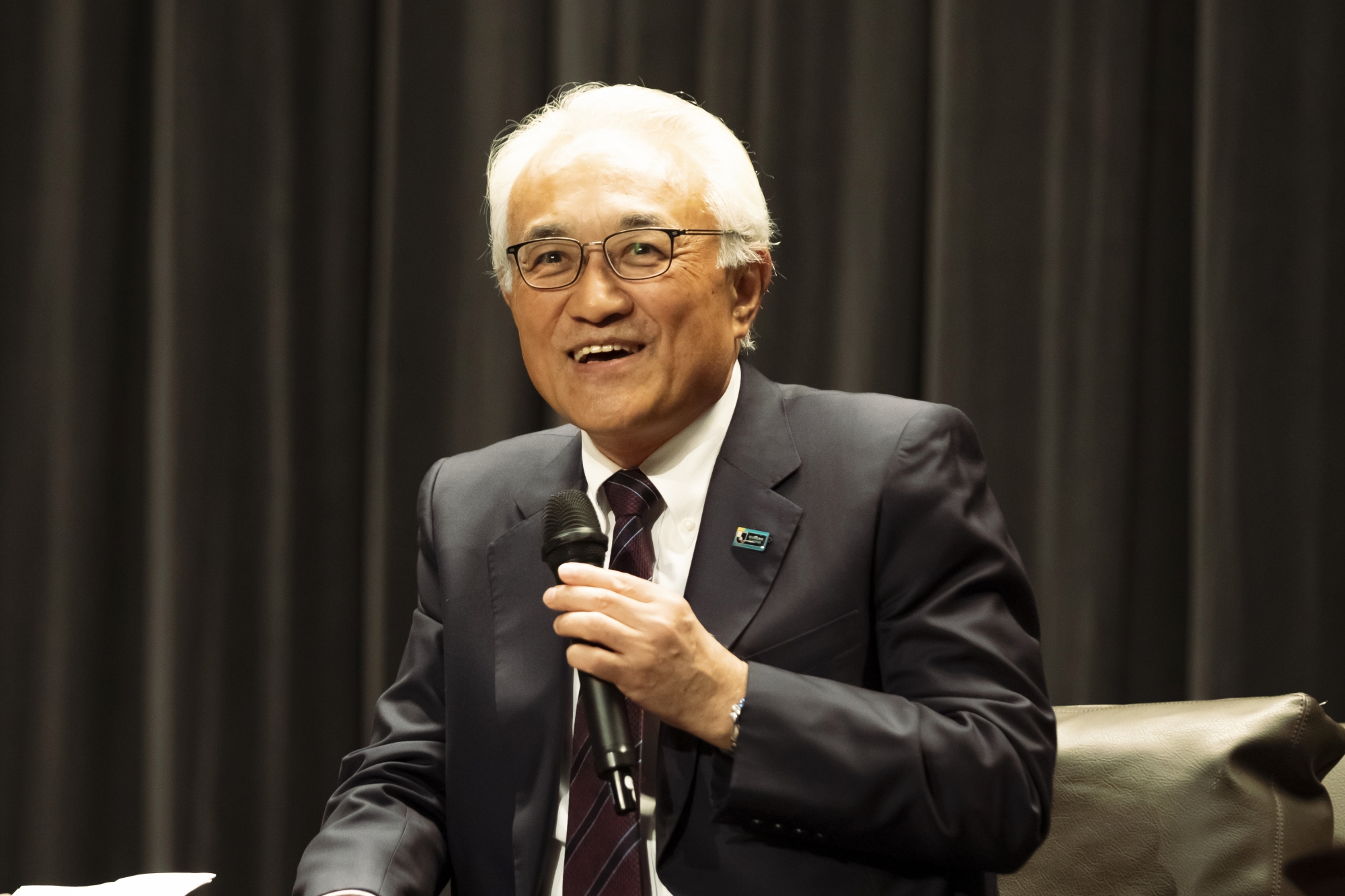
明治安田生命保険相互会社 根岸秋男氏


早稲田大学の人材と産学連携への期待
入山教授「大学と民間企業の連携も重要となっています。早稲田大学に期待することをお聞かせください」

入山章栄教授
中田氏「早稲田出身の企業経営者が、近年増えています。田中総長の改革は先進的であり、実社会で活躍できる人材も多く輩出している印象です。スタートアップにおいても、今日も最年少の上場記録を保持する村上太一さんは、早稲田出身。起業家同士のコミュニティも活発ですので、ビジネスにおける今後の飛躍に期待したいですね」
井上氏「当社に入社する従業員にも早稲田出身者がいますが、ベンチャー精神のような思考をどこかに持っていることを感じます。そうしたマインドを持っていれば、大企業も改革できるはずです。世の中には多くの社会課題がありますが、ぜひ新規ビジネスやイノベーションに挑戦してほしいです」
根岸氏「昔から早稲田は金儲けが下手ですから、企画力やビジネスモデル構築など、“稼ぐ”力を高めてほしいですね(笑)。そして、一人一人が頑張るだけでなく、互いを認め合いながら、融合していくことがポイントだと思います。大学と企業も同様で、連携を強化しながら、他者を認め合える新たなチャレンジャーを育みたいです」
漆間氏「今の学生は真面目な方が多い印象ですが、自分一人で新しいことを考えようとすると、ビジネスでは煮詰まる時が必ず訪れます。そんな際に必要なのは、遊び心です。人とコミュニケーションをとりながら、事業を育める人材を期待したいです。また、産学連携においては、いろいろな角度の社会課題に対し、アイデアを出し合える関係にしたいと思います」

座談会の様子:左から入山教授、漆間氏、根岸氏、井上氏、中田氏
座談会では最後に、田中愛治総長より総評が述べられました。

本座談会を企画した田中愛治総長から総評
田中総長「登壇の皆さまの話で一貫していたのが、企業は社会のニーズに応えるべきで、社会と実業がwin-winの関係になるべきだという点です。大学においても、学問の活用、人材の育成、社会への実装において、大きな使命があると感じています。本学創設者・大隈重信の言葉に『一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ。』というものがあり、利他の精神により人類社会に貢献する姿勢が表れています。今後も早稲田大学は学生諸君のたくましい知性、しなやかな感性を育むことで、産業界の皆さまと一緒に、より良い未来を共創していきたいと思います」

回廊での記念写真。左から須賀副総長、田中総長、中田氏、根岸氏、井上氏、漆間氏、入山教授、齋藤副総長


