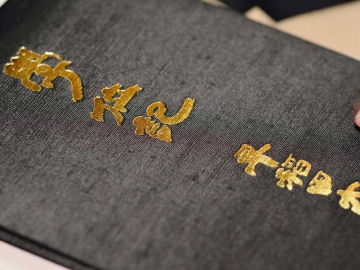東京都と全国清涼飲料連合会の「ボトルtoボトル共同プロジェクト実証実験」に協力
 早稲田大学では昨年の9月より、構内にリサイクルボックスを設置して、飲み終えたペットボトルを元のペットボトルと同品質に戻す「ボトルtoボトル」事業を展開しています。今回の実証実験は、その事業の一環として協力することになりました。
早稲田大学では昨年の9月より、構内にリサイクルボックスを設置して、飲み終えたペットボトルを元のペットボトルと同品質に戻す「ボトルtoボトル」事業を展開しています。今回の実証実験は、その事業の一環として協力することになりました。
全国清涼飲料連合会(以下「全清飲」)は、「清涼飲料業界プラスチック資源循環宣言」として2030年度までに「ペットボトルの100%有効利用」を目指しています。
一方、東京都も2050年迄のプラスチック削減プログラムを策定し、「ボトル to ボトル」を重要施策の1つに掲げ、昨夏 全清飲と「ボトルtoボトル 東京プロジェクト」を立ち上げ、活動を開始しています。
今回の実証実験は、「ボトルtoボトル」の推進のために、より効率的、効果的な方法を検証することを目的とし、西早稲田キャンパスと高等学院・高等学院中等部が協力しました。
実証実験①
斬新な設計によるリサイクルボックスを設置し、ボトルtoボトルに不可欠な「キャップをはずす・ラベルをはがす・飲料水が残っていない」状態になっているPETの回収量を確認します。
西早稲田キャンパスの2か所にリサイクルボックスを設置

実証実験②
ペットボトル自動回収機を設置して、実験①のリサイクルボックスと回収本数を比較します。

残念ながら利用率は少なく、普及させるためにはもう少し工夫が必要かも!?
この自動回収機は、キャップとラベルを外した後、投入口に入れると、完全圧縮されます。
ペットボトルを完全圧縮させることによって、大量のペットボトルの運搬が可能になり、リサイクル効率がが向上します。
 自動回収機で回収されたペットボトルはここまで圧縮されます。 |
実証実験 調査風景

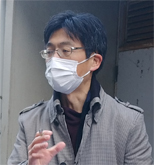 ポッカサッポロ フード&ビバレッジ(株)西内氏 |
|||
| 新たに設置したリサイクルボックスに投入されたペットボトルは、従来型のリサイクルボックスより、キャップやラベルがなく理想的なPETとして投入されている確率が高いことがわかりました。従来の回収ボックスに投入されるPETボトルにおいて、キャップとラベルとPET本体が分別されている状況が一部で見られたことから分別意識が広がっている印象も受けました。 一人ひとりがルールを守って水平リサイクルに協力してくれる風土作りが大切で、早稲田大学でもぜひこの取り組みを推進していただきたいと思います。 |
|||
高等学院では、環境プロジェクトの皆さんも協力してくれました!

今回の実証実験を行う際に、高等学院の環境プロジェクトの皆さんに設置場所や回収率をあげるための工夫などを打合せをしました。また設置した後には、SNSなどを使って生徒の皆さんに周知をしてもらいました。
プラスチックは、その生産に関わるCO2排出量増大や海洋への不法投棄によるマイクロプラスチック問題など、環境問題に多大な影響を与えています。しかし、その一方で、プラスチックは日々の生活に深く浸透し、私たちは沢山の製品のメリットを享受しながら生活しています。プラスチックの削減に向けて努力することは必要ですが、同時に、プラスチックの利用と地球環境問題の解決を両立させて、持続可能な社会にしていくことも考える必要があります。
今回のプロジェクト協力は終了しましたが、早稲田大学では早稲田キャンパスと戸山キャンパスにおいて引き続きBtoBプロジェクト(URL:https://www.waseda.jp/top/news/70891)を推進してまいりますのでご協力をお願いいたします。
総務部総務課