- Featured Article
【Podcastコラム】自衛権発動通報
Mon 10 Feb 25
Mon 10 Feb 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、政治経済学術院の多湖淳教授に、自衛権の発動通報に関する調査について、具体例をもとに説明いただきましたので、その部分を抜粋してご紹介いたします。
Q. 戦争や平和をめぐる研究分野において、多湖先生は科学的な研究アプローチを行っていますが、この戦争や平和をめぐるデータを用いた科学的、実証的な研究とは、具体的にどのように取り組まれているのか。実際の実験方法等も含めて教えていただきたい。
多湖 淳 教授:
1つの例として、戦争にまつわる自衛権の話、自衛権のデータ分析の話をさせていただきます。
前職の神戸大学の時、私は法学部にいました。そこに国際法の先生がいらして、その先生とインタラクションしていると、国連憲章の51条に自衛権と書いてありますが、自衛権について議論する時、自衛権自体はなんとなく本を読んでいて分かっていましたが、そこに実は見落とされている一文がありました。何かというと、自衛権を行使した時には安保理に通報すると書いてあります。
義務条項に読めるように書いてありますが、実はよくよく聞いてみると、義務条項じゃないという解釈もあるんだと。何かというと、国家実行が伴っていないので、自衛権だと通報する国はそんなに多くなかった。
それはすごいパズルなので、要はデータとしてどうやっていくかというと、国連の議事録とか国連の文章を全部ウェブサイトに行って探してきて、すごい古いPDFなので、文字が潰れて読めないものもありました。今、OCRで多分自動的にできますが、その時は学生を総動員して、自衛権を行使した、通報した時をカウントしていくんです。

すでにコンピューターに戦争のリストは存在するので、それに照合して回帰分析をかけてあげると、一体どういう条件の時に、自衛権の発動通報がなされるのかが見えてくる。よくよく見てみると、アメリカの軍事援助をもらってる国は、より通報が早い。しかも通報しやすい。
どうしてかというと、アメリカの議会は自分たちのあげる武器を自衛のためにしか使わないでくれという条件を付けています。
そのため、安保理に自衛通報しないと、アメリカの援助が止まってしまうかもしれない。今、それこそイスラエルでそういう話が出ています。イスラエルのネタニヤフ政権がやりすぎると、アメリカがその武器援助を止めるぞと言っている。ああいう脅しが実は自衛権を行使した時の通報行為、国際法の行為につながっています。

こういうのはデータ分析してみると分かる話で、色々な形で身近なところのパズル、不思議を見つけてくだされば、データ分析はいくらでもできると思います。
他には国際関係論だと商業的平和、コマーシャルピースという議論があるのですが、それも貿易依存度というので測ることができます。
貿易依存度のデータを、例えばIMFのデータもしくはOECDのデータから取ってきて、計測して、年ごとにまとめて、プラス何年何月、いつからA国とB国が戦ったという、ダイアドという組み合わせでカウントするのですが、それが収録されているのでマッチングして比べてあげると、やはり貿易依存度が高いと平和が生まれるのかというのは、データとして検証できますし、そういったいわゆる計量政治学の手法を使って、分析することになります。
多湖 淳 教授
1976年生まれ。1999年東京大学教養学部卒業。2004年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。2007年東京大学より博士(学術)取得。令和元年度日本学術振興会賞受賞。神戸大学大学院法学研究科教授、オスロ平和研究所グローバルフェローなどを経て、現在、早稲田大学政治経済学術院教授。専門は国際関係論。著書:『武力行使の政治学──単独と多角をめぐる国際政治とアメリカ国内政治』(千倉書房 2010年)、『戦争とは何か──国際政治学の挑戦』(中公新書 2020年)、『政治学の第一歩 新版』(有斐閣 2020年 共著)など。

城谷 和代 准教授(番組MC)
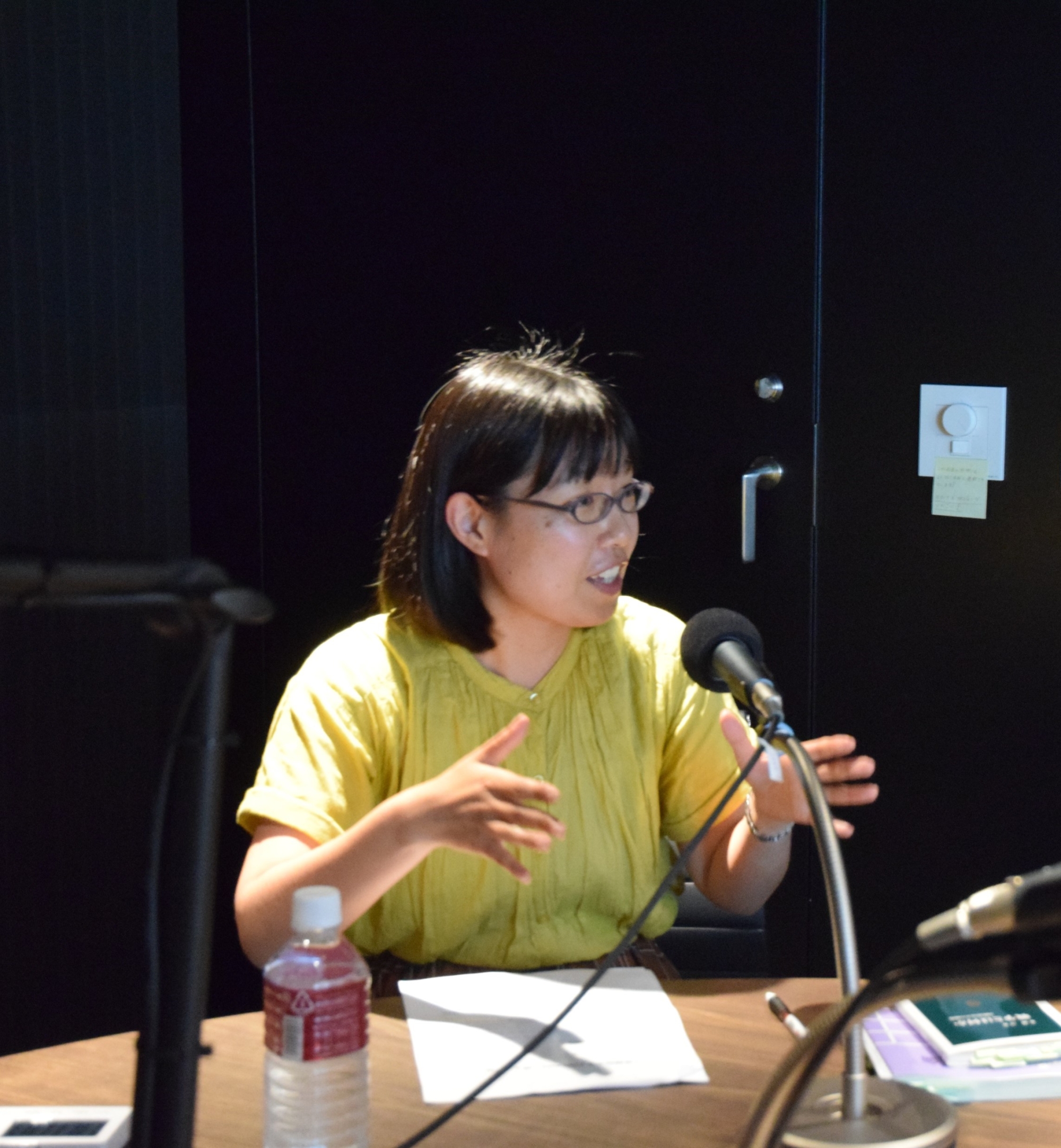
研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了博士(理学)、2011年産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。



