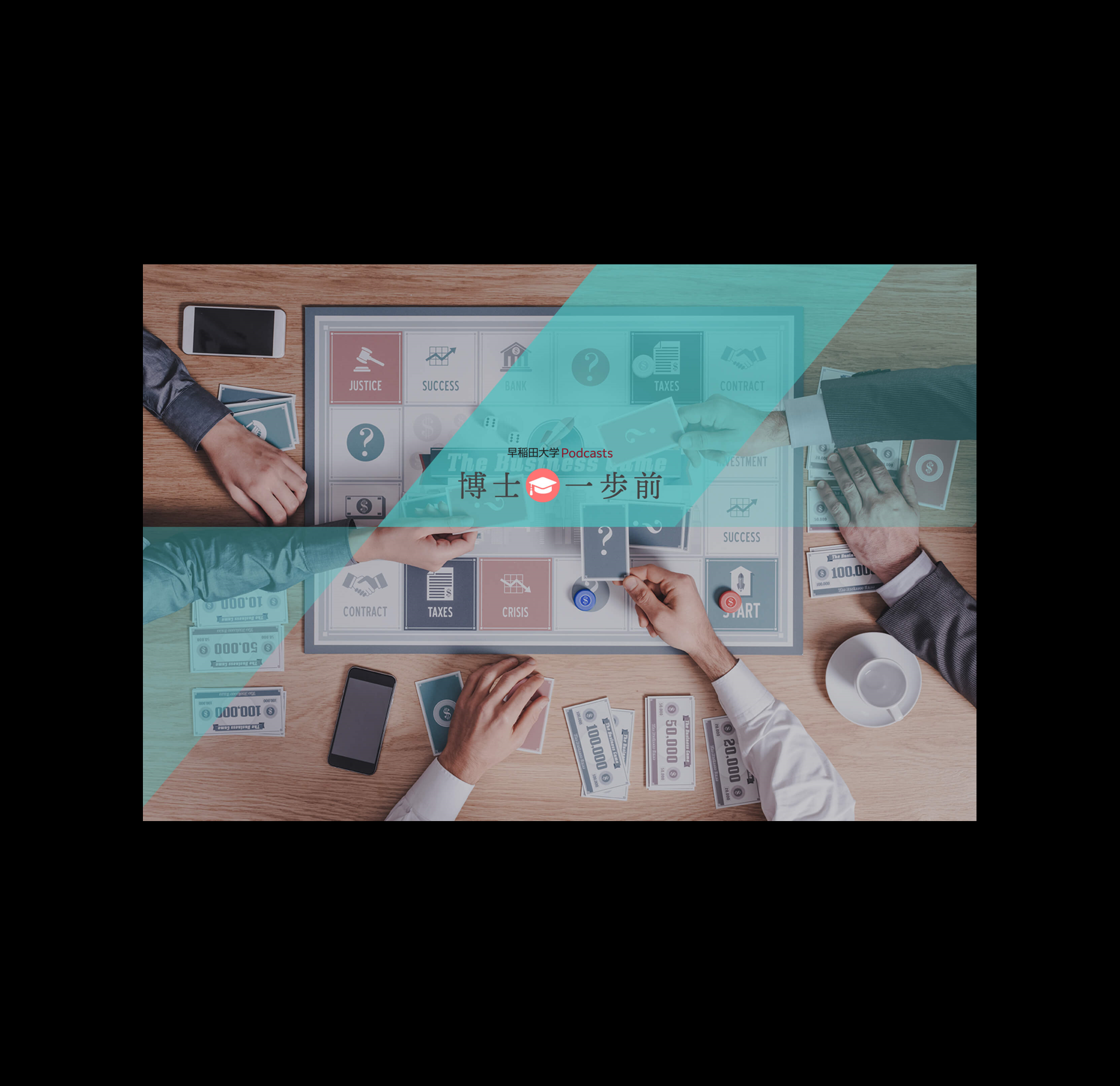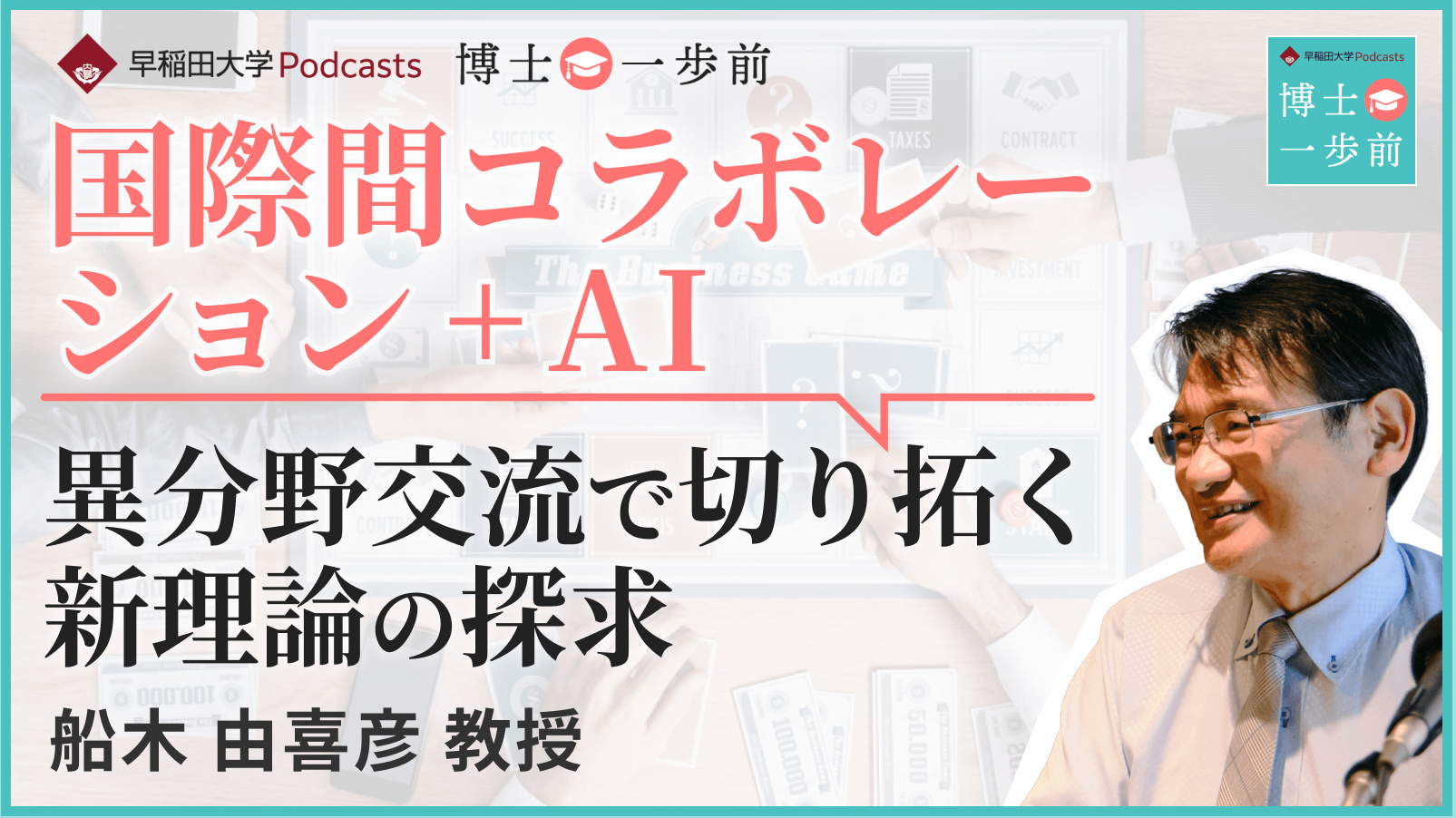- Featured Article
【Podcastコラム】BCGゲーム必勝法
Mon 03 Feb 25
Mon 03 Feb 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、政治経済学術院の船木由喜彦教授に現在注力している研究テーマについてお話いただくなかで、BCGゲームとナッシュ均衡の関係性を説明いただいたので、その部分を抜粋してご紹介いたします。
Q. 現在、船木先生が特に注力しておられる研究テーマとその研究によって解決しようとしている問題とはどのようなものか。
船木 由喜彦 教授:
現在はフォン・ノイマン(ジョン・フォン・ノイマン)、モルゲンシュテルン(オスカー・モルゲンシュテルン)の最初のテーマに関連した研究に注目しています。
どのような研究かと言うと、協力ゲームの実験は人々がどのような行動をするか、その結果をどう分けるかという二段構造になっています。その二段構造になっている問題を実験で分析したい場合、そもそも分け方の話とその前に何が起こるかは非常に重要な関係があるはずですが、実は現在の協力ゲームの分析家は全部それを外して、分け方だけ分析しています。
少し脱線しますが、実験は人々の行動を分析するために重要ですが、実験する人がどんどん増えてネタ切れみたいになってきており、協力・非協力ゲームではなく、もっと違うことをやりたい。そのため、協力ゲームの実験が最近流行ってきています。
その中でやることは協力ゲームの枠組みの中での実験で、元々の状況からどのような意思決定をして、どういう協力をするかまでの実験はないので、これをプロジェクトとしてこれから続けていきたいと思っています。つい最近、最初の実験も終わったので、その結果を分析しているところです。これはフランス人の研究者とうちの大学院の学生が一緒にやっているプロジェクトです。それが一点目。
それからもう一つは美人投票ゲームの実験です。美人投票と言うと色々な考えがあるかもしれませんが、元々はケインズの美人投票、例えば株式を購入する時に自分が買いたい、上がると思っている株ではなく、みんなが上がると思っている株を買いなさいという話で、それを実験で分析するのが美人投票ゲーム。あるいはビューティーコンテストゲーム、BCGゲームと言われています。

端的にどのようなゲームか説明すると、0から100までの中で好きな数字を選んでください。その中で皆さんの選んだ数字の平均、平均だけだと難しいですが、平均の0.7倍の数字を書いた人が優勝者です。どの数を書いて投票しますかというゲームです。
これをゲーム理論的に解釈すると、結構面白い理論になります。ゲーム理論的に言うと、0から100の中で、みんなが100を書いた時、平均は0.7倍の70が優勝になる。100より上はないので、70より上で勝てるわけがない。これは支配されないと言いますが、その支配されない戦略の中で考えてみましょう。
すなわち0から100ではなく、0から70の中で考えましょう。0から70の中で同じ合理性を考えるならば、0から70において最高が70なので、その平均の0.7倍は49となります。49より上で勝てるわけがありません。大前提として、参加者全員が同じ合理性であることを考えます。そうすると49より上で勝てないので、49までで考えないといけない。全員がそう考えるのであれば、49の0.7倍以下でなければならない。
これを続けていると0しか残らない。0が唯一のナッシュ均衡になります。そのため、ゲーム論的には、0を取りなさいとなります。ところがこのゲーム、0で勝った人はいません。なぜなら誰もそんなに先まで読めないので、読み方で言うと2回ぐらい。実はこの考え方は難しいです。
しかし分かりやすい考え方が実験経済学から出てきました。レベルKという考え方です。0から100の中でどれを選ぶかは、でたらめにコンピューターなどがランダムに選ぶのであれば、平均は50です。そのため、平均は50になります。50になるならば、それの0.7倍の35を選べばいい。まず、何も考えない人をレベル0と言って、50を選ぶ人です。レベル1の人はみんなが平均で50を選ぶから、その0.7倍の35を選ぶだろう。これがレベル1の人。

しかしそれはおかしいですよね。自分の他にも同じように考える人がいるわけですから、全員35と考えるはずです。平均が35になるので、35の0.7倍の数を選ぶのがレベル2の考え方。これもここでは止まりません。同じように考えるならば、それの0.7倍。これの繰り返しで、他の人がどこまで深く考えるかに依存する。理論であれば無限に深く考えますが、そこまで行かないので、だいたい私は一つか二つですが、私の講義に出て学生で第一回の講義で必ずやるので、このデータをたくさん集めています。
そうするとたいていの場合、レベル2あるいは3の人が勝ちます。レベル1では勝てない。そのくらいの数を書くと勝てるケースが多いです。
私の研究において、少し設定を変えると、合理性に近づくケースと近づかないケースがあります。設定の変え方は下から行くか上から行くか、あるいは上に行ったり下に行ったり、レベルKの考え方ですが、50に対しては35ですが、35に対して今度上に行く、そのような状況が起こった時にはより均衡に近づくという実験があります。しかしそれがなぜかはわからない。
2つの状況があって均衡に近づく状況と、均衡にあまり近づかない状況があって、その違いはわからない。それがどうして違うのかをアイトラッカーという目の動きを記録する装置、要するに視線を調べる装置ですが、どこの情報を見て、どのような意思決定をしているかを分析しながら実験します。少し高い機械なので、普通の実験室とは違うところに備えてあって、どのような情報を使うことによって、その違いが出てくるか、より合理性が出てくるか、人々によって合理性が違うのはそうですが、環境によってどう違うかを分析している。これがもう1つのテーマだと思います。
ファイナンスの実験、どうしてバブルが起こるのか、広い目で見ればゲーム理論にも関係しますが、そういったファイナンス関係の実験も私の博士の学生で興味を持つ人が多いので、なぜそうなったかの経緯も後でお話できればと思います。
船木 由喜彦 教授
1985年東京工業大学にて博士号を取得。 東洋大学経済学部教授を経て、1998年より現職 早稲田大学政治経済学術院教授に。Mathematical Social Sciences や Journal of Mathematical Economicsなど、国際学術誌の編集委員も務める。専門は、協力ゲーム理論、実験経済学。日本経済学会、日本OR学会、国際ゲーム理論学会、ESA(実験経済学学会)に所属。著書 『 演習ゲーム理論』(新世社, 2004年)『はじめて学ぶゲーム理論』(新世社, 2014年) など。

島岡 未来子 教授(番組MC)

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。