- 学部について
- 研究
Research
研究

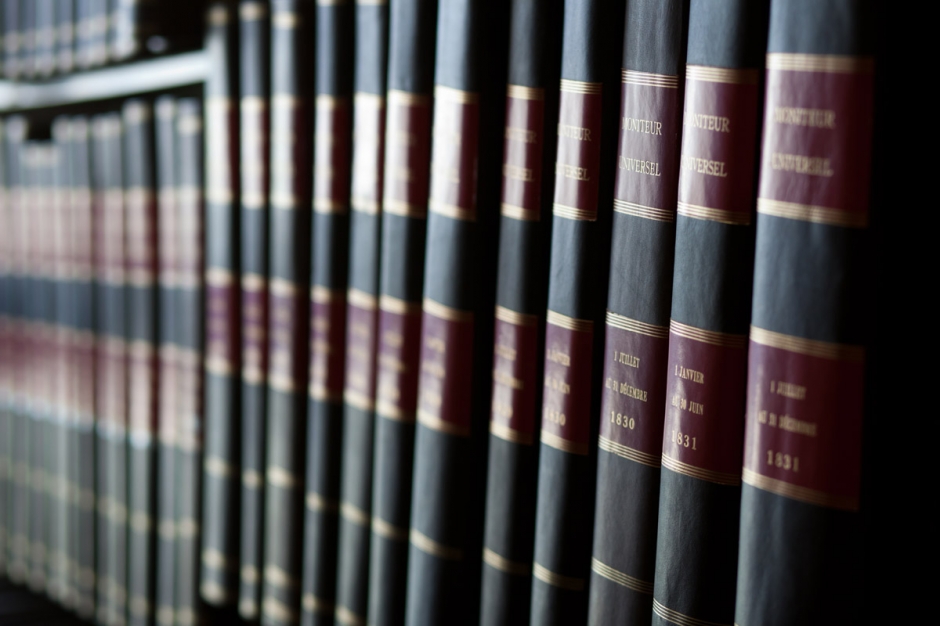
大学院法学研究科
早稲田大学大学院法学研究科は、文字通り、法を学問として研究する場です。法学研究科の主要な目的は、法学研究者を養成することにあり、その点で、法科大学院(法務研究科)が法曹実務家を養成するのとは、制度としての趣旨・目的を異にしています。いわば、法科大学院出身者が「法(律)そのものによって生きる」のに対し、法学研究科出身者は「法(律)学によって生きる」ことになります。
法学研究科は、一般入試のみならず、自己推薦入試・社会人入試・法曹入試等多くの入試制度を設置しており、多様なルートから様々な学生が入学しています。これらの学生が交流することで、当研究科は国際的かつ知的刺激に満ちた研究環境を実現しています。
法科大学院(大学院法学研究科法曹養成専攻)
法科大学院(大学院法学研究科法曹養成専攻)は、学生の多様な目的意識に応えられるよう、
多くの専門分野を自由に選択し学べる、全方位型の総合型法科大学院です。
早稲田ならではの多様性と総合性を基盤に、優れた研究者教員と実務家教員
のもとで専門知識と実務のスキルを学び、真の実力と実行力を持った
「挑戦する法曹」の育成をめざします。
入試は夏に一般入試と3年次生特別枠入試、冬に「人材発掘」入試を実施
しており、法学既修者(2年短縮課程)、法学未修者(3年標準課程)を
募集しています。
24時間利用できる自習室、法科大学院を修了した若手弁護士による学修
サポート及び早稲田大学法学部出身者を対象とした奨学金等の充実した
奨学金制度を用意しており、より安心して学びやすい環境を整えております。
比較法研究所
比較法研究所は、わが国および諸外国の法制の比較研究を通じて、日本の法制度および法学研究の発展に寄与するとともに、世界の法制度および法学研究の発展に貢献することを目的として、昭和33年(1958年)に設置されました。設立以来各国法制資料の収集・整備に努めるとともに、研究員による共同研究とその成果の発表、講演会の開催、原典の邦訳、諸外国研究所との学術交流、日本の法制・判例や学者の労作を海外へ紹介することなどを主な事業としています。
法務教育研究センター
早稲田大学法務教育研究センター(CPLER)は、研究や継続教育を通じて、優れた法律家を育成するために開設された機関です。
法律文献情報センター
法律文献情報センターは、日本の判例集と内外の法律雑誌の収集を基本とした法律系図書室です。
所蔵資料
- 和雑誌
新刊雑誌:新刊スペースに、紀要・専門雑誌・一般雑誌に区分して配架。
バックナンバー:書庫に、紀要・専門雑誌に区分して配架。 - 外国雑誌(専門雑誌)
新刊雑誌:到着後3週間までを、新着ブックトラックに配架。
バックナンバー:書庫に配架。 - 参考図書
書誌・文献目録・索引 等
辞書・辞典・便覧 等 - 日本の判例集
大審院・最高裁~下級裁判所判例集等の公式判例集・ 判例要旨集・判例評釈 等 - データベース検索
LEXIS: アメリカを中心に、ヨーロッパを含む法令・条約・ 判例・雑誌論文のデータベース。
その他WESTLAW, Beckonline, JURIS,Juris Classeurなど。
法学会
わが法学会は、1896年11月の都下法律学校連合大討論会に起源を発し、1922年6月に設立されました。同年10月『早稲田法学』第一巻が創刊され、以来、長きにわたる歴史を重ね早稲田法学の金字塔がうちたてられるにいたっています。とともに、1933年、別に『早稲田法学会誌』も創刊され、広く学生諸君にも、研究発表の場が与えられるようになりました。さらに、1963年には『人文論集』が創刊され、一般教育・語学関係の論文等が発表されています。
かくて、教員・校友・学生が三位一体となって、学問的気風をたかめるとともに、相互の親睦をはかるという本会の目的は、爾来、会員諸氏の努力により、今や、みごとに達せられ、さらに、その発展も約束されています。
研究者データベース
研究者データベースに採録したデータは、早稲田大学に在職する専任教員等の研究活動に関する情報等を、個人別にまとめたものです。
刊行物
早稲田法学
早稲田大学法学会の機関誌。
1巻(1922)以降を下記、早稲田大学リポジトリ(Waseda University Repository)に収録。
早稲田法学会誌
早稲田大学法学会の機関誌。
2巻(1950)以降を下記、早稲田大学リポジトリ(Waseda University Repository)に収録。
人文論集
早稲田大学法学会の機関誌。
45巻(2006)以降を下記、早稲田大学リポジトリ(Waseda University Repository)に収録。
