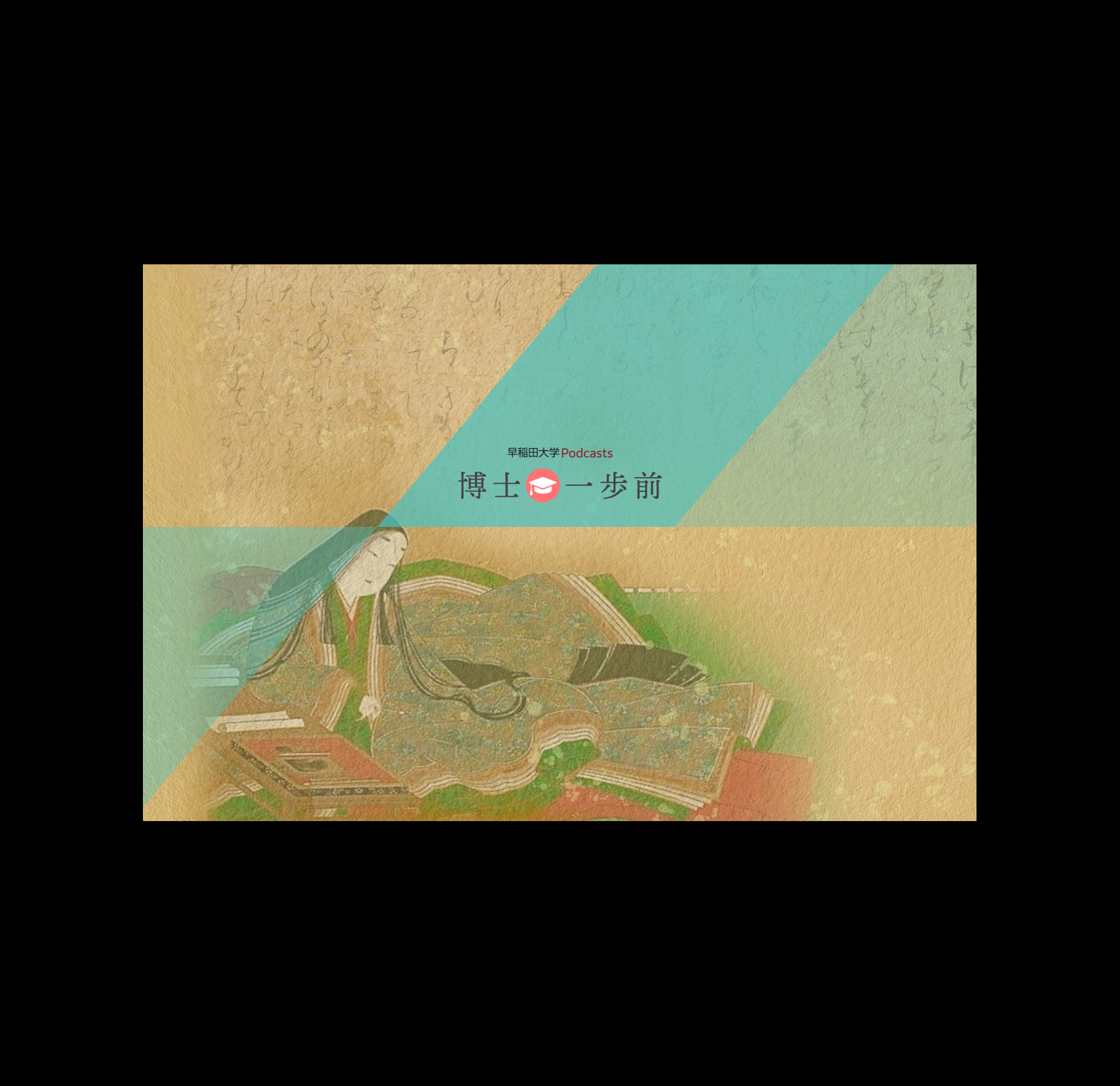- Featured Article
Vol.2 国文学(4/4)【仮名文学が映す平安の姿】宮仕え女房の日記に垣間見る、現実的な目的と創作への工夫 / 福家俊幸教授
Tue 28 May 24
Tue 28 May 24
全4回にわたってお届けてしてきた本シリーズの最終回では、平安時代の日記文学の特徴と、そこから読み取れる時代背景を探ります。
『紫式部日記』や『更級日記』をはじめとした平安時代の日記には、鎌倉などの後の時代とも、そして現代とも異なる特徴があります。平安の仮名日記は、個人をどのように捉え、反映していたのでしょうか。
また、国文学研究の目指す未来について、異分野との関わりから、福家教授にお話頂きました。
配信サービス一覧
ゲスト:福家 俊幸
教育・総合科学学術院教授。専門は平安時代の文学・日記文学。
1962年香川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学助教授、早稲田大学教育学部助教授を経て現職。著書に『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院)、『更級日記全注釈』(KADOKAWA)、共編著に『紫式部日記・集の新世界』『藤原彰子の文化圏と文学世界』『更級日記 上洛の記千年』(以上、武蔵野書院)、『紫式部日記の新研究』(新典社)、監修に『清少納言と紫式部』(小学館版・学習まんが人物館)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。
2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
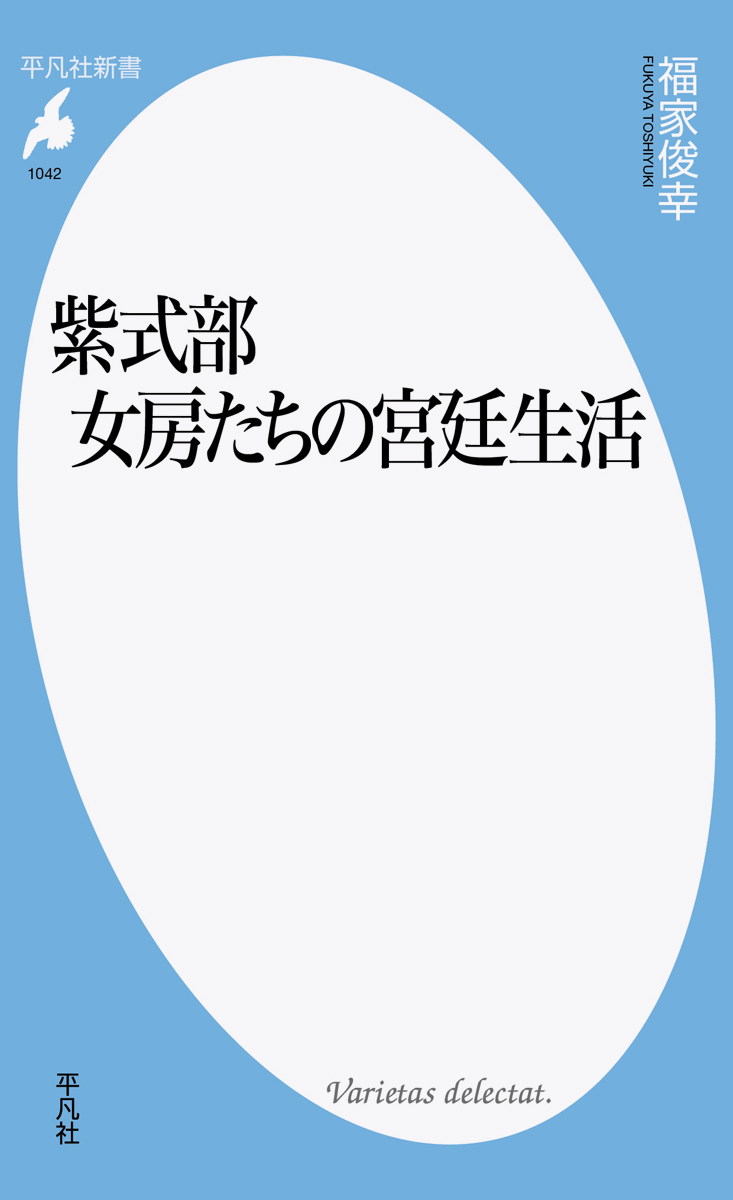
紫式部 女房たちの宮廷生活
出版社:平凡社
発売日:2023/11/15
言語:日本語
単行本:264ページ
ISBN-10:4582860427
ISBN-13:978-4-582-86042-9
-
エピソード要約
-個人と集団が密接に結びついた日記
平安時代の日記は集団の中の個人によって書かれており、個人と集団の関係が密接に結びついている。これは現代の日記とは異なるスタンスであり、教授はこの点に特に注目している。
『紫式部日記』などの平安時代の日記は、集団の中での個人の体験を詳細に記述しており、読者もその集団の一員として日記を読んでいた。このような日記は、集団の中での個人の視点から集団自体をも見ることができる。
-平安時代の仮名日記の現実的な目的
主家の記録を残し、後世の主家の人々が参照する現実的な目的を持っていた可能性がある。『更級日記』には言葉遊びや絵的な表現、色や数字へのこだわりなどが見られ、祐子内親王のような幼い読者が楽しめるように、意図的に子供向けに作り直された絵本のような形をしている可能性がある。平安時代の日記文学は、読者の好みや受けを意識して、個人の体験を改変して記述することがあったと考えられ、これは個人の感情をそのまま書いたものではなく、読者受けを狙った表現も含まれている可能性がある。
平安時代の女房たちは自分の職分や役割を非常によく理解しており、主人たちの期待に応えるとともに、自分の書きたいことを実現していく能力を持っていた。
-国文学と異分野との連携
異分野の専門家と連携し、『更級日記 上洛の記千年』を出版した。これは菅原孝標女の旅立ちの年を記念するもので、文学だけでなく古代交通、地方研究など多岐にわたる分野の専門家が寄稿している。歴史学とのコラボレーションを通じて、国文学の研究の発展性を高めることが重要であり、専門領域が細分化されがちな国文学研究の新たな可能性を開くことが期待されている。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以降、城谷):
仮名というと、女性が書くのかなと思うんですけれども。
福家教授(以降、福家):
基本的にはそうですよね。
城谷:
そうすると、仮名日記のご研究ということは、女性の視点というか、そこのご研究というふうにも捉えてよろしいんですかね。
福家:
『土佐日記』こそは初めは紀貫之によって女性のふりをして書いているわけですけれども、その後『蜻蛉日記』以降、女性が主体となって日記が書かれるようになっていったわけです。仮名日記がなぜそれだけ脚光を浴びているのか。特に平安時代の仮名日記って、先ほどの紫式部の話とも繋がりますけれども、日記の中に紫式部の思い、個人の思いみたいなものが結構出てきているんですよね。いろんな人を批評したり、要はキャラクターが出ている。
城谷:
日記というのが、先生の新書を読ませていただいたときに、今でいう自分自身の言葉を自分自身に書き留めておくというスタイルではなくて、その時の状況を記録するような意味合いというふうにこの本で拝見したんですけれども、そういうある意味、事実を書くというものに加えて、プラスで書いている人の気持ちであるとかっていうのが入っているっていう。
福家:
それは散文表現の中に入ってくるものもありますし、あるいはその時詠んだ和歌の中に感情が込められている。そういった場合もあります。いずれにしましても、『蜻蛉日記』もそうですし、『更級日記』もそうですけれど、自分の人生の一部を振り返って、それを記し留めているわけですけど、そこに個人の思いが色濃く出てきていると。実は鎌倉時代以降もそうした仮名日記は書かれているんですが、自分自身をあまり出さないと言いますか、結構控えめなんですよね。割と記録的なスタンスが強くなってくるわけです。あまり書き手の個人的な思いを書かないような感じ。
城谷:
人間くささというか。
福家:
そうなんですよね。そうした表現の中に人間が書いていることですから、人間の思いみたいなものは当然出てきていると思うんですけど、ただ平安の文学ほど、そこが濃かったりはしないわけです。まさにお言葉を借りれば人間くささといったものが、平安の方が非常に表面に出てきていると。それは一体どういうことなのかというのが一つ、私自身すごく関心があるところでもあります。ただもう一つ注意しなくてはいけないのが、その個人の思いといったものが必ずしも、現代の我々のような個人的な感情だけではなく、やっぱりある種の女房が書いている場合が多いんですね。
『蜻蛉日記』の場合は、道綱母という、いわば家で夫が来るのを待っているような立場で、ただ世間的に見れば彼女は兼家の妻で、彼女の社交というのも実は夫の関係者との付き合いがめちゃくちゃ多いんですね。夫の関係者とすごく歌のやりとりをやっていて、歌がいっぱい載っています。要は集団と個人との関係が分け難いといいますか、結びついているんですね。どこまでが集団なのか、どこまで個人なのかというのが微妙なところがあって、『紫式部日記』の場合でも、めったやたらとたくさんの仲間の女房たちの名前が出てくるんです。本名は書かれませんけれども、女房名って言われる宮仕えの名前で書かれています、そうした集団の中の個人といいますか、個人の有り様みたいなものと日記文学との関係というのを、より深めて考えていきたいなと思っています。そこは現代の私たちに直接結びつけて落とし込んで考えていくというのもどうなのかなというふうに一方では思ったりもしているんですね。
城谷:
その書いてる人のスタンス、位置づけが違うということになりますかね。
平安時代の日記は、集団の中にいる日記を書く個人がいる。今の日記はそれぞれ、もちろんそういうスタンスは何もなく、個人でこう思いを書く。もちろん集団の中にいて個人で書くというのもあると思うんですが、そういうスタンスの違い。
福家:
まさにおっしゃる通りで、本当にもう一言で本質をおっしゃっていただいたという感じがしますね。
城谷:
そうすると平安時代の集団の中にいる中での個人で書くということは、その中の個人を見ることにもなるし、集団を見ることにもなる。
福家:
そうですね。平安時代の日記というのは、おそらくは物語にパトロンがいて、最初は違ったかもしれませんけど、道長からの依頼で『源氏物語』が書き続けられたのと同じように、こうした日記にも自分の体験をこう書いてごらんなさいっていうような、そういうような要求があってこう書いていく。そしてまたそうした日記を読む人たちもそうした集団の中で読まれていくと。
『紫式部日記』でも皇子が誕生するときに、どの女房がどこにいたとかですね、事細かく書いてます。またどんな格好をしていたとか。紫式部は結構目が行き届くというのか、あるいはちょっと意地悪なのか、この皇子が生まれるときに普段メイクがバッチリ決まってるような女房が、茫然自失の状態で、若い男性貴族と顔を合わせていてもすっかり化粧をはげていて、別人みたいだったと言っていたりするわけです。そういうことまで書いていくわけですけれども、女房の配置だとか、あるいは女房の装束とか、そういったことも事細かく書いていくというのは、集団の中でこれが読まれていく。また集団の中での一つの皇子誕生という吉例を、この時代やっぱり過去の先例を非常に重んじる時代ですので、そういう非常にめでたい主家の記録を残していこう。で、それをまた主家の人々たちが今後読んでいくと、参照していくと、そういう現実的な目的みたいなものも、そこに見ていくことができるのではないかと思っております。
城谷:
先生の研究を通じて見えてきた世界観ですとか、研究の醍醐味を教えていただけますか?
福家:
国文学の世界は膨大な先行研究があります。そこにどういったものを加えていくのかが、日夜課題となっているところで、どこに新しいものを加えていくのかというところなわけです。それが十分私はできているとは思いませんけれども、例えば先ほど申し上げたところに結びつけますと、『更級日記』は前半の、冒頭から5分の1ぐらい、全体の5分の1ぐらいが、孝標女が13歳に、上総国、千葉県になりますけれども、当時上総国の国府から、都に向かって旅立つ旅の様子が書かれています。ここの箇所というのが、実は面白いことに、いろんな面白い地名、「いかだ」とか、現在どこかはっきりしない、「いけだ」が訛ったというか、聞き違えたんじゃないかとも言われたりしますが、実は「いかだ」という土地に来たら雨が激しく降ってきたと、木が浮きそうだったというのが書いてあるんですね。実は「いかだ」って木を組み立てて浮くじゃないですか、つまりこの『更級日記』の13歳の旅の地名って、そうした言葉遊びみたいなものが多くて、しかもやたらといろんな色が出てきたり、絵みたいな表現が出てきたり、あと数字へのこだわりですね、1とか3とかですね、いっぱい出てくるんです。結構ダジャレみたいな、そういう表現もいっぱい出てきていて、これって実は思うに、孝標女という『更級日記』の作者は、宮仕えに出たときに30数歳ぐらい、それぐらいで宮仕えしてるんですけれど、彼女が仕えた祐子内親王はまだ幼児、子供なんですよ。2、3歳ぐらいなんですよね。その後ちょっと成長していくんですけれど、ただ彼女が宮仕えした初期の時期は子供なんです。そうしたことを考えると、この旅の記録は、まだ幼い祐子内親王が読むことをかなり考えて。
城谷:
楽しめるように。
福家:
そうなんですね、作ってるんじゃないかという仮説が成り立つんじゃないか。実は祐子内親王は、主催した歌合わせを、歌合せって歌と歌を合わせて、優劣を競うという遊びなんですけれど、祐子内親王家の歌合わせって結構地名をめぐる歌合わせが多くて、ひょっとすると祐子内親王って、記録にはないんですけど、地名マニアだったんじゃないかって思ったりもするんです。そういうことを考えると、実は孝標女は自分の経験は間違いないんだけれども、それを読む、読者である祐子内親王、自分の主人のことを考えて、いわば絵本のような形で子供向けに作り直して、そうした自分の経験を書いてると。そうなってくると、読者の好みに合わせて自分の体験を改変していくということにもなってきますので、必ずしも個人に解消されない問題がそこにあるんじゃないかと思うんですね。
そんなような形で、平安時代の仮名日記、日記文学って自分の体験をそのまま書いて、『蜻蛉日記』の場合だと兼家が通ってこない悲しみみたいなものをぶちまけてるみたいですね。そういうイメージってあると思うんですけれど、もちろんそういった部分もあるかもしれませんが、もうちょっと読む人のことを意識して、ある意味『蜻蛉日記』も過剰に書いてるところもあるかもしれないし、一定の読者受けみたいな。
城谷:
そういうところを狙っているかもしれない。
福家:
そうですね。そんなふうに考え直してみても面白いんじゃないかなと思っています。
城谷:
いろいろ実験をしてやってみたっていうような要素はあるんですかね。日記にこう書いたら楽しんでくれるんじゃないかとか、こういうふうに表現したら楽しんでくれるんじゃないかとか、そういう実験的なところっていうのはあったりするんですかね。
福家:
それは十分あり得るんじゃないでしょうかね。もちろん現在は一つの日記としてまとまった完成体として書かれていますけれども、必ずしも書かれた当時はそのような形であったかどうかわかりませんよね。もっと小出しにして書いていって、少しずつ出していって後でまとめられたってことも十分考えられるでしょうから。そういう意味では、いろんな反応を見ながら書いていっているということは十分あると思いますし、『蜻蛉日記』という作品は全部で上、中、下巻、三巻に分かれているんですけど、実はそれぞれの世界が違うんですよね。上巻は兼家の歌を結構入れて、結構幸せな時代も書かれているんです。研究者によっては「幸せの記」なんていうふうに言う人もいるぐらいですね。中巻になってくるともう兼家がなかなか来なくなってしまって、ひたすら嘆き悲しんでいるような世界が書かれていく。下巻になるともっと身辺雑記的な、あと時々息子の恋愛模様みたいなものが書かれたり、非常に物語的な色彩も入ってきたりするんですよね。それを今おっしゃっていただいたような読者のリアクションを見ながら、書いていっている部分っていうのは十分考えられるんじゃないかなと思いますね。
城谷:
今私たちが読むとしても、そういったところも楽しんで読むといいかなとすごく思いました。
それと書いている当時の人たちは器用だなというふうに思って。面白いなと思うところがやっぱり今でも面白いと思うし、そういうふうにできるというのが、幼児に向けて、幼児に照らし合わせて書いたらこういうところがもしかしたら楽しんでもらえるんじゃないかってやって、それがちゃんと実現できる、出せるというのが皆さん器用なんだなとすごい感心しました。
福家:
そうですね。当時の紫式部もそうですけれども、やっぱり女房としてプロですからね。そういう自分の職分といいますか、自分の役割ということを非常によくわかっていて、それでその主人たちの期待に応えていくというところもある。
城谷:
賢いですね。
福家:
しかも紫式部の場合は自分の書きたいこともやっぱりこう書いていくと。読者の圧倒的な支持みたいなものもバックにつけて、そうした自分の思いを実現していったというところがあるのではないかと思いますね。
城谷:
では、今後取り組んでいかれたいことについてお話いただきたいと思います。先生が研究されていく中で、異分野といいますか、どこか別の分野と連携したいとか、そういうのもございますでしょうか。
福家:
先ほどの『更級日記』との関連で申しますと、2020年という年なんですけれども、実はこれ菅原孝標女が京に向けて旅だった年が1020年で、2020年は千年紀の年だったんです。実は菅原孝標女という人は『源氏物語』千年紀、2008年ですけれど、この起点となった1008年に生まれておりまして、実は2008年が孝標女の誕生千年紀だったんですが、しかし孝標女は、私自身非常に大好きなんですが、やっぱりマイナーで、紫式部にはかなわず、2008年はほぼ孝標女は特に取り上げられることも、一つか二つくらいはあったんですが、特になく、終わってしまったんです。実はあと孝標女の人生ではっきり分かるのは、1020年、旅立ちの年だけなんです。なので孝標女は唯一の1000年を記念する機会ということで、2020年に『更級日記 上洛の記千年』という本を、和田律子先生という『更級日記』などを中心に大変多くの業績を残していらっしゃる先生と共編という形で、武蔵野書院から出版させていただいたんです。実はこの本は、文学学術院の川尻秋生先生にもご執筆をいただいて、また古代の交通の専門家や、あるいは東北地方、関東地方を中心とする、専門の研究者や、あとこの上総国府付近、孝標女が4年間過ごしたところで、今やすっかり開発されてしまってるんですけれども、その開発前の区画整理前の地理的なことを示したDVDも掲載しました。そういった本を出して、これは歴史学とのコラボレーションということを考えて、出させていただいたんですね。歴史学の方法論と国文学の方法論は、違う部分もあるかと思うんですけれど、ただ国文学もかなり専門領域が細分化されてしまっていて、ちょっと表現は良くないですが蛸壺的な研究が多くなってしまうんですね。国文学ってやっぱりトリビアルな問題にかかずらわってしまうという、そういう傾向も無きにしもあらず、それは良い面もあるんですけれども。ただ、それだけではなかなか発展性もないので、歴史学とのコラボレーションは今後もやっていかなくてはいけないことだろうなと思います。
城谷:
本日は色々とお話を聞かせていただきありがとうございます。源氏物語・紫式部日記というキーワードは、私の中では知っていたつもりだったんですが、先生の著書や今回話を伺って、それが非常に広がりました。とても興味深いお話をお聞きできました。
最後に、今後国文学者を目指す、国文学に触れる機会を持ちたい人に向けて、先生から一言いただけますでしょうか。
福家:
国文学は分野が広く、時代によって古代から近現代まであるわけですが、どうしても国文学を学んでいる学生さん達は自分の好きな時代ばかり集中的に考えてしまう傾向が強くなります。やはり広く学ぶということは大事なことではないかと思います。それは国文学だけではなくて、周辺領域にも広げていくということもあると思うんですけど、蛸壺的なところでやっていてもなかなか新しい発想は生まれてこないので、広い範囲の、特に若い段階で読書、知見を広げるということを勧めたいと思います。
もう一点は、国語教育・古典教育にも関心を持っていただきたい。古典は中・高等学校では必修ではあるんですが、特に高等学校では重い位置を占めているわけですが、ただ、古典が嫌いだ、古典なんか無くなってしまえばいいのに、あるいはなぜ古典を学ぶのかわからない、といった学生が増えている。一時期までは、古典は学ばなければならないものだというふうに、ある意味前提条件となっていたところもあったと思いますが、今やそういう時代ではないと客観的に言って良いだろうと思います。古典の魅力を語れる力を身につけてほしいと思うんですね、ですから研究者として古典をより深めていくということも大事ですが、古典の魅力を語れるようになってほしい、第三者に自分の研究も含めて魅力を語れるように、是非これからの皆さんには考えてほしいなと思います。
城谷:
古典のとっつきにくさというのはあると思います。そこは背景を知ると、興味がわくなと思いました。ですので、先生の書かれた本を拝見しまして、こういうところも古典に触れるきっかけになるんじゃないかと思いました。