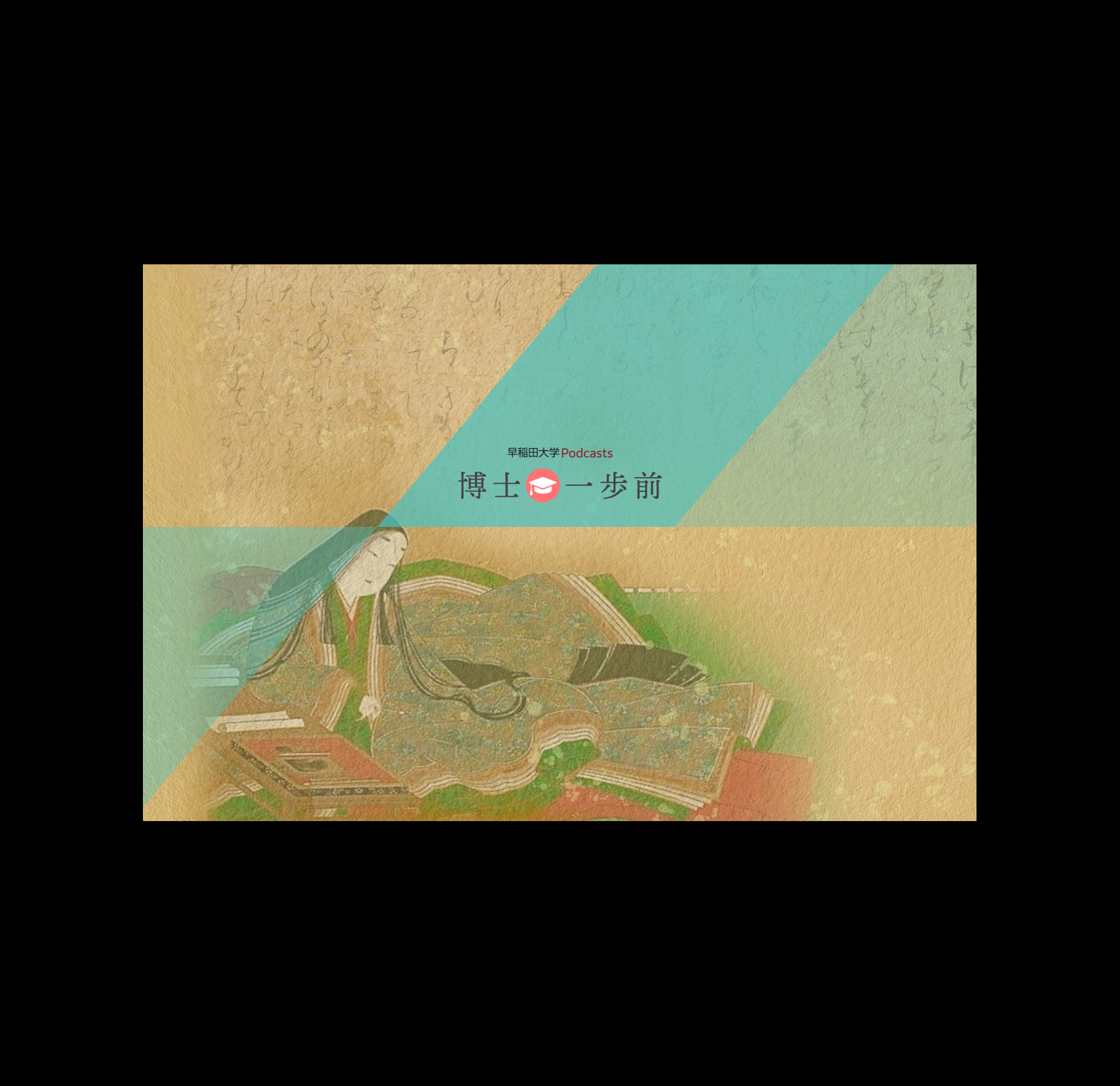- Featured Article
Vol.2 国文学(1/4)【紫式部の生涯】源氏物語、創作の動機と才女の生きた平安時代 / 福家 俊幸教授
Tue 07 May 24
Tue 07 May 24
今回から4回に渡って、教育・総合科学学術院所属で国文学を専門とする福家俊幸教授をゲストに、2023年に刊行された著書『紫式部 女房たちの宮廷生活』の内容を基に、「紫式部の生きた軌跡」「宮廷女房たちが映し出す平安社会の姿」を探求します。
初回である今回は、 日本が誇る世界最古の長編恋愛小説『源氏物語』の著者 紫式部の人生にスポットライトを当てます。才女として頭角を現し、源氏物語を執筆するに至るまでの経緯を、時代背景とともに紐解きます。
配信サービス一覧
ゲスト:福家 俊幸
教育・総合科学学術院教授。専門は平安時代の文学・日記文学。
1962年香川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学助教授、早稲田大学教育学部助教授を経て現職。著書に『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院)、『更級日記全注釈』(KADOKAWA)、共編著に『紫式部日記・集の新世界』『藤原彰子の文化圏と文学世界』『更級日記 上洛の記千年』(以上、武蔵野書院)、『紫式部日記の新研究』(新典社)、監修に『清少納言と紫式部』(小学館版・学習まんが人物館)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。
2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了。博士(理学)。2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
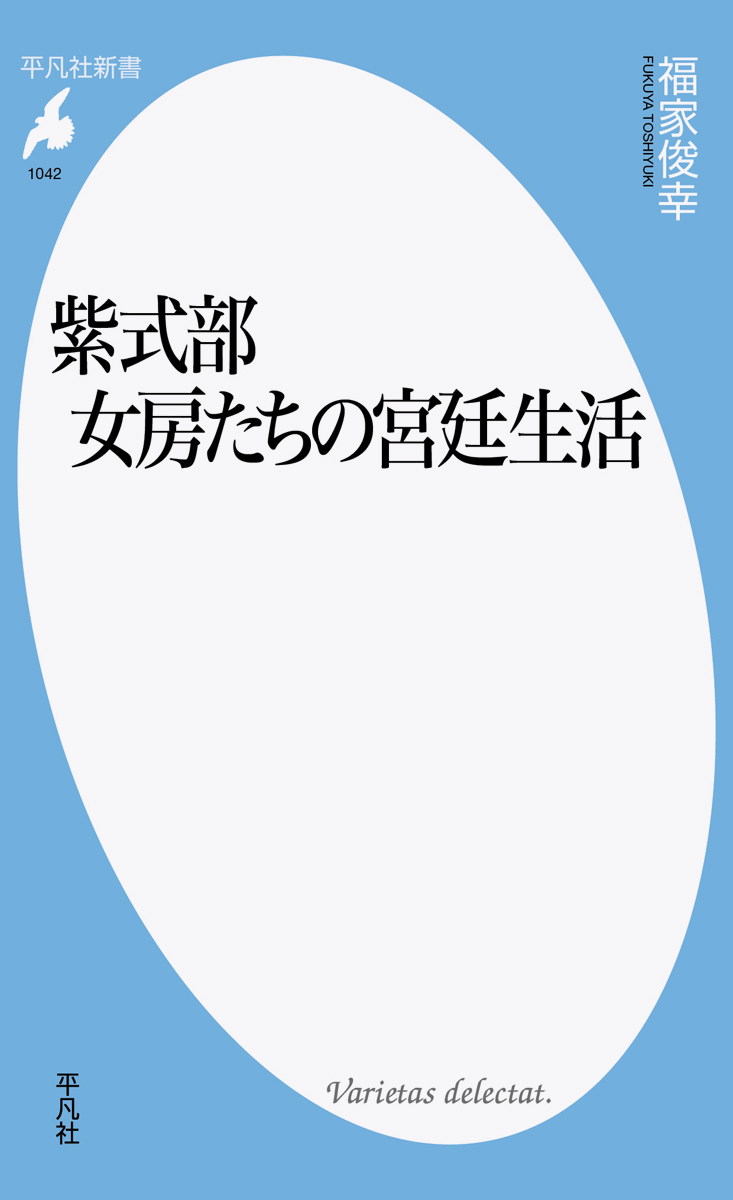
紫式部 女房たちの宮廷生活
出版社:平凡社
発売日:2023/11/15
言語:日本語
単行本:264ページ
ISBN-10:4582860427
ISBN-13:978-4-582-86042-9
-

エピソード要約
– 紫式部が残した主要な作品
世界的に著名な『源氏物語』、宮廷生活を綴った『紫式部日記』、そして彼女の晩年に編纂されたとされる歌集である『紫式部集』がある。『紫式部日記』は、紫式部が道長の娘の彰子の出産やその後の儀式など、特定の短期間を詳細に記録したものであり、『紫式部集』は彼女の一生を通じて読んだ歌のベストセレクションとして、紫式部の人生観を垣間見ることができる。
これらの作品を通して、紫式部の生涯や平安時代の宮廷文化、人々の生活が現代にも引き継がれる魅力として語り継がれている。
– 執筆の動機と紫式部の生涯
彼女が編纂したとされる『紫式部集』には、少女時代から晩年に至るまでの歌が収められており、これらを通じて彼女の人生の軌跡を残したかったと推測される。自分の作品をより広く読まれることへの願望を持ち、自己実現やステータス向上を目指していた可能性がある。
紫式部の生涯は、彼女自身だけでなく、時代背景や生まれ育った環境、そして女房への抜擢などの大きなターニングポイントによっても形成されている。特に『源氏物語』の執筆とその作品が道長に認められたことは、彼女のキャリアにおける重要な出来事であり、宮中で『源氏物語』が読まれることは彼女にとって最高の喜びだったと考えられる。
紫式部は中流貴族の家庭で育ち、漢学者であった父親・藤原為時の存在は、彼女の学問への興味と知識を形成する上で大きな影響を与えた。
『紫式部集』を通じて見る紫式部の少女時代は、一般的に想像されるおとなしいイメージとは異なり、明朗活発であり、同世代の友人たちとの歌のやり取りや人生相談が見られる。これは彼女の性格や人間関係においても、彼女が多面的な人物であったことを示している。
-夫・宣孝
紫式部は越前に赴任した父親に同行し、その地で宣孝という人物から求愛された。宣孝が持参した漢籍の多さから垣間見える教養の深さに紫式部が惹かれた可能性がある。
宣孝の死後、紫式部は『源氏物語』の執筆を始め、この作業を通じて自身の喪失感から回復していったと考えられる。初期の『源氏物語』は友人たちとのサークル内での手紙のやり取りを中心に展開された。紫式部は『源氏物語』を書くことで、自分自身を取り戻し、物語を通じてより身分の高い人々との交流の場を広げようとした。これは彼女の作家としてのモチベーションの一部であった可能性が高い。
エピソード書き起こし
城谷准教授:
まず、福家俊幸先生のご紹介をさせていただきます。福家先生は、2008年より早稲田大学 教育・総合科学学術院教授につき、学部では、国語国文学科、大学院では、国語教育専攻で教鞭を執られています。
今日は、急に雨になったということで、昨日と打って変わった天気で、すごい寒いなという気がしたんですけども、平安時代というのはどんな気候だったりするんですか?
福家教授:
平安時代は、比較的寒い時期が多かったというふうに言われています。科学的にも気温が高い時期と低い時期が交互に来るっていうことが。
城谷准教授:
地球科学の分野でもかなり調べられている。
城谷准教授:
そういったところも平安時代の中の文化とも非常に絡んでいるのかなと思いまして、先生の今回出された新書の中を拝見いたしまして、紫式部とかその時代に生きた人々は、とても秋が好きなんじゃないかなというのを感じました。先生も『紫式部日記』の中で取り上げられている秋の夕方から夜中に移るところのシーンを解説されている。そういったところがとてもいいなと思ったところです。このあたり『紫式部日記』ですとか、今回この本で扱われている紫式部の生涯を辿るというところでご注目されている紫式部が書いてきた著書、それぞれについて簡単にですが、ご説明をお願いできますでしょうか?
福家教授:
紫式部が残した3つの作品について、『源氏物語』は言わずと知れた世界的な文学として大変有名な作品ですけれども、全部で54帖というたいへん大きな物語で、光源氏の人生を中心に、また光源氏の死後の宇治を舞台にした薫・匂宮という男君と宇治の三姉妹を中心とした物語が展開されておりまして、非常に深い人間観察といったような部分にも事欠かない、非常にスケールの大きい物語になっております。それから『紫式部日記』ですけれど、これは紫式部が道長の娘の彰子という方ですね。その彰子の元で宮仕えをすることになりまして、彰子が21歳の時に出産をするんですね。初めて男御子を生むんですけれども、この時代は本当に男の御子を后が生むかどうかって大変大きな問題で。
城谷准教授:
彰子にとってもすごいプレッシャー。
福家教授:
そうですよね、おっしゃる通りです。道長にとっても待望の皇子だったわけですけれども、この皇子が生まれる場面、それからその皇子が生まれた後のお祝いの儀式などですね。それから有名な清少納言を批判した箇所も含まれていますけれども、ちょうど寛弘5年から大体2年弱ぐらいの期間の日記をまとめているのが『紫式部日記』となります。
それから『紫式部集』というのは歌集でして、これは紫式部が晩年に編纂したと言われていますけれども、いわば彼女が人生の中で詠んだ、少女時代から晩年に至るまでの歌のいわばベストセレクションみたいな感じになっております。おそらく紫式部が自分で選んだんじゃないかと言われ、全部で130首ぐらいの歌を集めていまして、紫式部の人生がある程度わかるのは『紫式部日記』と『紫式部集』の存在が大きいですね。『紫式部日記』はピンポイントですけれども、『紫式部集』はほぼ人生の大部分にわたっての歌を集めてますので、そこから彼女の人生がある程度復元されてきます。
城谷准教授:
彼女の生涯を辿ろうという今回のテーマの一つでもあるところですけれど、その『紫式部日記』と『紫式部集』が彼女の小さい頃からまた生涯全うするところまでというのが読み取れるというお話をいただきましたが、その中で『紫式部集』は特に彼女自身が選んだのではないかと。それは、紫式部自身が残そうとか、そういう思いがあったのでしょうか?自分自身をこういう人間だとか、こんな時代にこういうふうに生きてきたんだとか、こういう周りの環境だったんだとか、そういうのを残したかったという意図はあったんでしょうか?
福家教授:
この時代の歌を詠む人は、自分の詠んだ歌をですね、歌集として残したいと強く思うわけです。その歌集の中には、例えばいろんなテーマごとに集めたりとかですね、もちろん本人ではなくて第三者がおそらく選んだであろうっていう歌集も結構多いんですけれども、『紫式部集』の場合は彼女が選んでいると一般的に考えられていて、その歌が少女時代から晩年に至るまで、そのすべてがすべてしっかり年代順ではないんですけれど、大体大まかに見て若い頃から少女時代から中年期、晩年に至るまで、そういう順番にのっとりながら収められているんですね。ということは、自分の人生の軌跡を、歌を通して残したいというのが実際あったんじゃないかと思いますね。
城谷准教授:
それを今我々が読めるというのは、そしてそこからいろいろ感じ取ったり、こういうふうに先生とお話をさせていただけるきっかけができるというのは、すごく嬉しいことだなと思います。
この点について掘り下げていきたいと思います。紫式部の生涯は、自分一人で進んでいったわけではないと思うんですね。時代背景ですとか、あと生まれ育った環境ですとか、あと大きなターニングポイントと私が先生の本を読んで感じたのは、女房への抜擢というところが大きいかなと思うんです。それに絡んで、まず『源氏物語』が、書いて、それが道長の目に留まって、というストーリーがあるかと思うんですけれども、少女時代から『源氏物語』を書こうといった、勝手に言ってしまうと初期というか、そのあたりをちょっとお聞かせいただけますか?
福家教授:
紫式部は、中流貴族の娘と言われているんですけれども、お父さんは藤原為時という人でありまして、漢学者として非常に有名な存在です。身分こそ中流貴族ですけれども、当時はもう誰もが知る、そういう漢文学の大家と考えられていた。その人のもとでずっと育てられてきて、お母さんは病気か何かで早く亡くなったことはどうも確かのようなんですけれども、父親によって育てられた部分が大きかったということです。当然貴族ですので、乳母(めのと)、今で言う乳母(うば)はついてますけれども。その大学者の為時からいろんな薫陶を受けていたことは確かだろうと思うんですね。紫式部は、彼女の日記の中に書いているんですけれども、紫式部の弟に惟規という人がおりまして、当時漢文学は男の学問ですので、為時は一生懸命弟の惟規にマンツーマンで教えていたんですけれども、紫式部は女性ですので、目の前にはいないわけですね。ただですね、耳で聞いていたわけでしょうけれども、不思議なほどですね、父親が弟に教えているその漢文の内容が頭に入ってきたと。それを知った為時は、「お前が女の子であったことは本当に残念だ」と、男の子であればよかったのにと言ったというエピソードを日記の中に彼女は記しています。それだけ耳学問であっても、お父さんからの教育が大きかったと思うんですね。
実は、『紫式部集』を読んでみますと、我々の紫式部というと結構おとなしいとか、そういったイメージが強いかと思うんですが、実は歌集を読んでいきますと、同じような年頃の同性の友人ですね、女の子の友人たちといろんな歌のやりとりをしていまして。
城谷准教授:
そうでしたね。
福家教授:
いろんな人生相談にものっていたりするんですよね。そういったやりとりを見てみますとですね、かなり明朗活発な少女時代が見えてくると。これ後年のイメージとはだいぶ違う、根はそういう部分があったのかなと思うんです。そういった中で彼女は、お父さんの為時が越前守になり、現在の福井に赴任をして、彼女は一緒にくっついていくんですけれども、実はそこに宣孝という人物が彼女に求愛をしてきて、ひょっとしたら都にいた頃からももうすでに求愛していたのかもしれませんけれども、その宣孝の求愛を受け入れて、一足先にお父さんを置いて都に戻ってきます。
城谷准教授:
なかなか宣孝も求愛が届かなかったような、そんなようなところをこの本で読んだんですけれども、宣孝が紫式部に求愛した彼女の魅力とか、紫式部はどんなところでOKしたというのはあるんですか?
福家教授:
紫式部よりも夫の宣孝は20歳くらい年上のようなんですね、実は宣孝の長男と紫式部はあまり歳が変わらないといった感じでありまして。そういったところもあって、おそらく宣孝には他に奥さんもいたわけでしょうし、ですからなかなか踏み切れない気持ちもあったんだろうと思います。ただやっぱり越前に下ってまで求愛の歌を送ってきて、情が施されたという部分もあったかもしれませんし、宣孝も実は大変な教養人であったようで、『紫式部日記』には宣孝が持ってきていた漢籍のたくさんの本があって、それがいま虫の巣に、和本にはシミというのが入りますけれども、虫が食べちゃうわけですよね、和本の糊をですね、そのシミが入ってしまってもう本の体裁をなしていないようになっているけれども、と宣孝が持ってきてくれた漢籍について記していたりもしまして、大変な教養人だったとわかっております。そういったところも紫式部が惹かれた部分もあったかもしれません。
城谷准教授:
夫が亡くなってから『源氏物語』を執筆という流れになるかと思うんですけども、初期の『源氏物語』の雰囲気ですとか、状況ですとか、あと彼女の思いから道長に抜擢された後に、ある種職業作家というところが入ってくるかと思います。そのあたりになってからの彼女の思いですとか、『源氏物語』ってどんなふうに変わっていったのか。
これからこの新書を、先生の本を読んだり、『源氏物語』に興味を持って本を読むっていう人に向けて、どういったところに注目して読むと面白いとか、をお聞かせいただけますか?
福家教授:
宣孝に先立たれまして、宣孝との間には賢子という娘も残されていて、まだ賢子も幼い。おそらく1年間の喪に服すことになったと思いますけれども、そういった中で彼女は自分の人生をどのようにこれから展開していくのかを考えたと思うんですね。『紫式部日記』の記述などを重ね合わせていきますと、そうした夫を失った悲しみから抜け出すように、物語を中心とした一種のサークルといいますか、友人たちと物語を中心にしていろいろ手紙のやり取りをすると。そういったところの物語が、『紫式部日記』の中には儚い物語と言ってますけれども、そうした儚い物語が『源氏物語』の初期の巻々だったのではないかと現在の学会の大部分の方は考えていらっしゃるんですね。
つまり『源氏物語』の初期の巻々は、そうした友人たちとのサークルの中で書き始められて、彼女はそうした物語を書くことを通してだんだん自分を回復していくと言いますか、自分自身を取り戻していったという部分があったんだろうと思います。そして『源氏物語』を書き始めていったわけですけれども、『紫式部日記』の中で非常に興味深いのは、そうしたサークルの中で物語が作られていく中で、実はちょっと自分とは縁遠い、「気遠き人」と言ってるんですけれども、「気遠き人」を伝手を使って近づいていって、交流の場を広めていったって言ってるんです。でも、この「気遠き人」が一体どういう人なのかは、はっきり日記の回想の中には書かれていないんですけれども、おそらくは『源氏物語』をより自分よりも身分の高い人たちのもとに伝手を辿って広めようとしたのではないかと考えられるのではないか。
城谷准教授:
彼女のモチベーションもそういうのがあったんじゃないかと。
福家教授:
おっしゃるとおりですね。
城谷准教授:
そうなんですね。
福家教授:
作家はおそらく自分の作品をより広い世界で読まれたいといいますか、読んでほしいって思いを抱くんじゃないかと思うんですね。それは自己実現にも繋がってくるんじゃないかなと思うんですけれども、『源氏物語』を通して自分のステータスを上げていこうという、ある種の野心みたいなものも紫式部自身が持っていた可能性があると思うんですよ。
城谷准教授:
それで、道長に抜擢されたというのは、彼女にとっては良かったと考えてもいいんですかね?
福家教授:
そうじゃないでしょうか。『源氏物語』の評判が道長の耳に届いて、推測が正しいとすれば、紫式部が求めていた、まさにその道長の娘は時の天皇の一番地位の高い后であるわけで、そういったところで『源氏物語』が読まれていくというのは、彼女にとっては最高の喜びではあったと思いますよね。