- Featured Article
Vol.10 労働法学(1/2)/【「働く」の再定義】AI時代のキャリアと多様性/ 水町勇一郎教授
Wed 16 Jul 25
Wed 16 Jul 25
今回と次回の二回にわたって、早稲田大学法学学術院の水町勇一郎教授をゲストに、「労働法の羅針盤でひらく 激動の時代の働き方」をテーマにお届けします。
AIの台頭やライフスタイルの多様化により、私たちの「働き方」は多様化しています。
「正社員か非正社員か」といった働く立場による画一的な視点ではなく、最高裁判決を例に、個々の労働状況に応じた公正な答えを探る「複眼的な視点」で公正な判断を導く「法の“文脈化”」という考え方に、労働法の第一人者である水町教授の解説から迫ります。
変化の激しい時代を柔軟に乗りこなすための、新しい視点が見つかるはずです。
配信サービス一覧
ゲスト:水町 勇一郎
1990年東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員、東京大学社会科学研究所教授などを経て、2024年4月より早稲田大学法学学術院・法学部教授。専門は労働法学。
働き方改革実現会議議員、新しい資本主義実現会議三位一体労働市場改革分科会委員、規制改革推進会議働き方・人への投資ワーキング・グループ専門委員、労働基準関係法制研究会参集者等を歴任。
著書:『労働法〔第10版〕』(有斐閣、2024)、『詳解 労働法〔第3版〕』(東京大学出版会、2023)、『労働法入門〔新版〕』(岩波書店、2019)
『社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全』(KADOKAWA、2025)
ホスト:島岡 未来子
研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。
2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。

左から、島岡未来子教授、水町勇一郎教授。
早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリ)のスタジオで収録。
- 書籍情報
-
-
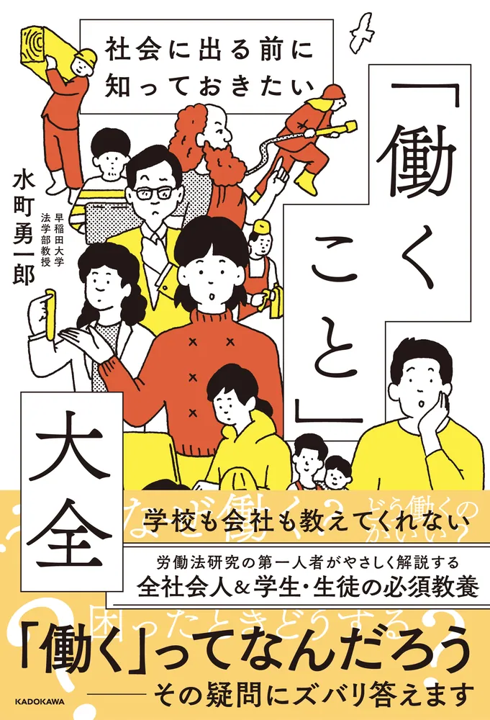
社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全
出版社 : KADOKAWA
著 者:水町 勇一郎
出版年月 : 2025年03月26日
言語 : 日本語
ページ数:360ページ
ISBN:9784041151228
-
エピソード要約
-「働くこと」とは
「働くこと」は、近代的な概念として「指揮命令に基づいて働き、報酬を得る」ことと説明され、社会的つながりの構築や経済的豊かさを得るといった”喜び”の側面がある一方、自由や手段性の制約といった”苦しみ”の側面も存在している。水町教授は、「働くこと」の意味は1つではなく、時代や社会背景によっても変化するため、働くことに対して多面的な視点を持つことは、人生においてより豊かな選択や前向きな行動につながると述べている。
-「働き方改革」の現状と今後の課題とは
政府が進める「働き方改革」は、正規・非正規の格差是正と、過労死を含む長時間労働の是正という2本柱で、法的整備(罰則付き労働時間の上限規制、不合理な待遇差の禁止)を進めてきた。この改革により、長時間労働による過労死や過労自殺のリスクは可視的に減少し、非正規への待遇改善も一部で進展がみられる。
しかし、欧米と比較して正社員は残業前提の働き方が根強く、欧米と比較して労働時間は長く、「フェーズ2」の更なる働き方改革が必要な状況である。水町教授は、今後、AIをはじめとしたデジタル化の本格的な進展による人間とデジタルの仕事のすみわけと少子高齢化の進展と合わせた労働環境も考慮した上で、働き方改革を推進することが重要になると述べている。
-働き方に対する現代の法解釈とそこから読み取れることとは
変化が激しい現代において、自分自身の能力や価値をどのように育て、どのような労働環境で働き方を選ぶか、日本の働き手に求められている。昨今、定年後に同様の業務内容を継続しているにもかかわらず職位の違いにより待遇が引き下げられたことに対する判決においても、不合理な格差があれば違法と判断される可能性が示された。近年の判決からも、現代の法解釈は「白か黒か」といったステレオタイプ的な二分法ではなく、状況に応じた柔軟な判断を尊重する方向に進化されている。
水町教授は、科学技術やAIの進展による予測困難な時代に突入している中、労働法は変化に対応しながら人間の尊厳や安心を守りつつ、より良い社会の在り方をともに模索する役割を担っていると述べている。
エピソード書き起こし
島岡教授(以下、島岡):
前回に引き続き、法学学術院シリーズをお届けします。
今回は2回にわたり、早稲田大学法学学術院の水町勇一郎教授をお迎えし、「労働法の羅針盤で拓く、激動時代の働き方」と題して、現代の働き方をめぐる課題や展望についてお話を伺います。水町先生、どうぞよろしくお願いいたします。
水町教授(以下、水町):
よろしくお願いいたします。
島岡:
まず初めに、水町先生のご経歴をご紹介します。
水町勇一郎先生は1990年東京大学法学部卒業、東北大学法学部助教授、パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員、東京大学社会科学研究所教授などを経て、2024年より早稲田大学法学学術院法学部教授としてご着任されています。
ご専門は労働法学で、日本の労働法研究をリードされてきた第一人者でいらっしゃいます。
とりわけ、政府の「働き方改革実現会議」では委員として参画され、また、「新しい資本主義実現会議」の分科会委員など、国の労働政策形成に関する重要な議論の場において中心的な役割を果たされてきました。
アカデミックな領域での教科書、専門書はもちろん、2025年3月刊行の『社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全』など、身近な視点から労働を捉えた著書も執筆されています。
それでは、水町先生から、研究分野の概要と、本日の収録にあたってお一言いただけますでしょうか。
水町:
ありがとうございます。私の専門は「労働法」という分野で、簡単に言うと「働くこと」に関する法的なルール全般を扱っています。具体的には、労働基準法や労働組合法などがあり、非常に多岐にわたります。
労働法の面白い点は、まず「働くこと」が私たちの生活と密接に関係しているという点です。人が80年、90年と生きる中で、最も長く費やす活動はおそらく睡眠時間ですが、その次に長いのが「労働時間」だと言われています。時には睡眠時間を超えてしまうこともありますね。このように、「働くこと」は私たちの日常生活と深く関わっています。さらに、働き方は社会や経済にも密接に関係しております。今進められている「働き方改革」によって、より働きやすい環境が整い、それが社会全体の豊かさにもつながっていきます。
また、労働は哲学的な意味や人間の存在のあり方にも関わってきます。私が授業の第1回目で学生に必ず問いかけるのが、「皆さんにとって、働くことの“喜び”とは何ですか? “苦しみ”とは何ですか?」という問いです。回答は「喜び」と「苦しみ」で半々になることが少なくありません。景気が良いとアルバイトなどの経験も含めて働くことが心地よく感じられ、「喜び」と捉える学生が増えますが、不況になると「苦しみ」と捉える学生が増えます。今は半々くらいかもしれません。
しかし、歴史を振り返ると、働くことは「苦しみ」とみなされていた時代や、「喜び」とされてきた時代があり、それは宗教や哲学、社会構造の影響を受けながら変遷してきました。
このように、「働くこと」に関連する労働法は、人間の根源に深く関わっていると同時に、常に変化しています。私が労働法という学問を研究する楽しさについて、本日、お伝えできればと思います。
島岡:
短い時間の中で、労働法が非常に多面的な領域であることをお話いただき、ありがとうございます。
それでは最初に、水町先生が研究される前提とされている「働く」ということの定義や考え方についてお伺いします。先生の最新刊『社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全』でも言及されておられますが、そもそも「働くこと」は何を指しているのか。そして、その定義について、先生の研究において、前提とされている考え方をお聞かせいただけますでしょうか。
水町:
「働く」という日本語は、漢字で書くと「人偏に動く」と書きます。基本的には「人が頭や身体を動かすこと」が働くことの根本にあります。現代的な法律の世界では、これに「誰かの指示・命令を受けて働き、その対価として報酬を受け取る」という点を加えたものを「労働」と定義しています。
「働くこと」の意味は時代背景によって大きく異なりますが、私が伝えたいのは、働くことの意味は決して一つではなく、多様であるということです。働くことに「社会的つながり」を感じる人もいれば、「経済的な自立」の手段として捉える人もいます。授業で、「働くことは喜びか苦しみか」と学生に問い、なぜそう思うのかを尋ねると、喜びとして挙げられる理由には、「人とつながること」や「経済的な安定」があり、苦しみとしては「自由が制限される」「やりたくないことを強いられる」といった意見が出ます。組織の利益、発展のために、自由に行動できない「他律性」と「経済的利益」を得るための「手段性」が混在しているのです。
また、「お金を稼ぐ」ということも、本来は何か目的のための手段だったはずなのに、いつの間にかお金を稼ぐこと自体が目的になってしまい、自分がなぜ働いているのか分からなくなるといったジレンマも生まれます。
このように、「働くこと」には多様な側面があり、それらを認識することが重要であると考えています。
島岡:
まさに今のお話にあったように、「働くこと」が多面的であるからこそ、時に苦しみと感じる方もいれば、楽しみと捉える方もおり、状況が変化したときに、自身の働き方を俯瞰し、異なる視点で見つめ直せることは、人生をより豊かに、そして前向きにしてくれるものだと感じました。
それでは続いて、先生が委員として関わられた「働き方改革」についてお伺いします。制度としての狙いや、その実施によって現場にどのような影響があったのかなど、詳しく教えていただけますでしょうか。
まず、政府の「働き方改革実現会議」で委員を務められたご経験から、この改革が目指した本質的な意義や、労働法の観点から見た最も重要なポイントについてお聞かせください。
水町:
実は、それぞれの国には歴史を積み重ねる中で独自の「雇用システム」、いわゆるアメリカ型、フランス型、そして日本型などが存在します。
その中で、日本的雇用システムは、「終身雇用」「年功序列」「企業別労働組合」という三つの要素に特徴づけられています。これらは欧米の先進諸国と比べても非常に特徴的で、これを言い換えれば、「正社員中心主義」ともいえます。終身雇用や年功序列では、年齢や勤続年数に応じて昇進・昇給していく仕組みがあり、また、企業別労働組合では加入している労働者の多くが正社員であることが多い。
この仕組みには良い側面もありましたが、1990年代後半以降、「失われた30年」とも呼ばれる経済低迷の中で、そのシステムの弊害が顕在化しました。具体的には、正社員以外の「非正規雇用」が急増し、両者の格差が拡大したことで、正社員でないと生活維持が難しいという構造が生まれてしまいました。加えて、そのような環境下から正社員の労働時間の長時間化が増加し、過労死や過労自殺、メンタルヘルスの問題も深刻化していきました。
こうした課題を受けて、「働き方改革」が目指したのは、「長時間労働の是正」と「正規・非正規の格差是正」の2点です。労働基準法では、「これ以上働いたら命に関わる」というレベルの上限時間を罰則付きで明記し、長時間労働を抑制する仕組みを導入するとともに、正社員と非正規社員の間に「不合理な格差」があってはならないという原則を法律に明記し、待遇格差の是正にも取り組み、現在も継続的に改善が図られています。
島岡:
その働き方改革によって、実際の労働現場にはどのような変化や影響があったと先生は評価されていらっしゃいますか。また、期待された効果と現実との間にギャップがあるとすれば、それは、どのような点にあるとお考えでしょうか。
水町:
罰則付きで、1ヶ月あたり週40時間を超える時間外労働の上限が設定されました。具体的には、残業が月100時間以上、または月平均80時間を超えてはならないという規定で、過労死や過労自殺につながるような長時間労働は、目に見えるか形で減少しています。また、正社員と非正社員の格差に関しても、例えばこれまで正社員のみに支払われていた手当を非正社員にも支払うような動きもあり、一部で改善が進んでいます。
しかしながら、この2点を見ても、長時間労働は減ってきたとはいえ、残業を前提とした働き方が正社員には依然として多く、欧米と比べても正社員の労働時間は長い状況にあります。定時に退勤して家族と食事をするということは、今なお難しい状況です。また、正規・非正規の格差についても、基本給や退職金などの制度面で、正社員と非正社員が同一である企業は大企業を中心にまだ少なく、格差是正は部分的に進んでいるものの、抜本的な解消には至っていません。このように、働き方改革は道半ばにあり、今後さらに推進・後押ししていく必要があります。
さらに、デジタル化や少子化という課題があり、働き方改革のフェーズ2と呼ばれる新段階において、これらの問題にどう対応していくかが重要な課題となっています。
島岡:
先生がおっしゃったフェーズ2の課題であるデジタル化や少子高齢化は、現代社会の大きな潮流として無視できません。
こうした社会変化の中で、私たちの働き方はどのように変わっていくべきでしょうか。
また、急速なAIの発展やリモートワークの普及などデジタル化が進むなかで、労働法や関連する制度は今後どのように進化していく必要があるとお考えでしょうか。
水町:
私は、アメリカやヨーロッパ、フランスの現場に出張すると、働く現場にデジタル化の影響はかなり出てきていると実感していますが、その一方、日本ではまだデジタル化の影響は部分的にとどまっており、全面的なデジタル化には至っていない状況です。しかし、日本も今後デジタル化が大きく進展すると考えられ、その際、欧米の先進諸国の事例を見てみると、起こることは主に2つあると思います。
1つはAIやロボットによって人間の労働が部分的に代替されることです。ただし、完全な代替ではなく、AIの得意な部分と人間の得意な部分をうまく組み合わせつつ、その制御・コントロールは人間が補完する、という働き方が増えていくでしょう。また、完全にAIに任せられる分野も増える一方で、AIにはできない、人間にしかできない部分の価値はさらに高まっていきます。人間にしかできない仕事とは、創造的な仕事やイマジネーションを用いた顧客への提案、ヒューマンスキル、価値判断などが挙げられます。特にAIに任せられる仕事が増えるほど、対人関係能力や価値判断力が重要となり、これらの能力を育て付加価値を高める教育訓練が大切になります。そのような教育機会を幼少期から高等教育までに身につけることが重要になり、その一方、いわゆるリスキリングも不可欠になると考えています。
もう1つは、働く現場における監督方法の変化です。これまでは直接、上司が指導・監督していましたが、リモートワークによる勤務場所の分散勤務が普及することにより、人間による直接の監督が減り、代わりにAIによるアルゴリズム監視が広がっていきます。例えば、パソコンの操作や検索履歴、音声や文字入力も分析される「監視社会」へと進展し、日常生活から労働時間中まで、情報が取られるようになります。そのような社会で、人間性やプライバシーの保護を、労働法の中でどう守るか、新たな課題となっています。
島岡:
先生がおっしゃった前半のリスキリングの話で、キャリアオーナーシップという概念がありますが、詳しく教えていただけますか。
水町:
キャリアオーナーシップは日本企業でも注目されています。例えば、アメリカなどでは、大学や大学院で専門能力を磨き、それに基づいて仕事を選び、身につけた能力が古くなれば、必要に応じて再教育を受けながらキャリアを築くのが一般的です。
一方で、日本は企業に入社後は人事部が配属を決め、配属後の異動のジョブローテションも社員が自らのキャリアを主体的に選択できない状況でした。しかし、これからは自身の能力を高め、どのようなキャリアを望むかを自らが選択しつつ、自身のアウトプットをもとに企業の付加価値を高めるよう、企業も従業員の成長を支援する方向に変わっていきます。
AI等が進化する中、自身のキャリア展望を主体的に考え能力開発を行うことが、今後、より重要になってきます。
島岡:
そうですね、大学生や社会人の皆さんも、ご自身のキャリアを主体的に考えることの重要性を改めて認識されたと思います。
ところで、2つ目に先生がおっしゃった、AIによる監視社会について法律的にどう考えるかということも大変興味深いのですが、現在の方向性やアプローチはあるのでしょうか。
水町:
アメリカではAIの進化と合わせて、企業の自主規制に任せる動きがありますが、EUは企業による自主規制だけでなく法的ルールを整備しています。例えばEU指令というルールにより、どのような情報を労働現場で取得できるか、利用の透明性や基準を明確にして、労働者が取られる情報をコントロールできるような取り組みが行われています。
日本では、個人情報保護法により個人情報は守られていますが、本人の同意が前提となるため、実質的にはサービスを受けるために個人情報の取り扱いを同意しなければならない状況です。何について自分の情報を渡しているのか分からないまま同意しているのが実態なので、利用実態の透明性が担保されていません。
EUは、同意は大切だけど同意だけでは万能ではない前提で、例えば、労働現場で取得できる情報のうち、どの情報を取得しどのように利用するかの基準を設け、その運用結果を示すよう、透明性を高めるようなルール作りが始まっています。
今後、日本でも現行の個人情報保護法を考慮しながら、監視社会への対応も行える法整備が労働法の中でも重要な課題になっています。
島岡:
日本は、少子高齢化による労働人口減少が深刻な問題となっていますが、その対策として、働き方の多様化や法制度面でのアプローチはどうあるべきでしょうか。
水町:
日本は労働人口減少の先進国として、これまで十分に活用できていなかった女性や高齢者、外国人など多様な労働力を活かすために、働きやすいシステム改革が必要になります。そのためには、差別の禁止や、時短勤務や休暇を取りやすい働き方など、ダイバーシティに対応できる多様な働き方を認める法制度の整備が不可欠です。
また、予測不可能な変化の激しい時代に対応する必要があります。そのためには、付加価値の高い仕事に移行できるよう、労働市場の流動性を高め、柔軟にキャリア形成やリスキリングができる支援が必要です。
例えば、これまでは雇用保険加入者に限られていた教育訓練の機会を、フリーランスやこれまで働いてこなかった方々にも拡充するなど、働き方改革のフェーズ2として拡充に向けた取り組みを進めているところです。
島岡:
ありがとうございます。ここからは、前半の最後として、判例から社会の変化を読み解いてみたいと思います。
近年の重要な判例をいくつか取り上げていただき、現代の働き方にどのような問題提起をし、社会にどのような影響を与えたかを解説していただけますか。
水町:
判例とは、裁判所の最終判断である最高裁の決定で、その後の社会や法律の解釈に影響を与えますが、ここでは、最近の判例で時代を表している2つの判例をご紹介したいと思います。
まず1つ目は、2023年7月11日の「国・人事院(経産省職員)事件」です。経済産業省に勤務していたトランスジェンダーの公務員の方が、自身の性自認に基づいて女性用トイレの利用を希望したところ、経済産業省は執務室がある階とその上下合わせて3階分の女性トイレの利用を制限しました。最高裁は、この制限が本人の日常的な不利益を軽視しており違法であると判断しました。これは多様性や個人の人格尊重を最高裁が重視した重要な判決です。
もう1つは、2023年7月20日の「名古屋自動車学校事件判決」です。60歳定年後に嘱託職員として再雇用された自動車学校の教官が、同じ仕事を続けながら給与と賞与が約半分に減額されたことについて争われました。最高裁は、正社員と非正規社員の職位の違いで画一的に格差を設けるのではなく、基本給や賞与、労働内容の性質、会社と労働者との交渉経緯を踏まえて合理性を判断すべきとして、名古屋高裁に差し戻しを命じました。これは、正社員・非正規社員という型にはまったステレオタイプの判断を行わない、固定概念を見直す判決と言えます。
島岡:
私自身も驚きました。判決は白黒の決着だけでなく、より柔軟で具体的な判断が求められているということですね。また、今後、AI自体が労働力になると、これまでの判例に無いことが起こりえると思いますが、法学の世界ではどのように考えられていますか。
水町:
多様で予測困難な社会に対応するため、法律も1つの傾向があり、単純な機械的な判断ではなく、当事者間の話し合いや具体的事象を踏まえ、公正な判断を行うことが重要になっています。複眼的な視点を持ち、自分で選択して職種を選択するということを後押しするように、法律の解釈も方向性が変わってきていると思います。
島岡:
判決と言うと「白か黒か」という印象を持っていましたが、柔軟な対応が行われ始めているということで、法律の世界も進化していると理解してよろしいでしょうか。
水町:
進化と言えるか分かりませんが、そのように変わってきているということですね。
島岡:
AI時代のように不確実性が高まる社会において、法律はどう対応していくでしょうか。
水町:
科学技術の発展は止められないので、その発展の中、どのように人間を守り、より良い社会を作るか、我々が考え続け、それを両立する社会を作るのが法律の役割だと思います。
島岡:
前編では、働くことの本質、働き方改革の意義と影響、さらにはデジタル化・少子化に対応した法制度の展望まで幅広くお話を伺いました。
後編では水町先生の研究の歩みや国際比較から見える日本の働き方の特徴、研究の社会実装、次世代へのメッセージなどをさらに深く掘り下げてまいります。
『早稲田大学Podcasts:博士一歩前』次回のエピソードもどうぞお楽しみに。
水町先生、本日はありがとうございました。
水町:
ありがとうございました。







