- Featured Article
Vol.10 労働法学(2/2)/【労働法は”生き方”の教養】解雇と異動でひもとく日本型雇用のユニークさ / 水町勇一郎教授
Thu 24 Jul 25
Thu 24 Jul 25
早稲田大学法学学術院の水町勇一郎教授をゲストに、「労働法の羅針盤でひらく 激動時代の働き方」の後編をお届けします。
日本ではなぜ解雇が難しく、異動は容易なのか?後半の今回では、水町先生の研究者としての歩みに触れながら、 労働法学の第一人者・水町勇一郎教授が、解雇と異動を切り口に日本型雇用のユニークな仕組みを解き明かします。複雑な法制度をシンプルに解説し、諸外国との比較や働き方改革の裏側にも言及。「労働法は自分の生き方を考えるための教養だ」と語る教授の言葉から、キャリアを見つめ直すヒントを探ります。
配信サービス一覧
ゲスト:水町 勇一郎
1990年東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、パリ西大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員、東京大学社会科学研究所教授などを経て、2024年4月より早稲田大学法学学術院・法学部教授。専門は労働法学。
働き方改革実現会議議員、新しい資本主義実現会議三位一体労働市場改革分科会委員、規制改革推進会議働き方・人への投資ワーキング・グループ専門委員、労働基準関係法制研究会参集者等を歴任。
著書:『労働法〔第10版〕』(有斐閣、2024)、『詳解 労働法〔第3版〕』(東京大学出版会、2023)、『労働法入門〔新版〕』(岩波書店、2019)
『社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全』(KADOKAWA、2025)
ホスト:島岡 未来子
研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。
2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。

左から、島岡未来子教授、水町勇一郎教授。
早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリ)のスタジオで収録。
- 書籍情報
-
-
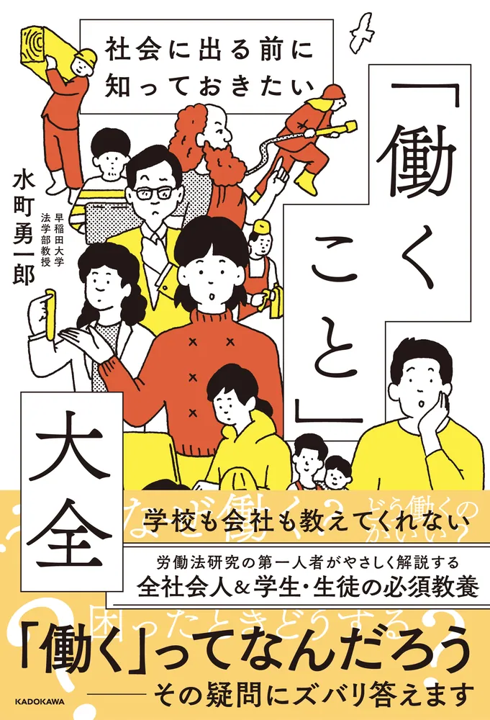
社会に出る前に知っておきたい 「働くこと」大全
出版社 : KADOKAWA
著 者:水町 勇一郎
出版年月 : 2025年03月26日
言語 : 日本語
ページ数:360ページ
ISBN:9784041151228
-
エピソード要約
-研究者として大切にしてきた視点とは
水町教授は、研究者として「複眼的な視点」と「明快で伝わる表現」の2点を重視してきた。フランスでは法と歴史・哲学、アメリカでは法と経済学という異なる価値体系に触れた経験を通じて、多面的な視野の必要性を実感。加えて、「Clarté(明快さ), Simplicité(簡潔さ), Élégance(優雅さ)」という理念に基づき、複雑な法制度も論理的に整理し、わかりやすく社会へ発信することを大切にしている。学生や市民との対話も重視し、法学を「開かれた学問」として社会とつなげる姿勢がうかがえる。
-国際比較で見える日本の働き方の特徴と課題
水町教授は、日本の労働法と雇用システムの特徴として、正社員を中心とした終身雇用や企業別組合、解雇規制と柔軟な人事制度の共存を挙げる。これらは高度経済成長期に発展した日本独自の制度であり、アメリカの「解雇自由」やフランスの「労使合意重視」とは異なる。ただしグローバル化により各国の労働法は共通点を増しており、日本も多様性の受容や長時間労働の是正といった課題に対応しながら、独自性と調和を図る法整備が求められていると述べている。
-「働くこと」と「生きること」の関係を見つめ直す意義
激動の時代において、水町教授は「どう働くか」の前に「どう生きたいか」を問い直す姿勢の重要性を説く。労働法の知識は、個人のキャリア選択や社会的判断を支える教養であり、若い世代にとっても有益だと指摘。情報や知識を積極的に取り入れ、自らの意思で働き方を選び取る力が今後ますます求められる。誤った選択もやり直せるという柔軟な姿勢と、主体的な学びの継続が、よりよい生き方と働き方の実現につながるというメッセージが込められている。
エピソード書き起こし
島岡教授(以下、島岡):
『早稲田大学Podcasts:博士一歩前』、今回も村上春樹ライブラリー国際文学館2階のスタジオから、法学学術院シリーズをお届けしております。
前回に引き続き、水町勇一郎先生をゲストに迎え、「労働法の羅針盤で拓く、激動時代の働き方」をテーマにお話を伺います。
後半では、水町先生の研究者としてのこれまでの歩みや国際的な視点、研究と政策・社会との接点、さらにはこれからの時代を生きる私たちへのメッセージについてお話いただきます。
水町先生、どうぞよろしくお願いいたします。
水町教授(以下、水町):
よろしくお願いいたします。
島岡:
後半の冒頭では、水町先生の研究者としての歩みについてお伺いしたいと思います。なぜ労働法という分野を志され、どのような経験を積まれてきたのか、その背景に迫りたいと思います。
先生は東京大学法学部をご卒業後、東北大学、東京大学社会科学研究所を経て、現在は早稲田大学で教鞭を執られています。これまでのキャリアを振り返って、研究者として特に大切にされてきた視点や哲学についてお聞かせください。
水町:
大変難しいご質問ですが、大きく二つ挙げられます。
一つは、複眼的に物事を見ることです。働くことにはさまざまな実態や側面があるため、できるだけ多様な観点から捉えることを大切にしています。
実際に、20代のときにフランスへ2年間留学しましたが、フランスの労働法学は日本と大きく異なり、歴史や哲学を重視しています。日本のように比較法の手法で外国法と比較するのではなく、フランスでは法律がない時代からどのような社会の中で歴史的変遷を遂げてきたかを研究し、法と歴史・哲学の関係を深く考察します。
その後、30代で1年間アメリカに留学しましたが、アメリカでは歴史や哲学よりも法と経済学が重視されており、労働法も経済学的効果分析によって法制度を評価します。日本に戻ってからも、歴史・哲学、経済学の両面から労働問題を考察することが重要だと実感しています。
こうした多角的な視点で物事を捉えることがまず大切です。
もう一つは、論理的にクリアで分かりやすく分析し、伝えることです。
フランスで教わった言葉に「Clarté, Simplicité, Élégance」(明快さ、簡潔さ、優雅さ)があります。法は複雑であるがゆえに、どれだけ明快に分析し、シンプルに整理し、かつエレガントに表現できるかが真の法学者の姿だと教わりました。
私はこれを心掛け、難しい問題ほど論理的に分析し、最終的には分かりやすくシンプルに伝えることが本質に近づく道だと考えています。
また、学生や実務家、一般の方々、政治家の方々とも対話し、社会に分かりやすく発信することを重視しています。労働法学の本質は、多面的に問題を捉えつつ、多くの人に理解と議論を促すことにあると考えて研究に取り組んでいます。
島岡:
なるほど。先生が法律、そして労働法に関心を持たれたきっかけや原体験についてもお聞かせください。
水町:
私は1980年代後半に大学生でした。最初の1、2年は理科系でしたが、3年生から法学部に移りました。法学とはどのような学問かと考え、憲法と民法のゼミに所属し、4年生からは労働法のゼミに入りました。
勉強を進めるうちに、教室やテキストで学ぶ法律の姿と、実際の現場や報道される労働実態との間に乖離を感じました。80年代後半から90年代初めにかけて、過労死やハラスメント問題が顕在化し、法と実態のギャップが浮き彫りになりました。
労働法学を学問として考え発信することで、その乖離の穴を埋め、働きやすい環境づくりに貢献できればという思いがありました。当時は単に面白そうだと感じて選択しましたが、後から考えるとそうした動機もあったのだと思います。
島岡:
理系から法学部に移られたのはなぜでしょうか。
水町:
数学や物理が難しく、夜遅くまで顕微鏡を覗いて勉強したくないと思い、公務員を目指しました。公務員試験に合格するには法学部が近道だと考え、移りました。
島岡:
現実的な選択だったのですね。
水町:
まさにそうです。将来の展望はなく、転々としながら今に至るという感じです。
島岡:
そうした先生のような方が日本におられることは非常に貴重ですね。
ここからは、日本の働き方を国際的な視点で見直したいと思います。先生は豊富な海外経験をお持ちですので、日本の働き方の特徴や改善のヒントについて伺います。先生はフランスのパリ西大学やアメリカのニューヨーク大学ロースクールで研究されました。これらの国々と比較すると、日本の労働法制や労使関係にはどのような特徴があると感じられますか。
水町:
日本の雇用システムと労働法が密接に関わっている点が大きな特徴です。日本の雇用システムは終身雇用、年功序列、企業別組合を軸とした正社員中心の体制であり、諸外国とは異なります。たとえば、解雇が難しいことや新規学卒一括採用などが日本特有の制度です。
島岡:
それはいつ頃から始まったのでしょうか。
水町:
戦後の高度経済成長期に広まったと思われますが、その起源は江戸時代や明治時代に遡る説もあります。経済学的にも様々な説がありますが、高度経済成長期に一斉に若年層を採用する新規学卒採用が拡大しました。企業にとどまる人は少ないかもしれませんが、企業グループの一員として定年まで雇用が保障される仕組みです。
一方で、解雇は民法上は自由ですが、労働基準法の規制や判例法理の解雇権濫用法理によって、合理的かつ社会的に相当な理由がない限り解雇は無効とされています。これが日本の終身雇用の法的支柱となっています。解雇のリスクが大きいと、労働者の生活やキャリアに大きな影響があるため、こうした保護が設けられているのです。
ただし、その反面で企業の人事権が非常に強く、部署の配置や労働条件の変更についても、合理的な内容であれば労働者の同意なく就業規則で変更可能とする法理が発展しています。これは、解雇が困難な代わりに柔軟な人事管理を可能にする、日本的な雇用システムと労働法の特徴です。
アメリカの労働法が解雇自由を基本とし、フランスが労働組合の同意を重視する伝統的な法体系と比べても、日本の制度は独特のバランスを持っています。
島岡:
日本の労働法のユニークな面には良い点もあるのでしょうか。
水町:
実は世界の労働法は中央に収斂する傾向があります。アメリカ的、フランス的、日本的労働法の間で大きく乖離するのではなく、互いに似通ってきています。ヨーロッパでは解雇も理由が必要とされ、日本でも人事権の行使に対して労働者の権利尊重の判決が増えています。
こうしたなかで、世界的にグローバル化が進みマーケットや働き方も近づいており、制度も収斂してきています。その上で、単に欧米の制度をそのまま導入するのではなく、日本的な良さを守りつつ発展させることが大切だと考えています。
日本は労働者の教育水準や能力が高く、人間関係を重視した柔軟で高品質なサービス能力があります。
一方で、長時間労働やプライベートの犠牲、家族との時間が取れないこと、そして多様性(ダイバーシティ)受容の遅れなど課題もあります。
これらの課題に対応しつつ、日本の良さを失わず、個人や多様性の尊重と両立させる法的ルールを整備することが重要だと考えています。
島岡:
いろいろなものが次第に近づいているというお話は非常に興味深いです。その中で、日本の良さが世界全体の労働に対して大きなインパクトを与えうるのではないかと、今お話を伺いながら感じました。
水町:
「おもてなし」というのは、実はそこに無限の労働力や忠誠心が注がれているからこそ成立しているのかもしれません。しかし、個人の時間や生活を大切にしつつも、他者を尊重することは可能だと私は考えています。問題は、その両立をどう実現していくかという点にあるのだと思います。
島岡:
そこに次の鍵があるように感じました。ありがとうございます。では続いて、アカデミックな知見を実際の政策や社会にどのように活かすか、研究と実践の橋渡しについてお伺いしたいと思います。先生は「働き方改革実現会議」の委員や、「新しい資本主義実現会議」の分科会委員として、国の重要政策の検討に深く関与されています。アカデミックな研究成果を政策や社会の仕組みに反映させていくうえで、どのような難しさややりがいを感じておられますか。
水町:
働き方改革に象徴されるように、労働法の学問と政策は直接的につながっています。例えばアメリカやフランス、ドイツ、イギリスの事例を研究しながら、日本的な解決策はどうあるべきかを立法政策や法解釈の面で示すことが、働き方改革に直結しているのです。そうした意味で、我々労働法学の研究者として、研究成果を社会変革に活かせることには大きなやりがいを感じています。
しかし難しさもあります。ダイレクトにつながっているがゆえに、働き方改革の提言に対しては様々な意見があり、特に日本的な慣行やシステムに根差した抵抗が強いのです。これをいかに変えていくかが現場での大きな課題です。
労働法の特徴として、政治システムの中で厚生労働省に「労働政策審議会」が設置されており、公労使(三者)で構成されています。経営者団体、労働組合、そして公益委員(労働法学者、労働経済学者、弁護士など)が参加します。ただし審議会は意見をぶつけ合う場ではなく、労使の意見を聞く場であり、公益委員は中立案をまとめる役割が求められるため、積極的な発言は控えがちです。
島岡:
つまり、まずは両方の言い分を聞く場ということですね。
水町:
そうです。公益委員は基本的に中立を保ち、最終的には経営者団体か労働組合のどちらかが反対すると法改正は成立しません。結果として、両者が賛成した部分のみが徐々に法律改正として繋がり、社会は複雑化しながらも少しずつ変わっていきます。働き方改革はまさにその「大きな改正・改革」を目指した取り組みでした。
島岡:
なるほど。
水町:
厚労省の審議会だけでは難しいため、安倍総理時代に働き方改革実現会議が設立されました。経団連会長や連合会長、研究者、担当大臣が参加し、総理のもとで方向性を決定し、抵抗勢力の沈静化を図りました。しかし安倍総理退任後はこの会議も解散し、現在はフェーズ2として少しずつ進めている状況です。日本的な慣行や土壌の中で大きな改革を進めるのは容易ではありません。
また政治的リーダーシップの欠如も大きな課題です。欧州では国政選挙のマニフェストで労働改革を掲げ、支持を得て改革を実行します。フランスでは政権交代に伴い労働法改革が繰り返されつつも収斂していきますが、日本はほとんど改革せず、微調整に留まることが多いのです。
我々研究者は、労使や経営者団体、政党、マスコミ等で研究成果をわかりやすく説明し、共感を得て、部分的に政策や法改正に反映させる努力を続けています。
島岡:
まさに地道な努力の積み重ねですね。
水町:
立派に言えば地道ですが、私は自分の信念に基づいて自由に発言や論文執筆をしています。
島岡:
その際に、嫌だと感じることはありませんか。
水町:
研究者は自由であるべきで、お金や権力から距離を置き中立を保つことが大切だと思っています。成果が受け入れられるかどうかは外的なことで、今は難しくても5年、10年後には変わるかもしれないと考えているので、ストレスを最小限にして自由な研究生活を送っています。
島岡:
なるほど。そうしたスタンスが先生の研究生活のコツなのですね。
水町:
学問の自由と中立性があってこそ、学問は存続できると思います。
島岡:
たいへん貴重なお話をありがとうございました。最後に、これからの時代を担う若い世代、そして働き方に悩むリスナーの皆さまにメッセージをお願いいたします。先生は早稲田大学で多くの学生を指導されていますが、若い世代が労働法を学ぶ意義や、そこで得た知見を社会でどう活かしてほしいとお考えでしょうか。
水町:
私の早稲田大学での主な仕事は法学部やロースクールでの労働法教育ですが、労働法は多くの人に関わる分野です。法学部の学生だけでなく、他大学の学生、さらには中学・高校生にも労働法の重要なポイントを知ってほしいと思っています。
働くことは人生そのものに関わり、困難な選択の際に働くことに関わる決断は多岐にわたります。恋愛や結婚、就職や転職、アルバイトでの出来事なども含まれます。そうした選択肢を考える上で労働法の知識は重要です。
また、労働法は社会のあり方とも関連し、個人の生き方とは別に社会全体を考える教養としての側面もあります。そうした教養を多くの人に身につけてほしいと考えています。
島岡:
最後に、このポッドキャストをお聴きの、さまざまな立場で働くリスナーの皆さまへ、激動の時代を生き抜き、より良い働き方を実現するためのメッセージをお願いいたします。
水町:
確かに激動の時代と言われますが、一人の人生における周囲の変化は、実際には限られた範囲のものです。ですから、過度に恐れる必要はないと思います。
働くことや人生を生きる上で、目の前のことにむやみに食らいつくことも大切ですが、時には立ち止まり、自分自身を冷静に見つめ直すことが必要です。働いている方も、これから働こうとする方も、一度立ち止まって自分自身について考えてほしいのです。
その際、「どう働くか」を考える前に、「どういう人生を送りたいか」をまず考えてほしいと思います。自分の人生の希望の中で、働くことがどのように位置づけられるかを相対化して考えてほしいのです。
島岡:
なるほど。
水町:
日本の伝統的な会社における働き方は、働くことが絶対的な存在となり、プライベートや家族を犠牲にしてまで没入するケースがあります。そうした中で逆に立ち止まり、働くことが最も大切なことではなく、いかに楽しく生きるかが重要だと考えてほしいのです。
そのうえで、働くことがどのように位置付けられ、生きていくのか、働きたいのかを考えてほしい。その際に必要となるのが、これまでの学びや得た情報です。どれだけ知識を持っているかで、自分の人生や働き方のイメージは変わり、選択にも影響します。
今は企業情報なども容易に検索できる時代であり、偏差値やブランドだけでなく、企業の実態をインターンシップなどで直接知ることも大切です。また、学部で何を学ぶか、語学を身につけること、映画や本を通じて社会の情報を吸収することも重要です。
そうした広い意味での勉強をしっかり行い、情報を身につけたうえで、自分の人生や働くことを主体的に選択してほしいと思います。選択を間違えたと思ったら、勇気を持って立ち返り、いつでもやり直しができると考え、長い目で選択を続けてほしいと思います。
そのヒントの一つが、私の著書『働くこと大全』や各所での労働法に関する話の中にあることを願っています。
島岡:
まさに、労働法の専門家として「まずはどう生きるかを考えること」の重要性を示していただいたと感じました。また、自らの生き方を考えるうえで学びや知識の意義についても示唆をいただき、ありがとうございます。
本日は水町勇一郎教授とともに、「労働法の羅針盤で拓く、激動時代の働き方」をテーマにお話をお届けしました。先生のご経験や研究から見えてきた働くことの本質と未来への展望について伺いました。最後に、今回の収録を終えてのご感想を一言いただけますでしょうか。
水町:
現在、村上春樹ライブラリーの2階スタジオで収録しています。私は実は村上春樹さんの大ファンで、全著作を読んでいます。彼の作品から人生に影響を受け、かっこいい生き方のモデルとして部分的に選択しました。このスタジオで彼も収録を行ったことがあると聞き、大変幸せな気持ちで今日のお話ができました。ありがとうございました。
島岡:
ちなみに「村上春樹的」とは先生にとってどのような意味合いがあるのでしょうか。
水町:
具体的には『村上朝日堂』というエッセイに書かれており、多くの教訓を受けましたが、一言で言えば「かっこよく生きること」だと思います。
島岡:
素敵ですね。かっこいい生き方だと感じながらお話を伺いました。ありがとうございます。改めまして、本日は早稲田大学法学学術院の水町勇一郎教授をお迎えしました。『早稲田大学Podcasts:博士一歩前』、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。水町先生、本日はありがとうございました。
水町:
ありがとうございました。







