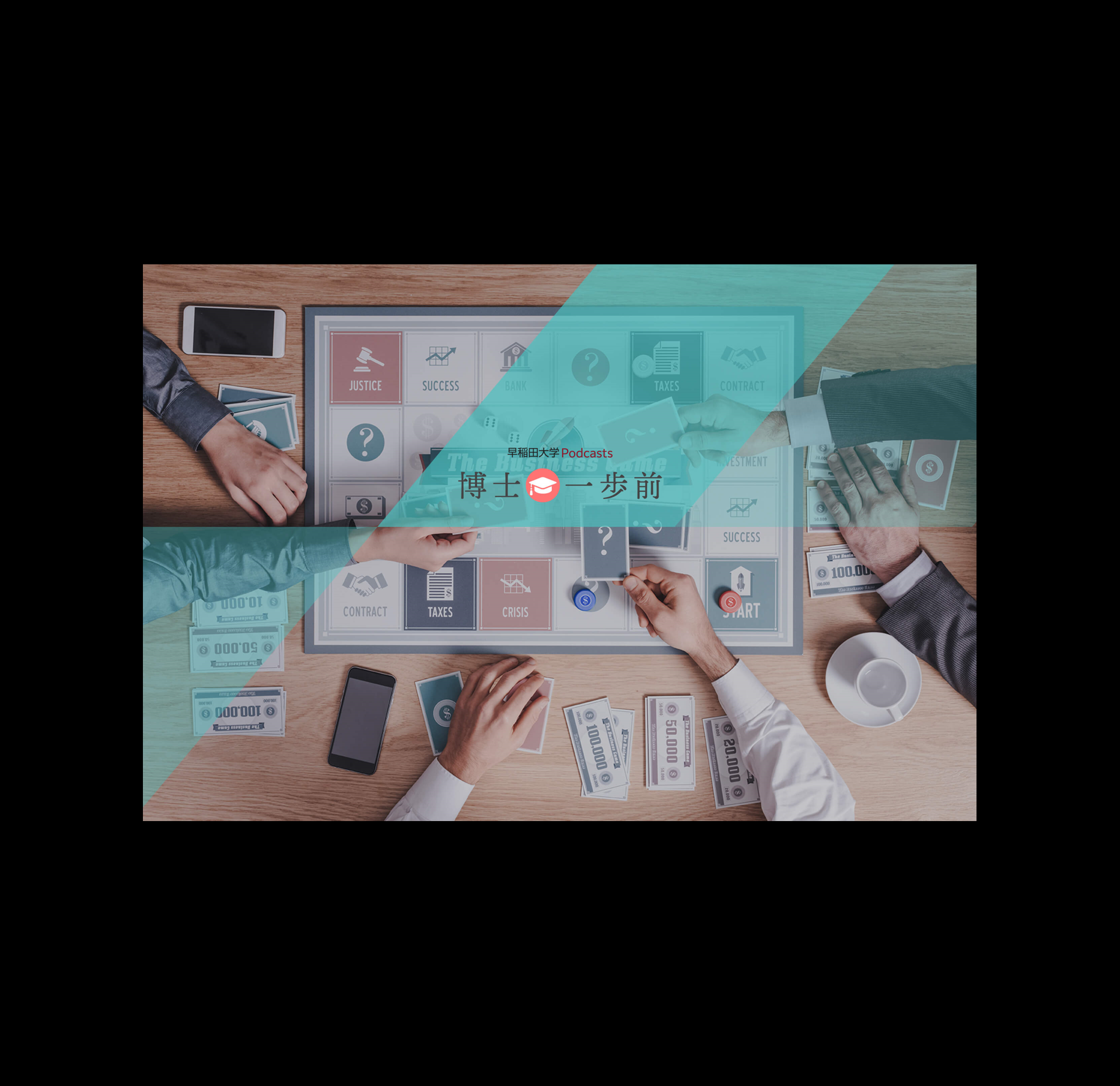- Featured Article
Vol.6 ゲーム理論(1/2)/ 【紛争や環境問題が陥る囚人のジレンマ】 最も合理的な意思決定を導く数理的なアプローチの探求/ 船木由喜彦教授
Thu 10 Oct 24
Thu 10 Oct 24
今回と次回の二回に渡って、早稲田大学 政治経済学術院 の船木由喜彦教授をゲストに、「ゲーム理論の現在地とこれから」をテーマにお届けします。
船木教授は、相互依存関係における意思決定を数理的に分析する「ゲーム理論」の専門家です。プレイヤーの行動が他者に与える影響や、最も利得を最大化する行動を探るこの理論は、金銭的な利益だけでなく、幸福度などの概念も含めて扱います。
地球の環境問題や家電量販店同士の価格競争を例に、「ゲーム理論」における代表的な概念「囚人のジレンマ」や「ナッシュ均衡」に注目しながら、様々なシーンで最も良い決断を行うために活用されるゲーム理論の面白さや役割について深掘りしていきます。
また、「人間の行動と理論は乖離する可能性がある」と考える船木教授の「ゲーム理論」の実験と研究の重要性、その取り組みへの情熱についてお話を伺います。
配信サービス一覧
ゲスト:船木 由喜彦
1985年東京工業大学にて博士号を取得。 東洋大学経済学部教授を経て、1998年より現職 早稲田大学政治経済学術院教授に。Mathematical Social Sciences や Journal of Mathematical Economicsなど、国際学術誌の編集委員も務める。専門は、協力ゲーム理論、実験経済学。日本経済学会、日本OR学会、国際ゲーム理論学会、ESA(実験経済学学会)に所属。著書 『 演習ゲーム理論』(新世社, 2004年)『はじめて学ぶゲーム理論』(新世社, 2014年) など。

ホスト:島岡 未来子

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。2022年2月から、アントレプレナーシップセクション副所長 兼任。
- 書籍情報
-
-
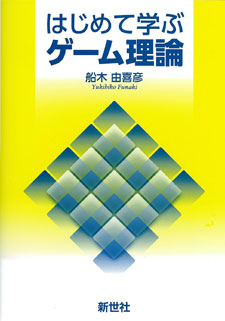
はじめて学ぶゲーム理論
出版社 : 新世社
著 者:船木 由喜彦
出版年月 : 2014年5月
言語 : 日本語
ページ数:224ページ
ISBN:978-4-88384-208-7
-
エピソード要約
-ゲーム理論における「囚人のジレンマ」と「ナッシュ均衡」
囚人のジレンマは、2人のプレイヤーが協力か裏切りを選択する状況で、合理的に考えると裏切りが最適行動になるが、結果的に最も良い結果(協力)に至らないというジレンマを生む。ナッシュ均衡は、支配戦略均衡の一種であり、ゲームが長期間続いたときの安定的な状況を示すが、複数の均衡が存在することがあり、その中からどれを選ぶかが課題となる。ナッシュ均衡は、さまざまなケースで応用でき、特にアメリカを中心に経済分析において広く利用され、発展してきた。
-ゲーム理論の実社会への応用
例えば囚人のジレンマは、環境問題や国家間の軍備拡大競争など、協力が望ましいにもかかわらず非協力的な行動が選ばれる現実の問題と類似しており、囚人のジレンマを解決することが、これらの現実の問題の解決の糸口になる可能性がある。囚人のジレンマを解決するためには、ルールや構造自体を変更し、プレイヤーに協力を促す仕組みを整えることが重要である。
-船木教授が研究者を目指したきっかけ
船木教授がゲーム理論に興味を持ったきっかけとして、将棋やボードゲームなどの遊びから理論的な興味を抱き、鈴木光男先生の研究室で学び始めた。そして研究室で最新の研究に触れられる環境に魅力を感じたことが研究者としてのキャリアを歩むきっかけとなった。
エピソード書き起こし
島岡教授(以降、島岡):
まず船木先生の専門であるゲーム理論について伺いたいと思います。
先生のご著書『はじめて学ぶゲーム理論』の中では、ゲーム理論とは端的に言うと多数の人々の間で相互依存関係にある状況における意思決定を数理的に分析する研究分野であると述べられています。これだけですとなかなか理解が難しいですが、まず先生にこのあたり解説いただきたいと思います。ゲーム理論を理解するための前提として、ゲーム的な状況とは何でしょうか。
船木教授(以降、船木):
まずは相互依存関係がある状況、一人で無人島に行って狩猟生活するみたいな場合は一切関係がありません、他の人たちと自分以外のものがいるというような関係性がある状況の問題を考えてみましょう。関係性があるということは、お互いに影響があるわけです。私の意思決定が相手に影響するし、相手の意思決定が私に影響する。そういう状況の中で、合理的な意思決定は何であろうか。人々が合理的に考えるとき、どのように行動するのか、ということを分析するのがゲーム理論です。我々はプレイヤーと呼びますが、人々の利得を最大化する行動について、分析します。例えば金銭的な、非常に利己的な行動を分析するみたいに捉える人もいますが、それだけに限らず、例えば相手がハッピーになれば、自分もハッピーになる。自分の幸福度、ハッピー度を利得と呼んで分析することもできます。そういったものを最大にする、合理的な意思決定の分析をしたい。当然自分は色々な行動の中で一番いいものを選びたい。それは当然です。相手も同じように考えるわけです。相手も自分の行動の中で一番いいものを選びたい。しかしお互いが相手のことを考えている世界ですから、私は相手がどのような行動をするかを考えて、自分の利益や利得を最大にする行動を選びたい。相手も同じ合理性を持っているから、相手も私がどう考えているかを考えて合理的な行動をとるはずです。しかしそれだけでは終わりません。私が相手のことを考えて、相手は私のことを考えているから、私は相手が私のことを考えている、私がどう行動するのか考えていることを踏まえた相手の行動を考慮して、私の行動を意思決定しないといけません。しかし相手も同じなので、どんどんどんどん上までいってしまって、どうやって分析していいか分からない。それをどう分析していこうというのがゲーム理論の根本的な考え方です。
島岡:
非常に面白いですね。
もう一つ数理的な分析というのも定義に入っていましたが、数理的に分析するとはどういうことでしょうか。
船木:
まずは論理の厳密性というのが一般的な答え方ですが、より簡単に言うとプレイヤー、人々はとても合理的である。とても合理的とは万能な計算機を持っていて、万能な記憶力を持っている。そういう状況の時に今お話したどこまでも先を読んでいくような合理性の結果がどうなるかということを考える。そういう意味で数理的と言っています。ただそんなに合理性はないですよね。私もそこまで先は読めないです。そのため、最近はその合理性を限定して、限定合理性の理論というものも流行ってきています。例えば確率を使って分析するとか、確率的な行動を取ったりすると計算が複雑になったり、それから順番に意思決定をしていくと、その順番性で最後の人が何をするかに基づいて、その前の人が何をするか考えていかないといけないから、それが続くと膨大な分岐、メモリが必要になってきます。だから完璧に問題の解、ゲームの解というのはどのように人々が行動するか、それを分析するためにはそういった数学的な能力がたくさんあるということを前提にしないといけない。そういう人たちがいる中で何が起こるかを分析するのがここでいう数学的な分析だと思っています。
島岡:
ゲーム理論というと囚人のジレンマ、ナッシュ均衡が有名ですが、改めて先生からこれらの重要概念について解説をいただけますでしょうか。
船木:
まず囚人のジレンマから始めましょう。
一番単純なケースとして、二人の人々、プレイヤーがいるケースを考えて、その二人が裏切りと協力という二つの行動のうち、どちらかを選ばないといけないという状況を考えます。
二人とも協力をすると最も2人にとっていい状況。例えば10・10という利得が得られる。それに対して1人が裏切ると、裏切った人は10よりも多い13という利得を得て、一人だけ得をします。しかし相手は0になってしまう。これは相手も同じで、相手だけが協力から裏切ると、相手は13もらって、私は0になってしまう。それでは裏切り裏切りの時はどうなるかというと、裏切り裏切りだと1・1という利得で0よりは良くなる。そのため、相手に裏切られるのなら、私も裏切った方がいいという状況になります。こういう状況の中で支配戦略というのは、二人にとって合理的な行動は裏切りであるというのが出てきます。どうしてかというと、相手が協力している時、自分が裏切れば3だけ得する。相手が裏切っている時も、自分が裏切れば1だけ得する。相手が何をしても、自分が得をするのは裏切りであると。相手も同じ合理性を持っているから、相手も私も裏切り裏切りをとって、1・1になってしまうというのが、このゲーム理論における支配戦略均衡の解です。一言で言うと支配戦略がパレート最適ではありません。それは10・10のように二人ともいい状態がパレート最適。それに対して支配戦略均衡は2人とも裏切る、悪い状態になる。一方で二人とも協力すれば、10・10をもらえてハッピーな状況です。しかしゲーム理論の答え、合理性の帰結は1・1になってしまう。実際にアメリカの共犯証言というか、共犯した人に司法取引で、私は罪を犯しましたということを自分から認めると罪が軽くなるのが、まさに同じ行動を持っていて、囚人というよりも、容疑者が自白をしてしまう。容疑者にとって自白は、相手に対して裏切りですから、そういう状況になってしまうこととパラレルです。ともかく協力的な行動を二人とも望みたい。二人にとってハッピーなのは協力・協力なのに裏切ってしまう。それが囚人のジレンマと言われる状況です。
今お話した状況、問題について、もう一つ付け加えてお話する必要があります。
囚人のジレンマがなぜ重要かというと、この構造が環境問題、二人とも環境が綺麗な方がいいのについ汚してしまうとか、国家間の紛争の問題、国と国は平和な方がいいのに軍備拡大競争してしまうという状況と非常に似ています。特に環境の問題は、みんなが環境保護しましょうと言いながら、個人的にエネルギーをたくさん使ってしまうような行動に結びつくから、この囚人のジレンマの問題をどう解決するかというのは世の中にとって、非常に重要な問題です。どうやってそういったプレイヤーに協力行動を取らせるかが非常に重要な問題となるわけです。
島岡:
それは構造の問題でしょうか。
船木:
構造の問題です。人々の考え方が悪いとか、人々に教育してもっと綺麗にするようにしましょうとか、そういった問題ではなく、ゲームの構造、ルールがそのような形になっているから、合理的な人々はどうしても非協力、裏切りに行ってしまう。それをどうやって解決すればいいかということが、ゲーム理論の大きな問題だと思います。
島岡:
ナッシュ均衡はどういうものでしょうか。
船木:
今お話した支配戦略均衡も、ナッシュ均衡の中の一つでとても強力な考え方です。
ただ支配戦略均衡は、存在しないかもしれない。しかしナッシュ均衡は常に存在し、ゲームを長く何回も続けた時の安定的な状況を示すとも言われています。そのため、重要ですが、実はたくさん問題点があって、どうやってそこに到達するかとか、ナッシュ均衡が2つ、3つある時もある。どれ選ぶのかとか、色々な問題があります。ただ経済現象の中で、安定的な状況がどこで起こるとか、どうやればそれが変わるのかとか、そのような分析の時にとても重要な概念で、経済学でよく使われていると理解していただければと思います。
島岡:
続きまして、ゲーム理論の研究分野としての歴史についてお伺いしたいと思います。そもそもどのような経緯を経て、この研究分野は発展してきたのでしょうか。
船木:
ゲーム理論の一番最初は、フォン・ノイマン(ジョン・フォン・ノイマン)とモルゲンシュテルン(オスカー・モルゲンシュテルン)の出会いと言われています。この二人が『Theory of games and economic behavior』という非常に厚い本に自分たちの研究を全部書いた。それが出発点になっています。フォン・ノイマンは多岐にわたった業績がある人で、例えば今のコンピューターのすべての枠組みのもとを作ったり、量子力学の業績があったり、経済学でもフォン・ノイマン成長モデルがあったり。天才です。
その人の一つの業績がゲーム理論で、モルゲンシュテルンがこういう問題がある、それは二人零和ゲームですが、そういう問題をどうやって解いていけばいいかを二人で考えたことが出発点になっています。二人ゲームについて、彼らは最適戦略、ザ・ソリューションを見つけてとてもハッピーだったわけです。本の最初の一部分はその二人零和ゲームの話です。実はその解はナッシュ均衡とも一致するのですが、ナッシュのことはあまり評価してなかった。なぜかというと、ナッシュ均衡の方は二人零和ゲームで、ナッシュ均衡を考えると、このフォン・ノイマンとモルゲンシュテルンが出したザ・ソリューションと一致していて、で完全に解けている。これは完璧だと思います。ただし戦略を混合する確率の問題を使わないといけません。ともかく二人零和ゲームは解けた。それではそれを三人にしましょうと。二人から三人といったら簡単そうに見えますが、全然違う。
二人だったら自分と相手です。三人だったら私たち二人と相手とか、一人ずつバラバラとか、相手が組むとか、そういうコアリッション、提携がどうできるかが重要になってきて、その問題でどうやって分析しましょうかと三人零和ゲームを考えました。そして三人零和ゲームの解、ザ・ソリューションを考えていくわけです。すごい時間がかかって、一冊の本ができましたが、三人で終わっています。
四人以上は存在証明できてなかった。定義はできるが分析はできなくて、非常に複雑だった。少し話が脱線したかもしれませんが、ともかくそこが出発点で、三人になると協力の関係を分析しないといけない。二人の場合は必ず相手とは非協力ですが、そこから非協力ゲームと協力ゲームの違いが生まれて、さらに非協力の状態から協力ゲームを作って、三人ゲームの解を分析する枠組みまで全部作った。現在、私の経験もそれに沿った研究を進めていると思っています。
その後、経済学に使えるという話になるのですが、その前に協力ゲームの解を考えていきましょう。
フォン・ノイマンとモルゲンシュテルンはコアというのを考えませんでした。コアという協力ゲームの解があって、それは三人零和ゲームでは存在しません。そのため、彼らは知っていたが、彼らのザ・ソリューション、フォン・ノイマン、モルゲンシュテルン、ステイブル・ソリューションを考えてコアは考えなかった。しかし、実はコアは、経済学の均衡の分析に非常に役に立つ話で、その後、ずっと一般均衡理論の中で、競争均衡とかコアの話、協力ゲームの定式化とかすごく流行りました。一時期協力ゲームのブームが起こった。しかしそれで終わってしまって、その後、どのように分析に使おうかというところで止まってしまって。もちろん続いていましたが。そこで現れたのがナッシュのナッシュ均衡。フォン・ノイマン、モルゲンシュテルンの二人零和は使いにくかったのですが、ナッシュ均衡は色々なケースに使えるので、万能ではありませんが、経済分析に使えるという形で、特にアメリカを中心にナッシュ均衡による分析がどんどん進んだ。ナッシュ均衡だけだと捉えきれないものをサブゲーム完全均衡や完全均衡など、色々な新しい概念を使って分析して、そういう意味で経済分析には非協力ゲーム理論がとてもよく使われて、どんどん発展したというのが今までの経緯だと思います。
島岡:
協力ゲームと非協力ゲームの話が出てきましたが、改めてその二つを定義していただくと、どのような感じになるのでしょうか。
船木:
協力ゲームは人々の合理的な意思決定を分析する。最初の目標に合うわけです。
相手が合理的だったら、自分はその相手の合理性を考えながら、どのような意思決定をするか。要するに意思決定の選択の分析の問題です。それでは協力ゲームとは何か。これはさきほどの三人零和ゲームからも来ますが、協力したらその後、何が起こるのか。協力したら、分け前が欲しくなるわけです。どれだけ分けましょうかという話になって、非協力で出た結果を協力して、どうやって分けていくかの分析に重心を置いたわけです。経済学は希少資源を分配する問題、分配を分析する学問と言われていますが、利益をどう分配するかという問題につながっていて、非協力ゲームは意思決定の問題、協力ゲームは利益の分配の問題と考えると、その違いがはっきりするかと思います。
島岡:
ここまで船木先生にゲーム理論という研究分野の面白さを感じる数々のエピソードをお話いただきました。実際にゲーム理論は、どういう場面で応用されているのか、この辺りについて、ぜひ教えてください。
船木:
本当に挙げればきりがありませんが、経済学、経営学、会計学、政治学、社会学、心理学。これらはその分野でゲーム理論を普通に使っているところです。生物学は進化ゲーム理論の発展とともにすごく描写親和性がよく発展しています。最近ではコンピューター科学者の参入もあって、AIなどとの関係でその分野でも使われています。
あとはオペレーションズ・リサーチ。世の中に生じる問題を数学を使って最適に解決する。この時に相手がいる場合は、どうしてもゲーム理論が必要なので、その分野でも関わっています。
島岡:
非常に広い範囲で応用されているということですね。
もう少し具体的にお聞きしたいのですが、先ほども環境問題と囚人のジレンマの話をしていただきましたが、例えば気候変動問題、非常に深刻な環境問題に直面しております。その課題についても、解決しないといけないことは各国分かっていますが、なかなか協調行動が取れない。このような問題に対するゲーム理論の役割をご説明いただけますでしょうか。
船木:
囚人のジレンマは環境問題と構造が似ている、構造が同じと我々は考えて、囚人のジレンマを解決する方法が環境問題の解決につながると考えるわけです。それではどうやって解決するか。やはりそう簡単にいかない。ただ考えないといけないのは囚人のジレンマの状況が繰り返されているわけです。何回も繰り返していると、1回裏切ったら相手にはそれに対して懲罰が下るから相手も裏切ってくるだろう、だから協力した方がいいといった考えが生まれてくる可能性があります。そのため、一つは何回も繰り返して、長期的な関係を続ければ囚人のジレンマは解決するだろうという考え方。しかしそれも問題があって、例えば10回しかないと決まっていると、10回目に裏切れば裏切られてしまいます。後がないから、裏切っても相手にそれに対するしっぺ返し、懲罰がない。10回目は裏切りが起こる。それが分かると9回目も裏切りが起こる、8回目も裏切りが起こるというわけで合理的な両者の関係は破綻してしまい、裏切りになってしまう。そのため、どう考えればいいかというと、あと何回と決まっていないような長期的な関係、終わりがないような関係になれば、ひとつは協力関係が生まれる素地がだいぶ生まれます。それと構造が悪いです。人々が悪いのではなくて。そんな行動を取らないようなゲームに変容すると二人とも裏切ったら最も悪くなってしまうなど、なにか新しいルールを作ることによって、解決になると考えられます。そうはいっても環境問題の解決は難しいので、ゲーム理論はそのようなことに対する提言ができると思います。
島岡:
通常考えられているものと全く異なる見方で視点が与えられるのはゲーム理論の役割、意義だなとお聞きして思いました。あと実社会での活用ですが、例えば行政など我々の身近な場面、この辺りで何か先生からお話いただけることはありますでしょうか。
船木:
一番わかりやすい例だと、色々な商品を量販している電気店の競争の話がいいかなと思います。お店まで見に行くと、こっちの店で冷蔵庫を買うか、あっちの店で冷蔵庫を買うか。だいたい同じ値段というか同じ値段のことが多いですよね。しかし業者が協力して同じ値段にすることは独占禁止法で禁じられている。なぜそんなことが起こるのでしょうか。よく見るのは他の店で1円でも安かったら、必ずうちの店も同じ値段にします。それは消費者にとって良さそうですね。しかし実は業者、店にとっても、とてもいいです。なぜかというと、私がそのような政策を取ると、相手が1円でも下げたら自分も下げる。相手も合理的だったらそのように言うでしょう。そうすると自分が1円下げる、あるいは10円下げるとお客さん増えるかもしれないが、同時に相手が下がるわけですから、合理的な店舗経営者は相手も下げるのなら、自分も下げない方がいいことに気がつくわけです。そのため、両者にとっては下げないことが暗黙に協定されてしまう。そこにコミットされてしまうのはまさにゲーム的な相手のことをよく考えて合理的な行動を取るというのが出ていると思います。
島岡:
他に身近な利用シーン、場面はありますでしょうか。
船木:
処世術に役立つと書いている本があります。
アクセルロッド(ロバート・アクセルロッド)という研究者が、とても面白い実験を行っていて、囚人のジレンマですが、それを何回か繰り返すと、これは数が限られている、繰り返すと、その時に世界中の経済学者、コンピューター科学者など色々な人にプログラムを送ってくださいと。協力か裏切りかを取るプログラムを送ってください。そのプログラムを対戦させて、一番得点が多かった人を表彰、優勝者にする。世界中から色々なプログラムが送られて、ものすごく長くて、何回相手がどうなったらこうなるとか、様々なプログラムが来ましたが、アクセルロッド自身も参加して、非常に短い3行、ティットフォータットというのですが、最初は協力します。相手がその時に裏切ったら自分も次は裏切る、相手が協力したら協力する。それを繰り返すだけ。相手が何かしたらそれと同じことをする。オウム返しみたいな。そのような行動をしたものが勝って、何回裏切ったらなんとかとか、そういうものはみんな負けてしまったと。
これがなぜ処世術に関係するかと言いますと、先ほどもお話したように、囚人のジレンマで協力を維持する一つの方法は、相手が裏切ったら永久に裏切る、永久懲罰という非常に簡単な方法があって、そうすると協力せざるを得なくなる。一旦裏切ったらずっと悪い状況になって、お互いにそうすることによって協力が維持されるという均衡、ナッシュ均衡がある。
ところがアクセルドットがやったものは、相手が協力してくれたら自分も直す。一旦裏切られても、もし相手が協力すれば協力するということによって、大きな利益が出る。残念ながら有限回だと均衡になりません。最終回の裏切りがあるから。しかし長い期間だとちゃんと協力を維持できる。これを人間関係に当てはめて考えると、人間関係でいろいろなことがあるから、裏切られるようなことがあるかもしれない。その後、永久懲罰で一切相手と断つよりは相手が裏切っても、相手がもし戻ってくれたら自分も戻る。あるいは自分が協力に戻るというものを加えた方がみんなハッピーになりますよ、といったことが本に書かれています。それは面白いかなと思いました。
島岡:
様々なシーンで最もいい決断をするためにゲーム理論を活用できると理解しました。その時に何か気をつけた方がいいことはありますでしょうか。
船木:
ゲーム理論は理論的に合理性を分析してくれるので、とても有意義で役に立ちますが、そんなに先読みができなくて、せいぜい2回が限度、1回ぐらいしかできない。そのため人間の行動と理論は乖離する可能性がある。それを調べるのは実験で、人々の行動を実際にラボで分析するのが結構重要になるかと思います。注意することは、理論だからこの通りで、全部それでうまくいくということではなくて、人間の行動は違うかもしれないので、それも分析する必要があることは言いたいと思います。
島岡:
その辺りの実際の実験については、後半のエピソードで先生にお伺いしたいと思います。
そもそも船木先生がこの実験経済学、ゲーム理論という研究分野に興味を持たれたきっかけ、そしてどんな経緯を経て、研究者キャリアを歩むことになったのか、この辺りについて教えていただきたいと思います。まず、ゲーム理論に興味を持たれたきっかけは何でしょうか。
船木:
私が始めた時代はまだテレビゲームが出始めたか、なかったくらいの時代です。そのため、ボードゲームや将棋とかそのようなゲームが面白いと思って、そこからどのような理論だろうと思って始めました。ゲーム理論の研究室に所属する際、研究室の先生、鈴木光男先生の著書を見て、ああこういうものか、全然思っていたゲームとは違うなと。最初はすごく面白いと思ったのですが、それよりももう少し現実に使える数学で面白い状況を分析することがやりたいなと思って、鈴木先生のところに伺って入れていただいた。
島岡:
その後、研究者キャリアを歩まれるわけですが、その経緯やきっかけの辺りはいかがでしょう。
船木:
私は理学部だったので、ゲーム理論の研究室を探して、そこに所属しました。そこで素晴らしい人と環境に恵まれたことがあると思います。当時はインターネットがなかったので、海外の論文なんてなかなか手に入らないのに、海外のディスカッションペーパーが常にたくさん置いてあって、いつでも好きに読めるし、先輩方、色々な大学の先生が先輩だったりするので、話を聞いてくれたり、助手の先生とかいくらでも研究ができる環境だったことが影響していると思います。色々な交流があったのが良かったです。研究の初めにそういう論文を読むのが当たり前という環境で、実際に図書館まで行って全部調べるよりも最新の研究の状況がいつでも手に入って、分からない時は聞ける状況があって、これは面白いなと思ったのがきっかけというか、研究者になっていく経緯だと思います。
島岡:
今までの研究者キャリアを歩む過程で、何かご苦労はありましたでしょうか。
船木:
一つは博士論文を書くときで、テーマは苦労しました。
鈴木先生は自由にやれということで、自分で探さないといけなくて、筑波大学の先生との共同で始めた研究でしたが、随分指導していただきました。それが学術誌に出版されないといけないので、それの目途がついて、やっていけるかなと思います。やはり博士のときは論文が書けるかなという点ですごく心配がありました。
もう一点、大学に就職するとまず教育をしないといけないし、何か会議があるし、研究する時間がなかなか取れない。今まで指導していただいた先生や仲間とかもいなくなってしまう。時間を取っていけばいいですが、そのような時間も取れない。そのため、しばらく停滞してしまって、論文がなかなか書けない状況になってしまう。そこが苦労ですね。