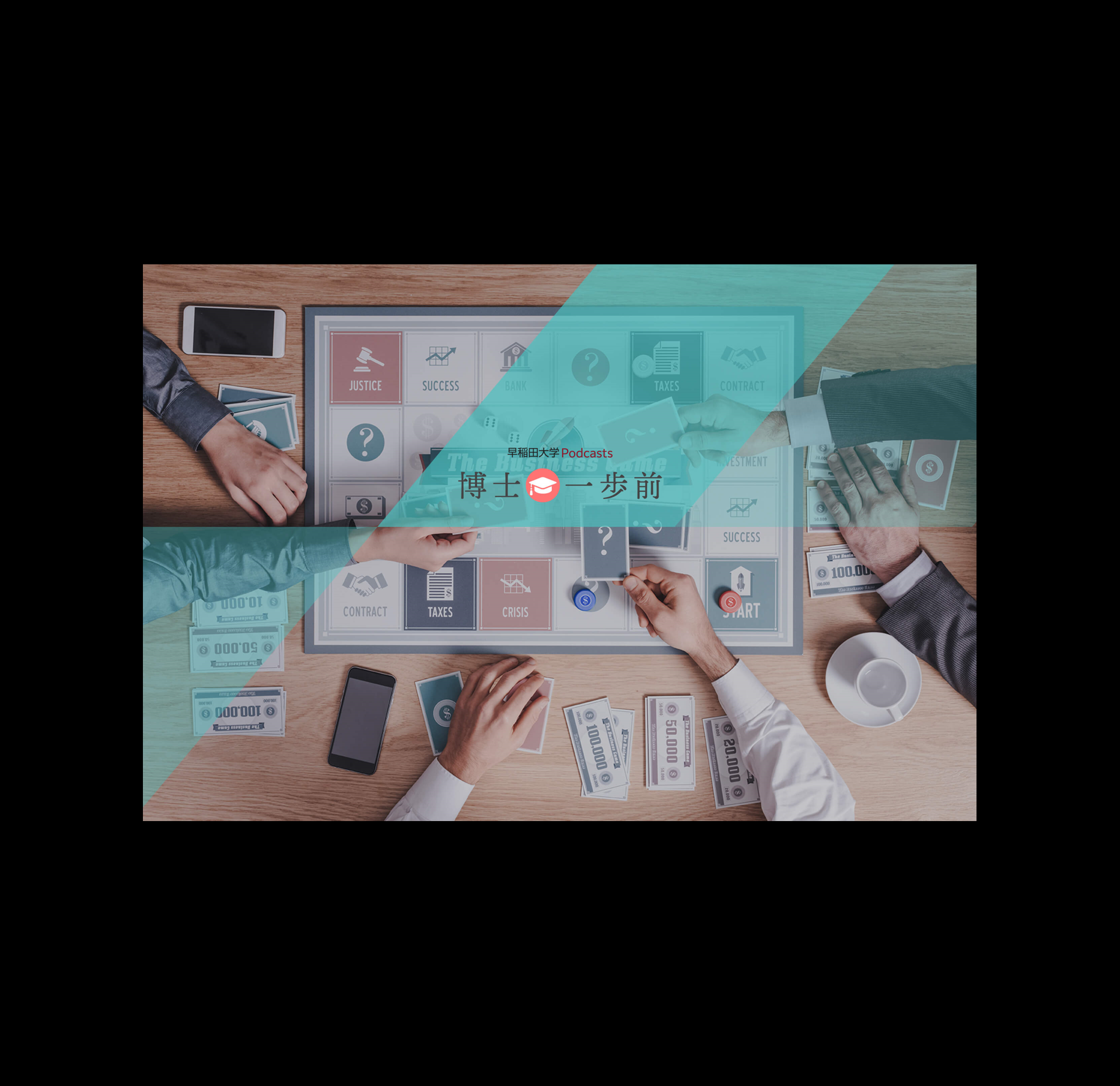- Featured Article
Vol.6 ゲーム理論(2/2)/【国際間コラボレーション + AI】異分野交流で切り拓く新理論の探求/ 船木由喜彦教授
Thu 24 Oct 24
Thu 24 Oct 24
早稲田大学 政治経済学術院 の船木由喜彦教授をゲストに、「ゲーム理論の現在地とこれから」の後編をお届けします。
船木教授は、「ゲーム理論」の学会がない頃から、国際的な研究集会に第1回目から参加されるなど、常に研究の最前線に身を置いてきました。
世界的にも珍しい早稲田大学内にある「ゲーム理論」の実験環境の紹介や、船木教授が現在注力されている研究テーマなど様々な話を聞きました。
船木教授自身も「世界的にも新しい理論の構築が必要ではないか」と語られるように、新たな研究フェーズに入った「ゲーム理論」。教授が考える異分野と連携した実験や研究の重要性、次世代の研究者へ向けた情熱的なメッセージも必聴です。
エピソードは下のリンクから
ゲスト:船木 由喜彦
1985年東京工業大学にて博士号を取得。 東洋大学経済学部教授を経て、1998年より現職 早稲田大学政治経済学術院教授に。Mathematical Social Sciences や Journal of Mathematical Economicsなど、国際学術誌の編集委員も務める。専門は、協力ゲーム理論、実験経済学。日本経済学会、日本OR学会、国際ゲーム理論学会、ESA(実験経済学学会)に所属。著書 『 演習ゲーム理論』(新世社, 2004年)『はじめて学ぶゲーム理論』(新世社, 2014年) など。

ホスト:島岡 未来子

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。2022年2月から、アントレプレナーシップセクション副所長 兼任。
- 書籍情報
-
-
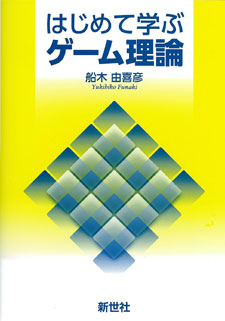
はじめて学ぶゲーム理論
出版社 : 新世社
著 者:船木 由喜彦
出版年月 : 2014年5月
言語 : 日本語
ページ数:224ページ
ISBN:978-4-88384-208-7
-
エピソード要約
-船木教授の最新の研究テーマ
船木教授は協力ゲームにおける人々の行動と結果の分け方に注力し、その二段構造を実験で分析している。またケインズのビューティーコンテストゲーム(BCGゲーム)の実験も進めており、視線追跡装置を用いて分析することで、人々の意思決定プロセスに関する新しい発見を目指している。
-海外と研究することの重要性
船木教授が協力ゲームの研究をしていたときには、国内に同じ研究をする研究者がほとんどいなかったが、海外まで目を広げれば多くの仲間達に出会うことができた。国際学会での懇親会や休憩時間に積極的に海外の研究者と交流を持つことが、その後さまざまな形で繋がっていく。
-共同研究の重要性
船木教授は共同研究において、ツールを活用して効率的に分担することが可能になり、異なる分野の研究者とのコラボレーションが新しい発見に繋がる可能性があると強調しており、幅広い知識を持つことも将来の研究に役立つとして、共同研究の重要性を強調、他分野との協力や知識の補完が研究をスムーズに進めるカギになると述べている。
エピソード書き起こし
島岡教授(以下、島岡):
前回のお話を通じて、ゲーム理論という研究分野の概要、それからこれまでの研究の経緯、実社会での応用のイメージが湧いてきました。
このような研究分野において、現在、船木先生が特に注力しておられる研究テーマとその研究によって解決しようとしている問題について、教えていただけないでしょうか。
船木教授(以下、船木):
フォン・ノイマン(ジョン・フォン・ノイマン)、モルゲンシュテルン(オスカー・モルゲンシュテルン)の最初のテーマに関連している研究を最新の研究としてやっています。
それは一言で言うと協力ゲームの実験ですが、協力ゲームの人々がどのような行動をするか、その結果をどう分けるかという二段構造になっています。
その二段構造になっている問題を実験で分析したい場合、そもそも分け方の話とその前に何が起こるかは非常に重要な関係があるはずですが、実は現在の協力ゲームの分析家は全部それを外して、分け方だけを分析しています。
少し脱線しますが、実験は人々の行動を分析するのに重要ですが、実験する人がどんどん増えてネタ切れみたいになってきており、協力・非協力ゲームではなく、もっと違うことをやりたい。そのため、協力ゲームの実験が最近かなり流行ってきています。
その中でもやることは協力ゲームの枠組みの中での実験で、元々の状況からどのような意思決定をして、どういう協力をするかまでの実験はないので、これをプロジェクトとしてこれから続けていきたいと思っています。つい最近最初の実験も終わったので、その結果を分析しているところです。これはフランス人の研究者とうちの大学院の学生とが今一緒にやっているプロジェクトです。それが一点目。
それからもう一つは美人投票ゲームの実験です。美人投票と言うと色々な考えがあるかもしれませんが、元々はケインズの美人投票で、例えば株式を購入する時に自分が買いたい、上がると思っている株ではなく、みんなが上がると思っている株を買いなさいという話で、それを実験で分析するのが美人投票ゲーム、あるいはビューティーコンテストゲーム、BCGゲームと言われています。
どのようなゲームか端的に言うと、0から100までの中で好きな数字を選んでください。その中で皆さんの選んだ数字の平均、平均だけだと難しいですが、平均の0.7倍の数字を書いた人が優勝者です。どの数を書いて投票しますかというゲームです。これをゲーム理論的に解釈すると、結構面白い理論になります。ゲーム理論的に言うと、0から100の中で、みんなが100を書いた時、平均は0.7倍の70が優勝になる。100より上はないので、70より上で勝てるわけがない。これは支配されないと言いますが、その支配されない戦略の中で考えてみましょう。すなわち0から100ではなくて、0から70の中で考えましょう。0から70の中でと言っても、同じ合理性を考えるならば、0から70の中で最高が70だから、それの平均の0.7倍は49なので、49より上で勝てるわけがない。大前提はみんな同じ合理性ということを考えます。そうすると49より上で勝てないので、49までで考えないといけない。全員がそう考えるのであれば、49の0.7倍以下でないといけない。それをずっと続けていると0しか残らない。0が唯一のナッシュ均衡になります。だからゲーム論的には、0を取りなさいということになるわけです。ところがこのゲーム、0で勝った人はいません。なぜならそんなに先まで読めない。みんな読めないし私も読めないので、その読み方で言うと2回ぐらい。実はこの考え方は難しいです。
しかし分かりやすい考え方が、実験経済学の方から出てきて、レベルKという考え方です。0から100の中でどれを選ぶかは、でたらめに何かコンピューターなどがランダムに選ぶのであれば、平均は50です。だから平均は50になるだろう。50になるならば、それの0.7倍の35を選べばいい。まず、何も考えない人をレベル0と言って、50を選ぶ人です。レベル1の人はみんなが平均で50を選ぶから、その0.7倍の35を選ぶだろう。これがレベル1の人。
しかしそれはおかしいですよね。自分の他にも同じように考える人がいるわけですから、みんな35と考えるはず。平均が35になるので、35の0.7倍の数を選ぶのがレベル2の考え方です。これもここでは止まらないですよね。なぜならみんなも同じように考えるならば、それの0.7倍。これの繰り返しで、他の人がどこまで深く考えるかに依存する。理論だったら無限に深く考えますが、そこまで行かないので、だいたい私は一つか二つですが、私の講義に出て学生で第1回の講義で必ずやるので、このデータをたくさん集めています。そうするとだいたいの場合、レベル2あるいは3の人が勝ちます。レベル1では勝てない。そのくらいの数を書くと勝てるケースが多いです。
私の研究において、少し設定を変えると、合理性に近づくケースと近づかないケースがあります。設定の変え方は下から行くか上から行くか、あるいは上に行ったり下に行ったり、レベルKの考え方ですが、50に対しては35だけど35に対して今度上に行く、そのような状況が起こった時にはもっと均衡に近づくという実験があります。しかしそれがなぜかはわからない。
2つの状況があって均衡に近づく状況と、均衡にあまり近づかない状況があって、その違いはわからない。それがどうして違うのかをアイトラッカーという目の動きを記録する装置、要するに視線を調べる装置ですが、どこの情報を見て、どのような意思決定をしているかを分析しながら実験します。少し高い機械なので、普通の実験室とは違うところに備えてあって、どういう情報を使うことによって、その違いが出てくるか、より合理性が出てくるか、人々によって合理性が違うのはそうですが、環境によってどう違うかを分析している。これがもう1つの今のテーマだと思います。
ファイナンスの実験、どうしてバブルが起こるのか、広い目で見ればゲーム理論にも関係しますが、そういったファイナンス関係の実験も私の博士の学生で興味を持つ人が多いので、なぜそうなったかの経緯も後でお話できればと思います。
島岡:
実験で例えば1年生と2年生で何か違ったりするでしょうか。
船木:
今の美人投票ゲームは授業の最初に必ずやります。そのデータを何年分も蓄積していると膨大なデータになって、どういう行動を取っているのかがかなりはっきり出てきます。そうすると集団による違いの分析も出てきて、講義としては2年生以上のゲーム理論という講義と1年生のゲーム理論。1年生のゲーム理論は他学部からもたくさん来ますが、結構な違いが見えてきて、ゲーム理論の方が選ぶ数字が小さくなって、これは高校生でやった実験との比較をするともっとはっきり出て、高校で模擬授業等を行った時にこの実験をやりますが、そうするともっと高く出ます。
島岡:
数字が。
船木:
数字が高く出る。高校生よりも大学1年生、それよりも大学2、3年生の方がより深く考える、合理性に近くなっていることが分かるわけです。
ただ1つ重要なことは、高校生だからあまり考えられない、大学1年生だからあまり考えられないことも少しあるかもしれませんが、重要なことは周りです。相手がどこまで深く考えるかと連動して、どういう人がいるか分かっていますから、それがこの読みの深さとそれから数の小さくなっていくことに結びついていることは分かっています。今、私の研究は実験が多く、理論的なものと人間の行動の違いがあるかもしれない。それを調べることはとても重要だと思います。1つ、どうやって実験するかを紹介したいのですが、早稲田大学、特に政経にありますが、30人が他の人がどのような意思決定をしているのか見えない椅子に座って、1人1人、条件のもとで意思決定を行っていく。いろいろな条件を与えて、その中での人々の行動を蓄積して分析します。
島岡:
それが早稲田大学早稲田キャンパスの政治経済学術院の建物の中に。
船木:
はい、8階にあって。月に何回もやっているので、多くの学生さんが知っていると思います。重要なことはそこで意思決定した結果に従って、お金がもらえる。
島岡:
やっぱりリワードが。
船木:
ただ一定の金額だけではなくて、要するにちゃんと利得を上げるような行動をしてもらわないといけないので、ただ楽しむだけではなく、たくさんポイントを上げた人はたくさんお金がもらえる仕組みにして実験しています。
重要なことはやはり匿名。誰かが来ると、先生が見ていると思ってしまいます。それで見えないようにして、処理もすべて匿名にして、審査委員会にこういう方向でやるけどよろしいでしょうかと許可を受けてやっています。
島岡:
そういう許可もちゃんといるわけですね。
船木:
そういうインストラクションがしっかりしていますので。
島岡:
そういう世界的な研究がこのキャンパスで行われているということも知れて大変よかったです。ここまで船木先生の研究に対する姿勢を強く感じるエピソードをお聞きできました。
そういった思いは国内にとどまらず、先生の活動活躍は海外にも及びます。船木先生は2006年から2008年までオランダのティルブルフ大学、アムステルダム自由大学で客員教授につかれており、海外での研究活動の経験もございます。
最初に海外の関わりを持たれたきっかけはどんなところにあったのでしょうか。
船木:
幸いなことに第1回の国際ゲーム理論の研究集会、まだゲーム理論の学会等がない頃、細かい数字ははっきりしていませんが、おそらく1985年だと思います。
ちょうどゲーム理論の国際インターナショナルジャーナルオブゲームセオリーが始まって、そのくらいの頃、そういったコンファレンスをやるという話だったと思いますが、そこで日本人の何人かの中でリストアップされて呼ばれていったのですが、とても良い経験でした。
まだ大学院を出て就職したての頃で、英語もたどたどしいし、海外の学会はどんなものだろうと思いながら行ったことをよく覚えています。
島岡:
どこでやったのですか?
船木:
オハイオ州のコロンバスというところです。学会での報告もできてとても良かったです。
島岡:
ナッシュ先生はもうお亡くなりになっていると思いますが、『ビューティフル・マインド』という非常に素晴らしい映画がありますよね。
船木:
はい、とても面白いです。
エピソードとして、ナッシュがナッシュ均衡を考えて、自分の指導教員の先生、タッカー先生のはずですが、そこに論文を持っていく。持っていった論文はナッシュ均衡の論文ではなく、ナッシュ解。ナッシュ解はナッシュが発明した2つの業績の1つ。ナッシュ均衡の方は割と考えつく概念で、ナッシュ解の方はその後、ナッシュプログラムと言われるぐらい協力ゲームと非協力ゲームを結ぶ、非常に重要な問題の最初です。面白い図が描いてあるナッシュ均衡を思いついたのに、ナッシュ解の論文を先生に持ってしまったのは映画上の演出かなと思いました。
島岡:
なるほど。それもこの研究に精通されている先生ならではの発見ですよね。
船木:
あともう一点。あのビデオを買うと、最後に特別編があって、ナッシュ先生が監督に自分の理論を教えるビデオがついていて。ぜひ見てください。あんなに嬉しそうなナッシュ先生の顔、見たことないです。いつも考え事をしているみたいな顔。とても嬉しそうに教えていました。
島岡:
そのナッシュ先生の姿を見られるだけでも見る価値がありますね。貴重な情報をありがとうございます。先生が出席された第一回のオハイオの学会で何か面白いエピソードはありますか。
船木:
とても印象に残っているのは協力ゲームの中にシャープレイ値というのがあって、今、私の専門の1つでもありますが、費用の分配をする問題でシャープレー(ロイド・シャープレー)という先生が書いたドクター論文が基礎になっていて、もう世界中で多くの研究者がその先生のシャープレイバリューを研究しています。その先生が偶然、私の前で道を歩いていました。
島岡:
オハイオで。
船木:
オハイオで。歩いていたら急にいなくなった。いなくなっちゃったから気になって、どこ行ったのかなと思っていたら、バスディーポ、バスの止まるところで座って、一生懸命テレビゲームをしていた。シャープレー先生はゲーム好きで、囲碁は相当強いと聞いたことがあります。日本に来られた時、囲碁クラブにも行かれていました。
島岡:
そうなのですね。
船木:
シャープレイ値はもう世界中の研究者が研究している。今、本を書いていまして、シャープレイ値に関して、今までの私の共同研究などを集めて、共著者と準備している状況です。今年度中に脱稿したいです。
島岡:
本当に楽しみですね。
今、先生の新しい著書の話も出ましたが、先生は非常に海外との研究者との共同研究等もされていますが、今まで海外と関わりながら研究を行う上での心がけといいますか、研究活動で関係性を築くために大切なこと、この辺りはいかがでしょうか。
船木:
まず、なぜ海外と研究することが重要なのか、私の考えを話したいと思います。協力ゲームが一旦すごく流行ったが、どんどん萎んでしまい、研究者も少なくなって、アメリカなんかほとんどいない状況です。日本でも私が協力ゲームを開始したときは数えるぐらいです。3人とか4人ぐらいしか研究者がいなかった。しかし海外に行くといる。だからやはり自分の研究領域は人が少なくて、あまり興味がないのかと思わずに、海外まで目を広げれば多くの人が色々なことをやっていて、自分と同じことをやっている人がいる。そういう人たちと話をすればとても楽しくなることが重要だと思います。そのきっかけは海外の学会に行って、苦労しましたが、そこでオランダ人の研究者に声かけてもらった。「お前の論文読んでいるよ、他にどんなことやっているの」と。だからこそやはり国際学術誌に載せることも重要だし、そこで何人かに声をかけてもらって、その人たちと共同研究を始めて、彼らが日本に来たり、私がオランダに行ったり、そういうことがきっかけだと思います。特にそのような話をするきっかけは、学会での報告もそうですが、懇親会や休み時間とかに少しでも話をすることが最初のきっかけかと思います。例えば、学会でレセプションやカンファレンスディナーがある時にテーブルごとに分かれます。できるだけ日本人だけのテーブルに行かない。1人だけ日本人だと少し行きにくいですが、そうならないといけないことも必ずあると思います。もうそこしか残ってないとか。それでどうやって話を繋ぐか。なかなか大変ですが、皆さん、日本のことは興味を持っているので、研究のこともそうですが、日本のことを話したり、話が苦手だったら趣味のこととか。私、実は折り紙や手品が趣味ですが、折り紙は常に持って行って、テーブルの人全員に折ってあげる。それは何年か経っても、私が忘れちゃっても、あなたに折り紙もらったと覚えていてくれる人がいるので、同じ分野であっても、同じ分野でなくても、そういうことで広がっていって、その場では直接繋がらなくても、後でまた会った時に色々な形で繋がっていくのではと思います。できるだけ多くの人と交流を持つことですね。交流、友人関係を作ることが重要だというのが結論ですが、それは日本でも難しいわけで外国も日本が変わらなくて、話しやすい人は話しやすい。そうでない人はそうでない。しかしそれは沢山の人と会うから、そういう人が見つかるわけで、たまたま隣にいた人と少し話すけど、あんまりということもあり得る。そのため、色々な人と色々な形で会っていくことを継続するのが重要かと思います。心が折れることもありますが、継続していき、関係を作ってきたのがよかったかなと思います。
島岡:
ありがとうございます。一緒に共同研究されることもあると思いますが、工夫されていることはありますか。
船木:
今は色々なツールがあって、オーバーリーフ(Overleaf)などがあるので、うまく共同研究を二人で分担しながらできます。組み合わせは友人が一番やりやすいですが、違った分野の人とやるのがよいかもしれない。
島岡:
改めてゲーム理論という研究分野を世界全体という視点で考えた時、現在、どのような研究フェーズに入っていると感じておられますでしょうか。
船木:
これは難しい質問だと思いますが、協力ゲームも非協力ゲームもエスタビリッシュされて、研究者もいると、学会も非常に活発です。しかしやはりもうこの理論だけで解けなくなっているというか、理論的な閉塞感みたいなのがあって、新しい理論を作りたい、新しい理論構築をしていきたい考えは随分あると思います。しかし、どうやってというのはやはり難しいです。最近思うのは、コンピューター関係の学者の方たちが興味を持って、どんどん参入してくれている。コンピューテーショナルゲーム理論という言葉もできるぐらいで、彼らがすごく細かく厳密に素早く計算して、新しい理論を作ってきて、面白いコラボレーションができ始めています。さらにAIですが、これは絶対外せなくて。私は最初、対立する概念かなと思っていました。ゲーム理論は、理論をどう合理的かを数学的に突き詰めて考えていく。AIは理論が別になくても、たくさんデータを集めて、どういう当てはまりがいいかとか、それを分析してくれると非常に役に立つ。だからこそ対極かなと思っていたが、そうではない。最近、色々なゲーム理論の学者などのお話で、ゲーム理論の国際学会の招待講演でAIとの関わりの招待講演がありました。そこでどうやって活用するかは、最も重要だと思いますが、色々な活用の仕方があって、AIが色々なことに答えてくれるから、どうやって人々が戦略を変更していくかみたいなことを分析する方法を教えてくれる。それから例えば実験するとき、実験は人を集めて、お金がかかるものですが、AIにある程度パターンを教え込んで、こういう実験をやったらどんな風になりそうかを教えてくれたり、そういう方法に使えたりとか。今までできなかったような新しいAIを助手みたいに使う方法がどんどん考えられているなと思いました。もっと色々な面で研究に役に立つと思います。それを用いて新しい理論ができればいいなと思いますが、まだまだ結構先かなと思います。
島岡:
これから船木先生自身がどのようなテーマをどのようなアプローチで研究に取り組んでいきたいと思っておられますか。
船木:
協力ゲームの実験は新しいので、これによって元々のフォン・ノイマン、モルゲンシュテルンの最初に戻って、どうだったのだろうかというのは考えられると思います。そこから新しい理論が生まれてくればよいのですが、まだまだ先かなと思います。今、継続していることとしては、その他の研究、現実に色々役に立つ実験やゲーム理論の話があって、それからもう1つ、株式市場が始まった時間帯に色々変なことが起こることがある。それが起こらないように事前に売りや買いの注文を集めますが、その方法がうまくいくケースとうまくいかないケースがあって、そういうケースを実験室で再現して、どのような時にうまくいくかといった話もしています。
島岡:
これから実験経済学、ゲーム理論やこういった分野の専門家を志す次世代の研究者の皆さんへのメッセージをぜひお願いいたします。
船木:
これが一番言いたいことですね。まずは今の流行りの学問よりも、自分の好きなこと、自分が興味あることをやることだと思います。これはまさに自分の今までの経験から、協力ゲームはすごく良かったのに、あまりやる人がいなくなって、今は復活していますが、何がいいかは今後分からない。協力ゲームを今やってもまた下がるかもしれない。人々の興味は移り変わるし、どこまでいってもなくなる学問はないと私は思っています。だからこそ自分が興味あることを続けることが一番いいかなと。みんながやっているからやっておいて、うまくいこうと思ったのに、その学問があまりその先進展しなかったことはあり得るので、まずは自分の興味あることをやるのがよいのではないでしょうか。もし協力ゲームに興味を持ったら、一緒にやりましょう。それから幅広い知識を持つことも重要だと思います。何をやりたいかというのは、よくわからない時もあるわけで、私は実験に少し興味を持ったので、少しずつ始めました。ファイナンスも興味もったので、少しずつ始めました。始めていってだんだん蓄積していき、実験経済学は今、例えば博士の学科では半分以上実験やっていますが、興味を持ってその分野の人と話をして、一緒に共同研究を始めるのが本を読むよりも早いです。ゲーム理論と実験は親和性が高いから、そうやって共同研究を始める。また実験をやっていると、ファイナンスの人たちとも話を始めて、ファイナンスの実験をやろう。私はファイナンスの知識は大学から学んでいなくても、実験をやりながら、そこで先生と相談しながらどういうものが重要かという形で設計していますし、色々興味を広げて研究するのがよいと思いますが、それは共同研究のベースが早いし、面白いと思います。共同研究でよい関係性を形成すると、相手の知識をすんなり吸収できるし、私の知識もあげられる。分からないこともすぐ聞ける。実際に論文が完成すれば、2人とも楽しいと補完的になるし、1人だとどうしても悩んでストップし、色々な人のアドバイスを聞いて、次のステップに進みますが、それよりも相手の色々な技能や知識を吸収しながらコラボレーションしていくのはとても楽しいです。これは日本人も外国人も関係ないので。実は私は明日からパリに行きますが、それもそこでの共同研究のためで、最終的にそういうことを続けていくと研究は楽しいなと。最初は辛いなと思った時期もありましたが、色々な人とコラボレーションして自分の興味があることをできるととても楽しい。それが皆さんに是非やっていただきたい、そういう風なことがあるよというのをお伝えしたいと思っています。