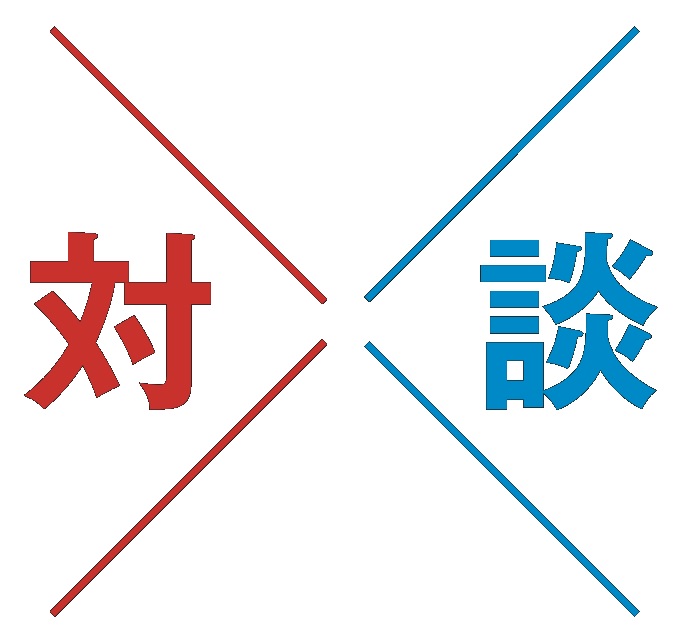- Featured Article
早稲田と慶應 歴史の転換期を迎えて
Mon 06 Feb 23
Mon 06 Feb 23
2021年5月に慶應義塾長に就任した伊藤公平塾長と、2022年9月より2期目の任期に入った早稲田大学の田中愛治総長。激しく社会が変化する時代の中で、私立大学はどのような使命を担うべきか。両者の対談をお届けします。
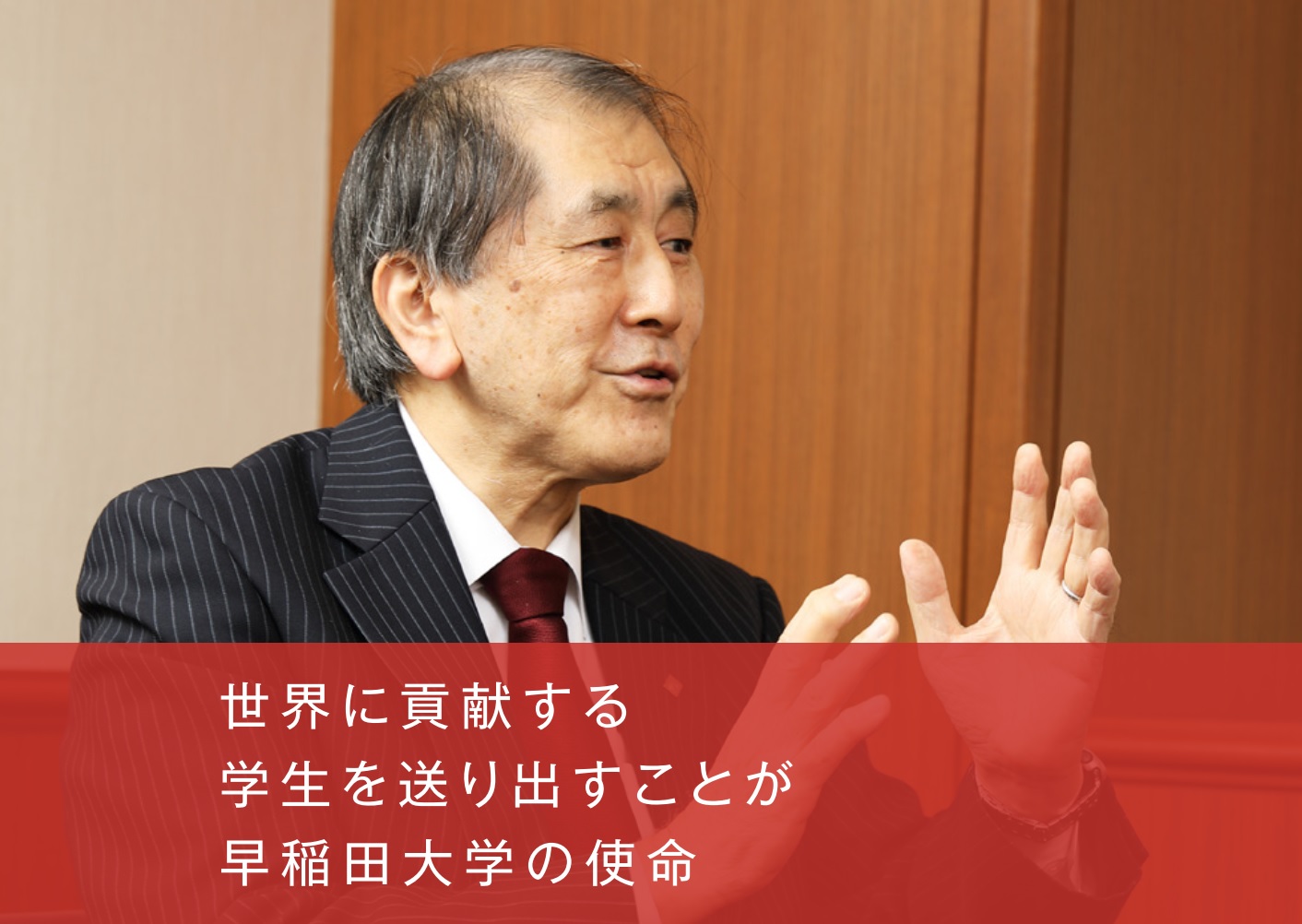
早稲田大学 総長 田中 愛治(たなか あいじ)
1951年東京都生まれ。1975年早稲田大学政治経済学部卒業。1985年The Ohio State University大学院政治学研究科博士課程を修了し、Ph.D.(政治学)取得。東洋英和女学院大学助教授、青山学院大学教授、早稲田大学政治経済学術院教授などを経て、2018年より早稲田大学総長。
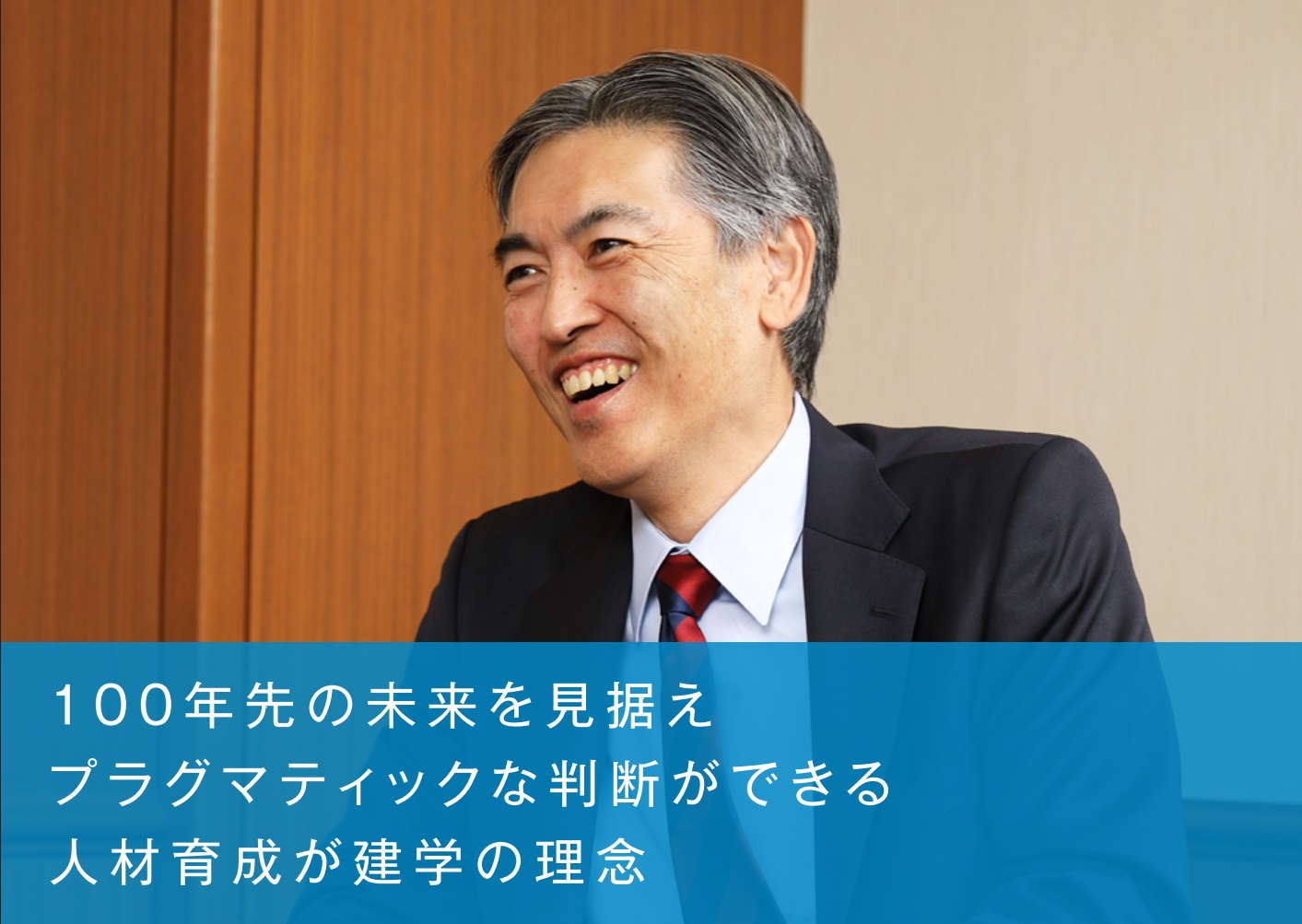
慶應義塾 塾長 伊藤 公平(いとう こうへい)
1965年神戸市生まれ。1989年慶應義塾大学理工学部計測工学科卒業。1994年カリフォルニア大学バークレー校 Ph.D.取得(Materials Science and Engineering)。2007年より慶應義塾大学理工学部教授。同学部長・大学院理工学研究科委員長などを経て、2021年より慶應義塾長(学校法人慶應義塾理事長 兼 慶應義塾大学長)。
- 西北の風&Campus Now
-
-
未来像を共有し、大学を設立した福澤諭吉と大隈重信
田中 福澤諭吉と大隈重信。両大学の創立者である二人は、互いの家を行き来するほど親交が深かったといいます。学者と政治家という異なる立場でありながら、目指す未来像は共有していたのではないでしょうか。
伊藤 福澤諭吉の主著『学問のすゝめ』は、1872(明治5)年に初編が出版され、昨年、2022年に150年を迎えました。そこには「賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなり。」という一文があります。時代は明治政府が近代社会へと大きく動き出した頃、民衆が学問に触れることの重要性を説いたのでしょう。日本はその後、民主主義に向け歴史を歩んでいくわけですが “ボトムアップ型の社会の構築” “権力に支配されない、学問の独立” という点で、大隈重信も同じ方向を目指していたのだと思います。
田中 立憲改進党を設立し、野党という立場から議会制民主主義の確立に向け活動をした大隈重信は、独立した一人一人の人間が社会を変えていくことを熟知していました。福澤諭吉からの影響も大きかったと考えられます。だからこそ、国民が平等に教育を受けられるよう、私立大学を設立したのでしょう。
激動の時代だからこそ 立ち返るべき建学の精神
伊藤 政治家としての大隈重信の功績として、鉄道の敷設と郵便制度の整備があげられます。鉄道と郵便ができるということは、日本中を“情報”が行き来するということです。このイノベーションは、現代のインターネット革命に通じるものがあります。そして同時に、民主主義のあり方が問われていること、地政学的な動揺が訪れていることなど、明治時代と現在は類似する点も多い。社会状況が大きく変化している今こそ、両大学の建学の精神を見つめ直すべきだと思います。
田中 大隈重信は本学の創立30周年記念祝典において、「一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ。」という言葉を残しました。早稲田大学はもともと、ダイバーシティに強みをもつ大学です。日本全国から学生が集まる大学であり、古くからアジアをはじめ多くの海外の国々からの留学生を受け入れてきた歴史もあります。
多様な価値観が入り混じる環境で育った人材は、社会のさまざまな“現場”で力を発揮し、世界に貢献するはずです。企業や国際機関、地域社会やNPO法人などで、人々のために活躍するならば、「早稲田で学ぶことが最も効果的」と思われる大学になれると考えています。
伊藤 福澤諭吉は慶應義塾の目的を「我日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し、之を実際にしては居家、処世、立国の本旨を明にして、之を口に言ふのみにあらず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」という言葉で表しています。
個人の尊厳や独立といった「立国の本旨」を徹底的に強調しながら、日本を変えていく。今こそ、このような姿勢が求められると感じます。
田中 日本がしっかりとした国になることで、はじめて世界に貢献する。福澤諭吉にはそうしたビジョンがあったのでしょう。
私立大学が果たすべき社会的責務と早慶が連携する必要性
田中 一方で今日、例えばデジタルトランスフォーメーションにおいて、日本は世界に後れをとっています。その原因もまた、教育にあるのかもしれません。文理を隔離した偏差値と大学受験突破を重視した教育では、早い段階から特定の科目に注力しなければならない。このような文理隔離教育の結果、自分の専門外の領域に対する理解力・想像力が乏しくなってしまう。こうした弊害を払拭するような今日の日本の教育システムのトランスフォーメーションに取り組むのも、私立大学の役目であると思います。
伊藤 少子化、人権、環境問題など、複雑な課題にアプローチするためには、プラグマティックなデータに基づく判断が重要です。100年、200年先の未来を見据えながら、各人が適切な判断・行動をしていくためには、「実学」が必要になります。実学とは、すぐに役立つ知識でもなければ、机上の空論でもありません。実証的に真理を解明し問題を解決していく「サイエンス」のことです。早稲田も慶應も建学以来、長い歴史の中で実学を重んじてきました。
田中 今、日本社会や人類が直面している課題の多くは “答えのない問題” であることは間違いありません。そこで求められているのは、100年後の未来を背負うことのできるグローバルリーダーでしょう。そうした人材育成の面で牽引していくのは、実学と多様性を重視する慶應と早稲田に期待されていると思います。両大学が教育・研究面で連携を強化し、大学改革において旗振り役となることは、未来社会を変える第一歩となるでしょう。