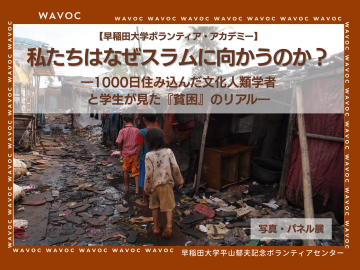名誉博士学位贈呈 ピーター サロベイ 教授
イェール大学名誉学長

田中総長、教職員の皆様、学生の皆様、ご家族、ご友人の皆様、本日はこのような式典に参加できることを大変光栄に思います。早稲田大学の名誉ある一員として迎えていただけることに、心から感激しています。
私の所属するイェール大学と早稲田大学は、フォックス国際フェローシップ(Fox International Fellowship)、サマーセッション(Summer Session)、ライトフェローシップ(Light Fellowship)などのプログラムを通じた学生や研究者の交流を含め、長年にわたる強固なパートナーシップを築いてきました。私の友人であり、イェール大学の政治学教授であったフランシス・ローゼンブルース(Frances Rosenbluth)氏(2021年に惜しくも逝去されました)は、早稲田大学の学外理事を務めていました。また、過去10年間だけでも、両大学の研究者による共同著作は1,000本以上に及んでいます。
イェール大学と早稲田大学の関係は、100年以上前に朝河貫一博士が築いたものであることをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。朝河博士は東京専門学校(後の早稲田大学)を卒業後、1902年にイェール大学で歴史学の博士号を取得しました。彼はイェール大学で初めての日本史の教授となり、イェール大学の東アジア図書館の責任者も務めました。朝河博士は日本の多くの著名な公人と交流し、日米の相互理解に尽力し、イェール大学のスターリング記念図書館(Sterling Memorial Library)における日本関連コレクションの発展に大きく貢献しました。彼の貢献を称えて、イェール大学のセイブルック・カレッジ(Saybrook College)には「朝河ガーデン(Asakawa Garden)」があり、早稲田大学にはイェール大学の研究者が早稲田大学で研究できる「朝河貫一記念研究者招聘プログラム(Asakawa Senior Fellowship)」も設けられています。朝河博士はイェール大学キャンパス内のグローブ・ストリート墓地(Grove Street Cemetery)に永眠しており、いずれ私と妻も彼の隣人になることになると思っています。ただし、それはまだしばらく先の話になることを願っていますが。
このようなイェールと早稲田の長い交流の歴史は、イェールと日本の関係が19世紀半ばにさかのぼることを考えれば、決して驚くことではありません。1853年にペリー提督が日本に来航した際、イェール大学の卒業生(後に教員となった)ジョージ・ジョーンズ(George Jones)が彼の牧師兼通訳を務め、また、同じく後にイェールの教員となるサミュエル・ウェルズ・ウィリアムズ(Samuel Wells Williams)も通訳を務め、1854年の日米和親条約の交渉に関わりました。1870年から1900年の間に、日本から60名の学生がイェール大学で学んでいます。最初の学生は、日本における物理学のパイオニアの一人である山川健次郎氏で、卒業後、東京大学、京都大学、九州大学の総長を務めました。イェール大学は北米で初めて日本関係の講座を開講した大学でもあります。しかし、なぜ私はこのように我々が共有する歴史について語っているのでしょうか?
それは、教室、研究室、実習室等での学習経験が、異なる人生経験や学習歴、文化的背景を持つ人々の存在によって、より豊かなものになると信じているからです。当然のことながら、私たちは皆、同じ人間であり、地球市民として共通する部分も多くあります。しかし、家庭背景、育った環境、受けた教育などにより、私たちは異なる見方をしたり、異なる方法で思考したり、異なる方法で問題を解決したりします。また、国・地域の教育制度によって、異なる思考法の習得が重視されることもあるでしょう。
このことに関する興味深い例を紹介します。ミシガン大学の社会心理学者であり(私も同じ分野を専門にしています)、イェール大学で研究者としてのキャリアをスタートさせたリチャード・ニスベット(Richard Nisbett)教授は、緻密な実験により、東アジアの国々で育った人々は、北米で育った人々とは強調点が異なる思考パターンを習得していることを示しました。
また、ニスベット教授が増田貴彦(Takahiko Masuda)氏と行った別の実験では、日本で育った学生と米国で育った学生に、魚が泳いでいる水中の情景を見せました。前景には魚が、背景には岩、水草、貝類、気泡などが含まれていました。20秒間この情景を見た後、学生たちは何を覚えているか尋ねられました。
全員が魚を見たと回答しましたが、アジアで育った学生が60%の確率で背景要素(水草、岩、気泡など)に言及したのに対し、北米で育った学生は最も目立つ要素である大きな魚を中心に説明する傾向がみられました。アジアで育った学生たちは、より背景を重視して説明する傾向があり、このシーンを「池」として認識したのです。
もう一つの実験をご紹介しましょう。Nisbett教授はLi-jun Ji氏、Zhiyong Zhang氏と共同で、東アジアと北米の大学生に単語を分類させる実験を行いました。3つの単語がセットで提示され、学生たちは、どの2つの単語がペアで、どの単語が仲間外れとなるか判断する作業を行いました。例えば、単語セットには「猿」「パンダ」「バナナ」といった組み合わせが含まれており、北米で育った学生たちは、単語を「動物」と「果物」のようなカテゴリーで分類するため、「猿」と「パンダ」をペアにし、「バナナ」は除外するという傾向が顕著でした。しかし、東アジアで育った学生たちは、単語同士の関係性に基づいて分類するため、「猿」と「バナナ」をペアとし、「パンダ」は除外する傾向が強かったのです。もしあなたが北米で育ったなら、「猿とパンダはどちらも動物だ」と言う可能性が高く、もし東アジアで育ったなら、「猿の好物はバナナだ」と言う可能性が高いということになります。この違いは、分類法の視点で学んできた北米の学生の経験と、関係性の視点から学んできた東アジアの学生の経験の違いに起因していると思われます。
Nisbett教授も私も、東アジア人や北米人の同質性を唱えるつもりはありません。また、それぞれの集団内でも相当のばらつきがあることは認識しています。しかし、家庭背景や教育、経験は、人々の間の重要な差異を生み出す役割を果たしており、社会心理学の研究は、それがどのように起こるのかを探る興味深い視点を提供してくれます。
では、北米人と東アジア人を教室や職場で一緒に過ごさせると何が起きるのでしょうか。双方の思考方法が発揮されるため、問題に対する解決策は格段に良いものとなるはずです。本日私が一番お伝えしたいことは「一緒であることで私たちはよりよくなれる」ということです。アメリカ人と日本人が教室で、あるいはアップルとソニー、フォードとトヨタといった企業で、隣り合わせに座れば、世界はより良くなります。私たちが自らの文化や思考方法の壁を乗り越えて協力することで、現在そして未来の世代にとってもより良い世界となっていくはずです。
これからの学生生活や人生の中で、私は皆さんに、自分とは異なるバックグラウンドを持つ人々と協力する機会を積極的に探すことを勧めたいと思います。そのことでより良い問題解決方法が見いだせるはずです。そして、アメリカと日本両国の政府に対しても、こうした機会が得やすくなるよう働きかけてください。私たちが協力して、気候変動の解決策を探ったり、次のパンデミックを克服するための手立てを打ったりすることができれば、世界人類が得る利益は計り知れないものとなるでしょう。
改めて、今日は皆さんと一緒に過ごすことができて大変光栄です。田中総長、このような栄誉を与えてくださり、早稲田大学の一員として迎えてくださったことに深く感謝いたします。
そして、早稲田大学での学びをさらに深めていく皆さんの幸運を祈ります。