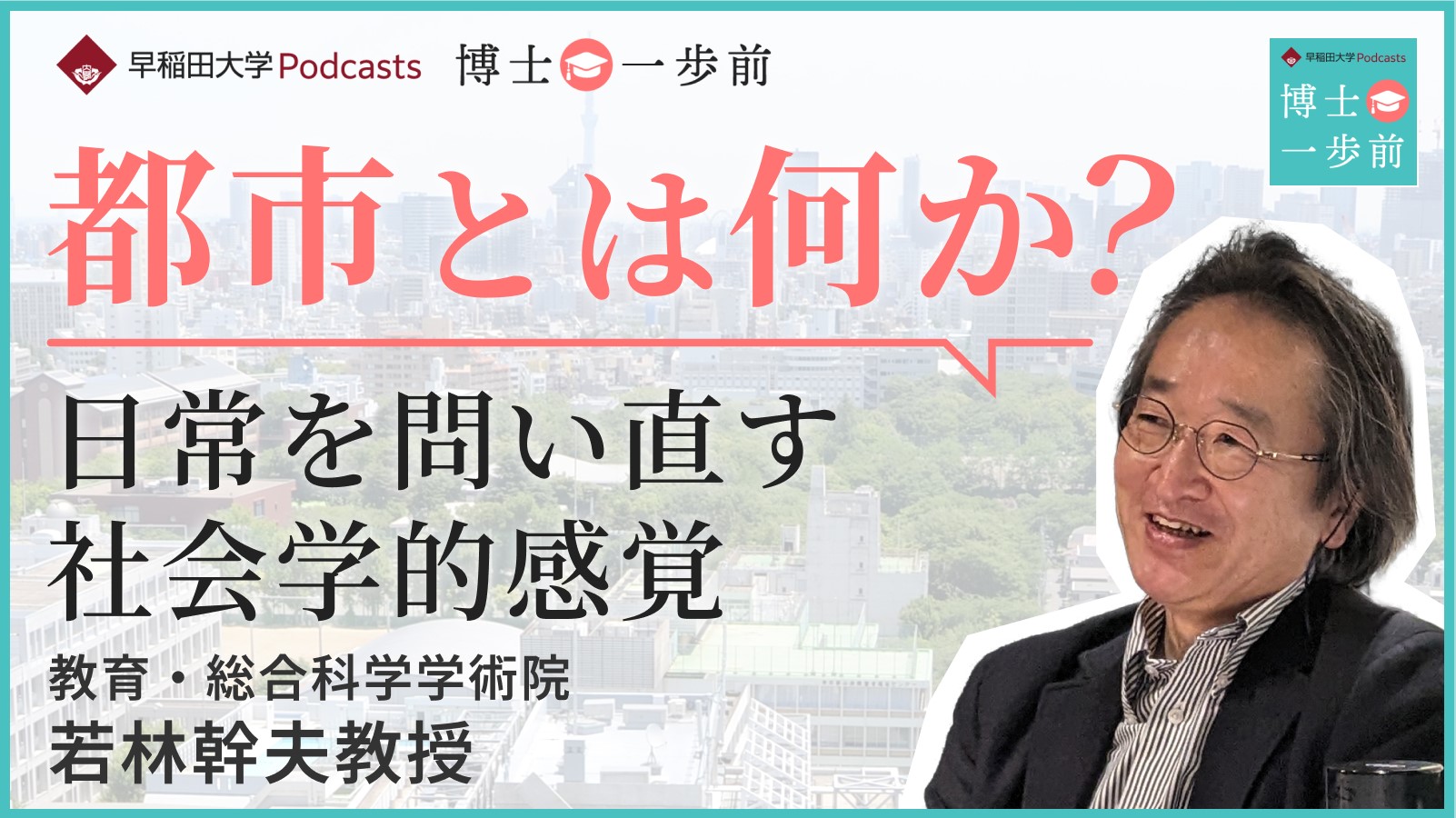- Featured Article
【Podcastコラム】大学で学ぶ意味
Tue 11 Mar 25
Tue 11 Mar 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、教育・総合科学学術院の若林幹夫教授に社会学の観点から世の中を考えていく中で「大学で学ぶ意味」についてお話いただいたので、その部分を抜粋してご紹介します。
Q.今の時代に大学で学ぶ意味とは。
若林幹夫教授:
大学は都市みたいな場所だと思います。
私が若い頃から付き合っていて、研究上でも影響を受けている吉見俊哉さんという方がいます。彼も大学は都市だと言っています。どういう意味かというと、私の都市論の理論とも関係ありますが、都市は共同体や村、部族をはじめ、他の都市や国から人々がやってきて出会う場所です。
いろいろなものの間で、その人たちがそれまで属していた文化やルール、考え方から一旦解放されて自由になれるような場所。それが都市というものの基底にある社会的な場のあり方だと思います。
大学もある社会の中で例えば4年間勉強しますが、大学生は勉強だけではなく、色々なことします。

それは例えば利益が上がるとか、ものすごく役に立つとか、大学出た後、役に立った方がいいと思いますが、そういうことを考えないで色々なことを試すことができる。
それからさまざまな考え方、もともと自分が知らなかった考え方とか、自分の価値や心情とは違うかもしれないような考え方に出会うことができる。そういう自由な出会いの場所だと思います。
そういう自由な出会いの場所に4年間、もっといてもいいんですが、いることによって自分の考え方や経験をすることができる。そうした自由、これは失敗することの自由も含めて、失敗したっていいじゃないか大学時代だから、と思うこともできます。
あるいはそこで今まで知らなかった全く新しいものと出会って、大学に入る前とは違う自分になることができる。そういうことが大学という場所だと思います。

その中の核になるものとして学問があると思います。学問も実は都市みたいなもので、日常的な考え方や道徳、偏見などそういうものから自由に、理性と事実を手がかりにして、何かを考えて発見して、あるいは作り出していくのは学問だと思います。
そういう都市的な場所で都市的に生きる。それによって自分を豊かにし、そこで得たものを社会に持ち帰って、社会をより良い場所にしていく。そういうことのために大学があって。
そうだとすると、大学で勉強することとは、大学は自動車教習所ではないので、すぐにこのライセンスを取ったらこれができます、みたいなことではなく、考え方とか何かをやることの手札を増やす。そういうことができる場所だと思います。
それが世の中、さっきの役に立つではありませんが、すごく役に立つことが求められていたり、効率性が求められていたりしますが、そういうのがあればあるほど、大学という都市的な場、学問という都市的な地というものは意味があるのではないかと思います。
若林 幹夫 教授
教育・総合科学学術院教授。専門は社会学、都市論、メディア論。
1962年東京生まれ。東京大学教養学部卒。東京大学大学院博士課程中退。博士(社会学)。筑波大学教授等を経て、2005年より現職。著書に、『社会学入門一歩前』(河出書房新社)、『郊外の社会学――現代を生きる形』(ちくま新書)、『モール化する都市と社会――巨大商業施設論』(NTT出版)、『都市論を学ぶための12冊』(弘文堂)など、多数。

島岡 未来子 教授(番組MC)

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。