- Featured Article
Vol.1 社会学(後編)【問いのセンス】 面白い「わからない」を見つける感度 / 若林教授
Tue 30 Apr 24
Tue 30 Apr 24
前回に引き続き、早稲田大学 教育・総合科学学術院所属で、社会学者の若林幹夫教授をゲストに、2023年に刊行された著書『社会学入門一歩前』の内容を基に、「世の中の前提を紐解く、社会学的感覚」 を探求します。
後編の今回は、若林教授が社会学者として研究の道に進んだ経緯や、領域を越境し、技術や社会制度の進展とともに移り変わる世の中を照らす視点を広げる社会学の立場から模索する異分野連携の可能性、原始時代から社会に生きる人間の感性の普遍性などに問いを向けながら、現代の社会を考えるアプローチ、世の中を見る感度を磨く重要性を探ります。社会学が社会に対して果たしうる意味、問いのセンスが試される研究者の特性、社会学を担う次世代へ届けたメッセージとは。
配信サービス一覧
ゲスト:若林 幹夫
教育・総合科学学術院教授。専門は社会学、都市論、メディア論。
1962年東京生まれ。東京大学教養学部卒。東京大学大学院博士課程中退。博士(社会学)。筑波大学教授等を経て、2005年より現職。著書に、『社会学入門一歩前』(河出書房新社)、『郊外の社会学――現代を生きる形』(ちくま新書)、『モール化する都市と社会――巨大商業施設論』(NTT出版)、『都市論を学ぶための12冊』(弘文堂)など、多数。

ホスト:島岡未来子

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。
2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。2022年2月から、アントレプレナーシップセクション副所長 兼任。
- 書籍情報
-
-
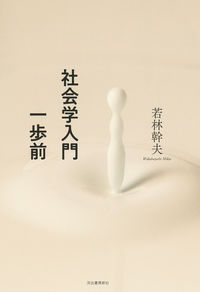
社会学入門一歩前
出版社:河出書房新社
発売日:2023/4/27
言語:日本語
単行本:240ページ
ISBN-10:4309231322
ISBN-13:978-4309231327
-

エピソード要約
-社会学へと進んだきっかけ
最初から社会学者を目指していたわけではなく、大学でたまたま出会った見田宗介氏の社会学の授業に魅力を見出した。
社会学に魅力を感じたのは、見田宗介の授業や人類学、日本史の授業を通じて、自分たちの生きる社会とは異なる視点や生き方に触れたことから。山本泰氏の助言により大学院進学を機に社会学を本格的に学ぶ道を選択した。
− 社会学感覚を最初に感じた出来事
高校の授業で夏目漱石の『こころ』を深く読み込んだとき、違う世代の人間が都会と田舎を行き来するなかでの絶望や孤独、寂しさが、物語の中の重要な視点であることに気づいた。この気づきが、後の自身の都市論の研究にも繋がっている。
– 研究者として重要なことは
研究は一人で行うものではなく、研究者や学生が自ら発信し、積極的にコミュニケーションを取り、世界中の研究者とのネットワークの中で行われるべきであり、学問の進行において人とのつながりが重要であると強調している。
研究や学問においては、答えを見つけることも大切だが、それ以上に自分なりの問いに達すること、つまり疑問や問題意識を持つことが重要であると指摘している。学問は答えを出すことだけではなく、わからないことからスタートし、わからないことに対する好奇心が研究をより進める原動力であるとしている。
– 社会学と異分野との連携について
社会学が対象としている社会自体がさまざまなテクノロジーや制度と結びついており、それがもう今の社会で不可欠のものになっている。つまり、そうしたものが作り出す関係の場やそうした関係の場を通じて人と関わることによって作り出される自我の意識や関係の感覚というものが、社会の重要な部分になっている。
– 社会学に興味を持つ方へのメッセージ
社会学を学ぶ上で古典は研究者たちの思考やまなざしを学んでいくことであり、著者の発見の瞬間を本を読むことによって追体験し、一緒に考えてワクワクするような感覚を持ってほしい。自分もそこに一緒に行けるという感覚を次世代には持ってほしい。
「社会学」をする上で学び得るようなスタンスは実はいろいろなところにあるのでそれを身につけてほしい。旅や芸術を通していろいろな経験をしたり感度を高めることが重要で、自分なりのセンスを身につけることが社会学をやっていくことを面白くし、モチベーションを高めることに繋がる。
エピソード書き起こし
島岡教授(以降、島岡):
「世の中の前提を紐解く社会学的感覚との出会い」と題を付けさせていただきましたが、まず先生がおっしゃっている社会学的感覚を意識し始めたきっかけとか、どのような道を辿って今の先生があるのか、お話いただけますでしょうか?
若林教授(以降、若林):
まず、最初から社会学者になろうと思ってはなくて、大学は早稲田ではなく東大だったんですけど、経済学部に進む文科二類に入ったんですよ。大学で授業聞いたら、経済の授業なんとなくピンとこないんですよね。人間が合理的に選択して何か行動するみたいな話とか、市場と政府の話とか、話はわかるんだけど自分が知りたい社会の感覚やリアリティと違うなと感じて。それでたまたま登録した社会学の授業で、なんかこれ面白そうっていうのがあって、それが前回もお話した見田宗介氏の授業だったんですけど、ある意味ですごくわかんなかったんですよ。これ日本語? みたいな感じの授業だったんだけど、同時にすごく魅力的で。他にも人類学の授業とか日本史の授業とかで、私たちが生きてる社会とは違う社会の生き方とか考え方とかに授業を通じて触れることがあって、こういうほうが面白いかもしれないなと思って。東大は最初はみんな教養学部に入るんだけど、3年生で専門課程に進むときに行き先選べるんですよね。それで経済学部に行くのやめて、でも社会学に行ったわけじゃなくて、相関社会科学という社会科学だったら何でもやってもいいけど学際的に何かやりましょうというところに進学したんですよ。そこでいろんな授業を聞いてて、就職がそろそろ目に見えてきたときにでもやっぱり学問するほうが面白いかもしれないなと思って、じゃあどうしようかなと思って、大学院に行ってから指導教員になってくれた山本泰先生に相談したら「あんたのやってるのは社会学なんじゃないの?」って言われて、それで社会学の大学院に行くことにしたっていう感じなので、社会学を選んだみたいな感じじゃないんです、私の場合。結果的に社会学になったみたいな感じですね。
島岡:
いろんな出会いを経て、先生が今ここに至ってるっていうのはよくわかったんですけど、先生がこの授業は面白いなとか、ちょっと違うなって、その差っていうのはどの辺にあるのですか?
若林:
経済って数量で形式化していくじゃないですか。それが自分が生きてる社会の肌感覚みたいなものと違う、のは当たり前なんですよねそれは、今になってみれば経済学はそういう学問だからそういうものなんだけど、それのリアリティが私にはピンとこなかったというのがあるんだと思うんですよ。逆に何て言うんだろうな、面白いと思った授業は、自分たちが普通に生きてる社会の中での感情とか、感覚とかを対象化してくれる、振り返ってみて、なんかこれって実はここ100年ぐらいでできたことに過ぎないんだとか、他の社会だと全然違う見方をするんだとか、あるいはヨーロッパと日本って全然違うって思ってたけど、でも中世の社会とか見ると同じようなところがあるんだなとかっていうことを教えてくれる授業というのが、やっぱり私にとってはピンとくる、面白いなと思った授業ですね。
島岡:
社会とご自身の関係とか、何か社会を意識したきっかけというか、そういう出来事みたいなのは?
若林:
一つ挙げると、高校2年の時に、他の方も読んだと思いますが、夏目漱石の『こころ』という小説を授業で習ったんですけど、その時に先生が教科書に出ているところだけじゃなくて『こころ』全部読んで、君たち自由に読んで報告しなさいという授業をやったんですよ。そこで、あの小説って都会と田舎の間を人が行ったり来たりすることによってできてるんですよね、違う世代の人間が都会と田舎を行ったり来たりすることによって経験することとか、絶望とか、孤独とか、寂しさとかということによって、物語が進行していくということを私なりに発見したんですよ。こういうのって面白いなって思って。多分私にとっての社会学的な思考みたいな、これ今私自身の都市論にも結びついてきますし、その授業がきっかけになってずっと後になって漱石についての本も一冊書いたんですけど、社会学的感覚を最初につかんだかなって思うのはその時かもしれないですね。
島岡:
そうですか。私も『こころ』は読みましたけども、そんなふうに全く読んでなかったんですけど、その後研究者としての道を選ばれて今に至っておられるわけですけど、その辺で何かこう不安というか、困難とかありましたか?
若林:
不安はなかったわけではないとは思うんですけど、でもなんかあんまり苦労もしてない感じがあって。大学院に入って、周りの先輩とか研究仲間にすごく恵まれてたなっていうのがあります。私はもともと社会学を目指してたわけじゃないし、社会学者の中だとど真ん中っていう感じじゃないと思うんですよ、キャリア的には。でも私が大学院に入った80年代半ばは、社会学を変えていこうという動きがすごくあって、これを聞いてる皆さんも知っている、例えば宮台真司氏とか、大澤真幸氏とか、有名な社会学者がいますけど、あの人たちが私よりもちょっと上の人で、前回お話をした吉見俊哉氏も彼らと同世代で、そういう人たちが社会学の風通しをすごく良くしてくれていて、自由にしてくれていて、そのまた上には橋爪大三郎さんとか内田隆三さんとか、もっと上には見田先生とか、吉田民人先生っていう情報社会学を日本で切り開いていった方がいらっしゃって、社会学ってすごく自由で面白いんだっていう時代に大学院に入ることができて、そういう人たちのおかげで好きなことをやっていいんだなっていう空気の中で院生時代を過ごせたっていうのがまずありますよね。就職も、博士課程に進んで、その後これはちょっと変わってると思うんですけど、理系の研究室の助手をやったんですよ。東京工業大学の都市工学の研究室の助手を1年10ヶ月して、これはね、面白かったですね。異文化体験。
島岡:
東大から東工大?
若林:
そうですね。まったく文化が違うので、理工系の研究室って研究室の先生が中小企業の社長みたいな感じで、博士の院生とか修士の院生とか学部生も使って、あれやれこれやれっていろいろやるわけじゃないですか。で、それは文科系の研究の文化と全然違ってて、それを知ることができたのは、すごく良かったなと思います。今でも理工系の先生とお付き合いするときに役に立ちますね。
島岡:
確かに文系の先生方というのは、どちらかというと一人で動く感じですかね。
若林:
そうですね。
島岡:
大きな組織を作るというよりも一人で。でも、先生は本当にいろんな、宮台先生の話もされてましたけど、いろいろな人と吸収し合いながらいろんなものを吸収して、連携して、ネットワークを作って、進んで来られたなっていう感じがするんですね。だから、孤独な学者というよりもすごく良いネットワークの中にいて、楽しく活き活き進まれたって感じですね。
若林:
そうですね。私、大学院生にもよく言うんですけど、やっぱり研究って一人でやるものじゃなくて、そもそも学問って世界中でみんなでやってるわけじゃないですか。日本でも同じようなテーマや、重なり合うテーマをやってる人たちでやっていて。そういう人たちとの出会いの中でやって、そもそも研究すること自体が学問の知のネットワークの中でやっていて、なおかつ大学の仕事だって、学会だって、そういう人とのつながりでできてるわけじゃないですか。例えば就職するとか、あるいは研究プロジェクトに誘われるということだって、こういう人がここにいるんだって知ってもらえないとダメなわけでしょ。だから人とのつながりってすごく大切だよって大学院生にもよく言っています。自分は学会とかの活動ってそんな熱心に若い頃やってませんでしたけど、でも学会に行って報告しないと、君がいることって周りの人は知ってくれないから、こういう面白い人がいるんだってことを示すために学会に行ったほうがいいよというふうには言いますね。学問って実は人との縁によるところがすごく大きいんじゃないか、どういう研究テーマを選ぶかとかどんな研究していくかというのもその中で結構変わってきますよね。それはとっても大切なことじゃないかと思いますね。
島岡:
そういう縁を引き寄せるために必要なことってありますか?
若林:
黙っていても誰も見つけてくれないので、発信する、たくさん書く、それから研究会に出て人と話すというようなこと。そういう機会を大切にするっていうのは一番重要なことじゃないですかね。
島岡:
例えばですけど、先生のご著書にあった「つながりを捨て去る自由」、今のSNSとの付き合い方とか、お一人様っていう概念がかえってポジティブに社会に受け止められるようなところもあるんですけども、逆に先生に回答を求めること自体がちょっと違うかなとも思ったりして。答えを先生に聞きたくなっちゃうんですけど。そのあたりで感じていることはありますか?
若林:
私も学生と話をしていて、つい教えたくなることがあるんですけど、話しすぎたなって思うことも結構あるんですよ。本当はやっぱり学生さんが自分で自分なりに考えて、答え、あるいは答えじゃなくて、自分なりの問いに達することが重要だと思うんですよね。大学で教えてて、割とよく思うのは、特に最近強く思うようになってきたかもしれないのですけど、勉強することは答えを出せるようにすることだと思っている子が多いと思うんですよ。でも、学問って答えが出たりしますけど、でもまずは何かわからないところから始まるわけですよね。何かわからないことがあるから、それについてああでもないこうでもないと考えたり、調べたり、実験したりして、そこからこうかもしれないという仮説を出すのが学問じゃないですか。そうすると「学問をする」というのは、答えを求めることじゃなくて、答えも出てくるけど、まずは問いを見つけることだと思うんですよ。わからないことがないと学問にはならない。先生もそうだし、私もそうだけど、だって全部わかってたら学者の仕事ないじゃないですか。わからないことがあって、わからないことを知りたいと思うから研究していて、あるいはわからないことを知ることができたらいいことがあるかもしれないから研究をしている、そういうわからないことと付き合うことによって今まで自分が考えたことのないこととか、思いもよらなかったことに出会えるのが学問だと思うんですよね。そういうことを学生には経験してほしいと思って、『社会学入門一歩前』で伝えたかったことの一つもそういうことです。だから、あまり教師が教えすぎてはいけないなと思いますね。
島岡:
私もアントレプレナーシップ教育をやっていますと、アントレプレナーシップ教育も、ある意味、問いを発見することなんですよね。何が今問題なのか、この人の本当にしたいことは何なのか、そういうことが出発点なので、先生が今おっしゃったことに本当に通ずるなと思います。今は、目標を立ててそれにいかに早く到達するかということに慣れすぎてるんですけど、でも今アントレプレナーシップ教育の世界で言われている一つの大きな柱でエフェクチュエーションというのがあって、エフェクチュエーションは今の手段から始めるんですね。なので、目標が変わってもいいんです。もう一つよく言われてるのはコーゼーションと言われてるんですけど、コーゼーションは目標を設定して、それに向かっていろいろな資源を動員していくと。ある意味真逆なんですけど、このエフェクチュエーションという考え方が今アントレプレナーシップ教育の中でも、あるいはこのイノベーション界隈でも話題になってますね。
若林:
そもそも目指すべきものが一つ決まってるかどうかわからなくて、そうじゃない方に行ってみたら、「あっちにあれがある」みたいなのが、起業家でも、あるいは研究者でも面白いと思うんですよ。わかっていることをやるのは、ある意味で新しいことが出てこないじゃないですか。発見がないし、自分が思いもよらなかったことがこっちに行くとあるんだという、それが面白いところですよね。それはある種の冒険なんだと思うんですよ。
島岡:
早稲田大学は人文社会科学系の研究者も多いですし、その学問も盛んですけども、社会学がその中で果たし得る意味はすごく大きい、しかもこれからどんどん大きくなっていくように思います。先ほど先生がおっしゃったように、いろんな風通しを良くするという表現でも、いろいろな分野と連携してきたと思うんですけども、これからの社会学を考えるときにどういうところと連携して、どういうふうな展開があり得るんでしょうか。
若林:
社会学が対象としている社会自体が、いろいろなテクノロジーとか、制度とか、そういうものと結びついてます。例えば、今だとSNSとかデジタルテクノロジーとか出てきていますけど、それが私たちの社会で不可欠のものになってますよね。そうしたものが作り出す関係の場や、そうした関係の場を通じて人と関わることによって作り出される自我の意識とか、関係の感覚というのが、私たちの社会の重要な部分になっています。
授業でもよく言うんですけど、例えばリアルとバーチャルというすごく乱暴な二分法があるじゃないですか。バーチャルは現実じゃないみたいな言い方がされることありますけど、全然そんなことなくて、あれ現実の一部じゃないですか。だってAmazonで買い物してるでしょ。ネット使ってるし、メールでやりとりしてるし、LINEで話しをしている、あれ現実じゃないの? というと現実ですよね。そうしたテクノロジーが作り出す環境と社会について考えるためには、既存の社会学の知識だけじゃダメですよね。
ここから振り返って考えると、実は私たちの社会って鉄道がないと成立していないし、自動車がないと成立していない社会ですよね。あるいは写真があること、ポッドキャストもそうですけども、ラジオがあることが私たちの社会生活をもう過去100年以上にわたって変えてきた。物やテクノロジーと社会がどういうふうに関係してるのかというのは、社会学の大きなテーマだったはずで、社会学って最近そのことに気がつき始めてるんですよ、実は。
社会学は基本的に人と人の関係、人の集団を問題にしてたんだけど、人と人と集団の関係だって、例えば今私たちがスタジオで話をしていて、今はスタジオで話をしてる私たちだけですけど、これが放送された時にはネットを通じていろいろな人たちの関係の中にいるわけじゃないですか。そういうものとして私たちは社会を生きてるわけですよね。
そうした関係って、実は例えば産業革命以降そういう社会にどんどんなってきてるし、文字に関していえばもう何千年も前から私たちの間にあって、そういう物やメディアと社会の関係を考えるためには、既存の社会学の道具だけじゃ足りないですよね。そうすると社会学って自分たちの社会を考えるためにも既存の社会学の枠を乗り越えていかなきゃいけないというところがあるんだと思うんです。
一つのフロンティアというのかな、情報やデジタルメディアのテクノロジーだと思いますけれども、他にも例えば医療の問題や、環境の問題とか、社会学が今まで対象としていなかった、あるいは十分にうまく扱えていなかった対象を扱う必要が出てくるんだと思うんですね。それが社会学の新しい道の一つかなと思いますね。社会学ってある意味で融通無碍にいろいろ使うことができるようなコンセプトや理論があると思うんですよ。でもその一方で社会学には社会学の伝統があって、私は最初から社会学を目指してたわけじゃなくて、今でも自分は結構社会学で素人っぽいんじゃないかなって思う時あるんですよ。社会学のプロの人たちって、もっと社会学はこういうものですということをしっかり背負ってて、でも社会学をそんな背負わなくても社会学できると思うんですよ。社会学を背負わないで自由に社会学をしていくことで、例えば情報科学であるとか、私の場合は若い頃から建築の人とかと付き合いがありましたけど、そういうところと付き合うことによって見えてくることってすごくいっぱいあるんですよね。向こうの人たちも社会学者の話を面白そうに聞いてくれて、ああ彼らはこういうこと知りたかったのねというのを感じることもあるし、そういう形で自由に社会学をやっていくというのがいいんじゃないかなと思いますね。
島岡:
今のこの新しい時代で、一時都市論とか社会学が大きく熱くなった時代があって、またその新しい時代が来てるという感じがしますね。
若林:
そうですね。
島岡:
技術がものすごい速さで、スピードで発展していったりとか、あるいはその社会情勢がある意味混迷している。そういういろんな要素が組み合わさって、これからの社会学っていうのがますます面白くなっていく。
若林:
その一方で、人間って変わってないと思うんですよ。人間という種自体はそんなに変わってなくて、だから社会を生きるという基本的なところは実は原始時代からそんなに変わっていないかもしれなくて、そうすると生身の体を持っている人が他者と関わって、道具を使って、自然の中で集団の中で生きていくということの基本は押さえなきゃいけない。それは社会学の古典と結びつくことだと思うんです。同時に、そういう視点を持ちながら現代の社会を考えるというのがすごく大切だと私は思いますね。
島岡:
社会学に興味を持ち始めている皆さん、この分野の専門家を志して学問をさらに発展させる次世代へのメッセージをいただきたいと思います。
若林:
社会学を学ぶ上では、社会学の本を読まなきゃいけないというのかな、古典を読まなきゃいけない。でもそれは字面を読むというよりも、古典を書いた社会学の研究者たちの思考やまなざしを学んでいくことだと思うんですよ。橋爪大三郎さんが私が若い頃に言ってくれたことがあるんですけど、古典というのはあることを初めて考えた人が書いた本だと言っていて、そうだなと思うんですよ。その考えていく、つまりすごい発見の瞬間ですよね、発見の瞬間を本を読むことによって追体験してほしいと思って、知識を得ることよりもウェーバー(マックス・ウェーバー)と一緒に、マルクス(カール・マルクス)と一緒に考えて、ワクワクする感覚を持ってほしい。自分もそこに一緒に行けるんだという感覚を持ってほしいというのがあります。
もう一つは、社会は本の中にあるのではなくて、もちろん本も社会の一部ですけど、自分たちの周りにある。そうすると、いろいろな経験をしたり、なんか見ることの感度を高めることが重要で、そのためには旅をするとか、あるいは芸術ってすごく重要だと思うんですよね、芸術は世界の見方を変えるもので、私はアーティストとか芸術やってる知人や友人もいますけど、彼らがやってることと私がやってることってあまり違う感じがしない時があって、社会学をする上で学び得るようなスタンス、姿勢みたいなものは実はいろいろなところにあるので、それを身につけてほしい。自分なりのセンスを身につけることが社会学をやっていくことを面白くするし、モチベーションを高めることだと思いますね。
島岡:
先ほど問いの話もされてましたけど、問いのセンスが重要。
若林:
そうですね。要するにわからないことのセンスが結構重要で、面白いわからないことを発見する、そのわからなさと付き合っていくことで自分の思考を展開させて、それを言葉にしていくことがすごく重要だと思うんです。だから研究者ってわからないこともプロだと思うんですよ。
島岡:
先生のご著書『社会学入門一歩前』を皆さんに読んでいただきたいと思うんですが、先生の次の計画があればぜひ教えてください。
若林:
今二つのことをやってるんですけど、一つは都市論で以前ショッピングモールについての本を書いたことがあるんです。「モール化する都市と社会」(「モール化する都市と社会:巨大商業施設論」)、私より若い人たちと共同で研究をして、そのチームで何年か東京臨海部、湾岸から現代の都市を考えることをやっていて、フィールドワークをしたり、一緒に本読んで議論して考えていて、臨海部の巨大スケールの空間とか、巨大な箱のような空間とか、あるいは流通基地もありますよね。あそこから見ると都市の現代を支えているいろいろな空間や時間のロジックが見えてくるんじゃないかと思ってるんです。それからフィールドを歩きながら考えることはすごく面白くて、一緒に歩きながら考えて発見して、そこから本を作っていくということを考えていて、それを近いうちに本にまとめたいというのが一つあります。
もう一つは、今までの私の仕事とはちょっと違うタイプの仕事なんですけど、私、趣味でバードウォッチングやっていて、その話を知り合いの研究者と編集者にしたら、それも面白いんじゃないのって言われて、ついその気になって、結構時間かけてやってるんですけど、人が鳥を見ることを通じて、人と自然の関係とか、人と社会の関係を考えることができるんじゃないかと思うんですよね。バードウォッチングってすごい変な趣味で、覗きですよね、ある意味で。鳥を覗くだけで捕まえて食べたりとか飼ったりしない。でも日本でもちょっと前までは捕まえて飼ったり、食べたりするのが普通だったんですよね。でも今それはいけないことになっていて、鳥を見て、たくさん見てカウントしたりするのが、側から見てると何が面白いのかよくわからないかもしれないんですけど、これは現代における人と自然の関係のあり方のある部分を表してるんじゃないかなと思うんです。バードウォッチングを切り口にして、人と自然とか、都市と環境とかそういうことについて考えられるんじゃないかと思って、自然と人間の社会学という、今までは都市について考えてきましたけど都市の外側には自然環境があって、実は都市の内側にも自然環境があって、さっきの社会学が物を対象とすることはあまり上手にしてこなかったということとも関係あるんですけど、普通、鳥って社会のメンバーだと思わないじゃないですか、私たちは。でも、私たちはいつも鳥と共に生きてきたのであって、その関係がどう変わったんだろうっていうことから、私たちの社会について考えるっていうことを今やろうと思ってて、それも本にして出そうと思っているので、楽しみにしてください。






